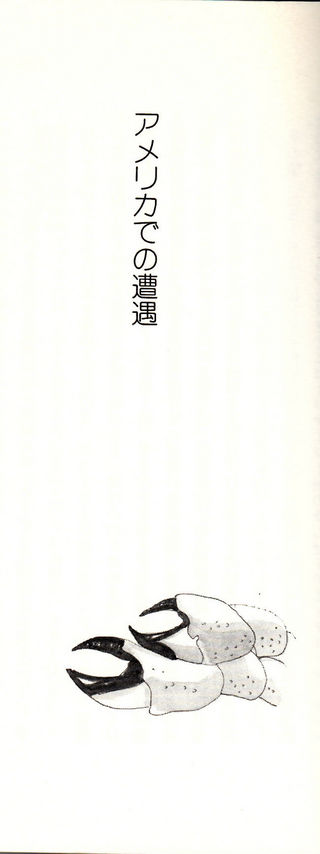父さんは、足の短いミラネーゼ
フランスの風と香りを吸って( 4 / 4 )
モスクワ・シェレメチボ空港
モスクワ・シェレメチボ空港
ヨーロッパへ飛ぶのに、昔はとてつもない遠回りをしていた。一番昔はアラスカ経由だった。しかもアンカレッジはまだ良いほうで、ひどい時はフェアバンクスなんて、アメリカ軍の北極基地があるような、氷の真ん中に飛んでから、パリとかロンドンに飛んだものだ。売店以外なんにも無いターミナルで1、2時間も待たされて、とにかく無駄だった。その後、やっとモスクワ経由で飛べるようになった。そのおかげでモスクワのシェレメチボなんて飛行場に何回か降りるはめになった。
ある時、大発見をした。滑走路の全体が、着陸する前にどういう加減か非常に良く見えた。びっくりした。一本の滑走路が、平らではないのだ。波打っていて、水平が出てはいないのだ。ちょうど雪が積もっていて、それで白い地面が起伏が起伏でグラデーションになっていて、はっきりその起伏が見えた。一本の滑走路が途中で二回も三回も、緩やかだけれど、丘になったり、下りになったりしているのだ。本当に驚いた。そこに、僕達の飛行機は、降りて行くのだ。着陸して、逆噴射をして、確かに停止するまで、機体がふわふわするのを感じてしまった。ロシア、その頃はまだソヴィエト連邦だったけど、やっぱり大まかなのかなと思った。
シェレメチボでは色んな物を買った。マトリョーシュカ、バラライカ、アルメニアのコニャックだとか、キャビアだったりした。そんな売店とか食堂で見たのは、ロシヤ・スタイルの算盤だった。二段になっているのは日本の算盤と同じだが、五の位が五つ玉になっているのだ。どうやって繰り上がるのよく分からなかったけれど、とにかく太ったお婆さんがぱちぱちとそれで外国為替の計算して、それで金を払ったものだ。交換レートは、お婆さんにお任せで、信じるしかほかない。
よほどの事が無ければソヴィエトの飛行機には乗るな、という会社の指示があったが、やむをえず、何回か使ったことがある。ヨーロッパに向かう時に何時間も、シェレメチボ空港で待たされた事がある。きちっとした理由説明があるわけでもなく、狭く暗いターミナルで代替の飛行機が来るまで待たされた。まったくサービス精神は見られなかった。スチュワーデスは太ったおばさん。にこりともしない。飛行中は乗客と同じ座席に座って眠り込む。ワゴンがしまってあるギャレットの留め金がちゃんとかかっていなくて、ちょっとした振動で扉が開いて中のプレートやなんかが飛びだしてきても、我、関せずだ。これもびっくりだ。通路に食器なんかが転がっていてもそのまま次のサービスを始めるまで置いておかれる。日本の飛行機に乗ったら、その違いに大感激だった。もちろんチョットやり過ぎのところもあると思うけど。
いつだったか、オランダの大学生たちと、東京行に乗り合わせたことがある。彼らは団体旅行で、半ばそのセクションは貸し切りになっていて、賑やかだった。酒が入っていて、たまたま近くに座っていた僕にもグラスを差し出してくれた。もちろん彼らの持ち込みのボトルで、強い酒だった。それはぼくが始めって知った「ジュニーブラ」と彼らの発音していたオランダ・ジンだった。ちょっと独特の匂いがするが、いい酒だった。またジュニーブラの入っていた、素焼きの、ちょっと茶っぽい、背の高いストレートなボトルがとても良くて、まだ半分以上も残っているボトルを、彼らから譲ってもらって、持って帰ったものだ。その後、僕の好きなジンの定番になった。
窓の下にはうねうねとシベリアの原野が川のうねりを見せているだけだから、他にすることもない。6時間以上も彼らと飲み続けた。全く修学旅行のノリだった。びっくりしたことが起こったのは、飛行機が日本海に出るとあっと言う間に本州の山々を飛び越えて、太平洋に出た時だった。飛行機が銚子沖の九十九里浜の上空を旋回し着陸のために高度を下げて、片方の翼を上げて機体を傾け、回転し始めた時だ。突然ざーっと、水が天井から窓をつたって、頭の上に降ってきた。右へ傾けば右側に、左へ傾けば今度は左側の窓を水が滴った。
あれは真夏だったのだ。軍用飛行機を改造したような代物だから、機体の気密性が弱くて、空気中の水分が、冷たい機体にふれて水滴に化けて天井一面に付いてしまっていたのだ。それが機体のバランスが崩れるたびに水の滝となって落ち込んで来たのだ。何しろ湿度の高い東京だから。悲鳴があがった。皆びっくりした。なかなか体験できない、希有な思い出だ。
それ以後は、再びソヴィエトの飛行機に乗る気はなくなった。
アメリカでの遭遇( 2 / 8 )
ニューヨーク州
ニューヨーク州
道は歩けない
初めて僕がアメリカに足をふみいれたのは、ニューヨークのジョンFケネディ空港だった。初めてヨーロッパにいった時に比べると、僕の心のときめきは、そんなに高くはなかった。時は9月。ニューヨークに着く前、アラスカやカナダの上を飛んでいるとき見えた地面は、さいしょは真っ白な氷の原っぱ、それが深い赤の地面、さらにだんだん明るい赤に移っていった。ニユーヨーク州の上空では、紅葉が緑と赤の混ぜ模様でとてもきれいで印象的だった。1973年から5年間の、大変なプロジェクトの始まりだった。
その頃、ニューヨークはとても怖いところだと聞かされていたから、僕たちはシティには泊まらず、頼んであったリモでニュージャージー州のラムゼーのモテール・ホリディインに入った。みんなで10人ぐらいのグループだった。全員が自分の車を借りることはできなくて、数台の車でのグループ行動だった。
モーテルのすぐ目の前に大きなショピング・モールがあったが、ちょっと買い物ものに行きたいなと思っても、しかし、前は歩いては渡れないディバイデッド・フリーウエイだ。しょうがない。車に乗って次の町の出口まで行って、一度フリーウエイを降り、逆方向に走ってやっと目の前のショッピング・モールにたどり着く。人間が歩くことをとんでもなく拒否した世界だった。車が大前提の世界だった。こんなわけだから、一人で歩いてどこかへ行くということはできなくて、グループで車を使って動くことになる。これがみんなにとっては凄いストレスとなった。
僕たちが詰めるオフイスは、ルート17をさらに北に上がって山の中、スターリング・フォレストという湖のある自然公園の中にある、人里はなれたソフトウエア開発センターだった。なにしろ「人間は車に乗って移動する」という前提で町ができているから、住宅地の中以外では人が歩く歩道がない。そんな所のふつうの道を、ちょっと近くのレストランまで、5分ぐらいの距離をてくてく歩いて、7、8人もの人が移動すると、次の日にはオフイス中の人が心配して「何かあったのか?」と聞いてくる。親切なのだけれど「ちょっとわずらわしいな」ってな感じになる。それほど人が徒歩で歩くのが、不思議にみえる土地柄のニューヨーク郊外だった。
道に沿って家が建っているが、それがまるで芝居の書き割りのように薄っぺらい。一列に並んだと家の裏は、もう森だ、林だ、何にもないだ。リスがぴょこぴょこ遊んでいる。やっぱり地べただなあ、と思う。西部劇なんかで、町の通りや商店とかがあって、その裏はもう原野ってのが出てきたけど、そのまんまがニューヨーク州やニュージャージー州の大部分の感じだった。
いろんな人種が一緒に暮らしているからだろうけど、ちょっとした注意書きも、僕たちからすると「きっちり書いてあるな!」ってな感じを受ける。公園に「ごみを捨てるな!」と書くところを「ここにごみを捨てると、あなたは120ドルの罰金を払うことになります」と書いてある。正確ではあるし、明文化してあるから、曖昧さは残らないが、ここまで書くのが誤解を生まない知恵なのだと感心したり、ちょっと考えちゃうなと思ったりもした。
家だって自分で作るんだ!
友達ができて彼のうちに呼ばれた。とても広い家で、周りは芝生と畑になってる。
彼の住んでいる家は、彼が全部自分自身で、一部屋ずつ次々に作っていているというのにはたまげた。もちろん、建物本体、屋根、外壁は最初に造ってしまう。最初は居間と食堂を完成させ、それから夫婦の寝室がちょうど今完成したばかりだという。DIYがマジで行われているのだ。子供たちの部屋は、今度君たちがくる頃には、完成しているだろうと言っていた。地下は彼の大きな工作室で、電動の大きなツールが完備している。ここで彼は休みになればこつこつと部品を作り、家具を作り、壁材を切り出しているのだ。僕が行った時には、子供達のベッドの骨格が出来上がっていた。その馬力に感心した。
アメリカの男性諸君には、まだまだ西部開拓時代の、自分で何とかするという精神が、脈々と生きて、動いていることが印象深かった。その後、何年もの間、彼の家を訪ねることになるのだが、その度に少しずつ彼の家が完成に向かっていくのを確認することになった。彼にとって家を造るってのは、金を払ってぽんと造って終わりというのではないのだと納得した。彼に言わせると、ほんとうは凄い人種差別がアメリカはあるという。彼はドイツ系で、順番から言うと、プロテスタントでもどちらかというと中くらいらしい。なにしろ「WASP」が幅を利かせているらしい。白人、アングロサクソンで、プロテスタントがそれらの意味だ。そんな中で彼は努力してアメリカの代表的な会社、I社で、それなりの地位にいる。しかし、彼に言わせると彼の生活レベルが普通だという。確かに考えようによってはかなり地味で質素かもしれない。日本では自分で部屋を造るなんてのは、どちらかというと地味な感じだ。しかし彼らの考え方からするとまったく普通なことだという。彼にとって家は彼の手作りなのだ。
冬の間の食べる野菜類は、みなすべてが自家製だという。もちろん千坪もある家のまわりは、いくらでも畑にすることができる。奥さんの仕事だといっていたが、もちろん彼も休みには収穫なんかを手伝う。そして夏の間に、大きな冷凍庫をいくつもいくつもいっぱいにしておくのだと言っていた。半地下には、そんな野菜のストックがいっぱいだった。自給自足に近いベースができているのには驚かされた。彼の住んでいるところはニューヨークから車で1時間ぐらいの郊外で、いわゆる田舎ではない。こんな生活が実質的なアメリカ人の生活だと驚いた。
働き者たち
日本人は働き者だといわれているけど、アメリカ人の働きぶりには驚いた。彼らは、定時に退社するのが普通だと思っていたけれど、僕たちの相手達はなかなかタフで、時間なんかあまり気にしないで、やる時はやるって感じだった。
前の夜(朝?)に、仲間と朝の1時、2時まで飲んで騒いでいても、翌日は眠い感じも出さずに、朝7時の会議なんかも平気でやってくる。どちらかというと体力のない日本人のほうがオタオタしていることだってある。夜も仕事の進み具合では、夜の10時だって11時だってがんばってやっている。SEという特殊な世界だからかもしれないが、本当によく集中して働く仲間だった。
時間をも無視して、ちゃんと期限にまで仕事を上げるということよりも、もっと驚いたことは、彼らの自分自身の仕事に対する誇りと情熱だ。今回導入するシステムを、日本の実情に合わせてデザインを変更することが必要になった。そんな時、僕たち日本人たちもSEだから「ここをこんなふうにこう変更したい」と提案した場合、返ってくる答えは常にこうだった。「希望する機能を決めるのが君たちで、どのようにその要求を満たすかは僕、システム・デザイナーの問題だから、変更のデザインまで言う必要は無い」と。確かにオリジナルのデザインに責任を持ち、全体の姿を含めて彼の持つオーナーシップを考えればこの言葉はあたりまえだ。ところが僕たちも難しい変更を次から次にだしていく時、こうしたら簡単だなあなんて思って、解をつけて出していくと必ず反論が来る。「それは君たちの考えで、僕には解は不要だ。本当の解は僕の仕事だ。」とくる。最初の頃は、こんなことが積み重なると、感情が波立ってきて、いい関係とはいえない空気ができてきたこともある。
しかし、一緒になって、デザインを検証していく日々が何日も続くと、いつのまにか彼の言うことの正しさがわかってくる。部分しか知らない僕の考えは、思いもかけないところで使われているそのデザインに対して、もっと大きなミスを起こすような変更だったりする。
そして、彼が本当の解決策として構築したデザインは、徹底して明確に文書化され、関連システムのデザイナー達の出席する検証会議の「ウオーク・スルー」にかけられて擦り合わされる。こうしてデザインの正当性と透明性が徹底されて保たれる。その後やっとプログラムのスペックの作成にはいる。こうやって徹底したデザインの保証性が保たれてくのだ。感服した。そうでなくては、デザイナーの頭の中にのみ、全くの「ブラックボックス」としてデザインが閉じ込められてしまうことになる。この方法は、その後日本で、システム・メインテナンスを担当する我々にとって、大変重要な技術となった。彼らは「ホワイトボックス」化のノウハウを、具体的に我々に教えてくれた。そしてこの手法は、単にシステム・デザインの領域だけではなく、プログラミングの方法だとか、はたまたシステムオペレーションの組み方までに及んだ。こうして、彼らは自分たちが作り上げてちゃんと運用しているシステムについて、絶対的な自信と誇りを持っていた。
そんなふうに時間が過ぎて、いつか僕たち日本人チームは「問題を解決する提案」よりも「解くべき問題をきちんと定義する」こと、そして「新しい彼らの変更が、本当に我々の問題を解決したか?」の検証に、自分達の役割を変更していった。それがオーナーシップを持った彼らに対するベストのアプローチになった。物の考え方が、一ヶ月も共にやっていると見えてきた。それがとてもいい信頼を生んでいった。最初のデザインが完成した3ヵ月後には、日本人もアメリカ人もすっかり一つのチームに変身していた。
ニューヨークの郊外
ハドソン川を東から西に渡る橋の一つに僕たちがよく使ったタッパンジー橋がある。ニューヨークステート・ハイウエイの3マイルにもおよぶ有料橋だ。最初びっくりした。トルゲートが東向きにしかないのだ。西へ向う車は通行料を払う必要がない。聞いてみると「どうせ奴らは、またきっと西から東へ帰って来るんだから、その時にもらおう」って言うのだ。いかにも大らかなアメリカらしい発想だと感心してしまった。3マイルは本当に長い。
少し行くとセブンレーク・パークウエイへの出口になる。ここには一人で、時にはみんなで、よく気楽にドライブに出かけたものだ。ハリマン・ベアー・マウンテン州立公園の中を走る。小さな湖がいっぱいあって、森の中にキャンプ場やバーベキューサイトが散在している。秋の紅葉は本当に素晴らしかった。日本では奥入瀬渓谷とか奥日光とか紅葉の名所がいっぱいあるが、あえて言えばここセブンレークの紅葉のほうがもっともっと美しいと思った。寒暖の気温差が大きい大陸だから、9月の最初は緑と黄色のコントラスト、その後、赤と黄色と緑のない交ぜになって、最後は暗褐色とくすんだ紅葉色と黄色の病葉の組み合わせになる。その組み合わせが本当にきれいで何回も見に出かけた。ベアー・マウンテンにはスキー場がいくつもある。小規模のものだけど十分楽しめそうだった。夏には、湖で泳いだり、釣りをしたり、ボート遊びをしたり、ゆっくり時間を過ごす。ニューヨークの中心から一時間ちょっとでこんな自然いっぱいの世界に入っていける。
僕たちが詰めていたサイトは、冬には湖が凍ってスケートの名所になる。そんな所に雪が降った朝など、町から車で通勤するのはかなり大変だ。凍てついた細い道を登っていくことになる。大きな道はきちんと除雪もしてあるが、大きな道を離れて山に向かって細い道にはいっていくと、もうそこは大変。途中に小さな丘がある。平地から登っていって頂上。そこから一気に下る。この丘が難所だった。タイヤはスノーだから結構すべる。丘の向うからの対向車のことはよくわからないが、同じ方向に向かっていく車たちは、先で何がおきているか丘の斜面だから良く見える。皆、前の車がその丘を越えていくのを下で順番待をしている。
前の車が、滑りながらでもうまく斜面の上がりきって峠の向うに消えると、次の車が、やおらスピードを上げてその登りを攻める。時にはうまく路面をつかめないで、途中で止まってしまって、ずるりと下がってくる車もある。そんな時のために、車は、かなり坂の手前で、前の車のチャレンジを見守っているのだ。やっと前がクリアーされて自分の番になる。滑らないようにゆっくりとスピードを上げて坂に向う。登れそうかな、上がれるかなという自問自答が続く。何とか頂上にたどり着いたら、後はブレーキを踏まないで、何とかうまく転がして坂の底にたどり着く。これで、やっと会社に着くことができる。雪の季節は、こんなことの朝の繰り返しが続く。
このスターリングフォーレストには、この他にユニークな、ここでしか味わえない道の状況がある。「鹿に注意!」の看板が道に出ている。結構狭い道だから、こんなのを見るとブレーキに足が行く。それはでも本当に大切なことだったのだ。イギリスから来ていたアサイニーが、あるとき突然現れた鹿に衝突してしまった。車は大破して、大鹿は即死。そして彼は全治3ヶ月の大けがをしたのだ。動物が住んでいる領域に人が入り込んだ結果だった。だからここにアサインされると、オリエンテーションで必ず「鹿に注意!」ということになる。
アメリカでの遭遇( 3 / 8 )
ホワイトプレーンの冬
ホワイトプレーンの冬
ニューヨークのダウンタウンから北へ1時間ほど走ると、もうそこはニューヨークの喧騒とは無関係な、自然の真っ只中に広がる住宅地だ。ウエストチェスター郡のホワイトプレーンという小さな町だ。もともとはニューヨークの街中を離れたニューヨーカー達が自分らしい住まいを求めてやって来たところだ。緑が多くて、なだらかな丘陵地でもある。
僕の会社のアジア・オセアニア本部は、あの大金持ち、ロックフェラー氏の持つ広大な林と住宅の散在する地域の中、池の辺に建てられていた。建物自体は結構でかいのだが、木々の間でこぢんまりと見える。環境協定がきっちり出来ていて、建物は周りの木立の中に、すっぽりと隠れることが条件。結果として、たったの2階建てしか認められなかった。もちろん自然だらけで、ちょっと足を伸ばすと、ハドソン川の川面が、ロックフェラー庭園の先に広がっていた。いろんな季節に訪れたが、冬には建物のすぐ側にある、小さな池に鴨たちがいっぱいやって来た。
こんな田舎にも、ちゃんとメーシーなんかがあって、いろんなブティックも結構あり、生活レベルは高いところだった。どうしてだったか忘れてしまったが、こんな田舎に極寒の2月のさなか、2、3週間も滞在することになってしまった。日本の冬の感覚で、トレンチコートとマフラー、それに現地で買った手袋で、この日々を過ごす羽目になった。
僕が滞在するホテルはちゃんとしたホテルで、モーテルではなかった。そのホテルは町中にあったが、ショッピングや食事にはどうしても外に出る。しかもこの年はやけに雪が多かった。町の中も雪だらけで、車は狭くなった道をすれ違うのにとても苦労していた。もちろん歩きだって大変だ。薄い防寒着のために、僕の体は零下20度以下の寒さでこちこちになってしまった。ちょっと建物や車の外に出ると、背中がドンと押されるように寒さに押し上げられる。そうかといって、こちらの人たちが着ているような分厚い毛皮やキルティングのコートは買うのには抵抗がある。日本に持って帰っても、北海道かどこかの雪国に行かなくっちゃ、とても着られものじゃない。飛行機に乗っける荷物だって空気を運んでいるみたいになる。そんなわけで薄っぺらいトレンチコートでもって、その3週間ぐらいを我慢して過ごした。
その年は何時になく寒く、しかも雪が多かった。車を運転するのも大変。自分で運転して郊外のサイトまで通うのは危険だと思って、毎朝タクシーを頼む。日本でいうと函館ぐらいのニューヨークの北だから、車は当然チェーンを巻いて、スパイクだと思うのに、簡単なスノータイヤのまんま走っていく。前の方に車が止まっていようものなら、遠くからポンピングしながら、すべるの計算しながら近づいていく。心のなかで「止まれ、止まれ!」と叫びはするが、自分でブレーキを踏んでいるわけではないから車は滑っていく。テカテカのアイスバーンのうえでは、こんな冷や汗も出るのだ。
田舎町でもやはり交通量が少ないと、森の中は深閑とした感じになる。鹿や熊も出て来るという所だから、公共交通機関はタクシー以外にはなんにもない。この冬は、僕のいた2、3週間の間に、そのサイトは何度か、急に雪のために閉鎖されることとなった。働いていたり、会議をしたりしていると、サイト全体に急に放送が流れる。「このサイトは午後3時を持って閉鎖されます。全員、退去してください。」という具合だ。僕は短期滞在者だから、そんなに知人はいない。町まで乗っけてもらう人を探すのが大変だ。みんな、あせっているから、人はどんどんいなくなってしまう。とにかく、町の方向へ帰る人を見つけるのが一苦労だ。いつもは一冬でこんなことが、繰り返されることはあまりない、ひどい冬だった。
ホワイトプレーンズ・ホテルは、とても静でしかも町中にあって、食事に出かけるのも便利だった。行きつけは、いつのまにか僕の古い思いがそうさせたのだろうが、イタリアンレストランだった。ホテルから歩いて5分ぐらいの所にあった。僕が入っていくのは、いつもその店の裏口からだった。表にはかなり遠回りしていかないと辿りつけない。雪道で遠回りすることは無い。だから裏口専門だ。
凍てついた氷の世界から裏口に飛び込んだものだ。他に行く所があまりないから、いつのまにか、常連さんになってしまった。味はいいのだが、何しろグニャグニャの茹で過ぎスパゲティは、とてもたまらない。とっかえひっかえして、レストランのメニューをほとんど食べ尽くしてしまった。薄暗いランプにてらされた、木造小屋の雰囲気は懐かしい思い出になった。
寝るまでには、もっと大変な苦労がある。ホテルの部屋のドアを開けるのは、本当に恐怖だ。静電気がバチンと襲ってくる。廊下は乾燥の局だからだ。悪いことに絨毯が電気を盛大に起こしてくれる。どんなにすり足を避けて歩いても、静電気は待っている。
ホテルの部屋でも大変なことが起きていた。空気が乾燥して、喉がガラガラ。風邪はなかなか治らない。仕方がないから、バスタブにお湯を落としてバスルームの扉を開け放して湿度を部屋に補給する。それでも足りないから、バスタオルをびしょびしょに濡らして、イスとかスタンドとかにかけておく。最後には床のカーペットに水を播く羽目になる。それでも空気はカラカラに乾燥していく。そんな日々が続き、ある日とんでもないことが起こった。僕の部屋の窓がどんどん見えなくなっていった。気がつくと、何時の間にか、僕の部屋の窓という窓は、全て天井から下の窓枠まで、ギッシリと厚いツララのような、氷で覆われてしまった。棒状の氷が窓のガラスに凍りつき、デコボコもできて氷柱そのものだ。もう透明なところはなくて、外はまったく見えない。厚いデコボコの曇りガラスの中に、いつか僕は閉じ込められてしまっていた。おかげで、僕の部屋はいつも薄暗くて、外のクリヤーな世界が見えてこない。何度か融かそうとして、手で撫でてみたのだが、とても間尺に会わない。手が冷たくなって、ちょっとだけ氷が手のなかで溶けるくらいのものだ。
そんな部屋に、メイドもあきれてはいたのだろうが、文句も言われず、僕はそのホテルで極寒の2月を過ごした。僕がその部屋を出た後に、その氷たちはどうなったのだろうかといつも思った。その後、僕はそのホテルに泊まるのをためらった。零下20度の冬は得難い思い出だ。
-
-
父さんは、足の短いミラネーゼ
5