小夜子の憂き世
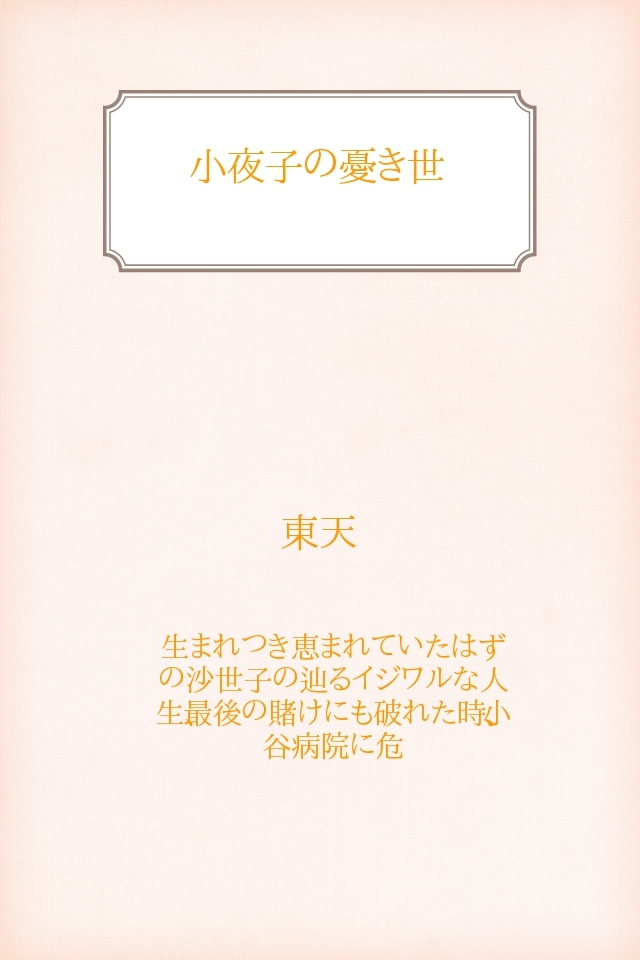
「小夜子の憂き世」
一
「母さん、もう嫌だよ、もうそちらに行きたい」
賢くて美人で勝気な子だった。小夜子が通るとみんなが振り向いた。父親の仕事が傾きかけたとき、小夜子は京都大学に合格していた。しかし、大学などもってのほかとばかり入学手続きをしてくれなかったのだ。実父でなかったことがこんな結果を生んだ。しかもそのとき初めて、そのことを知ったのであった。
それから半世紀を生きた。一年遅れで京都大学を卒業したのだが、恋をして中絶をする仕儀となり、裏切られて自殺を試みた。はっきりした意図はなく真っ白い頭のままで薬を口に運んだ。それから結婚と離婚を三度繰り返す羽目になったその今である。
秀でた額の照りが失われ、いつも長く垂らしていた黒髪がほとんど白くなってからもう十年たった。大きな瞳の輝きはまだ失われていなかったはずだが、一人息子の智一家に無視されてしまった古希の誕生日のその日、手鏡の中に力のない視線を見たのだった。
才気ときかん気、魅力的な容姿振る舞いをもってすれば、貧しい母子家庭から出発したけれども、小夜子に成し遂げられないことは何もなかった。子供の才能教育の分野で目覚しい成果を上げ、塾やセミナーを組織して多分にもてはやされてもいた。
それがいつから、どうして翳ってしまったのか、もう振り返る気が全くしなかった。やっと積み上がった積み木が崩れる、その瓦礫の上にまたも気丈に立ち上げたものが小夜子のせいでなく崩れる、それでもその上に踏ん張っていても、またもや小夜子の決定でないことが降りかかってきて心が潰れた。
それまでの仕事を辞め、数年間の介護ののち母親を見送った時、小夜子には半額ほどの国民年金しか収入がなく、借金すら残っていた。
その頃、初めて敬愛するに足る男に出会ったのに、彼は急逝してしまった。
英才教育の成果のような自慢の一人息子、智を捕まえて離さない女がいたのを、つい結婚させてしまったのがその次の、そして痛烈な決定打となった。
小夜子に言わせれば、嫁の里子は「人の心を解さない、機械のような反社会的パーソナリティ」であった。姑を姑とも思わぬ里子の態度に、失望し傷つけられるのは小夜子ばかりで、銀行家である、里子の実家との経済的な相違が一層小夜子を惨めな存在へと貶めてしまう。智といつの日か別れるとは夢にも思わなかったのに、同居は叶わぬ夢となった。
それでも、彼が音楽の世界で次第に名を成すようになったのは、小夜子にとって意味あることであった。孫が次々と生まれると、小夜子は嫁の育児のいい加減さを見かねて長子の世話をせざるをえなかった。思いもかけずそれは喜びとなったのだが、反面、小夜子の心を痛ませ、縛るものともなったのである。
それでもまだ、下には下があったのだ。智がのっぴきならない理由から高校教諭の職を辞したのだった。
小夜子はもう考えたくなかった。すべて嫁の影響であって、智も心理的に被害を被っているはずだった。
仲違いゆえに、仕方なく隣の家を借りて住んでいる母親に今や、生活費として七万円を渡すことができなくなって、それが一層彼を無残な気持ちにしているのであった。
一方、その頃には関係がより険悪になり、孫と会うこともできなくなった小夜子は、自分がほとんど育て上げた孫の海斗を今更嫁に取られるかと思うと気が狂いそうだった。感情の限界まで来た、と思った。
するとまだ辛いことが重なるのだ。大家が突然退去を強い始めた。認知症を発症したらしく、針のように細めた目つきで家の周りを徘徊するのであった。
そして、小夜子は田川実という老人と人を介して知り合った。
二
他人の病を治す、という立場でしか自分を考えたことのなかった小谷篤志院長に、始めて難題が立ち現れた。息子で跡取りの篤彦が急性白血病に罹患したのだ。
郡上八幡市では評判のいい中規模の内科外科病院だった。祖父の代からの医者一家であり、今は孫二人も眼科、整形外科として働き始めていた。七十五歳までには篤彦に院長を譲るつもりで、準備を整えていた矢先である。
彼自身も罹患した息子も一人っ子であった。抜かりのあるはずもなく血縁全員から骨髄移植合致検査を行ったのだが、結果を見て絶望に襲われた。孫二人にはまだ子供はいない。あとは運良く適合する提供者が現れるのを待つしかない。
「隠し子でもいなかったのかなあ」
と、眼科医の上の孫、典亮がとんでもないことを言い始めた。
「私にはいないよ」と篤志は慌てて手を振った。彼は恐妻家であった。
「そういえば」
と、ソファにだるそうに座っていた病人の篤彦が言う。「母さんから聞いたことがあるけどね、お爺さんはかなり艶福家だったという話」
「艶福家、なんて今頃聞かないよなあ」
と、整形外科医の下の孫が笑った。
「前院長か、そんな噂が確かにあったよ。親父はちょっと男っぶりもよかったし」
と、篤志が父親小谷篤の写真を見上げながら言った。「だけど、子種をまくようなドジはしてないだろうよ」「そうだよなあ、ならとっくに養育費を請求する女性が現れていただろ」
息子の篤彦の表情を見測るように視線を移した父親の篤志は、「まあ、全力で事に当たろう、すべて試してみるんだ」と言った。
「うん、頑張らなきゃな、気持ちで負けたらダメだ」
篤彦が唇を引き締めるようにつぶやいた。
三
小夜子は三度目の結婚に迫られていた。インターネット内の知人の知人として紹介された。写真では温和な害のなさそうな笑顔の老人で、京都府の郡部で町内の民生員をしているという。それが似合いそうなタイプに見えた。妻は数年前に病死、経済的な窮地にある薄幸の佳人である小夜子に、たちまち老後の夢を描き始めたと見える。彼が並べて見せた条件は、小夜子の必要に十分間に合うように見えた。
一応大学を出て、電気設備関係の会社を退職後も、時にその関係の仕事が入り、また町内の役や世話による収入もあり、築三十年の家がある。すでに独立して関東に暮らす二人の子は、父親の世話をしてくれるなら家屋敷の相続は放棄するという。
小夜子の借金を払い、引越しの費用を出し、面倒な大家との話し合いも彼独特の粘り強い話術を駆使して片付けた。小夜子の古くなったパソコンを買い換えてくれた。ちなみにそこにはたくさんの小説が書き貯められていた。極め付けのように、ラブレターまで書き送ってきたのであったが、小夜子は少したじろいだ。
小夜子の出した条件は、いわゆる「茶飲み友達」として結婚するということが一点。
何よりも重要なのは、自費出版であれ、自選ベスト短編集を世に問う、という小夜子の夢を実現できるかどうか、ということであった。彼女はその夢がいかに自分にとって大切であるかを、会うたびに田川実に話した。彼の反応は、そんな小説家の夢をかなえるなんて願っても無いことだ、誇らしいよ、というこれまた迎合的なものであった。
小夜子が確信が持てないでいると、通帳を見せて、年金がこうだから、ここにこれだけ貯まるはずである、と説明するのだった。
「あまりにうまくできすぎて無い? そこまで全て合わせてくれるのが、天の助けというか、胡散臭いというか」
友人からそんな一言も聞いたが、ともかく住む家がなくなっていることもあって、渡りに船と、乗っていくより他はないように見えた。田川の言葉を疑う理由がなかった。それほどに小夜子は、念には念を入れ、理を尽くし、自分の夢の重要性を説明したのだ。それを彼は請け負った。
息子の智は、実の気持ちはどうであったかともかくすぐに賛成した。夫婦して明らかに小夜子への対応が軟化した。別れ際に、戻ってきてもらっても困るから、頑張って、というような言い回しを聞いたような気がした。
四
小谷病院の院長篤志は、市の医師会報に病院の沿革を載せることになり、仏壇の引き出しに保管してある古い手帳をあらためてめくっていた。父の小谷篤、祖父の小谷典篤が愛用していたものが何冊も入っている。
父親の手帳には、仕事の予定の一杯に書き込んである中に時折、アルファベット一文字が丸で囲まれて散在している。それが朱色なので、これかあ、と篤志は苦笑いを浮かべてていた。
これまで気にかけたこともなかったのだが。彼の誕生の後にもアルファベットがあった。不倫だ。
Sという。頻繁に会ったらしい。半年ほどでSの文字が消えると、しばらく誰とも不倫しなかったようだ。
そのあとで、偶然に祖父のメモを眺めていた時、同じ時期にSが現れた。もちろん丸で囲まれているわけではない。サワ、木下サワとある。金額が記してあった。それを妙だと思った。
小説の謎解きのようなスリルに引き込まれて、戦後すぐの新病院再開時の看護婦名簿を探してみた。その名はそこにすぐに見つかったので、自分でも驚いた。単純な推測が当たったのだ。
木下サワの欄の外枠に、彼女がすでに戦時中から看護婦として勤務していた由、付け足してある。昭和二十一年四月の名簿にはもう名前がない。父のメモと符合する。
ただの好奇心ならもう放り出していただろう。息子への不安感に煽られると、今では誰一人知る人など残っていないことが、大事なものを逃したかのようで心がじりじりと燃えた。
五
梶野明美もそれなりの火宅にいる。大学生の息子寛一郎がまた家を空けるらしい。夫は海外勤務でインドネシアだ、全く当てにならない、もう長く帰ってこない。何をしてるか推測はつく。それはいい。金さえ回れば。
息子はどこに行ったのか。いつものようにやがて戻ってくるとは思うものの、携帯は無反応のままだ。イライラして、スカイプをつけた。
「小夜子さぁん、お邪魔しまぁす」
見るからに古い家具を背後に、田川小夜子が画面に現れた。先妻の家具だと明美は聞いている。小夜子がひどく憔悴して見えるので驚いた。結婚してからは少しふっくらしてきたと思っていたのだが。二人は同じ塾で教えていた同僚である。
「どうしたの、なんとかやりくりしてるようだったのに」
「それがね、聞いてよ」
という小夜子の声が荒れている。タバコをまた吸い始めたのだろう、それとも泣いたのだろうか。
「私、もう呆然としてしまって。怒ることも泣くこともできないのよ」
あの苦境からいわば救い出してくれた田川だからと、小夜子は大抵のことは我慢するつもりだった。小さな齟齬は当然あったが、なんとか状況を操縦できるように思えた。
ところがこの前から田川が上の空という様子だった。実はナ、この個人年金が七十五歳で終わりになるのを忘れとってん。それに民生委員も任期切れやん、委任料ものうなる。
「、、、それで?」
「あんたの夢の自費出版の二百万が消えてしもうたんや」
そこに来たか、と頭蓋が破裂しそうになった。田川はしおしおとしているが、謝りはしない、なんとか頑張ろう、とも言わない。計算違いだった、それだけの気持ちらしい。すっかり小夜子の夢を握りつぶしていた。ただの夢だと思っていたのだ。
私にはもう何もない、この世に残せるただ一つのものだったのに、私が全く無能なら諦めもつく、けど、私は実際いくつかこれまで賞をもらってきた、ただそれ以上のことを起こせなかった、そうするには、不運続きだっただけ!!
せめて一冊の本を、と私の全人生をそれに賭けていると、
あんなに口を酸っぱくして何度もなんども念を押して、わかってくれたかと尋ねたでしょ!!!
それを、あ、忘れとった、できへん、で済ますつもり、私という人間をそこまで軽んじているあんたこそ最低の男や!
野良猫を拾ったんとちゃうよ!
胸の内で叫んだのに、言葉に出てこない。
「もうダメだわ、一緒になんかいられない。顔を見るだけで吐き気がするのよ。あのしれっとした顔。我慢する理由がない」
「でもさあ、生活があるでしょ。スッパリ別れるわけにいかないよ。路頭に迷うわけでしょう」
「そうよね、家事炊事はするわ。でもあとはボツ交渉よ。これまでのような茶飲み友達でもない、別の部屋で暮らす」
「もし、本当に我慢できんくなったら、うちに来たらば? 部屋は空いてるし寛一郎もいないも同然。一緒に暮らそうよ」
「本気?」
「本気本気、女同士で住んだら鬼に金棒よ」
六
季節は初夏である。
長野県笛吹市の駅頭の足湯で観光客が楽しそうにしているのを横目に、小谷篤彦の長男小谷典亮はさっさと目的の旅館に入っていった。
女主人が木下サワの従姉妹であるらしいのだ。
彼女の実家の住所までは記録に見つけることができたのだ。総出で物置をひっくり返した。何かが分かるかどうか、可能性は低い。
ついでなので、その素人っぽい民宿に泊まることにしていた。女主人はかなりの歳であるのに、料理も手伝っていると見えた。
こういう者ですが、実は、と典亮が名刺を出してもろくに見えないらしかった。手伝いの女の子たちが読んで聞かせると、途端にまあ、と心を開いた。用事はまだ何も言わないのに。
典亮はすっかり気を良くして、木下サワの名前を出した。サワちゃんという器量好しがいたと言う。確か看護婦になってよそで働いていたが、あとはどこだったっけ、京都のどこかで結婚して、確か子供二人とかだったけどねえ。
(そうか、やはり隠し子じゃないようだな)典亮は気落ちした。女主人は、どうしてサワのことを知りたいのかと、立派な身なりの彼を見上げた。
「いえいえ、サワさんによくお世話してもらったという患者さんがいましてね。是非にもと、今際の頼みなんですよ」
そんなことで医者が出かけてくるはずもないのだが、彼女はむしろ気を良くした風で、
「市役所に行ってみましょうか、あたしだったら調べてみてくれるわよ」
と、意外に捌けた人柄になった。
翌日には、もう話が通じたようだった。老女は、善は急げ、と言いながら彼の前を丈夫な足で歩いていく。仕方ないな、という気持ちながら家族の気持ちに押されて典亮はついて行った。
こうして木下サワの婚家が佐藤であり夫は克男であることまではわかった。
サワが辞職して一年以上経った頃である。当時の住所は京都府綾部市であった。
七
「お宅って本当に火の車とは思えないよね」
「ふふ、だから全部タダ同然のセコハンだって言ってるでしょ」
新春の頃、明美が訪ねてきてその庭も見栄えもほどの良い貸家の、とりわけ家具やしつらえを見回して驚いて言ったのだ。
これも田川小夜子の才能の一つである。
あれから、しばらく田川の家に同居するうちに、小夜子の咳が止まらなくなった。ある夜、堰が切れたように小夜子は田川をののしり始めた。喉から血が出るほどに怒号した。そのまま咳となりのたうちまわるほど苦しんだが、田川は立ちすくんだように突っ立ったままであった。
翌日、だますつもりは毛頭なかった、と田川が弱気になった時、別居すること、それにかかる出費と、および月々生活費七万円を払うこと、と二人は念書を交わした。
部落の子供数人の家庭教師、近所のやもめの老人宅の片付けという収入があり、息子から三万円当座だけという援助があった。これが続けば、ということは、小夜子の健康が許す限りは、ということだが、生活保護に陥らなくて済む。
明美はそれを聞いて、ちょうどよかったというように、実は夫が帰国するという計画になったのよ、と言った。
ところがしかし、三ヶ月もすると、まず息子の援助が途切れた。彼も仕事が上手くいかないのだ。やもめ暮らしの老人が小夜子にセクハラをするようになって行くのを止めた。
そして梅雨の頃、田川が離婚届用紙を持ってきたのであった。副収入がなくなったという。
あと十年は生活費を払って欲しい小夜子は、彼の意図のきっと不穏なものであることを思い、怒りとショックで倒れそうだった。
いつもどこかに母が居るように感じている小夜子だったが、現世では、どこにも頼る存在がない自分をどう扱っていいかわからなくなった。
死ぬこと自体は恐ろしくない、死の世界は覗いたことがあり、それは解放と浄らかさを意味していた。
母に向かっての叫びは一歩間違えば実行されるかもしれない行為を含んでいた。ただ、唯一の心残りの上の孫、海斗の人生と心に汚点をつけたくなかった。
-
-
小夜子の憂き世
0










