花は散るけど
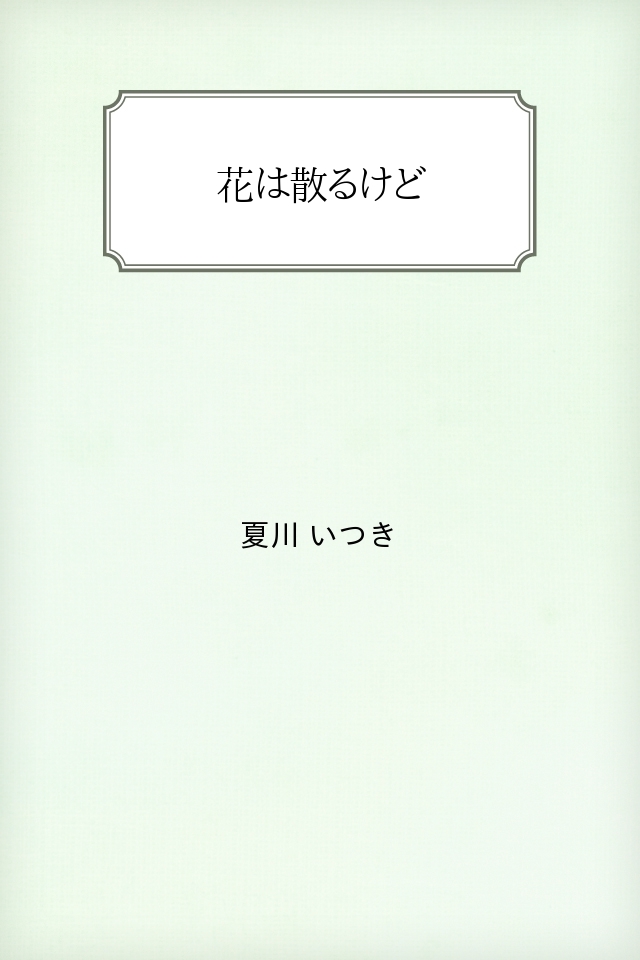
1章 9月4日( 1 / 1 )
櫻木さんについて、ぼくが知っていることを話そう。
櫻木さんは、ぼくと同じクラスの女子だ。いつも黒い髪を二つに結んでいて、何かあると、目と口をまんまるにするクセがある。
そして、なぜか、いつでも土の匂いをさせていた。
カレンダーの上では一応秋にはなったものの、まだまだ太陽は元気なまま。いまだにどこか夏休みの浮き足立った空気が漂っている朝の教室で、ぼくの前に座っている女子が話しかけてきた。それが、櫻木さんだ。
「櫻木さんは、たしか、園芸委員だったと思うよ」
昨日はほぼ半日を潰して、新学期のあたまに決めなきゃならないことが次々に決められていた。委員会の名前がひと通り黒板に書かれ、そしてその下に名乗りを上げた生徒の名前が埋められていく。そして最後まで、誰一人名乗りを上げなかったのが、園芸委員だった。
なり手がいない委員会に、欠席者の名前が書かれることは、もはやどこの学校でも暗黙のルールだと思う。最後まで残っていたせいで、少しかすれてしまった「園芸」という文字の下には「桜木」と白いチョークで書き込まれた。
(「さくらぎ」の「さくら」は、本当は「櫻」だよなあ)
運良く念願の図書委員になることができて、安心した気持ちで黒板を眺めていたぼくは、そのときふと最近読んだ、サクラが登場する昔の小説を思い出した。ずいぶん古い本だったからか、そこに登場するサクラは、ぜんぶ難しい「櫻」という漢字で書かれていた。
黒板にわざわざ難しいほうを書くのは、たしかに面倒くさい。だけど、ぼくは植物の漢字なのに貝が二つ並ぶ「櫻」という漢字をなんとなく気に入っていたから、それがなんとなく頭に引っかかった。だから、今朝まで覚えていたのだ。それが、自分の一つ前のぽっかり空いた席に座っているはずだった人の名字だってことも、一緒に。
よりによって、委員会を決める日に欠席してしまった運の悪い櫻木さんは、ぼくの言葉を聞いて目と口をまんまるにした。
「ほんとに? ありがとう!」
驚いてしまった。園芸委員の主な仕事は、月に一度、放課後に学級菜園の草抜きをさせられることだ。地味な上に、あらかた抜き終わるまで下校させてもらえないそれは、みんなから影で「強制労働」と呼ばれていて、黒板に最後まで売れ残るには充分すぎる理由だった。
そんな過酷な園芸委員に、自分がいない間に決められてしまったのに、櫻木さんの顔には暗い影は何一つ見えなかった。そんな彼女の笑顔が、ぼくにはとてもではないが信じられなかった。ついまじまじと彼女を見つめてしまったが、ぼくの視界がはっきり捉えた少し薄い背中だけだった。聞きたかったことが聞けて満足した櫻木さんは、さっさと前を向いてしまっていたのだ。
夏服の白いブラウスの上に並ぶ、二つに結んだ黒い髪が、9月の太陽の光に照らされてきらりと光った。彼女の肩が起こしたゆるい風からは、ふわりと土の匂いがした。
2章 9月16日( 1 / 1 )
それからは、一学期と変わらない、いつもどおりの授業がはじまった。
教室の浮き足立った空気が、影も形も見えなくなった頃、ぼくは図書委員としてはじめての仕事の日を迎えた。図書委員は週に一度、交替で図書室の「当番」になり、司書の先生の手伝いをするのが主な仕事だ。毎週のように近所の本屋へ通うのが習慣になっているくらい、ぼくは本が大好きだった。ここの図書室だって、入学してからほとんど毎日使っている。大好きな図書室の手伝いができるなんて、本当に中学生になってよかった。
どこかうきうきとした気持ちで、一人で図書室へ向かう。まだ朝早いせいか、教室にも廊下にも人影はほとんどなく、校舎はとても静かだった。
「あら、今日の当番さん? ずいぶん早かったのね。じゃあ、部屋のカーテンを開けてきてくれるかな」
「はいっ」
司書の先生の指示に従って、はりきって図書室のカーテンを開ける。図書室がある校舎は二階建てで、図書室の窓からは真下にある学級菜園が見渡せた。次々にカーテンを開けるたび、その上に広がるまだ青くなりきっていない朝の空がぼくの目に飛び込んでくる。
そしてついに、最後の窓のカーテンを開けたとき、学級菜園の中に人影を見つけた。そんなに大きな校舎じゃないから、二階からでも学級菜園に立つ人の顔はちゃんと見えた。あの日、園芸委員に決められてしまった、櫻木さんだ。
園芸委員の「強制労働」には、ついに早朝の水やりまで加わったのかと思った。しかし、上から見渡してみても、学級菜園にいるのは彼女ひとりのようだった。櫻木さんは、いつもと同じようにその黒い髪を二つに結っていた。大きな青いジョウロを両手に持ち、並べられたプランターの傍をゆっくりと歩いていた。
こんなに朝早くに一人で学級菜園にいるなんて、少し不思議だった。が、ぼくはそのことについてそんなに深く考えることもなく、窓から離れた。
「当番さん、ちょっとホッチキス取ってくれる? あそこの棚にあるんだけど」
「はい」
カーテンを開けることだけが、当番の仕事ではなかったからだ。
ぼくが当番としての朝の仕事を終える頃には、教室や廊下にはすっかりいつも通り騒がしくなっていた。教室に入ると、櫻木さんはすでにぼくの一つ前の席に座っていた。
特に、いつもと変わった様子もなかった。
でも、彼女の隣を通ったとき、また、かすかに土の匂いが香った。
それからぼくが図書委員の当番になって、朝早く図書室のカーテンを開けるたび、櫻木さんはいつも学級菜園でじょうろを持っていた。
もしかしたら、他の日にもそこにいたのかもしれないけど、ぼくは知らない。当番じゃない日に図書室のカーテンを開けて窓から様子を確かめたり、学級菜園の様子を見に行ったりしなかったからだ。
その頃のぼくにとって、櫻木さんがそこに立っていることは、そんなに重要なことではなかった。
なんだかわからないけど、最近よく窓から見かける。彼女に対して抱く思いといえば、その程度のものだった。
3章 10月14日( 1 / 2 )
10月半ば、ぼくたちの制服は夏服から冬服に変わった。入学式のときに、新鮮な気持ちでこのブレザーを着たことが、なんだか遠い昔の事のようだ。
ぼくはもう、図書委員の仕事にもすっかり慣れていた。当番の朝は、司書の先生に言われる前にカーテンを開けるようになり、そこから見える学級菜園に櫻木さんが立っていることも、もはや当たり前の光景だった。
ところがその日の窓から見えた櫻木さんは、少し様子が違っていた。ここ一週間くらい冬みたいに冷え込んでいたのが嘘みたいに、あったかい日差しが、学級菜園に降り注いでいる。そのやわらかい光の中で、いつも持っているじょうろではなく、白いプランターを抱えて、そして、嬉しそうに笑っていた。
図書室から学級菜園がいくら近いといっても、それでも校舎の二階にあるから、それなりに離れてはいる。そんなそれなりに離れた場所から見ていても、ああ笑ったなとわかるくらい、とくべつ大きな笑顔だった。
そんなふうに、とくべつ大きな笑顔を見せている櫻木さんが抱えたプランターには、白い花が植わっていた。ぼくは名前こそ知らなかったけど、その花を知っていた。よく道端の花壇で目にする、あの真ん中の黄色い丸が鮮やかな白い花だ。
ぼくは半分開けかけのカーテンを握ったまま、ぼんやり花のことを思い出していた。そして、ふと思った。
あの白い花は、櫻木さんにとても似合っているな、と。
それは晴れた空を見上げたときに、青いなあと思うのと同じくらい、さり気なくて単純なものだった。
だけどその数秒後には、そのおかしさに気付く。クラスメートの、しかもろくに話もしたことがない女子に対して、そんなふうに考えるなんて。どう考えたって、変だ。
目の前の、ただいつもの日常の光景に対して、そんな事を考えてしまった5秒前の自分が信じられなくて、とにかく急いで窓から離れた。
(……ぼくの頭は、どうかしてしまったんだろうか)
慌てて手から離したカーテンが、ゆらりと大きく漂ったけど、図書室の中は、普段と変わらず朝の静かな空気で満ちていた。
厚いブレザーの襟があたっている、ぼくの首のうしろだけが、ただじりじりと熱かった。
3章 10月14日( 2 / 2 )
その日の放課後、いつものように近所の本屋へ寄り道したぼくの目に、あの鮮やかな白色と黄色が飛び込んできた。あの、花だ。心臓が、一気にきゅうと縮んで、痛い。
大好きな本と触れられて嬉しいはずの場所で、こんな思いをするはめになるなんて思わなかった。普段と同じだったはずの朝を、少し恨めしく思う。
ぼくが立っているのは、文房具やポストカードが置いてあるコーナーの前だ。いつもは本に夢中だったから気づかなかったけど、そこには朝に見たあの花の写真が印刷されたポストカードが、他の花のものに混じってひっそりと並べられていた。
「ありがとうございました」
店員さんはそう言って、商品が入ったビニール袋を渡してくる。それを受け取ったぼくは本屋から出て、店の名前が印刷されたそのビニール袋から、例のポストカードだけを取り出した。……気がつくと、ぼくはそれを手に取って、買う予定だった文庫本と一緒にレジへ持って行っていたのだった。
店員さんの手によって、白くて厚い、しっかりした封筒に入れられていたそれは、思ったより軽いくせに、ひどく扱いに困った。買ってしまっておいてなんだけど、ぼくは別に植物が特別好きっていうわけではない。
やっぱりこれは、そういうのが好きなひとが持って楽しむものだと思う。
そう、櫻木さんとか。朝、あの花を見ながらあんなに笑っていたくらいだし、きっと気に入るだろう。そう考えて、とりあえず、通学用かばんの内ポケットに、その白い封筒をしまった。
そうして櫻木さんに渡そうと思いついたものはいいものの、すぐに次の問題が生まれた。
ぼくは、新学期が始まってすぐのあの日の会話以来、櫻木さんとは一度も話をしていなかったのだ。
もちろん、プリントを渡すときなんかにする必要最低限の言葉は交わしていたけど、それだけだ。図書室の窓から櫻木さんの姿を見かけるようになっただけで、ぼくと彼女の距離は少しも縮んでやしない。
ただのクラスメートの女子に、本屋で見かけて衝動買いしたポストカードを、どうやって渡せばいいのかわからない。そもそも、何て言って渡したらいいんだろう。でも、渡せないからと言って、一度でも渡そうと思ったものを、他の人へどうこうするのも気が引けた。
本屋で店員さんから受け取ったときのまま、宛名も何も書いていないただの真っ白な封筒が、この日から、ぼくのかばんの内ポケットに入れられたままになった。
-
-
花は散るけど
0










