対馬の闇Ⅳ
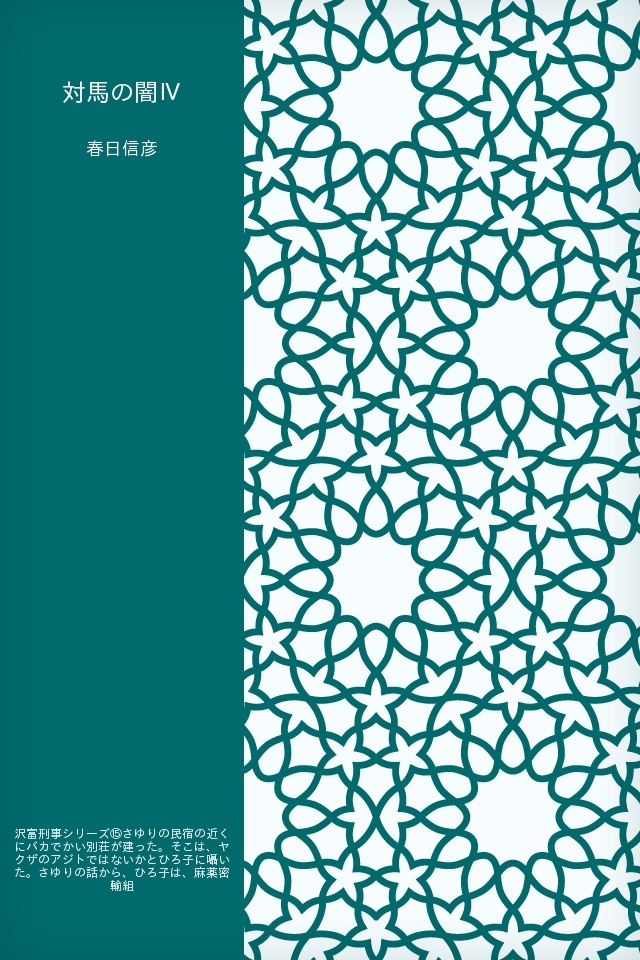
妹と後輩
10月5日(土)伊達は、クラブ・アリランの二階事務所で沢富を待っていた。というのも、瑞恵を紹介するためだった。午後8時過ぎ、事務所のドアにコツン、コツンと一定の間をおいて暗号のようなノックが2回響いた。沢富は、静かにドアを開き、笑顔を見せた。「先輩、お元気そうで、何よりです」沢富は挨拶すると小さな丸テーブルのパイプ椅子に腰かけた。「何が、お元気そうでだ。サワは、極楽トンボで、いいよな。俺は、毎日、モニターとにらめっこだ。目が痛くなる。まあ、それはいいとして、今日は、紹介したい人がいる。クラブの新人なんだが」沢富は、新人ホステスと何か打ち合わせでもする気でいるのだろうと察した。「へ~~、新人ですか。でも、ホステスとの打ち合わせは、ヤバイんじゃないですか?」
背もたれにのけぞって一度うなずいた。一呼吸置くと話し始めた。「まあ、そうなんだが、紹介したい新人は、亡くなった出口巡査長の妹だ」沢富は、出口巡査長の妹と聞いて、身を乗り出し、目を丸くした。「エ、妹ですか。マジですか?」伊達は、大きくうなずいた。「マジだ。俺も、こんな奇遇があるとは、驚いた。妹がいるとは、聞いていたが、まさか、ホステスとして、やってくるとはな~~」沢富は、あごを左手でゴシゴシとひっかくと尋ねた。「先輩、我々のことを話したんですか?それって、ヤバくないですか?たとえ、妹といえど、今回の捜査は、警察とヤクザ相手です。素人、しかも女性です。危険じゃないですか?」腕組みをした伊達が、うなずいた。「そうだ。サワの言う通り。彼女を仲間に入れるのは、非常に危険だ」
沢富は、身を乗り出した。「だったら、事件にかかわらないように忠告してください。我々だって、ヤバイんです。生きて、福岡に帰れるかどうか?」伊達は、ウ~~と大きなため息をついた。「俺も、最初は、そう考えて、事件にはかかわらないように、忠告したんだ。でもな~、彼女は、やわな女性じゃないんだ。単独で、仇を取る気なんだ。このままほっとけば、危険なことになるような気がしてな。それで、やむなく、素性を明かして、彼女の身を守ることにしたんだ。今も、悩んでいる。俺の判断は、間違っていたのか?サワ」サワもウ~~と大きなため息をついた。「そうでしたか。そんな勝気な女性でしたか。ひろ子さんみたいですね。困りましたね。後悔しても始まらない。素性をばらしたんでしょ。とにかく、彼女の身を守ってあげましょう」
伊達は、小さくうなずき話を続けた。「ところで、どうだ、何かつかめたか?そう簡単には、シッポを出すとは思えないが」しかめっ面になった沢富が返事した。「そうなんです。まったく、それらしき噂がないんです。それに、誰も、冗談一つ言わないんです。飲みに誘っても、断るんです。巡査とどうにか、約束したんですが、やってくるかどうか?」伊達は、警察内部にヤクザとつながっている人間がいるとにらんでいたが、聞き込みはかなり難航すると考えていた。「まあ、いい。焦っても、しょうがない。地道にやる以外ない。もうそろそろ、入店するはずだが」伊達は、腕時計を覗いた。同時に、階段を駆け上がってくる足音が響いてきた。コン、コンとノックの音がすると甲高い声が響いた。「みずえです」伊達は、即座に返事した。「入ってくれ」
ゆっくりとドアを開いた瑞恵は、ドアの隙間から顔をのぞかせた。そして、沢富の顔を見つめながらニコッと笑顔を作った。ちょっと間抜けな顔をした沢富を見て、瑞恵はほっとした。瑞恵は、やりてのエリート刑事と聞いていたため、偉そうにした強面の刑事を想像していた。瑞恵は、ちょっと安心したのか、笑顔を作ってお客の横にでも腰掛けるように沢富の横に腰掛けた。「始めまして、みずえです」沢富は、なれなれしい態度に、一瞬身を引いたが、即座に、あいさつした。「沢富と申します。こちらこそ」伊達が、ゴホン、ゴホン、と咳払いをして、話し始めた。「みずえさん、こちらは、北署の刑事です。我々の仲間の一人です。今日は、北署の巡査と飲む約束をしています。お相手をお願いします」瑞恵は、沢富の顔をじっと見つめうなずいた。「はい、了解です。巡査のクチを割らせるってことね」
女性刑事みたいな意気込みに、沢富は目を丸くした。「いや、まあ、そう、気負わなくて、今日が初めてですから。そう、みずえさんは、出口巡査長の妹さんだと聞きました。確かに不可解な事件でしたが、捜査は、我々刑事に任せてください。みずえさんは、知りえた情報を流してくだされば、それで結構です。お気持ちは察しますが、無茶だけは、なされないように」瑞恵は、小さくうなずいたが、口元を引き締め返事した。「はい。警察に、ご迷惑をおかけするようなことは致しません。兄の仇は、私が、きっと、取って見せます」伊達は、ちょっと青ざめてしまった。「みずえさん、この前も言ったとおり、事件は警察に任せてください。もし、出口巡査長の死が、ヤクザとかかわりがったら、とても危険です。我々の指示に従っていただかないと、みずえさんを守れなくなってしまいます。何度も言いますが、決して、単独行動はとらないように。いいですね」
沢富は、約束をした大野巡査のことが気にかかっていた。約束を忘れていないかどうか電話しようかと思ったが、彼を信じることにした。今のところ、彼からの情報が頼りだった。佐藤警部、安倍警部補、須賀巡査長らは、口裏を合わせたように、全く出口巡査長の事故死について話そうとしなかった。だが、大野巡査は、出口巡査長の死に納得がいかず、沢富の質問に快く答えていた。大野巡査にとって、出口巡査長は上対馬高校野球部の先輩であり、尊敬する先輩であった。また、彼は野球部の後輩ということで、出口巡査長にかわいがられていた。沢富がつぶやいた。「来てくれるといいんだが。大野巡査は出口巡査長の高校の後輩に当たるんです。それに、彼も、出口巡査長の死に疑問を持っているんです。彼なら、きっと、協力してくれると思っています」
伊達が、即座に口をはさんだ。「協力してくれるのは、大いに助かるが、捜査をしていることを上司に話すようなことはないだろうな。上司にヤクザの仲間がいたなら、我々の身が危ない。その点は、大丈夫なのか?」沢富は、真剣なまなざしで返事した。「彼は、口は堅いと思います。それに、出口巡査長の事故死について、捜査をしていることは、言っていません。あくまでも、参考までに、聞いていることにしています」じっと耳を傾けて話を聞いていた瑞恵は、大野と聞いて1年先輩の野球部の大野ではないかと思った。「大野巡査は、上対馬高校野球部の大野さんですか?その方だったら、知っています。私の1年先輩にあたります」伊達と沢富は、申し合わせたように瑞恵を見つめた。
沢富は、大きくうなずいた。「大野巡査は、上対馬高校野球部で、同じ野球部の先輩だった出口巡査長を尊敬していました。みずえさんも上対馬高校なんですか?」瑞恵は、笑顔でうなずいた。「はい、私は、テニス部でしたが、大野先輩は、野球部のエースで、イケメンだったので、女子にチョ~人気があったの。大野先輩に会えるんですか、ア~~ワクワクしちゃうな~~」情報をとるには、都合のいい人間関係だとは思ったが、沢富は、瑞恵の警戒心の無さが気にかかった。瑞恵と大野巡査は、同じ上対馬高校卒ということであれば、情報は取りやすくなる。だが、瑞恵が安易にこちらの情報を流してしまうということも考えられる。瑞恵を信用してもいいものか、沢富は不安になってきた。「そうでしたか。大野巡査とは、話が弾みそうですね。でも、軽はずみな言動は、慎んでください。今回の捜査は、極秘捜査ですから」
沢富は、腕時計の時刻を確認すると伊達に話しかけた。「もうそろそろやってくる時間です。みずえさん、行きますか」伊達は、うなずき、瑞恵に声をかけた。「あまり気負わず、気楽に、いつものようにやってくれ」瑞恵は、うなずくと、沢富の左腕に手をまわした。「はい。しっかり、サービスてまいります。マスター」二人は階段を降りると瑞恵は一足先にクラブに入っていった。沢富は、大野巡査がやってくるのを入り口で待つことにした。9時を少し過ぎたころ、黄色のヤマネコタクシーが入り口前に止まった。しばらく待っていると心細そうな表情の大野巡査が後部座席から出てきた。約束通りきてくれたとほっとした。沢富は、笑顔で歓迎した。「来てくれたか。今日は、大いに飲もうじゃないか。好きなだけ飲んでくれ」大野巡査の背中を押すようにして、沢富はクラブに入っていった。
沢富がドアを開けると瑞恵の笑顔に歓迎された。「お待ちしていました。どうぞこちらへ」二人は右奥のテーブルに案内された。大野巡査が腰掛けると右横に瑞恵が腰掛けた。いつもならば、沢富にもホステスがつくのだったが、今回は、沢富だけが大野巡査の前に腰掛けた。まずは、大野巡査を酔わせ、誘導尋問をすることにしていた。大野巡査は、瑞恵とは面識がないようで、顔をこわばらせ固まっていた。たとえ、高校時代に面識があったとしても、化粧をした瑞恵に気づくとは思えなかった。彼は、F大学卒業後、警察官になっている。年齢は、25歳。品行方正で上司の評価はまずまず。趣味は、草野球、ヤマネコファイターズのエース。本人が言うには、彼女は、現在のところいないらしい。彼は、たまに、居酒屋には同僚と行くようだが、クラブは一度も行ったことがないと言っていた。ほとんどのクラブは、韓国人観光客のためにあるようなものだとも言っていた。どちらかというとお酒には弱いらしい。
三人が水割りを手に取るとカチンと軽くグラスを合わせた。大野巡査は、いつも飲むのはビールということで、ウイスキーはめったに飲まないということだった。そのためか、ほんの少し飲むだけで、おいしそうな表情を見せなかった。沢富は、気を使って声をかけた。「水割りより、ビールが良ければ、まずは、ビールにしますか?」大野巡査は、気の毒そうな顔つきになって、苦笑いしながら返事した。「いや、ウイスキーも焼酎もなんでも飲みます。ちょっと、緊張しちゃって」どうも、美人の瑞恵に緊張しているようだった。大野巡査は、どちらかというと饒舌で冗談も通じるタイプだった。プロ野球は、ソフトバンクホークスのファンで、野球の話になると話が尽きなかった。彼もピッチャーであったためか、特に、千賀のファンで、千賀がいれば、優勝間違いなしとまで豪語していた。学生時代は、試合観戦だけでなく、ヤフオクドームでバイトしていたとのこと。
-
-
対馬の闇Ⅳ
0










