耄碌
-
耄碌は200円の有料書籍です。
書籍を購入することで全てのページを読めるようになります。
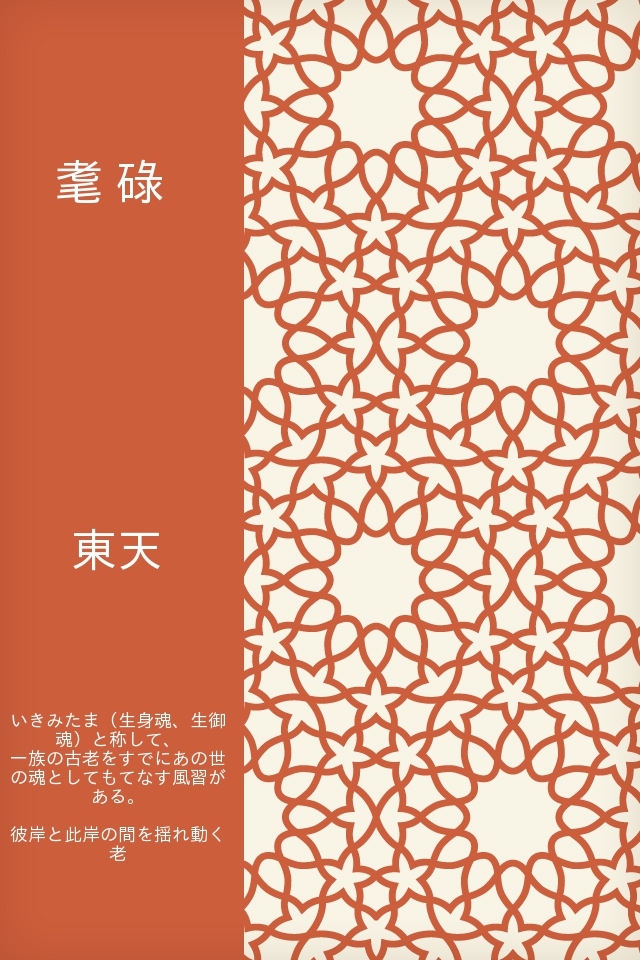
(一)( 1 / 1 )
幼心
(一)
寝床についていると突然脳がぐらぐら回る、ごっそり掴まれて振り回されているような、かなり強烈な動きだが、嫌な感じではない。
すると私は異なる周波数を感知して、彼らの存在がわかり交感することができる。
薫がベッドのふちに腰かけて姉である私を見ている。男か女か、子供か大人か、それを反映することはできないらしい。でも私にはわかる。この子は父に似ている。眉が太く眼が丸い、いわゆる縄文風。私の髪に混ざっている一束の美しい白髪をなでてくれる。
「へ~い、薫だね、おはよう。やっぱり会えた。このごろ、なんだか思われてならなくて。ここに居たんだ。いつも気づかなくてごめんね」
薫がうなづいてにっこりするのが見える。そこへ足音もたてずに姿が近づいた。
「あ、忍かしら、元気? 元気ていうのも変だけど、ふふ」
忍は時には大きい体格のようにも、ふっくらとした幼児のようにも見える。弟の和夫に似ている。忍が私を起こそうとするのに任せながら、私は尋ねた。
「和夫兄さんは何してるのかな。よそに行ってるの」
忍は色白の顔でうなづく。
「孫を見に行ってるよ」
不思議な音波に乗って声が聞こえる。
「そうよね、たくさん心残りがあるから」
私の弟はもういわゆる鬼籍にいる。まだまだやることがこの世にたくさんあった年齢なのに、すべてを手放した。もう十分だよとでも判断されたのだろうか。
スリッパも履き忘れ、私は薫と忍と前後しながら、寝室からキッチンへ廊下を進んだ。彼らの気配が花のように、そよ風のようにすぐそばにある。
「みんな~、私のはらから、どこで遊んでるの。久しぶりに一緒にブラックファーストしようよ」
桂と礼、5人目は翠、呼びかける間もあらばこそ、すでに私の両肩と、頭の上に3つの波動がくっきりと浮かんだ。五人もの名前を覚えるのは普段はできないのだが、彼らの姿全体がその名前そのもののようにも見えるので、忘れようがない。
私の見える光線の幅は尋常ならば七色の範囲なのだが、今日のような日にはかれらの特別に細かい周波数を感じる。ただ集中しさえすれば、桂の巴旦杏のような瞳がくっきりと見え、黒髪が柔らかに波打っているのを、触れば感じるのだ。
礼はふだんは恥ずかしがりのように思える。でも今日は私の左肩に安らってそのあるかなきかに柔らかいほほをすりよせてきた。遺伝子的には男女は決定しているのだが、私に感得できるかぎりでは区別がない。二歳くらいの幼い子供の匂いを思わせる。翠の小さな両足が額からぶらぶらしているのをかきわけながら、私は姉らしく朝食の支度をした。
「洋食でいいかい?」
私が珈琲をつくりながら尋ねると、五人は鈴のように笑った。そうだ、かれらは食べるまねをするだけだ。かわいらしい服を身に着けているかのようにふるまうのだ。
母が喜びにうちふるえながら迎え入れた父の精子たち、父が命の喜びに達したときに自由を得て卵子まで走りだした。ついに生まれ得なかったときに両親がいかに苦心して5人もの中性的な名前を考えたかが想像できる。目の前にいる姉と兄のように、かわいらしい子供でありえたはずと思って悲しみに両の拳を震わしたことだろう。
しかしながら、いつのまにか長い間、半世紀以上もだれも五人のことに触れなかった。私にしても知ったのが三十年前であった。それからも無視して過ごしていたのだ。この子たちには、人と知り合う機会もなかったから、両親以外にまず近しいのは血のつながるはらからであったのに。
こんな風に共に彼らと過ごすようになったのは、私が枯れ木に一枚のこった朽ち葉のような寡婦になって、一人暮らしになって以来である。頭がおかしいとも言う人もいるだろうが、何事にも正常に反応できる、少しぜんまいが緩んで速度が遅いだけ。耳の中に騒がしい風がいつも鳴っているので、聞き間違ったり、聞き返したりするのは八十歳にちかくなれば普通の現象として。
彼らは音楽が好きだ。色も好きだ。どちらも波動なのだから彼らが認識して当たり前なのだ。私は専門家ではないが、楽器の音や、和音やあるいは不協和音、ともかく空気の振動が同じくたのしい。お琴でチリチリと弾くと緑色のうす布がひらりと動く。するとそれは翠だった。全部の弦を琴爪でかきならすと、青から赤までのあらゆる紫色が楽しそうにはねる。それは桂と礼と薫が爪先立ちでくるくるくるくる、そこらを回っているからだった。エレクトーンでいろいろな楽器の音を聞かせる。意外にも忍は打楽器が気に入っている。その振動に体を任せ部屋中をはねまわった。
どんなに楽しく愛らしいか、あまりに愛らしくて涙が流れる。
私はもっと待っていた。ひそかに卵をあたためる鶏のように待っていた。
このチャンネルをただしく調整して待っていれば、きっともっと楽しくなるはずだ、それを、双葉からみるみる茎と葉と、蔓が伸びていくのと同じように待っていた。
先夜、夢を見た。いつもの夢では、私は永遠の放浪者であった。
本当の家を探していた。よくどこかの家にいるのだが、そこが間違いで出て行かなくてはならない。しかしとらわれている訳でもないらしいのに、なかなか出て行くことが出来ない。外には道があった。あの道を歩いて本当の家に帰らなくては。家族が待っているのに。
そしてその日、ついに本当の家に私はいた。見つけたとわかっていた。卵から孵ったひなが、苦しい旅の果てについに親の住む家を見つけたようだった。
家の中は薄暗かった。私が部屋に座っていると、その大きな果てしも無く広い部屋へ人々が入ってきた。澄んだお鈴の音が、幾重にも打ち鳴らされている。私の老いた耳にも美しく生き生きと響き渡り、空気にはまた色味がついた。
はたして、五人の小さな姿が私に寄り添った。人々も私の本当の家の中で、回廊の柱のように、私を立ったまま取り囲み、静かにしていた。しかもどことなく心が波だっているのが伝わってきた。
ふと、あれ、自分はもうこのまま死んじゃうのかしら、と風のように思った。
そうではあるまい。私の世界がまたひろがったのだ。その中に薫に似た顔がある。私の祖父と私の父である。と思った瞬間には、薫が彼らのそばにあらわれて、三つの同じ顔で私に微笑んだ。祖父の荒垣信衛門が五歳の私のほおにほおずりしたとき、私は「いたかやい」と照れた。そのときはじめて彼の愛情を感じたからだ。私は急性盲腸炎(当時はこう呼ばれた)になって、手術され入院していたのだ。回虫がいる時代だったので、虫下しなるものを飲まされたところ、虫が苦しがって虫垂に入り込んだのだ。
冬の夜だった。大八車に寝かされて、星を見ながら近くの医院へ運ばれた。その時はもう痛みを感じなかったから、虫は静かにして、あるいは死んでいたかもしれない。いずれにしろ開腹手術となった。私の父がそのさまを見ていることになった。母は膝が立たず外で待っていた。
別の祖父を、私は探した。母方の祖父母もいるのだろうか。少しうしろにそれとわかる瘦身の男の姿があり、天然パーマで顔立ちの良い老婆がいた。祖母は二十年間も寝たきりの祖父を看護したのだ。ひとりになると、かえって行き場所がなかったのは気の毒だった。長男の家で、ある夜看取られずに旅立った。私の大好きな心のふるさとの住人である。
どんなにたくさんの人を見送ったことだろう。叔父や叔母、ほとんどが亡くなった。その子供たちも幾人も。こうして二十世紀から二十一世紀へと、さらに私の孫も二十二世紀を迎えるのだろう。もし地球がまだ住める場所だったとして。あるいは、先進国の屋台骨がまだ老齢人口を支えることができていたとして。
私に優しかった叔母の顔、遊び友達だった従兄弟、私の長男、もちろん弟もあいかわらず大きく、にかっとした笑い顔でそこにいた。
私は、どうぞご自由にご歓談ください、お久しぶりです。こうしてお会いするとは思ってもいませんでした。みなさん、お幸せそうでなによりです、と思った。
彼らは一応に頭を動かした。同じような動きだが少しずつ違う、大洋から波の寄せるような感じだ。私という砂浜に懐かしい愛しい人々が心を寄せてきてくれた。父がいる、母がいる。最愛の息子もいる。夕顔のような美しい面輪は死んだ時のまま、永遠に清らかな知的な若者だった。
私はたまらず、彼を抱きしめた。生きた身体ではないが、ある重さが感じられた、存在の重さが。彼らにも質量があるようだった。わずかな質量、飛び回ることができるほどの。
「よく頑張ったね、充。母さんの誇らしい息子。これからたくさん話をしようね」
充の慎ましい微笑を私はいつまでも見つめた。言葉を交わさずとも理解し合えるのがわかる。ふとみると、充は猫を胸に抱いていた。それは一時えさを与えていたグレーだった。その周囲にも何匹か、それぞれ個性を持つ猫が数匹漂っていた。そうか、私の頭の中に保存されているすべてを、こうしてまるで霊ででもあるかのように彼らと交信しているのだな。今日の悟りであった。八十年生きていて、そんな簡単なことがやっと肚にすとんとおちていったりするものだ。わかりそうな事でも、脳神経がつながらない限り決して理解しないらしかった。
しかし、ここに集うものが私の記憶の中の幻影であるとすれば、私の印象やわたしの考えを通してのみかれらの考えを推測するにすぎない、かれら個人の本当の思いを聞くことはできないという理屈になる。私は悪夢になりかけた夢の中でのように、答えのない苦しい質問をつづけた。話をすればあるいはかれらの真正な声が聞けるのかも知れなかった。
しかし、私のような世慣れぬ老女に出来ることではないような気がする。
助けを求めるのではないが、かれらを、ぐるりとその顔を見渡してみた。
すると、かれらの姿は私の思い出の時代に応じて、若くなったり年老いたり変幻するのだった。どこかに、かれらの本性を潜ませながら。そのはずだった。
私に関する彼らの好意はたしかにわかる、と言わざるを得ない。幻影の父はときどき怒っていた。私には心当たりがある。
母はどこに、と思うや父の大きな肩の後ろによりかかるように、数年前逝った母の顔が笑って、私にありがとう、と口を動かした。嬉しかった。父はもう笑っていた。
友人の一団もいた。本気で本心を語り合った友人、憧れていた友人、十代で命を絶った友人、さまざまに忘れられない人々が。
(二)( 1 / 1 )
怨恨
(二)
突然、不気味な轟を聞いた。わたしの家の無限の広間も一瞬ざわめいた。
はるか彼方、本当はここに属さないものの影がふたつ、ぼんやりとしかし禍々しく揺らいでいた。
ひとつは私の亡き夫だ。四十九日もたっていない。かれは首根っこをつかまれて、ゆらゆらしている。掴んでいるのは小さな女の姿だが、すぐにわかった。怒りと恨みにうん脹れて巨大化している。その手が夫の影を動かしていた。
「どうだ、あんたの人生は滅茶苦茶だっただろう、この男のおかげで。こいつの人生もガラクタだったろう。そのはずさ、あたしがこいつに無念の念を送っていたのだから。復讐の念を。アハハ」
その長い波長がわたしに達したときには、女の姿は夫の姿もろとも、もう見えなくなっていた。おそらく最近死んだのだろう。恨みの深さのためにこうして一瞬、私の家に入り込んできたのだ。
しかし、誰だ。夫をどうして操っていたなどと。その姿はまったく見通せなかなった。
父がそばにいる。そうだった、私は父に深く謝らなければならない。
その人柄の優しさといい、娘への愛情といい父は本当に完璧だったのに、私は自己中心的にしか考えられず、というか、本能に振り回されて父をいつも落胆させた。ふさわしくない男ばかり追いかけて迷惑ばかりかけ、父のメンツもつぶした。それでもいつもそばに居てくれた。
私の長男があんなに早く彼岸にあらわれたとき、きっと悲しく思ったことだろう。私がここまで愚かだとは思わなかっただろう。私は父の眼を見つめ、心を大きく開いた。父はそれを受け入れてくれた。これからもずっと守り導くからね、と聞こえた。母は父のそばに立ち、安心した顔で、ながいことありがとう、と介護期間の礼を言う。父もそれには笑い顔をみせた。
ああ、 よかった、と私の心が花咲くように吐息をもらした。
弟の波動がわかった。五つの水子たちが彼にまとわりついている。
昔ながらに「和夫ちゃん」と私は彼に呼びかける。
「危篤になっていたときね、私がね、みんなここに居るからね、安心してねって言ったら、とても大きな声でオウと返事したでしょ。覚えてる?」
弟はにかっと笑った。どうしてか、大声が出せたんだよ、と聞こえた。
「残念ながらちょっと早かったけど、結局さあ、和夫ちゃん、強運だったよ。努力もしたでしょうけど。いい伴侶を見つけて子供はしっかり育って、ねえ、立派だった。十分な人生だったね」
私がそう言ったのか、たんに思ったのか。いずれにしろ、最も近い一家が丸くそろって立ち並んで揺れていた。
そこに、もうひとつの、いつも私の心に生きている長男の充が再び来て、ふわりとその優しい万全の配慮の網を私の回りにかけてくれた。
私は、彼の方を向き、これまで何故か夢を見ることも叶わず、いつもそれを願っていたのにやっとこうして出会いの機会をもてた感激ひとしおで、充の死の後、どんなにひどいことが世界に私に起こったか、話した。
知らなかったのは父も同じだったので、父にか充にか分からないような感じで、私は話した。話したのではなく、話すまでもなかったのだが。
父と充はまるで同じ人物ででもあるかのように、唱和して私を慰め、守ってくれていたのだ。それがはっきりとわかった。
ふたりの魂は百合の樹の花柄が裸の樹となっても永遠に枝先に天を向いて合掌しているように、ほの赤く、ほの緑に白かった。
私は、なにひとつなし得ず、何をしても失敗し、毎日が苦しく我慢するしかなかった日々のことを訴えたいと思った。するともうふたりはふんわりと頷いて、白百合の香りを漂わせた。
それから、子供の時から大好きだった父の弟、私の叔父もみつけた。
私に取っては子供心にもハンサムで優しい人柄であった。彼が亡くなる少し前、二十年ぶりにある葬儀で、見回していた私の眼に、世にも見目麗しい男の眼がみえた。あまりに美しく整っていて、懐かしく眼をはずすこともできなかった。
すると、あさこじゃなかと? と向こうから声をかけてきた。
あ、健二伯父さん、とやっとわかった。今、彼は遠くに遠慮がちに立っていたが、その眼だけはいつも私と彼との美の遺伝子的親和力を発信していた。
赤ん坊の時から父代わりだった母方の祖父もどうしても話したい人であった。私が知っている、瘦身のがんこそうな眼の鋭い老人だ。坊主頭で足にはゲートルを巻いている。あるいは、ふと私に強い言葉を使ってしまって、私がしょんぼりすると、皺の中のいたずらっぽい目つきで私を笑わせようと覗き込んだその視線とか、私の思いのままに祖父は姿を変えた。
「おじいちゃんが間もなく死ぬとわかったとき、本当に悲しかったんだよ。おじいちゃんはそんな私の顔を見て、どうした、泣いているようにみえるが、と言ったの。あのとき、私はもう二十四歳にもなっていたけど、心は子供とおなじだったんだよ」
「よかじゃっと。わかっとっと。おまいはむぞか子じゃった、みんなを幸せにしっくれたっと。敗戦のころのみんなの希望のごっじゃったと」
私は赤ん坊になり、祖父のふところに入っていたり、縁側で賢そうに議論していた姿になっていたと思う。
しかし、次第にさきほどちら、と接触したふたつの影が気になってきた。彼らは居ない。
頭の中の渦はゆるゆると穏やかになり、記憶の中の姿が薄れて、かすかな和音のようなお鈴の最後の響きのような、虹の色へと収れんするような、現実の感覚へともどるのがわかった。
(三)( 1 / 1 )
迷妄
(三)
翌朝は、普通の朝だった。ベッドから降りて、書斎に行き、しかし思い立って珈琲を作りに行く。
とうとう、人生でたったの一度も私のために珈琲を作ってくれる人は居なかったなあ、といまさらのように嘆きつつ。
ドリップする雫をみつめていると、夫の言動がますます謎で、不可解で自虐的とも思われてくる。
死ぬ間際には、これまで見たこともないほど立派であった。死をしっかりと見つめながら、刻々と私に説明してくれた。自分という存在がじわじわと薄まって行き、宇宙の彼方まで薄まって行くのだ、と。何度も呼吸困難に陥り、また戻ってきたのだが、ついにもう戻ってこなかった。
その時には、私は本気で悲しんだ。本当はこんなに立派な夫であったのにそれを見通すことが出来なかったと自分を責め、失った尊い者を惜しんだ。
しかし、日常的に思い出すのはどうしても理解不能、不条理そのものの彼の言動であった。
お前を 愛している、絶対に分かれたくない、というのがいくらか本当であるのなら、なぜあそこまで私が嫌うようなことばかりしでくれたのだろう、私にすがっていながら、私をいつも突き飛ばした、ますます激しく。
私が耐えられなくなって去るのを待っているのかとも思った。なぜもっと近づいて愛を感じさせてくれなかったのだろう。
ちがう、結局は愛はなかった、別の理由があったのだ、おそらく私を苦しめること。苦しめがいがあったことだろう。なぜなら私は本当に強かった。ある意味びくともせずに、どんどん彼から離れていっただけだ。決して壊れなかった。
私を壊そうとして、夫は早くから無茶をやった。健康に悪いことが好きで。健康を案じることを馬鹿にして。それが功を奏して早くから廃人になった。
寝たきりならまだしも、もっと無茶を始めた。私に手伝わせて。私をもっと束縛するために。
あるいは、私の一人暮らしの母を近くに呼び寄せようとしきりに提案した。もちろん、私はすぐに感づいた、きっと私をもっと束縛し自由を奪うためだと。母の看病のために家を留守にすることなどできないように。
しかし、実際はもっと巧妙だった。私が母と過ごす時間を、夫は自分に不利な時間として私を責める理由とした。頭のいいやつだった。
ただそんなことに使ってばかりで、才能をムダにした。それも私には腹立たしいことだった。せめて自分の仕事くらいきちんと果たしてくれたらまだ尊敬する余地が生じたことだろう。
そのすべての間に、彼は他の人を批判し罵り、軽蔑し、悪口雑言をはいた。私の前で。私に向かって。そのせいで、三男は対人恐怖症になったほどだ。父親の描く世間の様子は悪意に満ちていた、迫害と危険と嘘にみちていた。
その全ての間に、彼は潔癖性だった。
自分の手足を洗うことのみに時間をかけ、手と爪の細胞を破壊して、つまりなにひとつ手を使えなくなった。それが何を意味するか、私の仕事が増えたのである。片付けることもできない、つまり彼の回りはおのずとゴミ屋敷になっていく。
その中に通り道を確保し、少しの自分の場所を見つけて料理と洗濯をした。
さらに彼は経済的にも私を苦しめた。週の半分をパートにでかける私を彼は許した。それはしてよいのだった。そのお金で私はいま得ている個人年金を払った。それはしてよいのだった。
かれが会社からかすめ取るお金は、巧妙に、私が触れないように貯蓄され、おまけに遺書には、私には当座の生活費としてのみ使ってよいと書かれてある。
私が待っていたのは自由になる日であった。
あと五年、あと五年と医者は宣告したがそのたびにクリアして行った。
自由を得たとき、私はもう八十歳になろうとしていた。
だれもが離婚を勧めた。しかしいわゆる家庭内暴力の犠牲者である私にはとても恐ろしくてできるものではなかった。きっとストーカー殺人となるだろうと信じていた。それより目の前で観察している方がましだ。
夫の私への悪行を述べ終わることはとても出来ない。彼は女装を好み、私に性を強制した。長男をむざむざ自死させた。
もし、閻魔大王がいて、私に尋ねたら答えよう。
よく我慢しました。怖かったので自分を強く保って我慢しました。彼は私を壊すことに全力を用い、私はその中でも決して自分の出来ることを諦めませんでした。たとえそれが最も短い俳句という文芸であれ、スケッチという手早い業であれ。メールだけの友情であれ。
その間に、楽しい旅行など一度もなく、観光や文化的参加もしなかった。
そうです、彼が成功したのは私の出来たはずのことを妨げたこと、今や私は自分が何者でありえたのかまったくわからない、のこりの滓でいきているのですから。これこそ彼の成し遂げたことです。
閻魔大王様、なぜでしょうか。
こんな関係を何十年も耐えたのは愚かだったのでしょうか。
それとも私に何か利得があったのでしょうか。私は彼のせいにして自分の能力のなさあるいは家事を嫌いだということを見ないことにしたとでも。彼を怠ける理由にしたとでも。
そして彼も私を怠ける理由にしたとでも。
地獄、生き地獄、一種の。本当のではないけれども。愚かさとしか言いようがない。父が嘆くはずだ。それでもたくさんの愛が私を支えてくれていたのだ、それは確かだ。
しかし、あの幻は何を意味していたのか。誰だ。あの女は。復讐といっていた。夫に念を送って操り、私を破滅させようとした。夫をも? ということは夫が捨てた女たちのひとりか。その集団か。集団、、、待ってよ、そうだあの娘、彼の影響でインドのカルトに入団してそこで指導者にまでなったというあの娘。結婚後にも電話してきて、夫をそれに誘っていた。彼女ならそんなことも可能かもしれない。
夫の自慢話をうけたまわって聴くのはむしろ良い方だった。
多分彼が二十歳頃、高校生ほどの木下梓と知り合った。
彼好みの黒髪の長い、個性的な顔立ちをしていたという。梓は処女だったので、彼は徐々に処女膜を指で押し広げていき、出血などということにならないよう気を使って時をかけた。
性的な関係はうまくスタートした。年齢の差もあったので、梓が彼に依存するようになったのも当然であり、結婚へと押し流されていきそうにもなっていた。しかし当時の彼には結婚などは荷が重かった。
ただ一度の好奇心から、彼はなにかのドラッグを手に入れた。現実的な彼は普通そんなものには近づかないのだが、すべての条件が整ったのだろう。
ともかくセックスにおける興奮の高さといったら形容できないほどだったという。ただ、やっと薬効が切れた時の空虚感もまた形容できないほど嫌悪すべきものだったという。
ところが、梓はすっかりそれを忘れられなくなった。何度も彼にせがんだが、頑として拒絶された。
そうするうちに亀裂が大きくなって行き、彼が別れを告げた。ヒッピー時代の潮流というのだろうか、梓はいつのまにかインドに渡り、麻薬をつかったセックスカルトの一員となっていた。黄色の衣服を着た一団である。教祖自身はアメリカに逃亡して残されたのは大量の廃人たちであった。しかし梓は何故かそれを乗り越え、自身ある種の指導者となって、脳内麻薬による人間解放、という説を広めていたのだった。
梓が意気揚々として、虎視眈々として、かってのセックスの先生に誘いの電話をしたとき、驚くべきことに結婚していると聞く。あるいはその時期すでに梓の生活が狂い始めていたのかもしれない。尋常でなくなっていたのかもしれない。
そんな成り行きから、梓がなにかの秘法をつかって、夫を狙い撃ちにした可能性は他の誰よりもある。夫の様子には、結婚の最初はそれ以後ほど謎もなく、真面目で理性的で現実主義、清潔好き、完璧主義というポジティブな状態にとどまっていたのだから。
あ、そう言えば。もうひとつの存在が思い出された。私の過去から私を恨んでいるかもしれない人物が突然思い出された。それも同じく宗教がらみである。そうでなくては誰がそこまで夫を変化させ、私を苦しめる魔法のような力を使えるだろう。
立木篤はいつの間にか、私の近くに居て、非常に真面目に、世を動かすような大きなことをしたい、一緒に進もうと議論をふっかけてくる男であった。
私に恋人が出来たとき、君はピンクのセーターでひっかけたのだ、と私を非難した。その意味すらわからない私であったのだ。
数年後、東京に消えていた篤がまたあらわれた。以前とはまったく感じが違う。良い感じに変わっていた。当時若者をその言葉がどことなく引き付けていたのだ。もっと正しい、もっと本物が世の中にあるはずだと思わせたのだ。超理論研究会というその言葉が。
主に学生をターゲットにしたのは、後世の麻原彰晃と同じだったが、そこにも真面目故に誘われてきた若者たちが共同生活をしていた。私はまさにそんなものに憧れていた。何故だろう、普通でない別の有意義な生き方を探していたからだ。
しかもそこは、男女一緒に暮らしながら絶対禁止の世界であった。交際は愚か、心で恋することも許されなかったのだ。今から思えばよくぞ無事に戻ってこられたと思うが、当時はなにか危険があるとも思わなかった。それは結局キリスト教の一派であり、聖書を研究し現実世界へ対応するための教義を習うところであったのだ。
結局、私は俗物過ぎた。あるいは聖書と現実をあまりに摺り合わせるところを納得しがたかった。ふと我に返って連絡を絶った。それは正しかったと思う。
しかし、篤はどうだったか。そこの教義によれば、純潔をお互いに捧げ合い、永遠に愛し合う男女は結婚を許され祝福されるのだ。それはしかし簡単な過程ではなかった。もし篤がそれを全う出来なかったら、八つ当たりで私を呪ったかもしれない。影は女だったので、篤に関わる存在と思われる。それどころか、そうだ、そもそも逃げ出した私には救いはなく、悪魔の手に堕ちるしかないと言われていた。
ずいぶんと愚かしい収支計算ではある。
そう考えると、私にはもっとひどい人生もありえたわけだ。
そう考えると、また同じ伝だが、もっとひどい人生から、だれか私を必死で助けることが出来た人も居るはずだ。
そう言えば、あれか。三たび私のもうろくした頭脳が光った。
宗教関係というなら、神道系の古来の宗派、天理教、大本教の系譜にいくつかの小団体があり、父は老年になってからそこへたどり着いていた。
そこでは天照大神とか、天皇家とかとは別に、真の自分、実相という概念を中心にしていた。プラトンのイデア論を拝借したかと見える。
曰く、この世界は影に過ぎない、歪んでいる。しかしそれはただの影であり、その実像は黄金の輝きと鋼鉄の強さをそなえた完璧な存在である。神そのものである。無数の神がおわします。燦然たる鉄壁の実相の世界を実観すれば、即座にそれが顕現する。
身は泥まみれ、傷だらけであってもたいしたことではない。実相は光り輝いたままであり、心が揺らがなければ即実相がこの世に顕現することになるはずだ。
私もその祈りの形式をまねた。苦しくてたまらずまねて自分に言い聞かせ、唱えた。
夫は悪人ではない、私を苦しめてもいない。その実相は光り輝いている、云々。
そうだったなあ、それによって私が生き延びてきたことを最近は、耄碌して忘れていた。それで彼も、あと五年と何度も言われながら生き延びていたのだろう。何という矛盾だ。
あ、そうだ、彼の親族も彼の幸せを祈っていただろう。そこにどんな強力な祈り手がいたかはつまびらかではないが。ともかく親族には戦死が多かった。
そして、かの水子たち、かれらの実相もあそこに永代供養してある。
そうだった。あの子たちはこの秘跡を私に教えようとやってきたのか。いつもいたのだが、初めて私の脳波に関与してきたのだ。
(四)( 1 / 1 )
生と死を生きる
(四)
自分でも、毎日が食べたか飲んだか、わからない。起きたのか寝たままだったのか。
このままで死ぬのだろうか。あっちへ行けるのなら全然悪くないように思える。
それにしても、私はまた夫を許す理由をみつけてしまったのだろうか。悪意に操られていたと。耄碌した頭から生まれた妄想に違いないあの存在たち、かれらの力をもう信用してしまったとでも。
今日までの科学の考え方に従えば、物理的化学的に生命現象は機械的に生成すると説明できるだろう。そこに偶然の運不運はあるが、とりあえず有機体が死滅すると、あとにはその物理的科学的物質が灰となって残る。エネルギーは放出されてまた別の物質に化するだろう。頭脳が蓄えた記憶、思い、知識、すべて基盤を失う。それらがばらばらなエネルギーとなっては、もうどうしようもないことだろう。そこに摩訶不思議な神と魂を持ち出す以外には。つまり存在の永続性を。コンタクトの永続性を。
おおよそこれで、私の壮大なスピリチュアルな世界の全貌と働きが理解されてきた。ここではその真偽は問題ではなく、それでこの老いた脳が、幼い日ふるさとで父母を信頼し愛したその時のように、満足し安心できればそれでいいのだ。いやそれ以上の大きな愛の輪を信じられたらそれに超したことはない。悪さえも本源的なものではないとして。
「でもねえ、私や夫への恨みを持ち続けた人がいるとして」
私が頭を傾けると、翠がそこにいて香しい楠のような薫りをふりまいた。
「実相完全円満」
麗しい音波があたりに広がった。五人がそろって歌うかのように口を開け閉めしている。
「でもお姉さんにも非があったんでしょう? 恨まれるような?」
礼がそう言いながら、私の人差し指をぎゅっと握っている。孫のゆうりがよくそんな風に握った。
「確かに。私だって人を平気で苦しめた、あるいは苦しんでいると知っているのにほっておいた。恨まれて当たり前だわね」
腰の辺りの服に、薫と桂がしがみついている。息子たちがそんな風にまとわりついていた。子供の純な愛情というものの痛ましさが胸をつらぬいた。彼らは生存のために親を愛し必要とする、たとえそんな理由があるにせよ、美しく悲しい純情である。私もそんな風に自分の両親を愛し信じて、たよって生きていたのだ。
すると、恐らく昔からありながら、今の世でも隠されたままでいる中にもたまたま報道されるにいたった子供の虐待事件についての苦痛が私をとりこにしそうになった。
「でも、独裁者やサディストや、それは本源的な悪でしょうに」
五人の弟妹は、複雑な音波をばらまきながら、くるくる回転している。かれらとてそんな偶然か必然かわかりもしないことはくるくるするしかないのらしい。現に彼らが何故生まれなかったのか、そこから疑問は生じる。壮大なシステムの当然の結果として、なのかあるいは、そのシステムは不完全なものとしてすでに最高権力者から見捨てられてでもいるのだろうか。そのほうがつじつまが合うと私には見えて仕方がない。
「かもしれない、ちがうかもしれない」
「でもわからない、わからないなら」
「システムの意図を探すのじゃなく、システムをすみずみまで知って、うまく使う智慧だね」
「必要なのはそれ、システムをうまく使うのが人間の頭脳に与えられた課題」
「生と死、心の安定の人間的問題はお姉さんにはもう解けたでしょ」
「死は、生をもっと拡大してくれるんでしょ、そうらしいよね」
「システムを理解し、保管し万全に働くようにって、人間の課題」
「はあ、あんたたち五人でそう言うのね。そうかもね、でもまだまだ遠いじゃない。もう文明発祥から五千年は経っているのに、進歩がないのじゃない」
五人は声を揃え、同じ色の波長に染まりながら歌った。
「人間、がんばれ、もっと追求。社会の悪を苦しみを無くすための方途を研究するんだよ」
「かみさまに頼るんじゃなくてね、そのための知性なんだから理想の地球を作るのが役目だよ」
「そうなの!! 確かに知識人ほどもう人間を諦めているところがあるわねえ。そこを必死で各自が考えて、それを議論し共有しなくてはね。あまりにひどい今の地球。欠点を指摘し、改善し合う方法を開発するべきだよね。私も諦めすぎていた。夫とも、もう話さない、勝手にしなさい、とすぐに諦めた、だって水掛け論なんだもの。ここをクリアするディベートの方法があるのだろうか」
私はしばらく考え込む。この無茶苦茶な世界をすっきりと整理し、切り捨てたり足したりして、公益を旨とする人間関係、また情緒も充たされる社会、そんな満足のいく、というか努力のむくわれる世界を、どうしたら論理的にまとめあげていけるのだろうか。少なくとも私には無理だ、とてもその規模に追いつけない。ひとりで出来ることでもない。
ほんのこの前、ある天才について聞いたことがある。彼は(これが彼女だったら面白いのに)物事を見たとき、すぐにその骨組みと仕組み、細かな点の美醜、正否まで認識でき、かつそれを補正することができる。しかも数式が浮かんでくるというのだ。習ってもいない公式が抽出されてくる。こんな人物と義務教育もやっと終えられたような集中力のない、あるいはまずい親に育てられた人間とが、さてどんなディベートができるというのだろう。あるいはわがままいっぱいに育ち、オシャレとファッションと結婚しか頭にない人物と。あるいは日本であれ、イスラムであれ、アジアであれ伝統的な社会の枠組みでうまく生きることが重大であるような人間と。
かなり無理なように見える。蟻と象が結婚するようなものだ。
しかし、もし、こうしたらこんなに誰もが満足できる社会になりますよ、とうまく宣伝したら、ちょうどヒトラーのように、国中が挙げて賛成するかもしれない、洗脳されてであれ。それにしても、そんな試みにはものすごい年月がかかり、かつ担当者も何世代にもわたり熟慮を重ね、構築し、完成させねばならないだろうから、言っていいかどうかは別として、優生学ということを考えねばならないだろう。この二人には子供を諦めてもらうとか。あるいは、ウエイターにぴったりでそこに喜びを感じるような人種をつくるとか、あながち不可能ではないだろう。言うべきではないだろうが。
「お姉さんたら、ご苦労様、ひとりでそんなに考え込んで」
「もう十分だよ、世の人には知られなくてもわかっているんだよ」
「ほら、ちょっとお父さんとそれから長男とゆっくり話したら」
「いつも夢見ていたんでしょ。いつでも話せるんだよ」
「お姉さんがその能力と、環境の許す限りのことをやってきたこと、認めてくれるよ」
「愚かだから仕方ないって?」
まだ慣れていない、私が彼らと生活していることに。呪いから解放され、正しい関係が築けるかもしれない。わからないことではあるが、その可能性の方を信じたほうが良さそうだ。
私は、頭の中がいっそう激しく回転するのに任せる。
もちろんまっすぐ歩けてはいないのだろう。手をさしのべて挨拶しながら嬉しさが莫大であるのを感じる。
私の両脚の筋肉はまだ剛い。心臓は正しく血液を末端まで送る。まだ肉体は死なない。そのままで彼らと共に無限の色と音と動きを生きるのだ。 了
-
耄碌は200円の有料書籍です。
書籍を購入することで全てのページを読めるようになります。
-
-
耄碌
0











