芸術の監獄 ジャン・バラケ(後編)
-
芸術の監獄 ジャン・バラケ(後編)は120円の有料書籍です。
書籍を購入することで全てのページを読めるようになります。
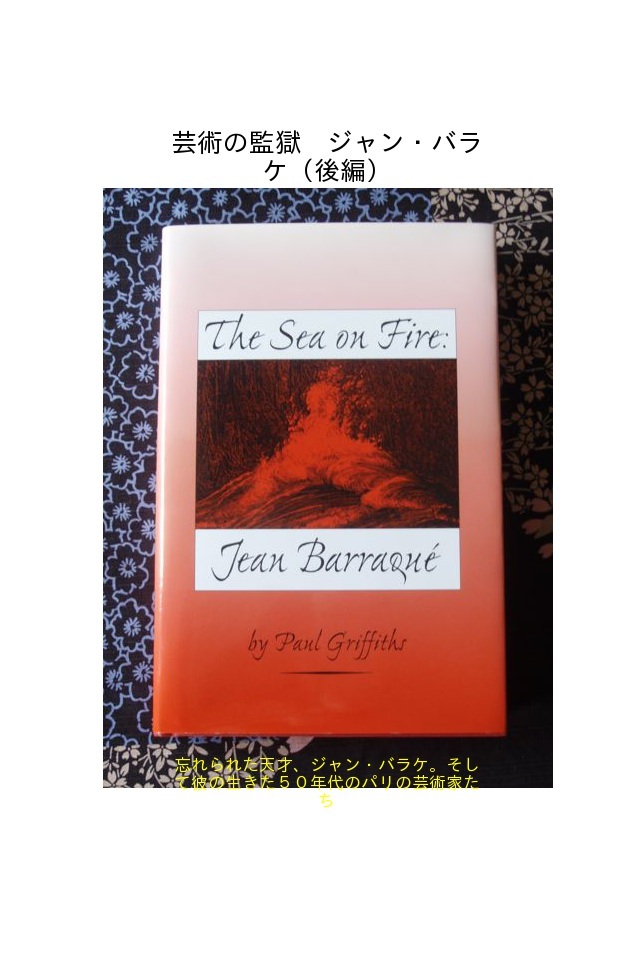
ジャン・バラケ(後編)( 1 / 3 )
もうお分かりの方が多いと思うが、バラケは文学的な気質の持ち主で、恐らく詩人の才能も有していただろう。そうでなければ、詩人を主人公とした大長編小説のオペラ化などを思いついたりしないだろうから。
もっとも、ではバラケだけが特別文学に耽溺していたのか、といえばそんなことはなく、文学と音楽と哲学との接近というのは、この時代のパリの芸術シーンの特色であった。それに演劇人も加わって「フランスの前衛芸術」のいろいろな実験がなされていくわけだが、詳しく述べているとバラケから離れてしまうので省略する。言い落としていたが「この時代」とは、1953年頃からの10年間と思って頂いて結構です。
ところで、ジャン・バラケはいきなり作曲家になったわけではなく、もちろん音楽院で作曲法をみっちり学んだ。師匠はあのオリヴィエ・メシアン。彼は学生たちに十二音技法を(註:音階上の12の音から基本音列を作り、それを用いてシステマティックに無調を達成する技法)習得させた。この手法は「セリー主義」と呼ばれ、50年代を通じて音楽シーンの主流となる。(そして、60年代には急速にすたれる)「セリー」とは、「音列」のフランス語訳である。
このメシアンのクラスでバラケとともに学んでいたのが、ピエール・ブーレーズ(1925−)だ。出ましたね。現代音楽界の皇帝。最近では作曲家と言うよりは指揮者として世界を股にかけているが、1950年代のこの時期は、作曲一筋だった。
「基本音列」の考え方は彼の作品にも顕著で、彼の作った「Sonate pour piano Numero 2ピアノソナタ2番」(1948年)は、バラケの「ピアノソナタ」と雰囲気がそっくりだ。私は音楽学者ではないので確信がないが、鍵盤音が「じゃじゃじゃー」と低音から高音に階段状にあがってゆくのも、「音列」の技法なのか?などとも思う。だがしかし、私は彼の「ピアノソナタ2番」には全く感心しなかった。聴いていて雑音に聞こえてしまった。どう違うのかというとブーレーズの方は、しーんと静まりかえることなく音が鳴っているのだ。「とまったら終わり」と思っているかのように、延々と不協和音がジャンプする。疲れた(少なくとも私は)。ときどき止まってくれるバラケの音楽の効用が、ブーレーズのおかげでわかった。
ジャン・バラケ(後編)( 2 / 3 )
ブーレーズはバラケと違って、「大スター」になったわけだが、50年代末頃は両者の名声は拮抗していた。やはりバラケは、寡作なのがたたった、と言わざるを得ない。ブーレーズは1年に3作くらい書いて、その上論文を書くような人ですからね。私は「ピアノソナタ2番」は好みに合わなかったが、彼の「Pli selom pli 襞にそって襞」(1960年)は好きである。これは、フランスの大詩人ステファヌ・マラルメの詩を構成し直して曲をつけたもので、「文学と音楽との接近」の例として挙げることができる。だが、50年代のブーレーズが熱中していた詩人はルネ・シャールで、彼はシャールの詩編をむさぼり読んで暗記していた。(のちに、シャールの「Le marteau sans maitre 主なき槌」がブーレーズの器楽曲の代表作と呼ばれることになる)
そして、文学作品に深い造詣を持つ新進の学者が、この音楽家たちと出会うこととなる。彼の名前はミシェル・フーコー。1926年生まれだから、バラケより2歳上。1951年に哲学の教授資格試験に合格し、フランス独自の「学術文化のエリート公務員」(いや、そんな名称は本当はないのですが)の道を踏み出した青年だった。
バラケとフーコーの関係は、一部の人々の間では妙に有名になってしまって、かえって書きづらいのだが、端的に書くと、2人は恋愛関係に至ったのですね。
ずいぶん長い間、このことは噂にすら上らなかった。(まあ、「僕たち同性愛です!」などといえる時代ではなかった)有名になってからのフーコーは、少しづつ少しづつ「自分のセクシュアリティ」「同性愛者である自分の生存の美学」などについて発言していったが、その時にはバラケはすでに死亡していた。
フーコーは、意識せずしてバラケの人生を大きく変えた。なぜなら、「ウェルギリウスの死」をバラケに紹介したのがフーコーだからだ。
2人が出会ったのは、1952年から53年にかけてのことで、最初はフーコーとブーレーズが意気投合し、その後バラケと出会った。フーコーの最大の目標は「ジャン=ポール・サルトルを越える哲学者になる」こと。今では考えられないが、実存主義哲学というのは当時は、「可能性に満ちた新しい時代の哲学」だった。しかし、この神経過敏な青年には(フーコーは学生時代、しばしば自殺騒ぎを起こした)サルトルのテクストの、その哲学の「落ち度」が見えていた。いずれ彼は、サルトルの権威を引きずり下ろすことになるだろう。歴史の証拠資料を、自身の社会批判の主張の周りに美術品のごとくに配置し、鮮烈で単純なイメージと、陰影のある仮説と、その忍耐強い証明の記述によって。
先走ってしまったが、当時のフーコーはあくまでも「学者の卵」である。ニーチェに没頭し、覆面批評家モーリス・ブランショの書評を毎月読み、その神秘性にあこがれていたようだ。実は私もブランショのファンで、今でも著作の文章を書き留めている。例えば:
「象徴は物語であり、その物語の否定であり、その否定の物語である。」
「意味は説明から解放されてこそ説明であるが、説明と不可分であればこそ説明ともなる」
分かりやすいですね、という冗談はさておき、「ウェルギリウスの死」の書評を書いたのがまさにブランショだった。なんというか、文学ー哲学ー音楽、の綺麗な連関ができてしまっている。
-
芸術の監獄 ジャン・バラケ(後編)は120円の有料書籍です。
書籍を購入することで全てのページを読めるようになります。
-
-
芸術の監獄 ジャン・バラケ(後編)
0











