有罪
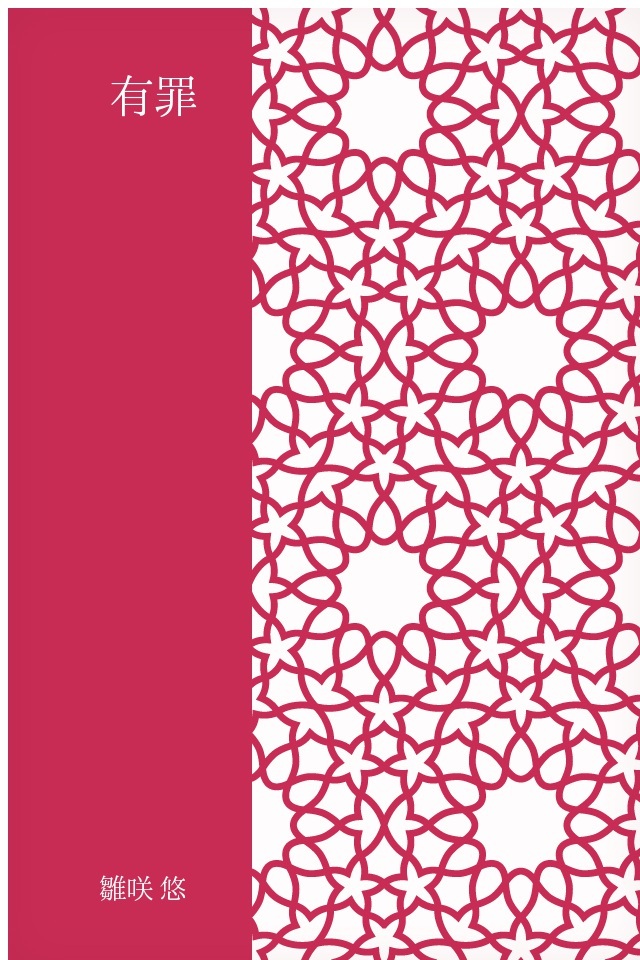
息切れが激しい。目が眩む。自分の吐息する声しか、聞く余地はない――
鬱蒼とした緑が、自分の肌を切る。鮮血が飛び散る。痛みが脳裏を掠める。それでも、彼女は走り続けた。いつも微笑んで自分を見下ろす、森の木々たちが、自分を追いかける男たちのようにしか見えない。
恐怖だった。それは、本能が察知する悪寒だったのだろう。後ろから聞こえてくる別の吐息たちを、認めない訳にはいかないのだ。これは現実である。皮肉にも、現実は決して悪夢ではないのだ。
起こり得る事こそが、実体となり得る。
我が身の危険と共に。
僅かな時間と共に、迫ってきている。
突然、彼女の視界が暗転した。衝撃。思わず、舌を出す。土の味がする。いつの間にか、根に足を取られてしまったらしい。
そんな事を、ぼんやりと考える。とうの昔に酸素が欠乏した脳では、現実を虚ろに受け入れる事くらいしかできなかった。終わったのだ。全てが。
真後ろから、同じように息切れが二、三ほど聞こえてくる。ただその吐息には、微妙に悦楽が混じっているように思えた。「手こずらせたな」、という男の声が、やけに頭に響いてくる。そして前触れもなく、彼女の服に一人の男が手をかける。絹の裂ける音。白い肌が露出する。下卑た笑いを浮かべる男たち。
――逃げたい。
彼女は祈った。果てしなく、神でもない、何かに必死に祈りを捧げた。
――逃げたい。逃げさせて。厭厭厭厭
スカートが千切れ、布が彼女の髪に絡み付く。
――厭。助けて。もうこんな所、いたくない――
その瞬間。
男たちは、一斉にこちらへのし掛かった。
気を失っていたらしい。目を開くと、代わり映えのない土の色が目に入った。朦朧としながら、上半身を起こす――が、近くにあの男たちは居なかった。身につけている服だけが、引き裂かれたままにされている。ただ、下着はちゃんと身につけていたのを見ると、何もされなかったらしい。明らかに不自然だった。
どこにいったのだろう?
漠然と、誰にでもなく問い掛けてみる。当然、答えは出ないのだが。
足下をよろつかせつつも、起き上がると、彼女は何かを踏んだ。グチャリと肉が弾けた音がして、一瞬身を引きつらせる。
おそるおそる、足元を見ると――
草むらに転がっていたのは、三体の人形だった。その内二体は、自分の背に潰されたらしく、原形を留めていない。残り一体は、しっかり自分が踏み潰していた。白い陶器の、可愛らしいビスクドール。姿形は、ただの人形に過ぎない。
ただし、一点だけ、異様な風景が広がっていた――自分の周囲が、血に染まっていたのである。それだけではない。先ほどのあの音は、しっかりと肉を潰した音だった。自分の足下にある、明らかに無機質なはずのビスクドール。潰した場所から波状に広がるひび割れには、明らかに異質であるはずの、真っ赤な血と肉がはみ出していたのだ。
だが、不思議と恐怖は沸かなかった。明らかに非現実的なせいだろうか、臓物が足に絡み付いていてても、全く不快感はなかった。ただ、疑問だけが残る。
(なん――なの?)
草むら。うんざりするような森の木々たち。それらが、視界を埋め尽くしているはずだった。ついさっきまでは。
前方には、小さな小屋が見える。延々と続く、緑の草原。むせるような、太陽の光。そして、不釣り合いに降り積もる、雪。ここにはないはずの景色が、自分の目の前に広がっている。
彼女は、その小屋へと近付いていった。
小屋の中は、意外にも、爽やかな風で潤っていた。埃っぽさは感じるか、決して不快ではない。寒さは感じなかった。ただ、彼女を取り巻く暗闇だけが、小屋の中を静かに隠している。静寂の中で、彼女は明かりを灯そうと動き出す。
「灯りが欲しい?」
後ろから甲高い声が聞こえて、少女はひっと声を上げた。そのまま、慌てて後ろを振り向く。
入り口のドアから、小さな人影がこちらを見つめていた。ただし逆光になっていて、その表情は伺えない。
「灯りが欲しいの?」
人影はもう一度言うと、戸をぱたんと閉めた。暗闇に戻ってしまった室内を見ながら、少女は囁く。
「……うん。暗いと、何も見えないもの」
「ふぅん、分かった。ちょっと待っててね」
素直に応じて、その気配が遠のいた。と同時にゆっくりと、ただし確実に、部屋の内部が炎で照らされていく。そして――息を飲んだ。
狭い小屋だというのに、天井から床まで、全て様々な人形で埋め尽くされていたのだ。ビスクドール、硝子人形、ブリキの人形、ありとあらゆる人形と名の付く全てが、この小屋の中で静かに眠っていた。時たま揺れる炎の灯りに、どことなく生きているような印象さえ受ける。
いや、と彼女は呟いた。生きている人形はいる。自分の目の前に。
少女の背丈より少々低い少年が、静かな青い瞳で、こちらを見つめ返している。白く透き通った肌と整った顔立ちは、そのまま人形を連想させた。生気を感じさせない。単に、無表情なだけなのかもしれないが。
神秘的な印象が漂う人形は、長く美しい睫を翳らせる。
「何かに追いかけられていたんだね……服がボロボロだよ」
「………」
嫌な事を思い出して、俯く。そして、足に広がっていた赤を思い出した。男たちは、どこに姿を消したのだろう。
こちらの心を読むように、少年は薄暗がりの中で、そっと笑いかけてきた。
「心配しないでもいいよ。ここは安全だ、誰も追いかけて来やしない……貴方が望む限り、ね」
その笑顔は、ひどく彼女を安心させた。同時に、不安にもさせた。自分でも気付かないまま、その言葉を口にする。
「君は……君は一体、誰なの? ここは、何処?」
「面白いね。ここに行き着いた人たちは、みんなそんなことを言うんだ」
彼は相変わらず笑って、ゆっくりと奥に進んだ。慌てて、その後を追いかける。やがて、さらに埃をかぶった部屋へと通される。そこにも、無数の人形が所狭しと鎮座していた。
ここには窓がついていて、外が見える。こびり付いた埃を拭って外を見ると、真っ白な銀世界が広がっていた。
そんな自分を眺めながら、彼は言う。
「僕は、Father Time……『時の翁』。時間軸を支配し、どこにでもいて、どこにもいない存在。世間一般では、翁なんて言われてるけどね。失礼なもんだよ、こんなに若いのにさ」
すらすらと、まるで冗談でも言うみたいに、彼――翁は言った。
時の翁。お年寄りが、片手に砂時計を持って立っている、時の神である。村の学校ではそんな風に習っていたのだが、あまりにもイメージと違いすぎて、彼女は戸惑うしかなかった。
しかし当の翁は、そんな彼女を楽しげに見つめ返すのみである。
「驚いた? こんな子供が、歴史から未来までの全てを、この手に握っているなんて。馬鹿馬鹿しいと思ったでしょ。ううん、いいんだ。そう思っていても、仕方ないしね」
次の瞬間、その笑みは静かに解け消えた。先ほどの無表情な仮面が、じわじわと彼の顔に覆われていく。
「でも、この光景は現実なんだ――雪も、人形も、君が潰した人形たちも」
「じゃあ、やっぱりあの人形は――」
「君が、望んだことなんだ」
こちらの声を遮って、彼は断言する。決して荒らげてはいないものの、その響きは、氷よりも冷たい心持ちがした。
「君が望んだことなんだよ。現実から逃げたいと思う全ての意志が、彼らを人形にさせ――そして、結果的に殺した。僕は、その手助けをしたに過ぎない」
透き通ったビスクドールを思い出す。血にまみれ、亀裂部分からはみ出していた臓物の束。それが、あの男たちの変わり果てた姿だったというのか?
段々と、言いようもない嘔吐感に襲われ、少女は顔をしかめた。
しかしそんな中でも、翁の顔が崩れる気配は無い――もう、微笑むこともないかもしれない。彼はただ、寂しげな目だけを人形たちに向けていた。窓からの光で、人形たちの姿はおぼろげだが、認識はできる。その中で一つだけ手に取り、翁はこちらを向いてきた。
「そんな絶望感、逃避感から、この次元の狭間に迷い込んできた者たちを、僕は導いて行く必要がある。ちょうど、今の君のようにね――フーニルキア」
自分の名前を呼ばれて、少女はぴくりと身体を震わせた。絶望感。逃避間。自分がずっと味わい続けてきた、苦い感覚だった。
運命は、味方してはくれない。
運命には、決して逆らえない。
逆らうために、罪を背負う力など無い。
自分は、無力でしかない。
絶望するしかない。
「さあ。君には、選択権がある。この小屋で人形になって、永遠の安らぎにつくか――それとも、もう一度時間を戻して、追いかけられるか。二つに一つだ」
審判の声が聞こえる。
決められなかった。決めることはできなかった。
だから、彼女は駆け出した。部屋の外へと。悲鳴を上げながら。
後ろから、翁が追いかけてくる気配はなかった。彼女はただ、走り続けた。逃げて、もつれて、転んで、それでも走り続けた。手近にあったドアノブを掴み、一気に入って鍵を閉める。暗闇の中、静寂だけが周りを支配していた。
不意に、前方で明かりが灯る。勝手に,奥の蝋燭へ火が点いたらしい。最初、翁かとも思ったが、気配は感じられなかった。ただ、静かな闇だけが灯に照らされている。ここには、人形はいないのだろうか。
すると、カタリと音がした。明かりの範囲内に、それは落ちてくる。人形の腕だった。ただ決定的に違うのは、こびり付いた血と骨。それが、コロコロと足下まで転がってくる。
指先でそれをつまみ上げると、天井を仰いだ。視界の範囲内に、人形は居ない。
しかし、異変は起こった。
靴の下に、肉を潰す音が聞こえ出す。驚いて壁に身体を預けると、またグチャリと潰れる音が聞こえる。背中に手をやると、血でべったり濡れていた。
同時に次々と、幾本かの蝋燭に灯が点される。一本、二本、三本……全てが明るくなったとき、彼女は知った。この部屋の壁、床、天井全てが、人形たちで埋め尽くされていた事を。
先程背中で潰してしまった人形と、目が合ってしまう。血塗れになり、眼球が白く垂れ、脳髄があらかた飛び散ったその人形は、こちらを見つめていた。
あらん限りの声を出して、彼女はドアへと向かう。そこに、翁が立ち塞がった。静かな微笑みを浮かべている。
美しい、狂った人形のように。
「ここの人たちはね、特別なんだ――特別、現実が嫌になった人たちさ。完璧に無我になりたい時、人はこの家になるんだ。集団に溶け合い、考える気力も無くしていく。彼らは、それが一番幸せなんだよ。絶望感も、逃避感も、既に感じられなくなってるんだから」
「厭……こんな風になんて、なりたくない……なりたくないわ!」
泣き叫んで、少女は座り込んだ。また足下で潰れた肉の触感と、血の暖かさを感じながら。
それをしばらく翁は見続けていたようだったが、蒼い瞳を瞼で閉じる。噛み締めるように、
「それなら、帰るべきだよ。貴方の元いた場所、元いた空間に。ただし、ひとつだけ忠告しておくよ。絶望だけに飲み込まれたら、君はあの場所で、必ず死ぬ。それを防ぐには――」
霞がかったように、声が遠くなっていく。視界が白く濁っていく。
「罪を味方にするんだ。罪深く、強くなりなさい」
その言葉と共に。
全ては、消え去った。
息切れが激しい。目が眩む。自分の吐息する声しか、聞く余地はない――
鬱蒼とした緑が、自分の肌を切る。鮮血が飛び散る。痛みが脳裏を掠める。それでも、彼女は走り続けた。いつも微笑んで自分を見下ろす、森の木々たちが、自分を追いかける男たちのようにしか見えない。
恐怖だった。それは、本能が察知する悪寒だったのだろう。後ろから聞こえてくる別の吐息たちを、認めない訳にはいかないのだ。これは現実である。皮肉にも、現実は決して悪夢ではないのだ。
起こり得る事こそが、実体となり得る。
我が身の危険と共に。
僅かな時間と共に、迫ってきている。
突然、彼女の視界が暗転した。衝撃。思わず、舌を出す。土の味がする。いつの間にか、根に足を取られてしまったらしい。
そんな事を、ぼんやりと考える。とうの昔に酸素が欠乏した脳では、現実を虚ろに受け入れる事くらいしかできなかった。終わったのだ。全てが。
真後ろから、同じように息切れが二、三ほど聞こえてくる。ただその吐息には、微妙に悦楽が混じっているように思えた。「手こずらせたな」、という男の声が、やけに頭に響いてくる。そして前触れもなく、彼女の服に一人の男が手をかける。絹の裂ける音。白い肌が露出する。下卑た笑いを浮かべる男たち。
――逃げたい。
彼女は祈った。果てしなく、神でもない、何かに必死に祈りを捧げた。しかし、それが無駄であることにも気付いていた。
運命は、味方してはくれない。
その動く視界の中で、銀色に光る物が目に入った。目の前の男が、服に気を取られて投げ捨てたのだ。手が届く距離にあった。手を伸ばせば、拾える。
今までの自分ならば、それを取ることに躊躇ったろう。刃物を持てば、間違いなく殺される。汚れるだけで済むのなら、このままの方がいいと。
だが、今の彼女は違っていた。勝ちたかった。何かに勝ちたかった。もう、負け続けることはうんざりだった。
だから――
彼女は、ナイフを握った。
血にまみれたナイフ。三体の、転がった死体。
勝ち残った、自分。
無我夢中で、何をしたかはよく覚えていない。ただ、死にたくないという思いだけが、脳裏で渦巻いていた。それだけだったのに。
いつの間にか、笑っている自分に気く。罪を犯してしまったのに、この清々しさは何だろう?
今まで無力だけが支配していたこの世界が、やけに自由に感じられる。
自分は無力ではなかった。
ただ、変わる努力をしなかっただけ。
変わるために罪を作る事を、恐れていただけだった。
罪を味方に。罪深く、強くあれ。
時の翁に授かった言葉を、もう一度繰り返す。
永遠に自らの身体へ、刻みつけるために。
頬にこぼれる、しずくの意味さえ気付かずに。
-
-
有罪
0











