芸術の監獄 夢野久作(前編)
-
芸術の監獄 夢野久作(前編)は120円の有料書籍です。
書籍を購入することで全てのページを読めるようになります。
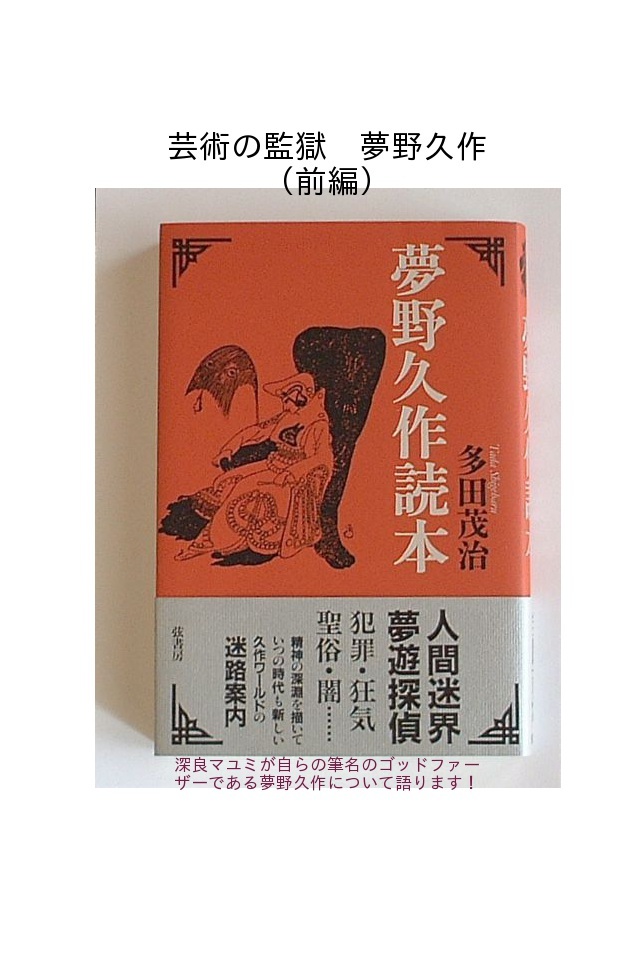
芸術の監獄 夢野久作( 1 / 4 )
夢野久作は異形の作家だ。このエッセイは芸術家を取りあげるのが主眼で、彼が小説家であり芸術家であることは今さら強調するまでもないことだが、しかし彼は、一種唖然とするくらい、かつて私が主題とした芸術家たち(はっきり言うと谷崎潤一郎や江戸川乱歩)とは異なっている。谷崎や乱歩は、どう転がっても「文学者」であり「この世のほかの世界」にうつつをぬかし、「世の中は美しいからっぽである」(谷崎潤一郎の初期作品)との諦観から出ようとはしなかった(勿論私は、それを非難する気は毛頭ない)。
久作は違った。彼は世界の中に置かれた虚勢を張る日本を、欧米に見習った唯物功利主義と、「忠孝」「忠義」といったお題目とを使い分ける明治、大正の国家指導者たちの狸ぶりを的確に見抜き、権力者たちの二枚舌を作中で痛罵している。その最たるものが長編「犬神博士」(1931年)だ。
「戦争もないのにサアベルをつるして、見せてくれとも言わないのに勲章を並べて、電車自動車がある世の中に馬に乗って、エライとも言わないのに反りくり返っていくのは、ありゃあ何だ。誓文払いの広告か。それともオッチニの親方か。(中略)銭もないのに一等旅館に泊って、何事もないのにフロックコートを着て、配っていけないのに大きな名刺を配って、先祖代々下げなかった頭を下げて、頼まれもしないのに演説会を開いて、万世一系金甌無欠の日本を亡びる亡びると怒鳴っている連中は、ありゃあ何だ。舶来の乞食か。それとも大本教の凝り固まりか。」
主人公(そして語り手でもある)は、「吾輩の眼から見れば世間の奴らの方がよっぽどキチガイじみている」とも述べ、自分の生活たるや、家は流木やトタン板を拾って組み立てたものだし、地所は箱崎八幡宮(註:物語は北九州が主な舞台)の好意で借りているもの、帽子は九州大学総長のお下がりの山高帽で、着物は「別にない。寒いときに浴衣を1枚着るくらいのもんだ。」そして、マントにはポケットが4つあって野良猫や野良犬を拾い混んでくるのに便利、だそうで、まあ見てくれがひどいことは推して知るべし。久作はこういった、社会の最底辺(らしく見える)人種を書くときに筆が冴える。冴えるばかりでなく、そこには深い愛情がかいま見えるのだ。
芸術の監獄 夢野久作( 2 / 4 )
この語り手は、神様以上の神通力を持ち(それ故に「犬神博士」と呼ばれている)、その能力のいわれを聞くべく新聞記者のインタビューを受けているという体裁をとっている。問われて話すのはその幼少時代だが、「俺の記憶に残っている両親はドウヤラ本物の両親ではないらしいから困るんだよ」と言わせている。死神博士、違った犬神博士は大道芸を演じて歩く男女の「商売道具」だったのだ。女親(母、と書かないあたりがミソ)が三味線を弾いて男親が鼓を打って、おかっぱ頭、振り袖、厚化粧の、ほぼ女の子のなりの「吾輩」が踊るというわけだ。この辺の語りは、見物から少しでも稼ぎをもらうために両親が「吾輩」に猥褻な踊りをさせたりして結構過酷ないじめ話のはずなのだが、不思議と描写はからっとしていて、本を片手に吹き出しそうになる。
「男の子を無理矢理に女の子にして育て上げて、生活の合理化を図ると同時に、性教育まで施していたんだから斬新奇抜だろう。」という文句やら、巡査が通りかかった途端に唄の文句を卑猥なものから真面目なものに急変させる男親の姿やらが、しみじみおかしい。昭和初期の日本、戦争へと向かう暗さと捨て鉢な明るさがない交ぜになった地方都市の姿、埃を吸って生きる労働者は、芸人の口上にヤジを飛ばす。
それは、谷崎も乱歩もあえて書こうとしなかった、近代日本のなまの「民衆」だ。名もなき衆生と言い換えても良い。田舎の都会に根を張っている政党関係の因循さに嫌気がさして、山奥に赴任してきた巡査や(「巡査辞職」)、青島戦争で右の腕がなくなった郵便配達夫(「眼を開く」)、農繁期で読者が減ってゆくから事件を作りあげてでも、記事を取らなくてはと鵜の目鷹の目になる、地方新聞記者(「空を飛ぶパラソル」)。中央集権の象徴、東京の上流夫人は、弄んだ少年たちを手にかけ、その爪を引き出しに仕舞い込む(「けむりを吐かぬ煙突」)。
こういった作品を書きつづる夢野久作は、私の目には文学者というよりも、社会悪を告発するジャーナリストのように見える。勿論例に挙げた作品はみなフィクションだが。「夢野久作読本」(2003年 弦書房刊)の著者、多田茂治は、「夢野久作は単なる怪奇作家、探偵作家ではなかったのです。作品の底に、独自の哲学、国家観、社会観を深く沈めていた作家でした。」としているが、全く的確な論評である。
芸術の監獄 夢野久作( 3 / 4 )
しかしながら彼の作品は、声高に社会を変えろ!とは言わない。あくまで人間のグロテスクな心性をこれでもか、と書いている。その結果、彼の作品は「美」に重きを置かない。美しさに酔わせるかわりに、人間心理の暗さ、エゴイズムに茫然とした感慨を抱かせる。
これはいかにも奇怪なことである。「美」に重きを置かない芸術家が存在するというのは。勿論一般的な意味では、久作の美に対する感性は鋭かった。能楽喜多流の教授免許を持っていたのは有名な話だ。昭和10年11月24日の日記には次の記述がある。
「喜多でお能。大蛇。三井寺。乱。六平太先生(註:喜多流14世家元)の乱を見て胸が一パイになり立ち上がるのがイヤになる。一生涯かかっても六平太先生の乱ほどの探偵小説は書けず。」
びっくりするほどの勢いの良さで「自分の小説は、能のもたらす陶酔には遠く及びません」と断言している。この辺が私には面白い。普通の文学者なら、「あの芸に近づくような小説を書くぞ!!」となるのではないか? 多分谷崎なら(そして私も)そう言うだろう。「六平太先生にはかないません」と絶賛するならば、その素晴らしい点を微にいり細をうがち、これはこうで、と分析してくれても良さそうではないか。(これは乱歩がやりそうだ)だが久作はどちらもやらない。「能はいいねえ。六平太は最高だね。でも、それだけ」。このあたりが、彼は「美」の持つ力を信じていない(全く、ではないが)し、一時的にぼーっとなったとしても心底耽溺はしない芸術家だ、とする根拠である。
-
芸術の監獄 夢野久作(前編)は120円の有料書籍です。
書籍を購入することで全てのページを読めるようになります。
-
-
芸術の監獄 夢野久作(前編)
0











