オレンジ
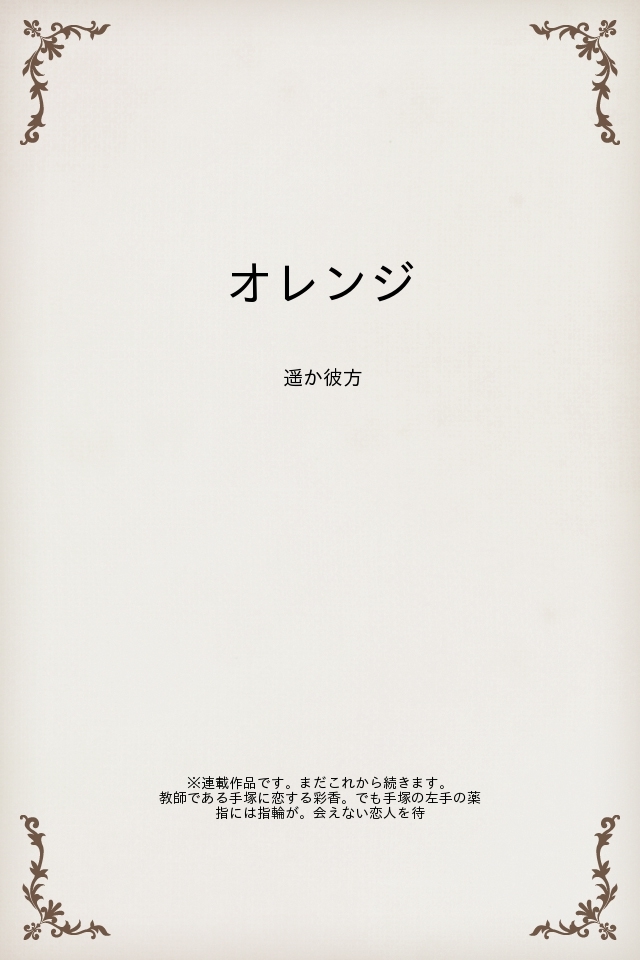
声が、好きだと思った。
まだ若いのに深みのある低い声に、厳格な性格がよく表れている。厳しいけれど優しいその心地よい低音を、いつまでもずっと聞いていたい、と思った。
「鈴木、俺の話聞いてるか?」
担任の手塚に注意され、彩香はハッとした。まただ。先生の声を聴いてしまって内容が全く頭に入ってきていなかった。手塚が彩香のノートを覗き込む。そんなに近くに来ないで、と念じる。心臓の音が聞こえたらどうしよう。
「練習問題今やれって言ったろ。ぼうっとしてるとついてこれなくなるぞ」
「はい、すみません」
うつむいたまま返事をして練習問題に取りかかる。どうしよう、きっと耳まで赤くなっている。とてもじゃないけど顔なんて上げられない。
最近の自分はどうもおかしい。
初めて手塚を見たとき、まだ二十代後半だというのにもう四十代であるかのような貫禄に彩香は圧倒された。一体、どういう年の積み方をしたらその若さでそんなに貫禄がつくものか、目の前の男の人生が気になった。簡単には動じなさそうな安定している大人の男だった。
手塚の担任の挨拶を彩香はまだ覚えている。遠くまで聞こえる、芯のある声で彼は言った。
「初めまして。今回、この特進クラスの担任を受け持つことになった手塚孝弘だ。君たちも知ってのとおり、この特進クラスは学科の特色上、三年間クラス替えをしない。さらに、滅多なことでは担任も変わらない。だから、ここにいる全員がこの先三年間を共にする仲間だ。受験は団体戦だ。ここにいる皆は、ライバルではなく、苦しみを共にする仲間だ。それをよく肝に銘じておいてくれ」
落ち着いた大人の声に、熱血先生よろしくの青臭い台詞がなんとも似つかわしくなく、彩香は心の中で笑った。
話している内容はともかく、いい声だ、と思った。
手塚は教室を見渡した。目が輝いている。この伝統ある進学校の顔とも言える、この特進クラスを受け持つことが、この学校の教師の中でどんなに名誉なことか、その目が物語っていた。
実際これは過ごしてみて気づいたことだが、特進クラスに教えに来る先生たちはどの先生もその教科では学校で一番と言える先生たちであったし、先生たちにしても、特進クラスに関わる先生とそうでない先生の間では格差があるように感じられた。
手塚は学校側からしたら金の卵である特進クラスの担任を、二十代という若さで受け持っているのだから、相当腕が立つのだろう。自信に満ち溢れているのが見て取れる。
彩香は、こういう熱血先生は苦手だ、と思った。
この人も、どうせこういうタイプにありがちな、生徒のためと言いながら自分のための偽善者だろう。
そんな彩香の胸中をよそに手塚は続ける。
「それから皆、入学おめでとう。この学校の、この特進クラスに入学したことは、君たちの人生の小さな成功だ。とりあえずはおめでとう、受験勉強よく頑張った。君たちは能力が高い。それは間違いない。だが、勘違いしないで欲しい。ここは決してゴールではないし、この程度の学歴では君たちはまだ何者にもなっていない。君たちは、やっとスタートラインに立ったに過ぎない。これからが本当の戦いの始まりだ。これからこのクラスで過ごす三年間で、君たちは何者かになって欲しい。僕は、全力で君たちそれぞれの夢の実現をサポートする。君たちが苦しいときは僕も一緒に苦しむ。約束する。そして、君たちも僕に約束して欲しい」
すると手塚は、彩香の制服の左胸にある赤い校章を指差した。彩香は突然指差されてドキッとするが、手塚が見ているのはブレザーの左胸についている校章だと気づく。この校章は、特進クラスだけ他の普通クラスとは色が違っている。普通クラスは青だが、特進は赤となっている。
「その赤い校章の制服の袖に腕を通した今日から、このクラスの一員としての誇りを持って、このクラスの名に恥じない行動をとること。さらに、普通クラスの模範となるように心がけること。これが、君達特進に求められていることだ」
彩香が手塚のその堂々とした声に聞き惚れていると、目が合った。心臓が飛び跳ねた。
たまたま彩香が教室の中央に座っていたから。ただそれだけのことだが、手塚のまっすぐな目を正面で受け止めてしまい、彩香は心臓の鼓動が大きくなるのを感じた。頭の良さそうな深みのある茶色い瞳。逞しい意志を感じる。彩香は、その時初めて会ったこの若い男の瞳に信念の輝きを見た。こんな落ち着いているのに情熱的な瞳は見たことがない。
そして、自分の中の何かがざわめくのを感じた。この目の前の男が、きっと鍵を握っている。これから、大きな何かが始まる。きっと逆らえない何か大きな流れに自分はとうとう飲まれる。そんな予感がしたのだ。
これが、全ての始まりだった。
「先生は!?」
移動教室から帰ってくるなり彩香が実香に聞く。
季節は残暑が消えて少し肌寒くなってきた秋。彩香はワイシャツの長袖をたくしあげて暑そうにしている。走ってきたのだろう。
「たぶん進路指導室だと思うけど、どうしたの」
「ん、ちょっと、数学の問題聞きにいく!」
実香は、バタバタとノートと問題集を抱えて進路指導室へと走っていく彩香の背中を見ながら
「分かりやすいな」
とひとり笑った。そんな嬉しそうな顔して数学の問題聞きにいくやつがいるか。
最近の彩香は恋をしている。他の皆は気づいていないかもしれないが、いつも一緒に居る実香には分かる。
実香が彩香の変化に気づいたのは、一年の夏休みの、特進クラス恒例の勉強合宿で夜、二人で布団に入って話をしていた時だ。
彩香は言った。
「私さ、このクラスに入ったとき、うわ、なんてところに来てしまったんだ、って思ったんだよね。こんなに夏休みもなく勉強ばっかする所だなんて思ってなかったんだ。こんなことなら普通クラスにでも行って、部活頑張って推薦もらって大学進学すればよかったって思った」
「それ、私も思った。こんなに一年の時から課題とか補講とか授業以外の講座があるなんて知らなかった。昔は本ばっかり読んでたのに最近全然読めてない。課題と空手の稽古で一日終わっちゃう」
実香が同意する。本当にこの特進クラスは、受験勉強に特化しすぎていて課題や講座の量が半端ではない。朝は七時から早朝学習時間があり、点数の伸び悩んでいる教科を重点的にやり、放課後はセンター対策講座、難関国公立二次対策講座と受験のための講座が続き、真面目に全てに出席すれば帰るのは八時になる。だが担任からの圧力もあり、部活動や習い事をやっている生徒以外は大体残って勉強している。
「平日は朝早くから夜遅くまでずっと勉強だし、長期休暇も講座とか合宿とかあってほぼないも同然だし、すっごく大変って思っていたんだけど、でもさ、よく考えたら先生たちの方がもっと大変だよね。朝早くから学校に来て講義して授業して放課後も生徒に付き合って遅くまで残って、長期休暇も返上して仕事してる。すごいよね、うちらは自分の受験が終わったらこの生活は終わりだけど、先生たちはずっとそうなんだよ」
「まぁ、たしかにそうだね」実香が同意する。
「でも、そう考えると、こんなに自分たちのために頑張ってくれる先生に出会えたから、このクラスに入ってよかったって思うんだよね。手塚先生みたいな人に出会えてよかった」
そう言う彩香の横顔が光輝いているように見えて実香は目を見張った。この内側からくる光の正体はなんなのだろう。
「手塚先生みたいな人は初めて。あそこまで自分の生活を削って生徒に尽くす先生なんてそういないよ」
そのとき、実香はもしかして、と思った。
もしかして、彩香は……
「でも、彩香、ああいう熱血タイプの先生苦手って最初言ってなかった?」
実香は何故か胸が一瞬痛んだ。どうしてか分からないけど、少し暗い気持ちになって彩香に聞いた。
「うん、そう思ってた。でも、手塚先生は違う」
枕を見つめて彩香が言った。はっきりと自分に言い聞かせるように違う、と言ったその顔を見て実香のもしかしては確信に変わりつつあった。さらに原因不明の闇が実香の胸に広がった。
認めたくない。
「何が違うの。どういうこと?」
「あのね、実は、私、中学の時にちょっといじめにあっていたんだよね。でもいじめって言っていいのか分からいぐらいの嫌がらせで、実際意地悪される人も頻繁に変わっていったから、全然大したことじゃないんだけど、でも田舎の中学だったから同級生も少なかったし、人間関係も閉鎖的でいじめは常にあった。一回いじめにあった人はその過去を清算するのがなかなか難しかったの」
実香は突然の彩香のカミングアウトに動揺していた。意外だった。こんなに優しい子がいじめられるなんて理不尽としか言い様がない。少しの憤りを感じるとともに、彩香の大人びた一面はこの経験から来ているのかもしれないと納得もしていた。実香の動揺も気にせず彩香は続ける。
「その時の先生が、典型的な熱血先生で、いじめなんて最低だ、みんなの前ではっきりさせて謝らせよう、っていって、学級会とか開いておおっぴらに対応したの」
「あぁ。そういうことかぁ」その先は聞かなくても実香にもだいたい想像がついた。
「そういうことしたらね、火に油だよね」
「そー。案の定、いじめは表では解決したように見えて、影でエスカレートした。ほっといてくれればもういじめの標的は移りつつあったのに、みんな私のことなんて気にもとめなくなっていっていたのに、私はもうそのまま目立たないようにしていれば自然と戻っていけたのに、あの先生の自己満足な正義感のせいで全てが狂った」
そこで彩香の表情が一段と険しくなった。苦々しい顔をして続ける。
「みんなは私が告げ口したものと思ったし、そうなったらもう回復は望めなかった。はじめはクラスの中心グループだった一人の強い女の子の気まぐれで始まったものが、クラスの意志になった。たいしたことのなかったいじめも、さらに陰湿でひどいものに変わった。それまで話してくれていた友達も私とは話さなくなった。全部、普通ならその強い女の子が飽きたら通りすぎる台風のようなものだったのに、私はその先生が厄介なことをしてくれたおかげで卒業まで逃れることが出来なかった。そのくせ先生は何にも気づかなくて、もう解決したものと思っていた。自分の対応は正しかったと、満足していたように思う。だから、私が勇気を出してまだ続いているんです、って言ったとき、気のせいだって言ったの」
「え、気のせいって言われたの!?」実香は驚いて思わず聞き返した。彩香は笑って言った。
「うん、気のせいって言われた。もうその時は文字通り目の前が真っ暗になったね。気のせいって。もう何も言えなかった。先生は、この人は、自分に満足していて、自己完結的で、何にも見えていないどころか見ようともしていないんだって。そんな人に何をどう言っても無駄だって、そう思った」
彩香は諦めたように笑ってそう言った。
「それで、私は教師ってものに絶望したし、しかも、いかにも生徒のために頑張ってますよ、って感じの熱血先生って、大嫌いになったんだ」
「で、手塚先生は、違うんだ?」
胸がチクリと痛んだ。何なんだろう、私は。小学生か。友達に好きな人ができて、嫉妬するなんて。
でも嫉妬なのか、この寂しさは。
ただ、彩香が自分には分からない世界へと進んでいってしまうのが嫌なのだ。
恋愛なんて、実香には本当によく分からない。
そんな実香には構わず彩香が答える。また目を輝かせて。
「うん、手塚先生は違うよ。そもそも、先生は生徒に好かれようとしてないし。生徒の前では厳しいし、甘くないけど、そうゆうのも全部生徒のためなんだって、分かる。むしろそういうのが本当に生徒のためになるんだと思う。先生は自分がどう思われるかなんて気にしていなくて、本当に生徒のためになることをしている。だから先生は私が嫌いな熱血先生とは違うの」
一息おいて、
「先生は、本物。信じられる」
そう言った彩香の横顔はこれまで実香が見てきたどんな彩香よりも輝いていて、実香は胸の奥をぐっと押さえつけられた気持ちになった。
この感情をなんて呼べばいいか実香にはまだ分からない。果たしてこの胸の奥にぎゅっと詰まった塊は、憧れなのか、寂しさなのか、切なさなのか、嫉妬なのか、愛しさなのか、一体なんなのだろう。その全てが混ざった感じ。
実香が思うに、言葉は少なすぎる。言葉はいつも実香の気持ちのほんの表面しかすくっていってはくれないのだ。
彩香は続ける、
「私ね、前に夜の九時ぐらいに忘れ物して学校に取りに来たことがあったの。数学の課題、すっかり忘れてて。流石に誰もいないだろうって、だめもとだったんだけど。そしたら、職員室もどこも電気が消えていたのに、進路指導室だけ電気がついていたの。教室に行くときに、進路指導室のドアが少し空いていて、手塚先生が問題集作っているのが見えたんだ。ひとり、黙々と作業してた。あの後ろ姿を見た時、初めて先生を見た時に感じたあの瞳の奥できらめいた信念の正体が分かった気がした。あれはきっと、覚悟だ、って、そう思った」
彩香はふっと遠い目をして、それから
「ああ、こんな先生もいるんだなぁって、思ったんだよ!」
と語尾を強めて明るく笑った。実香は、いいなぁ、と思った。彩香が羨ましいのか手塚が羨ましいのか分からなかったが。
あの夏休みの合宿から一ヶ月が経った。もう季節は秋になり、あたり一面鮮やかな暖色で包まれていた。
皆、一週間後の学園祭の準備で浮き足立っている。移動教室の時に合唱曲を歌いだすやつもいれば、お昼休憩に教室でダンスを踊りだすやつもいる。それぞれの教室には劇の大道具やダンスの衣装などがごちゃごちゃとロッカーの上に積み上げられている。
実香が手塚のところへ行った彩香を待っていると、手塚と彩香が一緒に進路指導室から出てくるのが見えた。仲良さそうに話している。
手塚はきっと何にも気づいていない。彩香のことを優秀で聞き分けがよく、自分を慕ってくれている真面目な生徒、くらいに思っているのだろう。いつだって手塚を見上げる彩香の目は恋する乙女のそれなのに。全く何も疑っていない様子だ。
ただの鈍感なのか、それとも自分が指輪をはめていることで安心しているのか。それにしたって気づかないなんてやはりただの鈍感だな、とひとり結論づける。
仕事は出来るのに、この手のことはからきし、なんていう男の人、本当にいるんだな、なんてまだ出口で話している二人を見ながらぼんやり思う。
それにしても彩香は幸せそうな顔をしている。少し悔しい。どうやったって実香は彩香にあんな顔をさせてあげられない。
すると、彩香が手塚の左手の薬指の指輪にチラと視線をやり、少し俯いた。それを実香は見逃さなかった。
あの子は、なんて馬鹿なんだろう。
でも実香は彩香のそこが愛しくて、すごいと思うのだ。実香には到底真似できないから。彩香はたくましい。
実香は逃げてばかりなのに。
掃除の音楽がかかり、彩香が足早に戻ってきた。
「ごめん実香、待っててくれたんだね! 掃除行こ!」
「ん、全然いいよ。聞けてよかったね」
このもどかしい会話をなんとかしたい。早く、打ち明けて欲しい、手塚のことが好きなんだって。そうしたらこの漠然とした寂しさも、少しはマシになる気がする。
「手塚先生はいつ休んでるんだろう。手塚先生は私たちの幸せを考えて私たちの幸せのために尽くしてくれているけど、じゃあ先生の幸せは誰が考えるんだろう。さっき話しただけでも、先生がすごい忙しいのが伝わった」
廊下を片手でモップがけしながら彩香が言った。
「手塚先生てさ、結婚してるのかな。してるよね。指輪してるもんね。全然そういう話しないけど」
声のトーンが一音落ちた。表情も暗い。やっぱり分かりやすい、彩香は。それなのに、あの鈍感男め。
「先生の幸せなら奥さんが考えてるか」
彩香はそうひとりごちて悲しげに笑った。
「でも、一人暮らしみたいだよ」
実香は何か言わなければ、と思って、クラスの男子が言っていたことを思い出して言った。
彩香はばっと顔を上げると
「それ本当!?」
と明るい声を出した。
「いや、私も本人から聞いた訳じゃないから分からないけど、前に男子がそう話してるの聞いた」
「そうなんだ」
彩香は少し考えているようだった。
学園祭の振替休日。この日は授業も無ければ部活もない。バスケット部の顧問をしていて放課後も休日も部活のために返上し、生徒と同じような生活をしている手塚にとっては貴重な一日休みだ。だがしかし、何もすることがない一日など珍しすぎて逆にどう過ごしていいのか分からない。きっと普段時間がなくて出来ないような買い物や趣味に時間を使えばいいのだろう。だが、生徒たちのことを考えると、彼らは振替休日であっても、昨日の学園祭で勉強できなかった分を今日一生懸命取り戻しているのだろうなと思い、素直に外出する気にもなれない。職業病なのだ。
真面目すぎる性格がたたって、生徒に楽しいことは我慢して勉強しろと言ったからには、自分も同じように享楽を我慢し生徒のために全力でサポートしなければならない、という強迫観念が常にあるのだ。
結局、外出する気にもなれなければ、家でゆっくり休むことも出来なかったので、学校に行き、明日する予定だったテストの採点をしてしまうことにした。
それに休みでも学校で勉強している生徒がいるかもしれないし。その生徒が質問に来るかもしれない。
けれど本当の理由は、ひたすら考えないようにしていたが、昨日の彩香の告白にあった。正直手塚は彩香の昨日の発言に動揺していて、気もそぞろで、外出するにも家でゆっくりするにも、どうしても考えてしまうのだった。それならば集中できることをしようと、学校へ来たのだ。だが、そのことすら手塚は認めたくなかった。
自分と一回りも年下の高校生の告白に、動揺しているなんて。子供の世迷いごとを本気にするなんて、馬鹿馬鹿しい。
それなのに、どうしても思い出してしまう。学園祭の余韻が残る学校、夕日に染まった教室。彩香の赤い頬と、潤んだ瞳。そして震えていた唇。
学生時代に戻ったようだった。
あの瞬間、手塚は少年に戻った。そうして、胸の奥の一番柔くて不安定な所に風が吹きこんで、忘れていた情熱と不安を揺らしたのだった。
「先生はどうして奥さんと住まないんですか」
彩香は言った。
教室で、学園祭の教室展示の後片付けをしているところだった。クラスのほとんどが、テントの運搬やら出店の片付けで外に出ており、教室には彩香と手塚の二人だった。普通担任は後片付けなど手伝わないのだが、彩香が一人で片付けをしているところに通りがかりそのまま手伝っている。
手伝わないわけにはいかなかった。大人でしっかり者のこの生徒は、人に助けを求める、ということをせず、気づかれないところで、気づかれないうちに、一人で何事もやり遂げてしまうのだ。ちょうど今みたいに。手塚は、外でクラスの皆が片付けをわいわい言ってしているのを聞きながら、一人黙々と教室の片付けをする彩香の姿を見て、まただ、と思った。こいつはそういうやつなのだ。自分が通りかかってよかった。
もう外はすっかり日が落ち、夕焼けに、祭りの興奮冷めやらぬ元気な生徒たちの声が響いていた。教室には赤い西日が差し込み、床に座って展示パネルの解体に勤しむ二人の背中をオレンジに染めた。
突然の質問に、彩香を見ると、夕焼けのせいか、頬が赤かった。
手塚は質問に困惑した。一人暮らしであることは手塚も公言していることであり、周知の事実なのだが、奥さん、とは。そして自分の左手の薬指を見て「あぁそうか」と納得した。高校生から見てこの歳で指輪をしていれば普通は誰でも結婚していると思うのか、と。
「奥さんじゃない。結婚していないんだ」
彩香が驚いた顔で手塚を見た。そして指輪に視線を落とした。
「この指輪は、ただのペアリングだよ。婚約指輪でもない。付き合って三年目のクリスマスにプレゼントした。俺は婚約指輪のつもりだったけど、向こうはそう思ってないだろうな」
自分で言って、自嘲気味に笑った。相手にあげたもうひとつのリングが丁寧に箱に入れられて引き出しにしまわれているのを考えて悲しくなった。
実験の時に邪魔だから。それに、無くしたら困るもの。彼女が指輪をしない理由は本当にそれ以上でも以下でもない。それは分かっているのだが、やはりしまわれたままというのは切ないものだ。
そしてちょっとした感傷に浸ってから、我に返って、どうして生徒にこんなことまで話しているのかと焦った。だが彩香はどこか他の生徒より大人びていて不思議と素の自分が出てしまうのだ。しかもそう真っ直ぐな目で質問されたら自然と答えてしまう。
「先生、その人と結婚しないんですか?」
彩香は心臓が跳ねるのを感じたが、必死でそれを押さえつけて平静を装っていた。浮かれたらダメだ。結婚していなくたって、相手がいることには変わりないのだ。それなのにこんな立ち入ったこと聞いて、自分はどうするつもりなのだろう。どうせ傷つくことは目に見えているのに。
「さぁ、どうだろうね。今は出来ないかな」
そう言って少し微笑んだ中に哀愁が混ざっていた。そんなに悲しそうに笑わないで欲しい。彩香は胸が締め付けられる思いがした。当たり前だけど、先生は彼女さんが好きなんだ。
「どうしてですか?」
やめろと頭の中で止める声がしたが聞かずにはいられなかった。深入りしてしまう。
「どうして、かぁ。うーん、いろいろ理由はあるんだけど、当面は、むこうが日本にいないからかな。彼女はアメリカの大学に行っているんだ。その大学の研究室でずっと研究している。成果が得られるまで帰ってこないつもりみたいだから、実際、いつ日本に帰ってくるのかも分からない。もしかしたら帰ってこないのかもしれない」
「え、それでいいんですか」
彩香は驚いて聞いた。
「そんな帰ってくるかも分からない相手を、先生はずっと待っているんですか?」
手塚は、痛いところを突くな、と思った。返答に困る。どう説明しようかと考えて、誠実に対応している自分に驚いた。どうして生徒にこんなありのままのことを話しているんだろう。まるで同年代と話しているようだ。彩香は、この生徒は、不思議だ。
こんな距離を感じさせない生徒は初めてだ。手塚は人には滅多に話さない真理佳のことも、この子には話していいような、聞いて欲しいような気持ちになった。
「分からない。待っていることになるのかな。でも、結婚の約束もしていないし、待ってくれとも言われていない。むしろ、空港で見送った時に私のことは待たないで、と釘を刺されたよ。俺たちの関係は、客観的に見たら付き合っているのかもよく分からないと思う。でも俺は、待っていようと思っていなくたって勝手に彼女のことを好きだし、それは彼女が俺のことをどう思っていようがずっと昔から変わらないことで、どうしようもないことなんだ」
手塚は視線を手元の作業に落としたまま、彩香に話して聞かせる、というよりはまるで自分に確認するかのようにそう言った。
彩香は、頭の中でもうひとりの自分が「だからやめろって言ったのに。馬鹿だな」と自分を嘲るのを聞いた。本当に馬鹿だ。自分で自分を傷付けに行っている。心臓が握られているように痛い。一体どんな返答を期待していたんだろう。馬鹿だな、私は。足元が抜けて奈落の底に落ちてゆくような絶望感だった。浮かれたり、落ちたり、恋愛っていうのはなんて面倒なんだろう。
どうせなら、もっと傷ついてしまいたい。再起不能なまでに。もうこんな面倒からは抜け出したかった。
「私、知りたいです」
「何を?」
そう言って彩香に顔を向けた手塚の輪郭が夕日のオレンジに縁どられていてすごく綺麗だった。こんなに切ないのに、どうしてそばにいることがこんなにも嬉しいんだろう。彩香は眩しくて、泣きそうで、目を細めた。
「先生の、彼女さんのこと。先生が、そんなに好きになるなんて、どんな人なんですか? どうやって付き合うことになったんです?」
手塚は少し考えたが、彩香の真剣な目に若干押されて静かに話し始めた。
「彼女と出会ったのは大学四年の時。俺の大学では、理系は四年の時から研究室に分かれるんだけど、彼女は俺の入った研究室の一つ上の先輩だったんだ。院生ってやつだな。ものすごく頭がいい人で、研究室の中では誰がどう見ても抜きん出ていた。教授と対等に会話ができるくらい知識があったし、頭の回転も早くて、俺の研究室では電子回路やらプログラミングやらをやっていたんだけど、彼女の仕事の速さ、正確さには誰も敵わなかった。分からないことがあれば皆彼女を頼った。彼女は本当に天才だった」
手塚は昔の記憶を慈しむように目を細めた。
〈続く〉
-
-
オレンジ
0










