18歳、秋
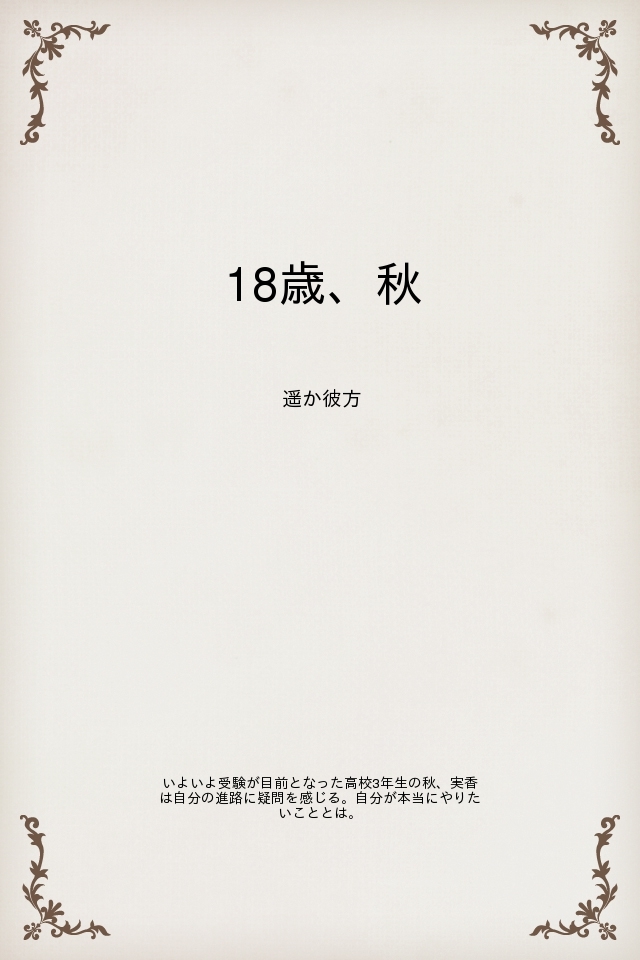
「私、京大受験すんのやめるわ」
三年の秋、いよいよ志望校を確定しだす頃、ミカはあっさりとそう言った。
アヤカは親友のあまりに急な進路変更に戸惑った。
「え、じゃあせっかくミカのためだけに設置してくれた京大対策コースとかはどうなっちゃうわけ。アキ先生の日本史の授業はどうするの。ミカのために開講したのに」
「それを、今から担任に相談しに行くの。担任が納得したらアキ先生のところにも、今日謝りに行くつもり」
「担任にまだこのこと言ってないの!?」
アヤカは驚いて思わず大きな声を出した。
「うん、昨日決めたことだから。アヤカに初めて言った。親にもまだ言ってない」
「親は賛成すると思うけど、担任は納得しないと思うよ。てか、どうせ説得されるって」
アヤカには、驚いて、ミカに考え直すように必死で説得する担任の姿が容易に想像できる。担任は、頑として京大に行けと言うだろう。
「それはどうだろう、結局は私の人生だし、担任もそんなに強く言えないんじゃないかな」
ミカのあまりに楽観的な発言に、アヤカは最早呆れた。ミカは、あの、テヅカという男のことを何も分かっていない。テヅカは、本当にミカの幸せを願っているからこそ、頑なに京大に行けと言うのだ。
「ミカは分かってない。ミカは今までずっと優等生で、テヅカ先生の望む通りの生徒だったから、先生と食い違うところがなかったから、先生も優しくて理解のあるように見えたかもしれないけど、先生の考えに逆らうようなことをするのは本当に面倒だよ。あの人は本当に高学歴イコール人生の成功だと思っているから。その価値観しか知らないんだよ。説得するのは、骨が折れると思うなぁ」
アヤカはテヅカのことをよく分かっている。彼は、よく言えば純粋すぎる。そして真っ直ぐすぎる。だから教え込まれたまま勉強してきて、そのまま学歴社会に何の疑問も持たず、反発もせず、教師になり、同じように勉強していい進学をするのが生徒にとっても幸せだと信じて疑わない。そして、そのためのサポートなら全力でする。
だから、この進学校において、テヅカ信者は多い。そもそも皆そういう価値観からこの学校に進学してきているのだ。そんな生徒からしたら、若くして腕もあり、この福島県内でも有名な進学校の顔とも言える、特進クラスを受け持っているテヅカは尊敬の対象であり、その熱心な教育態度には生徒だけでなく、保護者からの信頼も厚い。
アヤカは、高学歴こそが人生の成功と思っているわけではないのでテヅカ信者ではないが、そんなテヅカをただ、真面目で不器用なのだと思う。そういう生き方しか知らないのだ。
それで、冷静に見えるが実は熱血教師で、いつも生徒のために一生懸命なのがアヤカには分かって、そういうところが好きなのだ。
「それに何より、うちらの代は文系で京大を受験するのはミカだけなんだから担任は譲らないと思うな」
アヤカが言うと、ミカは
「そんなの関係ないじゃん」
と肩をすくめた。
「確かにうちらにとっては何人東大に行って、何人京大に行って、そのうち文系は何人、理系は何人、なんて本当にどうでもいいけど、学校からしたら、次の優秀な人材を集めるのに大事な結果なんだよ」
こう考えると、自分たちは商品のようだ、とアヤカは思った。
受験というマーケットに売りに出される学校という店の商品で、差し詰めテヅカは優秀な営業マンといったところだろうか。
テヅカはミカからこの話を聞いたら一体どんな反応をするのだろうか。
期待していた優等生のミカに突然期待を裏切られる担任を見てみたい、とアヤカは思った。若くして貫禄を出しているあの冷静な数学教師の取り乱すところを見てみたい。アヤカの前だって、テヅカはいつも大人で、すましていて、焦ったりはにかんだりしない。
いいな、ミカは。成績優秀で頭がいいだけで、無条件にテヅカに気に入られて、アヤカがどれだけ頑張ってみたところで崩せないテヅカの平常を壊すことだって出来るのだ。アヤカはミカに、少し嫉妬した。
「確かに、担任は、そういう節はあるけど、大丈夫だよ。話せば分かってくれる」
ミカのこの自信に満ちた発言に、アヤカは、ミカは単に楽天的なわけではなく、決心がよっぽど硬いのだ、と悟った。こういうところも羨ましい。アヤカは、これが惚れた弱みというのだが、テヅカに打ち勝てる気がしないのだ。
「一体、どうしてなんだ」
テヅカはミカが予想していたよりはずっと冷静だった。動じていない。だが、そこにミカを言いくるめられる、という大人の余裕を感じて、ミカは、これは一苦労だ、と覚悟を決めた。
「オープンキャンパスに行って、嫌になりました」
我ながら、バカみたいな言い訳だ、とミカは自嘲気味に思った。もっとマシな言い訳はないものか。これでは高校受験する中学生のようだ。そして、想定通りに、
「具体的に、どこがだ」と聞かれた。
ですよね、と思いつつ、
「えーっと、なんか、デモみたいなことしている人達がいたり、宗教団体が構内をうろついていたりしていたから…」とでまかせを言う。
「そんなことはどこの大学にもあるよ。それにデモがあるのも、学生が社会に興味を持って活発に行動している証拠だよ。いいことだと思うけどなぁ」
「でも、怖かったんです。それに、親も近くの方がいいって言っていましたし」
これは嘘じゃない。
「なに言ってんだ、京大に合格したらそれが一番に決まっているだろう」
でた、高学歴絶対価値観。この学校の先生はみんなそうだ。みんな、高学歴であればあるほど良いと思い込んでいる。しかもタチの悪いことには、世の中には学歴やテストの点数なんかよりも大事なものがあるという考えを理解できないでいる。ずっとそう教えられてきて、さらにその通りに生きて、それで教師になり成功しているものだから、それが絶対であると思っているのだろう。そしてまた自分の二世を生み出しているのだ。
「お言葉ですが先生、うちの親はきっとそうは思っていませんよ。本当に近くにいて欲しいと思っています」
そう言われたことはない、だが本心ではそう思っていることが確実に分かる。そして、父親が、実家から通えるような近場の大学に行って欲しいと思っているはずなのに、決してミカにはそう言わず、「好きなところに行ってやりたいことをしろ」と言うことが、ますますミカに、父親の本心から目を背けづらくしたし、いたたまれない気持ちにさせた。
あの人は一体、ミカが本気で京都にでも行ってしまったらどうするつもりなのだろうか。奨学金をもらって、バイトをして、なんとか一人暮らしは出来るにしても、家はどうなるだろう。家事は誰がやるのだ、それと、寝たきりの祖父の世話も。仕事もして、祖父母の畑も耕して、家事と祖父の介護を一人でするなんて、今度こそ父親は本当に死んでしまうのではないか、とミカは思った。
「まぁ、お前がいなくなったら親父さんは家にひとりになるし、気持ちは分かるけど、お前が京大に行くことも十分親孝行になると思うけどな。娘が京大に通っているなんて誇りだろう。将来だって心配しないで済むし、親父さんも安心してこっちで暮らせるんじゃないか」
ミカは、担任のあまりに主観的で呑気な意見に目の前が暗くなった。この人はなんにも分かっていない。まぁ、ミカも、自分の置かれている状況を分かってもらおうとしていないから、担任のこの態度も仕方ないと言えば仕方ないのだが、それにしたってこんなにも分かり合うことが困難だと思うことはそうそうない。アヤカの言った通り、説得するのは骨が折れそうだ。
「それになにより、親父さんのこととかを抜きにして、お前は京大目指して一年の頃から頑張ってきたんじゃないのか」担任が食い下がる。
「それは、一年生の時なんかは、大学の名前なんかまず有名なところしか知らないから、めざせ東大、京大とか言っておけば格好もいいし、モチベーションも上がるからそう言っていただけで、全然具体的に自分が京大に行くビジョンなんて持っていなかったんです。二年生の時も、先生が、初めから偏差値の高いところを狙っていれば、いざ受験の時、選択肢を沢山持てるし、どんな大学にも対応出来るから、志望校は下げるな、って言うから、それに従ってやってきただけなんです。本当に、それだけなんです」
テヅカは驚いた。果たしてそんな気持ちでこの時期までずっと成績を維持できるものなのか。今まで、東大や京大、早大レベルを目指して勉強してきたどの生徒も、その大学に対する憧れや、行きたいという確固たる決意のもとに、苦労して難関大学を受験するに足るレベルにまで成績を上げてくるのに、テヅカにとってミカは不可解でしかなかった。一体何故そんな漠然としたモチベーションで、この、福島の田舎といえど、県内でも有名な進学校の学年トップに君臨し続けることができているのか。不思議でならない。
「お前は、負けず嫌いなのか」思わず聞いた。
「いえ、ただ勉強が性に合っていて、好きだっただけです」
その言葉もテヅカに衝撃をもたらした。受験勉強は、長く苦しい戦いであり、だからこそそれに打ち勝った暁には、勝者としての人生が得られるものだ、と考えていたからである。勉強で苦しんだものは、後で楽が出来る。そして勉強から逃げ、楽をしたものは、後で苦しむことになる。これがテヅカの持論であった。変わったやつだ、と思った。
勉強が好きだというのは嘘ではない。
ミカは昔から読書が好きだった。最早ミカにとって読書は、趣味という枠では収まらず、生活そのものだった。時間さえあればのめり込むように本を読んだ。本を読んでいれば、その間だけは、現実から離れていられるからだ。本を読んでいるその間だけ、悲しくて鬱陶しくてやるせない現実を忘れていられる。どんな本でも良かった。小説でも、実用書でも、図鑑や辞書であっても構わなかった。そこに新しいことや知らなかった気持ちが散りばめられているだけで、ミカは集中出来たし、そっちの世界に行けたのだ。ミカにとって本を読むことは、呼吸に等しく、時には麻薬であった。
だが、家から近いから、という理由で県内でも有名な進学校に進学すると、ミカから読書の時間は残酷にも尽く奪われた。毎日の予習復習と課題と、ずっと続けている空手の稽古で一日はあっという間に終わった。本を読む時間はなく、ひたすら勉強のために机に向かった。ミカははじめ、そんな生活に焦りを感じていた。「早く課題を終わらせて、睡眠時間を削ってでも本を読まなければ」「このままずっと本を読めない生活が続いたら、自分はどうにかなってしまうのではなかろうか」
しかし、ミカの焦りは杞憂に終わった。勉強が読書に取って代わったのだった。勉強をしている間も、本を読んでいる時と同じく、現実を忘れていられる。暗記をしているとき、数学の問題を解いているとき、ただひたすら没頭していられた。それが楽だった。だからずっと勉強していた。そしたら気づくと学年トップになっていて、知らぬうちに京大に行くことになっていたのだった。
そして秋になり、受験にリアリティが感じられるようになって、ふと、このままではいけないと思った。急に危機感を覚えて、現実に目を向けると、母親に取り残された父親と、寝たきりの祖父と、仏壇に祖母と母の写真があった。現実はつらい。これが小説だったらよかったのに、と願った。でも現実はいつもそこに、ずっしりと横たわっているのだ。
今までミカが目をつむっていただけで。
ミカが教室に戻ると、クラスメイトが何人も残って勉強していた。アヤカも部活を引退してからは、ほぼ毎日学校から追い出される八時まで教室で残って皆と勉強して帰る。ミカは空手の稽古がない日はアヤカと一緒に八時まで勉強して帰るが、一週間のうち、稽古がない日の方が少ない。
アヤカが、
「どうだった」と聞く。
「確かに説得するのは難しそう」
「どうすんの」
アヤカは心配そうにしている。
ミカは持ち前の楽観主義で、
「んー。なんかでも別に、最悪担任に納得してもらわなくてもいいんじゃないかな。勝手にするよ。誰に分かってもらえなくても、私の人生だし」と軽く言う。
そう、これはミカ自身の人生なのだ。
するとアヤカは意外な反応をした。
「ま、担任が分からなくても、私はミカの味方だよ。ミカの考えていること、分かるよ。お父さんが心配で、おじいちゃんの世話をしようと思っているんでしょう。担任の言っていることなんて、確かに無視しちゃってもいいかもね、最悪」
ミカは驚いた。アヤカがこんなことを言うなんて。アヤカはいつも担任を尊敬していて、担任の肩ばかり持つし、反発する者もよく思っていないのに。そんなアヤカが、ミカの味方だと言ったのだ。ミカは、不意にも感動してしまった。
「ありがとう、アヤカ」
でも、それだけではないのだ。本当の理由の方は、今はまだ誰にも言えない。担任にも、親にも、アヤカにも。
本当はアヤカには言いたい。今すぐにでも。だが、アヤカがテヅカと親密であり、さらに東大を目指して頑張っていることが、ミカにそれを躊躇わせた。こんな時期にそんな夢見がちなことを言って、受験から逃げているとでも思われたらどうしよう。そんな不安が胸をよぎるのだ。
そんな私の胸の内など知らずに、アヤカが続ける。
「なんか、つらいことがあったらいつでも言って。私は、聞くことしかできないかもしれないけど」
「うん、ありがとう。アヤカも、なんでも言ってね。特に先生とのこととかさ。私は悪いふうには思っていないから」
「それに関しては、ミカにしか話せていないから本当に助かる。いつも頼っちゃってごめんね。こんな、誰にも言えないような話しちゃってごめん」
「全然いいよ、それより溜め込んじゃダメだよ。最近はどんな感じなの?」
「うーん、最近はね、どうなんだろう。もう向こうも忙しいし、私も本当に勉強しなきゃだから前みたいに会ったりはしていないんだけど、それでもメールはずっとしているし、休みの日も学校に来て、勉強教えてもらったりとか……。あ、それは普通か。でもたまに、先生の家で教えてもらうこともある」少し照れた感じに笑った。
ミカは、テヅカのことを話すときのアヤカの、はにかんだ感じとか、照れた感じが可愛いなと思った。好きな人の話をする時、皆こんなに急に女の子になるのだろうか。これが恋か。ミカにはまだよく分からない。
でも、テヅカのことを話すアヤカは、嬉しそうでいて、だがやはりどこかにいつも切なさや悲しみが入り混じっていて、それがまたミカの胸を締め付けた。
どうしていけないと分かっている人を好きになるのだろう。どうしてテヅカはアヤカを突き放せないでいるのだろう。どうしてふたりは関係をあやふやにしておくのだろう。どうして。
どうして人は、一人では生きていけないのか。
ミカは、母親が入院した時のことを思い出していた。
新緑の木々が眩しい初夏のことだった。周りは命の輝きに満ち溢れていたのに、ミカの家には死の影が忍び寄っていた。
当時ミカはまだ小学三年生で、ただただ母親が死ぬのではないかと、毎日怯えていただけだった。小学校にいても、いつ教室の電話が鳴って担任の先生が「ミカちゃん、お母さんが……」と言い出すのかひやひやしていた。だから毎日学校が終わると、今日も母親がまだ息をしているか、大急ぎで病院に確かめに行った。母親の時間が残り少ないことを感じていて、学校が終わってから眠くなるまでずっと母親の隣でおしゃべりをしたり、母親が疲れて眠ったら宿題をやったり漫画を読んだりしていた。
母親が入院していた時の父親は大変だった。ミカは、あの時ほど父親の憔悴しきった姿を見たことがない。
母親の胸に癌があると分かった時、父親は冷静だった。「早期発見すれば癌は怖くないし、むしろ早くに見つかって良かったよ」と母親を励ましていた。だけどその日の夜、父親が書室で一人泣いているところを見て、ミカは幼心に、「あぁ、もう母親は手遅れなのだな」と悟った。ミカはその場面をまだ鮮明に覚えている。泣くことなど永久に無さそうな父親の涙は、幼いミカには衝撃的だった。絶望と悲しみが父親の肩に手を乗せているようだった。ミカが父親の涙を見たのは、あとにも先にもあの時だけである。父親は、母の葬式の時も、実の親の葬式の時も、一度として涙を見せることはなかった。
父親は相当ショックだったはずなのに、そんな様子はおくびにも出さず、仕事へ行き、帰ってきては家事をして母親の看病にも足繁く通った。ほとんど寝ずに母親について、そのまま仕事に出かけることもあった。精神的にだけではなく肉体的にも父親に限界が来ていた。
そしてそんな父親を気遣うように、その年の秋、母親は息を引き取った。
父親はそれから、小さくなってしまった。それまで、特にこれといって仲の良い夫婦ではなかったが、それとは関係なしに、母親が死んだことによって父親の半分も一緒に死んだかのように思えた。
一人で生きていたはずなのに、いつの間にか誰かがいないと生きていけなくなってしまうものなのだろうか。父親の半分は一体どこに行ってしまったのだろう、何によって作られていたのだろう。
それともはじめから一人で生きてなどいないのだろうか。
でも、ミカは今、自分は精神的には、一人で生きている、と思った。
ミカは家に帰るとまず真っ先に仏壇に手を合わせる。仏壇には祖母と母親の写真が飾られている。それから祖父の様子を見に行く。祖父は、母が亡くなってから急に老化が進み、すぐに寝たきりになってしまった。
娘に先に死なれた悲しみなど想像もできないが、母が亡くなってからの祖父の弱り方は、まるで母の後を追おうとしているようで、ミカは切なくて見ていられなかった。
祖父に食事をとらせておしめを替え、あとはたまに様子を見るくらいで、祖父を見ていられるリビングのテーブルでひたすら勉強する。お腹が空いたら適当になにか作って食べて、父親が帰ってくる時間になると風呂を沸かしておく。父親は家に帰るなり風呂に入ってお酒を飲んですぐに寝てしまう。酒を飲むので夕飯は食べない。この日も父親は八時に帰ったと思ったら九時には寝室に引っ込んでしまった。朝が早いのだ。いつも午前三時に起きてまだ暗いうちから畑に出る。そして夜が明けるくらいの時間に出勤していく。だから朝、父親とミカが顔を合わせることはほぼない。父親にとって家は最早風呂に入って寝る場所でしかない。こうしてミカはまた父親と受験の話をする機会を逃してしまった。疲れているのが分かるので、自分のことで煩わせたくない。この話は明日の夜にでもしよう。
そして寝静まった家のリビングでまた一人勉強するのだった。
けれど、本が読みたい、と切実に思った。高校に入ってからは勉強に追われて久しく本など読んでいなかったが、一昨日、久しぶりに本を読んでから、また本を読みたいという欲求に駆られるようになった。
一昨日も、父親が寝静まった後に、祖父の様子を見つつ一人リビングで勉強していた。勉強に飽きて、でもまだ眠りたくなくて、ふと、久しぶりに本が読みたいと思った。本を開くと、活字の並びと、紙の手触りが、とても懐かしく感じられた。文字が目から吸収されて脳へとどんどんと流れていくのが心地いい。ミカは文章の濁流に飲まれてただなされるがままその流れに身を任せた。かつてそうしていたように。安心した。やはりここは時間が経ってもミカの居場所だ、と思った。やっぱり、ずっとこの世界にいたい。ただ現実逃避のために本を読んでいたと思っていたが、どうやらそれだけではない。ミカにとって読書は疲れた心を癒してくれる精神安定剤だったのだ。
「ミカ、京大、受けるだけ受けてみればいいのに。せっかくここまで勉強したんだから、行くかどうかは別にして、記念受験的な」
夜、珍しく不安になり、勉強に集中出来なくなってしまって、アヤカに電話した。アヤカは、ミカが京大を諦める決断をしたことを不安になっているのだと思ってそう言った。この言い方からすると、恐らくアヤカは、「ミカは、本当は京大に行きたいと思っていて、けれど落ちるのが怖いから、家の事情などを理由にはじめから受験をリタイアしようとしている」とでも思っていそうだ。
けれどミカの不安はそんなこととは全然違うところにある。漠然としたこの不安は、そもそも先が見えないことから来ている。京大に行ったあとのビジョンが全く見えない。見えたとしても、それは、父親が死んでから、後悔する最悪のイメージだ。
「そんなことするわけないでしょ、私立の学校なら話は別だけれど」
「まぁ、そうだよね、ごめん」
一瞬沈黙があった。ミカは本当のことをアヤカに言おうか迷っていた。いざ言おうと思うと緊張してドキドキする。もしかしたら、分かってもらえるかもしれない。でも、逆に軽蔑されるかもしれない。馬鹿だと呆れられるかも。
「私はミカの味方だよ」アヤカが放課後にミカに言った言葉が思い出された。ミカは、意を決して話すことにした。
「アヤカ、あのね、私、確かにお父さんのことが心配で、おじいちゃんの世話もしなくちゃと思っている。でも、それだけじゃないんだ。私、なりたいものがあるの。夢があるの。それで、この前、あ、このまま流れにまかせて京大に行ってはいけない、と思ったの」
「夢があるなんて初耳。何? どうして京大ではだめなの」アヤカは興味津々だった。
「私ね、本が好きなんだ。それで、小説家になりたいんだ」
心臓が飛び出そうだった。電話越しで本当に良かった。きっと今自分は、とても真っ赤になっているだろうな、とミカは思った。アヤカの反応をじっと待つ。
「そっかぁ、小説家かぁ。それはまた、一筋縄ではいかないね。でもどうして京大ではだめなの」
アヤカの反応は意外だった。ミカは、アヤカなら分かってくれるかもしれないと思った。
「京大に行く必要がないんだ。私には学歴なんて必要ないの。それに、京大に行くことになったのは私の意志ではないし。それに、京大に行くことで大切なものを失うのが怖い。さらには、夢を叶えられなくなる気がする」
「京大に行くことで大切なものを失うってどういうこと」
「うーん。うまく説明できないんだけど、ただイメージの問題なだけなのかもしれないけど、なんかね、私ね、これまでつらいことから目を逸らし続けてきたの。まともに考えないように、向き合わないようにしてきたんだよね」
「うん、それで?」
そう続きを促すアヤカの声が優しい。それだけでミカは、涙ぐみそうになった。アヤカはミカの家のことをよく知っていたから、色々とミカの心のうちを想像しているのだろう。
「それで、私は、現実を見ないでいるためにひたすら勉強していた。勉強していれば誰にも何も言われないし、常に問題を考えていれば他に余計なことは考えなくて済む。楽だったんだ。それで、勉強してたら、先生に、京大を目指せって言われた。別にそれでも構わなかった。将来やりたいこともなかったし。でもね、最近思ったんだ。」
「なに?」
「このまま現実逃避して勉強していただけのことで京大に行って、おじいちゃんのこともお父さんに任せっきりにして家から離れてもっと現実から逃げてしまったら、あとで、すっごい後悔することになるって。皆死んでしまったら親孝行も何も出来ない。そんなにつらいことはないと思う。後から自分の人生は空っぽだと気づいたのでは遅すぎるんだよ。私には予感がするんだ。京大を卒業しても、また受験の時と同じように周りの思惑や状況に流されて就職して、また与えられたことをこなしていて、気づいたときにはもう取り戻せない時間が山積みになっている、そんな予感がするの。それに、もう現実逃避に時間を費やして無闇に生きるのは止めようと思って。それじゃあいつまでたっても自分の人生を生きているとはいえないじゃん。やりたいことも、やっとみつけたんだ」
「それが、小説なんだね」
「うん、そう。一昨日、久しぶりに本を読んだの。小学校の時に、初めて読んで、すごく面白くて、私が小説にハマるきっかけになった本。あの本に、おかえりと言われた気がしたんだ。それで、あぁ、私はこの世界をずっと漂っていたい、この世界で生きていきたいと思ったの。バカみたいなこと言っているよね」
自分でも、夢をみていると思う。
「いや、そうは思わないよ。いいじゃん、夢見て。ミカの小説、読んでみたいよ。すごく素敵だと思うよ。応援する。頑張れ」
アヤカは、嘘はつかない。ミカは嬉しくなって、心の底から打ち明けてよかったと思った。
「ミカは偉いね。すごいよ。私はミカを尊敬する。強い」アヤカが急に褒め出すから
「どうしたの急に、やめてよ」
と慌てて謙遜すると、アヤカは少し落ち込んだ声で、
「それに比べて私なんて、将来のことも、今のことも、ちっとも向き合えてなくてダメだなぁ」と言った。
「先生とのこと?」ミカが聞く。アヤカは、
「うん。どうしたらいいんだろう。もう、よくわからないや」と笑った。
ミカは何も言えなかった。恋愛の経験のないミカには何を言ってあげることも出来ない。そんな自分が歯痒かった。
「ね、ミカが夢の話をしてくれたから、私も私の夢を話してもいい?」アヤカが唐突に切り出した。
「もちろんだよ、むしろ聞きたい! お願いします!」ミカが答える。
「じゃあ聞いて。あのね、私の夢はね、先生と結婚することなんだ。驚いた? バカみたいでしょう?」
驚いた、というか、衝撃が胸を貫いた、と言ったほうが正しい。なんてことだろう。アヤカはテヅカを愛しているのだ。
「そんなに…」その先を言えずにいると、アヤカが
「うん、そんなに好きなの」と続きを引き取った。ミカは
「驚いたけど、バカみたいだとは思わない。むしろ、この年で、そんな風に思える人と出会えたこと、羨ましく思う」と言った。本心だった。
「叶うといい。心からそう思う」願いを込めて言った。
「ありがとう」そう言ったアヤカの声は涙ぐんでいた。
切ない。苦しい。
アヤカの現実も、向き合うには辛いものがある。
アヤカが、担任の左手の薬指に光る指輪に目を向ける度、それを見てミカは悲しくなる。
現実はいつだって厳しいのだ。
時間を見るともう丑の刻になろうとしていた。部屋の温度も冷えてきて、夜の冷たさに身震いした。
「寒くなってきたね。これから、冬が来るね」とミカが言うと、
「秋なんてあっという間だからね。覚悟しなくちゃ」とアヤカが言った。
覚悟、か。
ミカは、秋の夜長に、受験勉強そっちのけで読書でもしてやろうかな、と思った。
これから来る、現実を思わせる厳しい季節に備えて。その次に来る芽吹きの季節のために、収穫の秋を楽しまなければ。
〈終わり〉
-
-
18歳、秋
0










