仮想現実を
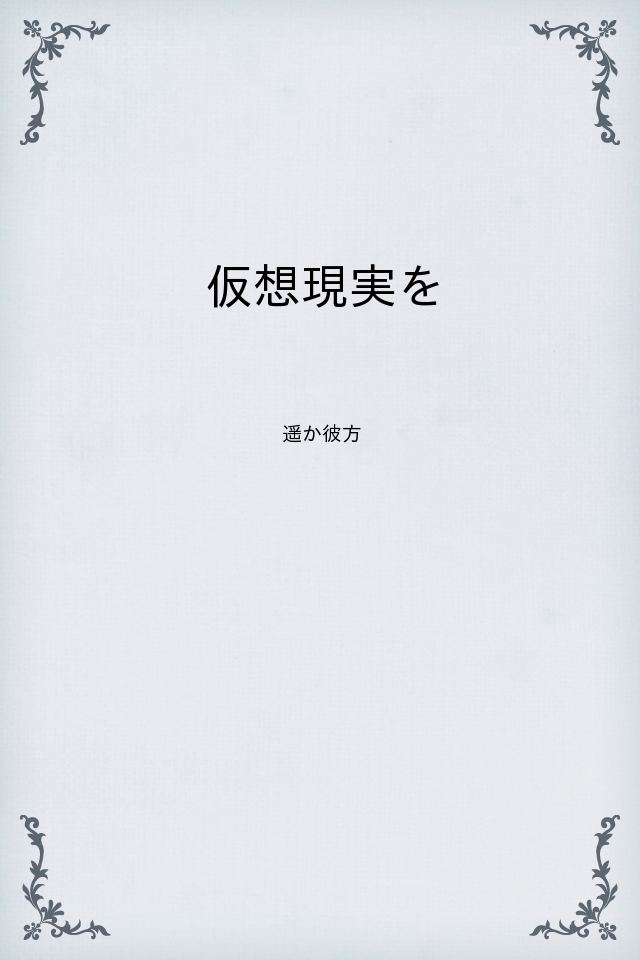
僕の鼻がもうちょっと高かったら。
僕の背がもうちょっと高くて、足が胴に比べてもうちょっとだけ長かったら。
僕の記憶力がもうちょっとだけ良くて、効率も良くて、ついでに野球の才能があって、クールで、女子にもモテモテだったらなぁ。
僕のこの冴えない人生も、もっと変わっていただろうな。
そんなやつになれていたら、人生さぞ楽しいのだろうなぁ。
そして僕は今日もノートにペンを走らせる。
もし僕がそんな奴だったらって空想して。
最近の僕は、横にいる容姿にも才能にも恵まれた親友を横目に、そんなことばかり考えている。そして、僕はその親友をモデルに密かに小説を書いている。僕がこの主人公だったらって、妄想しながら。
僕の親友の勇は、僕の隣の家に住んでいて、小さいころから一緒に遊んでいた幼馴染である。勇は僕とは違って、精悍な顔つきでスタイルもいい。野球のセンスもあって、一緒に始めたリトルリーグのころから勇のセンスの良さは際立っていた。今ではうちの中学のピッチャーで四番、内実ともに頼れるキャプテンだ。
それに引き換え僕はといえば、勇と一緒に野球を始めたにもかかわらず、今では勇との実力の差は歴然になってしまって、三年になった今でも上手い二年にレギュラーを取られやしないかびくびくしている状況である。
勇は勉強も出来る。成績優秀で、先生たちにも一目置かれている。僕は成績のことは今まで気にしてこなかったけど、高校受験を目前にした今となっては、もっと勉強してくればよかったと頭を抱える状態だ。勇は実力でも県内でも有名な進学校を選べるし、有名私立からも野球の実力で声がかかっているらしい。それに比べて僕は模試の結果を見ると目の前が真っ暗になる有様だ。
どうしてこんなに僕たちの間に差が生まれてしまったのだろう。
いつから僕はこんなにも勇に引け目を感じるようになって、次第に羨ましがって、挙句の果てには妬ましくも思い始めてしまったのか。
子供のころは、あんなに純粋に友達だったのに。
勇のことを考えると、心の端に黒い渦が出来るようになったのはいつからだ。
勇が困っている、悲しんでいるとき、どうにかしてあげたいと、親友のためなら何でも出来ると、熱い友情を燃やせなくなってしまったのはいつからだ。
僕の心に黒い煤がつき始めたのはいつから。
中学一年生の春、僕は人生で初めて人を好きになった。
初恋だった。誰かのことをあんなふうに情熱的に思い続けたのは初めてのことだった。
僕は中学一年生の春、見事に中一ギャップに直面し、軽い鬱状態になっていた。
中学にあがって、それまでの小学校の友達とは離れ離れになり、人見知りをする僕は新しいクラスにも上手くなじめず、部活も、勇と一緒に野球部に入部したものの、上手い勇が先輩にも監督にも認められてどんどんチームの主力になっていっているのを見ながら、いつまでも他の、ほぼ初心者の新入部員と一緒に球拾いをするのは苦痛でしかなかった。
野球は好きだったけど、勇がいる部活は嫌だった。でも次第に野球も嫌いになっていった。勇ばかりちやほやする先輩たちと監督。実力がないと認められない世界。結果主義の世の中。
そのうち学校もつまらなくなった。勉強する意義を見出せない。どうしてみんなと同じ格好をして同じことをしないといけないのか分からない。
こうして僕はまんまと中一ギャップにはまった。
そして世の中は灰色一色になった。
そんな僕の目の前に、鮮やかなピンク色の桜の花びらが舞った。
彼女に恋したとき、たしかにそれが見えた。彼女はクラスに上手く馴染めないでいる僕を察してか、度々僕にかまった。優しい子だった。人懐っこく明るい子で、僕はそれが全然嫌じゃなかった。僕はあんまり女の子と話すのは得意じゃなかったけど、彼女には自然と心を開いていた。ある日僕は、灰色の世界にこらえきれなくなって、勇気を出して
「世の中が灰色に見えるんだ」
と彼女に打ち明けた。彼女は泣いてくれた。
「つらいね」と言って泣いた。
彼女が泣くから、僕も泣けてきて、泣いたのはそのとき初めてだった。まだ涙なんて出せるのかとほっとした。
泣いたからなのか、胸の内のもやもやを誰かに打ち明けられたからか、その後本当に胸がすっきりとして、同時に、彼女のことをとても好きになった。初めて、人を愛しいと思った。
僕の世界は色を取り戻していった。
僕と彼女はとても仲良くなった。異性の初めての親友になった。
そんな彼女が、一年の終わりに、僕に隠し続けてきた胸の内を明かしてくれた。
あのときの絶望感と喪失感を、僕は忘れられない。今でも思い出して、胸にぽっかり穴が開いたような気分になる。
「私ね、これ、ほんとに誰にも言ってなかったことなんだけど、実はね、四月からずっと、勇くんのことが好きなんだ」
彼女は、神聖なことを口にするかのようにそういった。声に出して言うのが躊躇われる程の思いを抱えていたんだなと、彼女の言い方から僕には分かった。彼女の目に光が揺れて、頬が赤く染まった。こんなに恋をしている彼女の顔を、僕はその時初めて見た。
どうしてあんなに一緒にいて、全く気づかなかったのか、彼女の告白は衝撃以外の何でもなかった。足元がそっくり抜け落ちて、暗闇に落ちていく感覚。体中の血が冷水に変わった。僕は、彼女が一世一代の秘密を僕に打ち明けてくれたという喜びと、その秘密を受け入れたくないのとで、大変複雑な心境だった。それでもその場は、彼女に動揺を気取られないように努めて冷静に振舞った。
「そうなんだ。全然、気づかなかった。同じクラスだけど、そんなに話しているところも見かけなかったし」
平静を装う自分の声が白々しくて自分が言った台詞なのか分からなかった。
「私、好きな人の前だと何も出来なくなっちゃうの、緊張して。話しかけたりとか出来ないよ。見てるだけで精一杯だった。それで、一年過ぎちゃった」そういって照れている彼女の顔が最高に可愛くて、僕は胸が押しつぶされそうだった。
「せっかく同じクラスだったのに」
僕は、まるで僕じゃない誰かが僕の体を借りてそう言っているかのように自分の言葉を聞いた。普通に会話を続けているこの男は一体誰なのだろう。僕の頭はちっとも何が起こっているのか理解できていないままなのに。
「うん、そうなんだ。ばかだよね。せっかく同じクラスだったのに、なんにも出来なかった。また二年生になって同じクラスになれる保障もないのに」
目から光を失っていく僕には全く気づく素振りもなく、逆につぶらな瞳に揺れる光を湛えながら彼女は続ける。
「違うクラスになったら、もう見ることもなかなか出来なくなっちゃうな」
切なそうな顔をするから、こっちまで切なくなる。
僕も何にも出来なかった。自分の気持ちは何一つ伝えられないまま、失恋してしまった。
「それで、どうするつもりなの」
また僕は、自分の声にびっくりした。あまりに普通の声で、何気なく聞くものだから、本当に自分じゃない誰かが僕を操っているようだ。こんな時でも、僕は上手に本心を隠して相手の話を聞けるらしい。
でも、もうひとりの僕は、彼女が今になってずっと胸に秘めていた思いを打ち明けたのだから、何かするつもりなのだろう、と冷静に思っていた。
「告白、しようと思うの」
やっぱり、と冷静な僕が言った。現実を受け入れられない僕は耳をふさいだ。
だけど、彼女の目を見て、覚悟の強さを思い知って、僕は自分のやりきれなさを同情した。
それからしばらくの、僕の勇に対する態度は、はっきり言うと、ぎこちなかったと思う。自然にしようと意識すればするほど不自然になって、今までどんなふうに勇に接していたか分からなくなって、普通に出来なかった。
勇と居ると常に
「もう告白はされたのだろうか」
「こいつはそれにどう答えただろう」
「彼女のことをどう思っているのだろう」
なんてことを考えてしまう。しまいには
「付き合ったのだろうか、だったらなんで言ってくれないのだろう」
「そもそも告白されたならそれも言ってくれるはず」
「言わないのは、僕のことを信用してないからだろうか。俺が誰かに言うとでも思っているのだろうか」
「それとも実は僕が彼女のことを好きなことに気づいていたのだろうか。そうだとしたら、僕に同情しているのか」
「そもそもこいつは僕のことをどう思っているのだろう」
なんて疑心暗鬼になって、勇との友情さえ疑い始めてしまう始末だ。
僕からは何も勇に聞けない。もちろん彼女にも。
僕は臆病者だ。
それから、僕たちは二年生になり、彼女と勇はクラスが別れた。
そして幸か不幸か、僕と彼女はまた同じクラスになった。
「勇と、クラス別れちゃったね。残念だったね」
これが僕の、その話題に対する精一杯のアプローチだった。
彼女は言った。
「うん、でもいいんだ、もう思い残すことはないから。告白して良かったよ。まぁ、ふられちゃったけどね」
彼女はすっきりとした顔をしていた。それから
「優とはまた同じクラスになれたしね」と、僕をみて笑った。
なぜだろう、僕はその笑顔をみて、喜んでもいいはずなのに、ちっとも嬉しくなかったし、まるで僕が失恋したかのような気分になった。それに彼女の切ない顔よりもそう言って僕に笑いかけた顔のほうがよっぽど僕を切なくさせた。
「どうして」
そういって僕は泣いた。自分が失恋したときは全然出てこなかったくせに、こんな時にだけお節介に涙なんか出てくるものだから、恥ずかしくて仕方なかった。
彼女は呆れているだろうかと思って顔を上げると、彼女も涙ぐんでいたから、ますます僕の涙は止まらなかった。
どうしてこうも、世の中はうまくいかないのだろう。
そして僕は、勇が僕に彼女から告白されたこと、そしてふったということを言わなかったのは、彼女のためだったのだとすぐに悟った。勇はそういう男だ。
勇は、いつでも僕が欲しくてたまらないモノを持っている、そして、僕が欲しくてたまらないモノを、あっさりと捨てる。
もし、僕があいつだったら、絶対に彼女を幸せにしたのに。
僕が勇だったら、彼女を幸せに出来たのに。
めでたく、友情の疑心暗鬼は晴れ、ぎこちない態度も治ったけれど、でも、それからもう以前のように勇を素直に好きでいることが出来なくなった。小学校の頃のような絶対的な友情を感じられなくなってしまった。もちろん、そのことに関して勇は何も悪くはない。僕が勝手にコンプレックスを感じて、やっかんで、羨ましがっているだけなのだ。
もし僕が勇だったらと考えて、都合の良い仮想現実に夢中になっているだけなのだ。
見た目も格好よくて、頭もよくて、スポーツの才能もあって、人望もある。そして僕の好きな人が僕を好きでいる。一体どんな世界なのだろう。
どうして僕は勇として生まれて来なかったのだろう。
どうして僕はこんなにも不完全で、完璧な勇の隣にいるのだろう。
そして僕は、小説を書き始めた。
僕が勇で、そしてめでたく彼女のことを幸せにする話を。
「勇が羨ましいよ」
部活の引退試合の帰りのバスで、僕は勇に言った。
試合は感動的な内容だった。負けてしまったけど、県大会ベスト四まで勝ち進んだことは、うちの中学の野球部の歴史を振り返ると、快挙だった。
「なんで」
いつものポーカーフェイスで勇が答える。このポーカーフェイスのせいで、よく勇はクールだと誤解される。
「生まれつきのヒーロー気質が、だよ」肩をすくめてみせる。
「どうゆう意味だよ」
「お前は英雄になるために生まれてきたようなやつだよ。今日だって、試合には負けたけど、勝負には勝った。あのピッチャー、お前があのヒット出さなきゃ、完封だったぜ。結局お前のことは三年間、誰も封じ込めなかったな」
ふん、と嫌味っぽく言ってしまった。どうしても、勇のことを素直には認められない自分がいるのだ。
ちなみに僕はまんまと封じ込められて、一回もバットに当てることさえできず、ベンチに下げられ、ベンチでチームの最後を見守った。三振の後、監督から交代の指示を受け、自分が悔しくて、情けなくて、溢れそうになる涙を、歯を食いしばって堪えた。気を緩めるとすぐ最後のチャンスで失敗した自分を責めて、後悔の念に襲われるから、必死に声を張り上げて最後まで応援した。僕の中学野球はこうして悔しさと後悔を残して幕を閉じた。
「そこじゃねぇよ、生まれつきってどうゆう意味か聞いてんの」
珍しく勇がつっかかってきたからドキッとして、ついたじろいでしまう。
「だってそうだろ、お前は恵まれてんだよ。父親元プロ野球選手だし、そりゃ野球も上手くなるし、期待もされるよ。サラブレットだもんな。はじめから俺らとは持ってる才能が違うよ」
つい勢いで、ずっと思っていたことを言ってしまった。しまった、勇は元プロ野球選手の父親の話をされるのが嫌いなのに。
「…お前、それ本気で言ってんの」
予想外に勇がショックを受けた顔をするので、僕は動揺して、言いたくもないのに止まらなくなって、気づいたらどんどん勇を傷つけてしまっていた。
「本気だよ。だってそうじゃんか。お前は元プロ野球選手の親父に子供の頃から練習見てもらって、そりゃ上手くなるよ。見た目もかっこいいし、タレント性、バッチリだ。恵まれてんだよ、お前は」
三年間最後の試合で、勇はノーヒットノーランの投手からヒットを出し、チームのヒーローになったのに対し、自分はベンチで観ていることしか出来なかったというのが、僕の心にこたえていた。勇のことを考えると出てくるもやもやした闇が一瞬で僕の心を支配した。
「俺もお前みたいな奴だったらって、ずっと思ってたよ…」
きっと僕は今、とても情けない顔をしている。
「お前もみんなとおんなじだな、残念だよ。お前とはずっと一緒にいたのに、そんなふうに思われていたなんて」
みんなとおんなじとは、何がおんなじなのか、聞こうとしたけど、勇はそう言うとすぐに眠ってしまった。本当に寝たのかは分からなかったけれど、これ以上は話したくない、という明らかな意思表示を汲み取って、僕も寝た。僕はフリだったけど。
実際ぼくは内心ビクビクドキドキで眠るどころじゃなかった。勇を怒らせてしまったかもしれない。傷つけたかもしれない。嫌われたかもしれない。
僕はなんなのだろう。勇のことを、この世の不公平の代表みたいに思って、妬ましいはずなのに、認めたくないはずなのに、勇に嫌われることがこんなに不安になるなんて。
それから勇は僕を避けるでもなく、今まで通り普通に接していたけど、それがますます僕を不安にさせた。思っていることがあるなら言ってくれればいいのに。
僕は呆れられたのだろうか。
それから、僕は、勇が僕に一線を引いたのを感じた。
勇は僕にあまり本音を話さなくなったような気がした。勇はそれまでだって弱音や相談などを僕に言ったことはなかったけど、何をしたとか、どうだったとか、やりたいこととか、他愛の無いことを僕には話していたのに、それが無くなったように感じた。
そう、他のみんなには話さないことも、僕にはよく話していた。
勇はみんなには無口でクールなやつだと思われている。さらに一部の女子からは、とても高尚なやつだと思われている、まるで神話みたいに。
だが、実際はよくしゃべるし無邪気だ。話すことも、笑うことも僕や他のみんなとそんなに変わらない。普通の男子中学生だ。ふざけたり、馬鹿なことを本気でやったり、たまに下ネタだって言う。少なくとも僕の前ではそうだった。僕はそれが嬉しかった。僕だけが、みんなの知らない勇を知っているという優越感と、勇が僕には心を開いてくれているという確信があった。
だけど、あのバスの中での会話以来、勇は僕に対してもみんなが知っている無口でクールでなんでも卆なくこなすただただかっこいい勇になっていた。
僕は、勇がとった距離の長さを痛感し、自分の浅はかさを思い知った。
勇が僕に対してまでクールで格好いい勇になったことは、僕には想像以上の痛手だった。勇に心を閉ざされたことがこんなにも自分を弱らせるなんて思いもしなかった。あの妄想小説も、あのバスの一件以来、気が進まなくて書いていない。
僕は、もしかしたら、なんでも出来る勇のことを疎ましく思っている以上に、ずっと一緒に過ごしてきた親友として勇のことを、自分で考えている以上に好きだったのかもしれない。幼少期からずっと一緒にいた勇は、今まで意識したこともなかったけど、僕の中で相当大きな存在になっていたらしかった。
勇の信頼を失って初めて、そのかけがえのなさに気づいた。勇が信頼して心を開いてくれることは、本当にかけがえがないことだった。僕は、その信頼を少しでも汚してはいけなかった。
なぜなら、勇が心を開ける人間は少ないから。そのことを僕は知っていて、さらにそれを知っている人も数少なかったから。
「勇、今日うちで一緒に勉強しない?母さんもお前に会いたがっているし、久しぶりにうち来いよ」
僕は勇と、ずっと白々しい親友を続けていくのかと思うと、心底嫌になって、なんとかしたくて、勇が腹の底で何を思っているのか、勇が羨ましいと告げた僕をどう思っているのか、問いただすつもりで、家に誘った。勇は一瞬驚いたような顔をしたが、すぐに
「マジか、サンキュー。じゃあお邪魔するわ。一人で勉強してると心折れるもんな」
といつもの調子で返した。
「お前の部屋、なんか来てないうちにだいぶ変わったな。前はこんなに本とかなかったじゃん。本棚とか漫画ばっかりだったしよ。ふーん、お前、小説とか読むんだな。増えてる」
勇が僕の部屋の本棚を興味深げに眺めて言った。
「うん、中学入ってからはまったんだ、小説。面白いよ」
「へぇ、なんかオススメの作家とかあるの?」
「オススメかぁ、ミステリーが好きなら、この作家さんは面白いよ。ミステリーのなかにも、小説としてのメッセージ性がちゃんとあるっていうか。僕は好きだな」
「ふぅん。タイトルは変だけど。受験終わったら、読んでみるわ」なんて僕の部屋で話していると、昔に戻ったみたいで懐かしい。中学に上がる前、よく僕の部屋でくだらないことをして飽きずにずっと遊んでいた。勇といれば、何をしていても、どこに居ても楽しめた。
「そういえば、勇が最後にこの部屋来たのっていつだっけ」
「うーんと、いつだったかな。中一の終わりとかじゃん?それからはまぁ、クラスも離れたし、勉強も部活も本格的になって、あんまし遊んだりもしなくなっちゃったもんな」
部屋にちょっと重い空気が流れた。お互いがお互いに思うところがあって、少し気まずい感じになった。切り出すなら、今しかない。
そのとき、部屋のドアが勢い良く開いて、母親が自分の部屋のように入ってきた。
「あら、勇くん久しぶりねぇ。身長えらく伸びたのねぇ。ますます男前になっちゃって」
僕の勇気は、母親の空気の読めない突然の登場によってかき消された。
「母さん、部屋に入るときはノックしてっていつも言ってるでしょ」
僕は脱力して、開け放たれた部屋のドアを閉める。
「あ、こんにちは、お久しぶりです。お邪魔してます」
勇が礼儀正しく挨拶する。
「あらやだ、あんたせっかく久しぶりに勇くん来てくれたのにお茶も出さないで。ちょっとお茶の用意するから手伝いに一緒に降りておいで」
僕は母親に引っ張られながら叫ぶ。
「ごめん、ちょっと待ってて。棚の本とか、勝手にみてていいから!」
「お、おう。ありがとう。あの、どうぞおかまいなく!」
なんだかな。まだなにも話そうと思っていたこと話せていないけど、なんだか昔に戻ったみたいな感じがする。嬉しい。やっぱり僕は勇のことが好きなんだな。
お茶とお茶菓子を持って部屋に戻ると、勇がなにやら熱心に立ち読みしていた。僕に気づくと、開いた大学ノート手に振り返る。僕は冷水を頭から被ったかのように青ざめてその場に立ち尽くした。
勇が手にしているのは僕の妄想ノートだ。
「なんだよコレ。なぁ、これって俺のこと?」
時が止まった。僕はその場に凍りついて、何の言葉も発せないまま口をパクパクさせた。
バレた。バレたバレたバレたバレたバレたバレたバレた。どうしよう、なんて言おう、どう誤魔化す?
「これ、絶対俺のことモデルにしてんだろ。元野球選手の父親とか、主人公のやったことだって、全部俺がしてきたことじゃん。でもこれ、一人称僕なんだな」
勇が、冷たい目で僕を見据えて言った。全て見透かされている。
僕は穴があったら入りたかった。穴に入ってそのまま消滅してしまいたかった。
惨め。滑稽。
その二文字が僕の頭を埋め尽くして、まともに勇の顔を見られない。
バレた、もう終わりだ。僕の仮想現実。惨めな僕の、ささやかな楽しみ。
顔が熱い。きっと僕は今真っ赤な顔をしているのだろう。友達を自分に置き換えて書いている秘密の小説を知られ、顔を真っ赤にして立ち尽くしている僕の姿はさぞ滑稽で情けないだろうな。と、頭のどっかでもう一人の僕が冷静に同情した。
恥ずかし過ぎて死にたかった。
そんな僕をよそに、勇は淡々と話す。
「勝手に見て悪かったよ、棚から本引っ張り出したとき落ちて、拾うときについ見ちゃったんだ。で、これの感想言ってもいいかな」
勇は静かに怒っていた。パニック状態の僕の頭でも、それだけははっきり分かった。
「こうゆう、生まれつきイケメンで、才能あって、努力もしないで世間に認められてってやつ、すっげーむかつくね。お前がおれのことどう思ってんのかよく分かったよ、改めて。まぁもう知ってたけどさ。お前も、周りの奴らと一緒で、俺はスゲー奴で、特別って思ってんだろ。俺のこと羨ましいんだもんな。俺からしたら、お前のほうが、昔からよっぽど羨ましかったけどな」
一息で一気にそう言った勇は、僕がこれまでに見たことがないような表情をしていた。怒っていたけれど、今にも泣きそうな顔だった。
「どうして、お前まで俺を置いていくんだよ。お前は、俺のこと分かってくれてると思ってたのに」
悲しそうに、うつむいて言った。僕にはかける言葉が無かった。
「なんでお前まで、羨ましいとかすごいとか言って、勝手に俺と一線引いて俺だけ置き去りにすんだよ。もっと張り合えよ、俺に。お前は自分をもっと頑張れよ、俺のこと特別扱いなんかしてねぇで、お前は自分と向き合え。ずっとそう思ってたよ。優は、もっと頑張ればいいのにって。お前結局俺のこととか、生まれつき恵まれてるとか都合良く一線引いて、自分とは違うんだって納得させて、自分と向き合うこと放棄してるだけだろ。こんなくだらない小説書きやがって。お前はなぁ、もっと現実の自分と向き合えって!負けることに慣れんな!」
こんなに熱くなっている勇を、僕は初めて見た。肩が震えている。
勇が怒鳴った衝撃のあまりにか、その言葉に感動したからか分からないけど、不外にも目から涙が溢れてきて、止まらなかった。
勇の言葉はまっすぐに僕の心に刺さった。
言われて初めて、ハッっとした。
僕は、自分と向き合うことから逃げていたのか。
「俺もお前も、なんも変わらないよ。俺だって、始めからなんだって出来たわけじゃない。努力しないと、練習しないと何も出来ない。そのことを、お前は、分かっていてくれていたと思っていたよ」
最早勇の言葉は最後の方になって消えるようだった。
僕は、自分の愚かさを呪った。
僕は、とんでもない見当違いをしていた。
勇が野球もできて、勉強も出来て、人から好かれるのは、恵まれているからなんだと。
それは恐ろしい誤解だった。弱々しくそう言った勇みて、僕が今まで見て見ぬふりしてきたものが鮮明に思い出された。
どうして、苦労なんてなくて、悩みなんてなくて、完璧だなんて思っていたんだろう。ずっと勇の側で見てきた、この僕まで。
そうだ、こいつは苦しんでたじゃないか、頑張っていたじゃないか。弱かった勇を、僕は知っていたはずだろう。
勇が、小学校のとき、僕に初めて愚痴を言ったことを思い出した。めったに勇は愚痴や文句を言わないから、そのとき僕は驚いたし、嬉しかった。勇は、皆に父親の話を聞かれるのが嫌だと言った。当時はまだ勇の父親は現役のプロ野球選手だったし、周りもみんな小学生だったから気も使わず、勇は何かにつけ父親について聞かれていた。それについて、勇は
「俺は父さんの息子としてしか受け入れてもらえてないんだ。野球やるのが当たり前みたいに思われているし、さらに上手くて当たり前と思われてる。期待もされる。たまに、それがすごく重く感じて、野球じゃない別のスポーツやりたくなるんだよ」と悲しそうに言っていた。
「それに、チームのみんなは野球選手のお父さんに練習見てもらえて羨ましいって言うけど、俺は普通のお父さんが羨ましいよ。うちのお父さんは、俺に野球しかさせてくれないんだ。遊園地も動物園も連れていってもらえない。うまくできないと、怒るし、練習は厳しいし、楽しくない」
僕は幼心に、野球選手を親に持つって言うのも、羨ましいけど大変なんだな、と思ったことだけ覚えている。
「あの時、お前は俺に、『勇が頑張ってるのは、僕が知ってるよ。勇の努力は、僕が見てるもん』て言ったんだ。おれは、その時、お前とずっと友達でいられる、こいつは俺のことちゃんと理解してくれてるって思ったんだよ」
そう言う勇の声は切なかった。
覚えてる、ちゃんと僕も覚えてるよ。
あの頃から、勇は周囲の期待に答えようと、一生懸命努力していた。努力し続けていた。練習が終わってからもひとり走り込んで、夜も、隣の家で投球練習とすぶりの音が毎晩していたし、勉強だって、勇が宿題をやっていなかったり、授業中寝ていたりするところを見たことがない。それなのに。
それなのに、僕はいつの間にか、勇の努力を無かったことにしてしまっていた。僕が努力できないからって、勇の頑張りを見てみぬふりしていたんだ。そのうち努力できるのも才能だなんて理屈付けて、自分を甘やかし出したんだ。
勇が今こうあるには、全部勇が苦しい思いして努力して自分で掴み取った結果なのだ。僕と違って、諦めなかった結果なんだ。どうしてそんな分かりきったことに、今まで気付かなかったんだろう。
あぁそうか、僕はずっと自分の都合の悪いことに目をつむって頑張ることから逃げていたんだな。
勇を一人高いところに置き去りにして。
「ごめん、勇。俺は、ひどい親友だな。親友なのに、自分の都合のいいようにしか勇のこと理解していなかった。勇がどんだけ努力してきたか、苦労してきたか、知ってたよ。それなのに、恵まれているなんて言ってごめん。素直に頑張りを認められなくてごめん。僕は、勇を認めて、僕も頑張るべきだった。敵わないなんて諦めちゃいけなかった。勇に対抗するためじゃなくて、同じ立場で、同じ目線で居続けるために、本当の親友であり続けるために、僕はもっと頑張るべきだったんだ」
僕は誠実に言った。今は、とても素直な気持ちだった。勇が熱くなってくれたからだ。
僕が驚いたのは、そんな僕の言葉で、勇が泣いたことだった。それを見て僕は、完璧と思われているが故に勇がこれまで抱えてきたであろう孤独を知った。きっと、弱音も吐けず、期待に応え続けて、苦しかっただろう。ひとりぼっちで。周りには羨ましがったり、妬んだりする奴しかいない。
まだ間に合うだろうか。僕はもう一度、勇と肩を並べたい。周りの奴らみたいに、勇を遠巻きに見たりしたくない。
「それ、貸して」
僕は勇の手から大学ノートを奪うと、まっぷたつに破いた。勇が目を丸くして僕を見つめる。僕が、勇になる夢をみて書き綴った、現実逃避の入口は裂けてバラバラになった。
真っ黒に走り書きの文字が書き連ねられたノート。歪んだ自己投影の鏡。僕が夢見た、仮想現実。
何枚ものそれらが、僕の足音に音を立てて舞い落ちた。
勇と僕は、それを見つめていた。
それから、僕は勇に言った。
「待ってろ。いつまでも一人にはさせないから。すぐに追いついてやる。もうお前のこと羨ましがったりしねーからな」
勇は、満足そうに微笑んだ。勇の笑顔を見たのは久しぶりだった。
僕は、鼻は高くない。
スタイルも良くないし、記憶力がとびきりいいわけでもない。
野球のセンスもないし、効率も悪い。
好きな子は僕の親友のことが好きだし、僕の気持ちは伝えられないまま。
何をやってもすんなり上手くいった試しがない。
だけど、でも。
僕のこの冴えない人生は他の誰のものでもない僕だけのもので。
僕が羨ましがっている勇にも勇にしか分からない苦労がきっとあって。
さらに言えば、もしかしたらこんな僕のことも羨ましくて仕方ないって思っている誰かがいるかもしれない。
僕は、もしかしたら誰かがなりたいと思っている誰かなのかもしれない。
それなら僕は、満足して「僕」を生きよう。
冴えない人生も、冴えない僕も、これからいくらだって好きになれる。
向き合うことから始めよう。
そして僕は歩き始める。
自分自身の人生を。
-
-
仮想現実を
0










