言葉の手前で
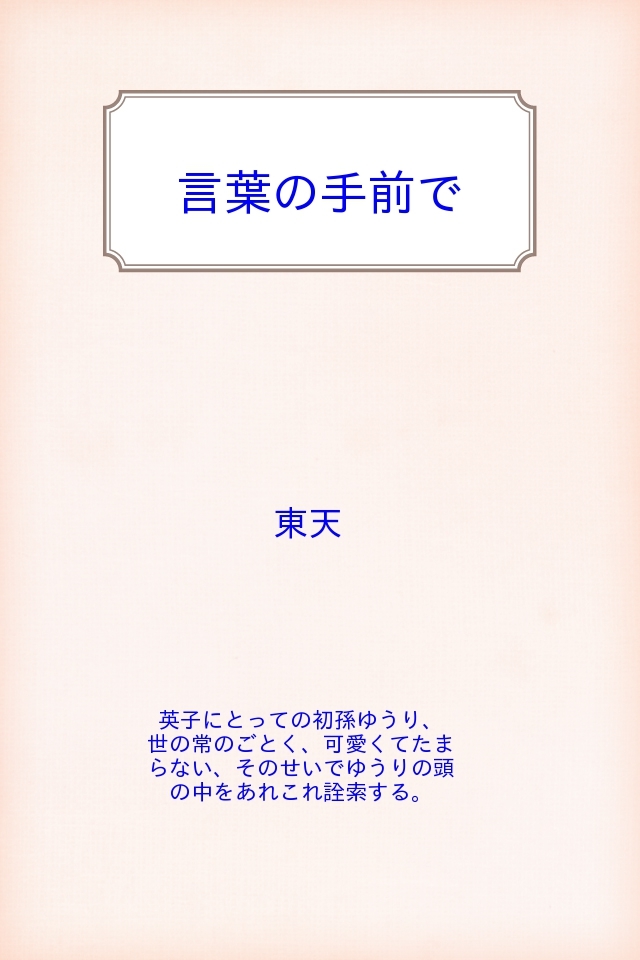
言葉の手前で
一
五十九歳の英子にとって自分に孫が与えられたなんて、自分が神様だとして天から
落っこちてしまうほどの衝撃であった。第一、世の趨勢として結婚難の時代でもあるし、
一人息子の啓司が結婚すると宣言したときも、空いた口が塞がらない程の想定外のこと
だった。
そもそも英子自身が子を持つことを想像できていなかったのである。自分が結婚するこ
とについては、良い悪いの判断もせず、ただ自然の力に闇雲に押しまくられたからだ。社
会の圧力はあまり感じていなかったし、いわゆる花嫁さんへの願望も全くと言っていいほ
ど、そんなものは持っていなかった。
その意味で、昭和五十年ころの世間から少々ずれていた英子は、そのままのずれたおば
さんとなった。しかし自然は実に確かに力強い。否応無しである。英子の思惟がいつも数
歩自然から身を引いているとしても、新しい生命の及ぼす高揚感から逃れる術は無かった。
確かにごく普通のおばあさんとなって、親を助けて、脆い人類の子を育て上げる一助と
なったのである。
喜んで。感情的に喜んで、というより、もっと強力な信念と血族への愛情をもって。
二
それのみならず、英子は二〇一一年六月一一日、急にメモし始めた。ゆうりと呼び習わ
されている孫の記録である。東北大震災と津波と福島第一原発壊滅の三、一一から三ヶ月
経った日のことであった。
「唯一の宝子なれば慶びをたがためならず喜び記さむ、とて、曇り空深き六、一一、この
日がこの種の忘れ得ぬ日にならざること、もちろん念じつつ、かすむまなこをこすりつつ
記するもの也。なにゆえか擬古文なのは短歌量産の試しの最中なればのこと、さらには更
級日記発祥の地なるとて、この市原に縁ありて居をかまえたる影響もあらむ。しかし、現
実の話なれば突然切り替わらざる得ざる事もあるらむ。さて、どこから始むべきか。」
三
佑司、英子夫妻の引っ越し以来、ゆうりとの出会いは週に一度である。これを多いと言
うか少ないというかは、例によって相対的なものに過ぎない。
初めての出会いは、手術室から母親よりも一足早く運ばれて来た時である。そのころは
若夫婦のどちらの両親も関西に住んでいたのだ。
静かに眼を閉じて顔を横に寝かせている白い肉付きの美しい、凹凸のバランスこの上な
くまたとない麗しさ、眉と眼と鼻と口の総合的造作、英子は心の底からゴージャス!と叫
んだのであった。見事な珠のような男児であった。予定日より一週間程遅れた二〇〇九年
一一月.三〇日であった。
その次に出逢ったのはひと月くらいたっていただろうか。可愛らしい丸い形の頭に誰の
系統か薄茶色の薄い髪の毛が一様にそろって柔らかい。長い、といって過言ではない腕を
振り回したり結んだりするのが、ただその単純な動きが見飽きぬ眺めだったのがあとから
思うと可笑しい気もする。
四
二ヶ月ほどして母子は東京へ戻った。そのころ送ってくれた写真が英子の携帯待ち受け
画面にいまでも笑っている。
しかも下をちょろっと右下に出している。まだいたずらもできないいたずらっこ。
おまけにたとえようもない美しい額である。彼の夭折の叔父に似ていた。もっともそれ
ぞれが誰かと似ていると思っていたのだろうが。
夏前の六ヶ月ごろに細菌感染して脱水が懸念されたので入院した。両親共に感染してし
まった。そこらへんのバックアップはしかしゆうりの母方が一手に引き受けたのも、父方
がまったく手薄だったからに他ならない。しかしそのへんのことは余り重要でない。
さらに数カ月して事情あって、ゆうりは母方の実家に、若い親と別れて引き取られる事
態となった。
父方の祖母として英子も週末にはできるだけ訪れるのだが、それはかなりおジャマ虫的
振る舞いでもあった。しかしそんなことも大人の観念であるので重要でない。
英子がゆうりの記録を書くには、自分なりに思うところあってのことであった。
五
ともかく、生後三ヶ月経ち、小さな脳内にからまるほどに神経網がこみあってきて、そ
ろそろ不必要で不要な接続と必要で有意な人間の網の目へと整理しはじめたころ、つまり
人間らしくなって来たのは、まずはひとりでおすわりができ、はいはいをしようとすると
後ろに滑ってしまうころだった。
誰かが玄関のチャイムを鳴らすと、かならずそちらを見て「オ」の系統の発音をした。
それはチンパンジーの子どもがことにつけ発するのと似た態度であった。律儀に必ずチャ
イムに反応するのが面白かった。
大きな木製の車に窓に見立てて三角や丸やらの穴が空いているのへ、正しい木片を入れ
る、というおもちゃをすでに買ってもらっていた。そんないくつかをすでに入れることが
できたのに英子は驚いた。
啓司もそうだったかしら? ひょっとしてこの子は賢いかも。
テーブルによりかかり長い腕で派手にそこらへんを叩くのは恐らく音の出るのが興味深
かったのであろう。腕の長さに比して、脚はまだかなりO脚で短く見えた。
はいはいの姿勢のまま後ろへ後ろへ滑ってしまい、椅子の下へ入り込んでしまい、そこ
で座ろうとして、椅子の座面の下に頭がぶつかりそうになる、すると短く薄い髪の毛の先
にその抵抗を感じるらしく静かに前傾姿勢のままで居た。そこで誰かに助け出されるとい
うわけだ。
六
その頃には、母方の祖父母も共働きという事情もありすでに保育園に通っていた。ゆう
りはそこへ喜んで行き、喜んで帰って来るのだと言う。
そこでたくさんの情報と知識を一歳と言う年齢には多すぎる程与えられているようだっ
た。保母さんのように気取って「ゆうりく~ん」と呼ぶとさっと右手を上げ、「はあい」
という息を出した。声ではない。
外に行きたい時は、手のひらをくるくると回してバイバイの合図を出した。英子が別れ
を告げると喜んでこの挨拶をした。
冬の頃、人見知りがひどくなったらしく、英子が行くと散々いやがられた。見るだに疎
ましい、という感じで顔をしかめて、手を振りいやいやをして泣いた。それも当然の発達
過程であるので、悪くとらないことにする。風邪で具合も悪かったのだ。
その次に会いに行く時は、少しアイデアをためていた英子が、まるで保育園の先生のよ
うに、こんにちはと頭を下げ、ゆうりく~んと言った。
ゆうりはお辞儀をして、息だけではあい、と返事をした。
七
もう数歩歩ける。オランウータンよろしく両手を高く上げて丸い脚で前進した。鼻をか
んだ紙を、さあポイして来て、と言われると決まったくずかごに捨てに行った。捨てると
自分で手を打ってほめた。大人もほめた。
かんぱーいとミルクを飲み、丸ボーロをひとつずつ口に押し込んだ。両手を合わせてご
ちそうさまの挨拶を自分からしていると、母方の祖母がごちそうさまね、と理解してくれ
た。
「本当に分かりが早いのですよ」
と玲子さんは言った。
「明るく機嫌がよく育てやすい子です。啓司さんもこんな赤ちゃんでしたか?」
「そ、そうですねえ、余りなんの問題も無い子でしたっけ」
広いリビングの床にレールを敷き、英子の方がむしろゆうりに遊んでもらった。スイッ
チを入れることが好きである。踏切を通るとき警報がチンチンとなるのを喜ぶのだった。
八
ゆうりの弱みは車に酔うことである。あちこちにその被害を及ぼしていた。眠ってし
まった間なら大丈夫ということで、ある日、一度親子三人で曾祖母宅、つまり英子の母親
宅に挨拶に来た。
そのときはまだはいはいだけだったが、非常にスピードが出るようになっていた。英子
が賢ぶって、お手玉をしてみせるとおおいに喜んだ。この遊びはすでに知っていたのだと
あとでわかったのだが、余りに喜んだので、そして自分でもしているつもりで、お手玉を
両手で持ち、今にも放り投げそうに上下に揺すって、にたーと笑って得意げにした。余り
にうれしいと眼の間に小さな皺を寄せた。それは啓司もした表情であった。
この日忘れられない出来事の一つは初めて父方の祖父佑司に会い、ゆうりが凍り付いて
しまったことだ。
泣くでも無く無視するでも無く、父親の膝で安心しながらも、テレビを見ては、ちら、
と大柄な祖父のひげ面を交互に見た。祖父が初めて部屋に入って来た時、ちょうど頼りの
啓司が居なかったので、ゆうりは仕方なく英子にしがみついた。泣かずにじっと考えてで
も居るようだった。
一体あれは何の動物なのだろう、と両手で英子の腕に食い込むようにしっかりいつまで
もしがみついていた。本当に考えているように見えた。何であるかわかるはずもないのだ
が。英子のことすら何も分かってはいないのに。
九
震災のその日と重なってしまった引っ越しを堪え、夫婦共にそれなりに落ち着いた頃、
風薫る五月が近づいた。広い平地が広がる千葉県市原市では、早春、海から強風が毎日吹
き付けた。これがいわゆる関東の空っ風なのね、と思い知らされた。
ゆうりは比較的風邪も引かず保育園に喜んで通っていたので、出番がなかったのだが、
やっと英子へ要請がきた。啓司が仕事に忙殺されているので、いわゆるイクメンをやって
いる暇がない、というのである。
三日続けてゆうりに会った。
アクアラインをバスで通う。市原市から羽田空港までのその道の、これも人の、特に男
たちの協力の結果であることをこんなにも具現している例は他に余りないであろう。
呑気な真っ平らな田園地帯を高速が走る。
海側には人工の土地にずらりと並ぶコンビナートの、とりどりの煙突と煙がうっすらと
浮かんでいる。
突然東京湾の波の上を掠めて高速道路が浮かんでいる。
引き潮の時には、小舟に乗って人等が働く。その湾に降り立って海苔か何かを作ってい
るらしい。ほとんどの場合そうだったが、曇っていると、空も海も同じ灰色となる。霧が
でるとまさにどこに進む路なのかわからない。風が強い時には最悪だ。運転手がたえずバ
スの車体を修正しつつ走らせる。手に汗握るという感じで見守っている。
すると突然、風がない。海底に潜る道があらわれる。
これはこれで恐ろしい。三、一一の前日に通って市原市まで辿り着いた同じトンネルで
ある。どこまで運の強い自分であろうか、と英子は思う。
不運だと思う時もある。
十
しかし、今はゆうりの世話をしなければならない。それが英子への至上命令である。
必死で共に遊んだ。最初、ちょっとやり通せないような気もしたが、実はなんら深刻な
問題は起きないのだった。
一歳になるやならずから、あちこちの保育所をたらい回しにされ、時にはボランティア
のおばさんと数時間を過ごす、そんな生活をゆうりはタフにこなしていた。生活の細々し
たパターン化がよく理解され、喜んで実行されているさまは他の子どもに見られない程だ
と英子は舌を巻いた。
待つべき時は待ち、必要なものは要求した、文句があると大声で叫んだ。
さて三日間日参して最後の夕刻帰るとき、ゆうりは啓司の自転車の前に乗り水色のヘル
メットをかぶっていた。それは保育園に行く時のスタイルである。ついでに買い物に行く
のでふたりで英子をバス停まで送って来たのだ。
英子がじゃまたね、と急に横断歩道を渡り始めると、ゆうりは少し慌てて理解できない
ような顔をした。そしていつまでもいつまでも顔を曲げて祖母の立つ姿を見つめ続けた。
子どもの心の一途さが英子の乾いた心に沁みた。
また似たような振る舞いがその次の週にも見られた。別れぎわに今度はバギーで母子三
世代バス停まできた。ゆうりは勿論そこで別れが来るとは知らなかったのだろう、急にバ
ギーの向きを変えられ、祖母が見えなくなった。
それで、まず右に頭を傾げ祖母の姿を後ろに確認した。ところがバギーが少し斜めに進
んだためすぐに見えなくなった。すると案の定、かしこいゆうりは今度は逆の左方向に頭
を傾げて振り返り、祖母の姿を確認した。それからは真っすぐバギーが進んで行った。
十一
ゆうりはまだ言葉を発しない。男の子は遅いとよく聞くように、すべて理解しているの
に自分の意志もはっきりしているのに、それを言葉で伝えることが不可能な状態だった。
もちろん指で指したり、取ったり、行動で示すことはできる。
ゆうりに独特なところは、イエスノウがはっきりしていることである。言葉は使わなく
ても首をこっくりし、あるいは顔を左右に振った。質問の意味はすべて理解していた。た
だ否定疑問文で尋ねられると、困ったような顔をした。
おしっこした? こっくり。おむつかえる? いやいや。でもおしっこしたんでしょ?
こっくり。じゃ替えよか。いや。
この時、ただの孫に夢中のおばあちゃんでない面が英子にあらわれた。
いったいゆうりの頭の中はどうなっているのだろう。言葉の理解力、行動や物事の手順
の意味、してはいけないこと、したいこと、すべてすでに脳内に明らかに備わっている。
十二
英子の腕時計は、あたらし好きらしくおおぶりのGPS、ソーラー電池つきの男物である。
英子自身は耳が少し遠いので聞こえていなかったが、一時間ごとにピッと小さな高い音を
発した。ゆうりはさっと、自分の首に触った。
そうなのだ、その音は体温計の音と同じだったのだ。一時間ごとにゆうりは首をさっと
触った。何も言わない。
その後、ゆうりの母親のさとみさんが熱を測ったことがあった。体温計を腕の下に入れ
てまもなく例の高い音がした。英子はゆうりの反応をふたたび話したりした。さとみさん
が体温計をしまおうとすると、ゆうりが叫んだ。
アブ、と聞こえる。
「なに、自分で測るの」
こっくり。そして首に押し当てた。
「そこじゃなく、脇の下でしょ?」
しかしあくまで自説に固執の様子。さとみさんは、半ば英子に向かって言った。
「ゆーくん、保育園では首でお熱を測るの?」
こっくり。
ゆうりはこのすべてを本当に理解したのだろうか。
この文章をそっくりわかったのだろうか。
英子はますます孫の頭の中の様子に興味を引かれた。
十三
これまでの英子の知識では、大脳皮質にコラムとかいう小さな細胞塊がたくさん並んで
おり、それぞれがかなり具体的な形象に対応しているということだった。
三角、四角、丸、のような。
それは概念であるが、言葉として捉えられる言語野までは遠いのかもしれない。
脳卒中で言語野が壊れると、言葉を使えなくなるというのは知られているが、ある種の
神経症による超過敏な言語野の活動、つまりたとえば一日中凄いスピードで喋り続けると
いうような症状のあと、突然けいれんが起こり、その間ひとことも言葉にすることができ
なくなると言う。
言いたいことはわかっているがそれが言葉にならないのである。周囲の言葉も理解でき
るのに。
十四
二人で家の前の公園に初めて歩いて行ったとき、ゆうりは鳩にすっかり夢中になった。
階段があろうとおかまい無しに近づいて行こうとするゆうりを、必死で捕まえる。しかし
彼の好奇心はおさえられない。鳥が目の前でぱたぱたと飛び立っていくことに驚き喜んだ。
犬にも走って行く。ふっているしっぽをつかもうとした。さわったりもした。
ワンワンね、ハトさんよ、と英子は概念をくり返す。この積み重ねしか無い。
滑り台ではちゃんとお腹で滑った。こんなところは保育園の教育の賜物である。そして
なによりも頭の巡りと理解力の高さは素晴らしかった。
その帰り、英子はもうへとへとになっていたのだが、ゆうりは頭を振って、道をさっさ
と曲がってしまった。横断すればそこが家であるのに、さっさと左へ、しかも凄い早さで
歩いて行く。
余りに小さいので、手をつなぐには背を曲げなければならず苦しいと言ったらないのだ
が、顧みる余裕は無い。もう二百メートルくらい進んでしまった。やっと次の信号がある。
ここも回避しそうな勢いである。
後で聞いたのだが、このルートはよく通るのだ。英子は同じ高さに座りこみ、信号に注
意を向けた。
「赤だよ、信号、もうすぐ青だよ、緑だよ」
ゆうりがちょっと油断した隙に、英子は彼をさっと抱いた。そのまま帰る方向に歩き出
したのでゆうりは頑固者らしく叫び出した。ここで落としたら一大事。まるで誘拐犯のよ
うに横抱きにする。
まるで猫の仔を捕まえようとしてその筋肉の多様な動きについていけず結局は手を離し
てしまう、そんな感じでゆうりは右へ左へ、英子の隙をついて逃れようと大暴れした。
逃れたら下まで落ちるなんて思ってはいない。大汗をかいて五十メートルも誘拐したあ
と、地面に下ろした。もう限度。十二キロ程の重さだった。
するともうダダをこねずにすたすたと家まで戻った。
だだをこねた訳ではなく、ゆうりにはゆうりの理由があったのだ。英子が分からなくて
も。青洟をおおいにたれていたのだが、ティッシュがなかったのでゆうりのシャツの裾で
ふいた。散々なことになった。
こんな風に、子どもと必死で遊んだのだが、考えてみると啓司に対してまれにしかこん
な必死さは無かった。ついでに遊ばすくらいだったと今にして思う。それはもちろん他の
家事や仕事が目白押しであるせいであったのだが。
十五
鉄道の例のレール遊びで、一歳五ヶ月になったゆうりは、スイッチを使わず自分で押し
て動かしたがった。しかし強く押しすぎるのでたちまち脱線してしまう。なんどやっても
うまくいかないのでかんしゃくを起こしてしまった。
英子は慌てず、そっと列車を押しやるこつを示した。手の角度がまるで違うのをゆうり
はすぐさま理解した。そして何度かの失敗のあと脱線しないように静かに動かすコツを会
得したのである。それはまるで子どもらしくない動きだった。凄いなこの子は、またもや
その理解と集中に感嘆した。
三月末に最終的に転勤引っ越しをして以来、六月までにゆうりに十二回ほど会った。
思い返してみたが、五回目くらいだったろうか、息子夫婦が買い物に数時間出かけた。
天にも地にも英子に取っては初めてのゆうりベビーシッターの時である。
実は内心どうなることかと思っていたのだが、置いて行かれるとき、ゆうりが少し動揺
しかけたので英子が、
「パパママ、おとうさんおかあさん、いってらっしゃい、早く帰って来てね」
と音頭をとると、さっと気分を変えて手首をくるくる回す独自のバイバイをしてもう遊び
相手と遊ぶ気十分になっていた。啓司によると初めてのボランティアの女性とでも平気
だったそうだ。
-
-
言葉の手前で
5










