夢の話
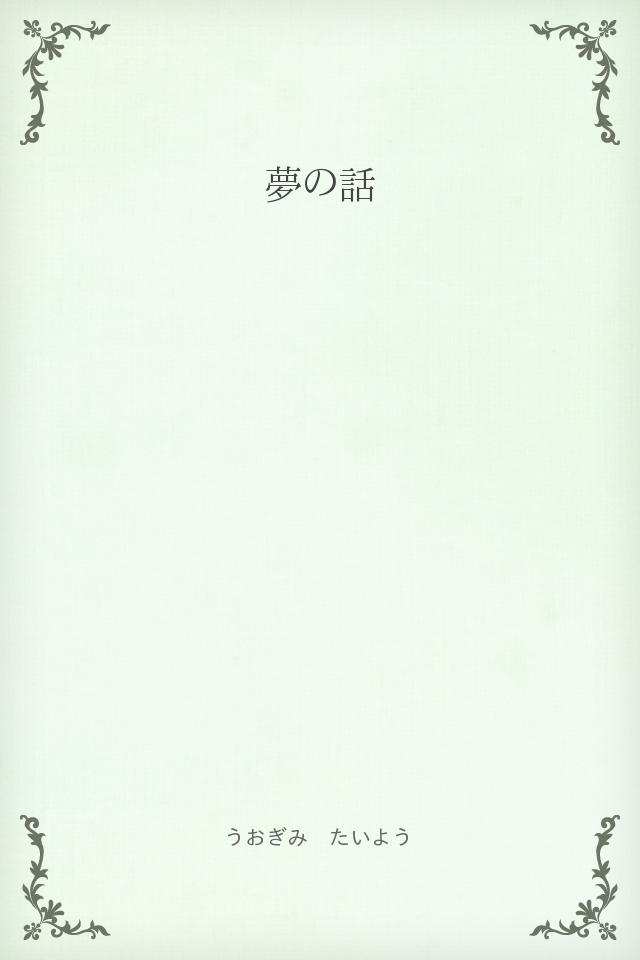
page 1
こんな夢をみた。
そこには洗練された学び舎があった。割れている窓ガラスは一枚もない。おまけに学び舎中の扉という扉がしっかりと枠に嵌められており、それは時代遅れも甚だしい外観だった。
夢には日常の記憶というものもぼんやりとあった。
私は学び舎に、足繁く通うのだ。用事があろうとなかろうと、登校して授業を受けるのだ。そうして放課後には友人達と、これまた洗練された街へ繰り出し、遊び回る。
私はその友人達の中でも特に仲の良い、椿という名の女子のことを好いていた。頭が良く、顔立ちも整っている彼女を、私が好きにならぬはずがなかった。私だけではない。同じ教室で勉学に励んでいる全ての男子が彼女のことを恋愛の対象にしていた。そんな有智高才を体現したような彼女と近しい仲にある自分を、私は内心誇っていた。普通に考えればそんなものはハムスターにでも食わせておくべき甘ったるい誇りであるのだが、不思議なことに私は己の愚心を何の疑問も持たずに受け入れていた。
こんな夢をみた。
その日、椿は私を近所に開店した喫茶店へと誘った。勿論私は二つ返事で了承の旨を伝えた。二つ返事は行儀作法に欠けるものだが、内心舞い上がっていた私にマナーや礼節を重んじている余裕はなかった。
放課後、私達は早速件の喫茶店へと足を運んだ。その喫茶店は開店したてだというのに人が疎らで、本来ならば暖かい光を携えているはずの白熱電球も、何だか見窄らしく店内を照らしている。
空いているねえと椿が唖然としたように言った。しかし人ごみの苦手な彼女にとってそれは好都合だったようで、直ぐに気を取り直し、店内の奥の席へと腰掛けた。
私は何故だか全く趣味に合わないカフェオレを注文し、椿はココアを注文した。ココアと言えば一般的にはメニューに記載すべきでないゲテモノだが、その文字は素知らぬ顔でメニューの一番最後に記載されていた。
私達はその喫茶店の中で、沢山話をした。最近見た映画の話、好きな小説の話、嫌いな音楽の話。それは取り留めのない、と言ってしまって差し支えないほどに雑多な会話だっただろう。しかし椿は突然襟を正したように制服の襟元を正すと、君は人を殺すということに着いてどう思うと私に質問をした。それは核心に触れるには充分な質問で、私に、この光景は夢なのだと自覚させた。
「最近この辺で立て続けに殺人事件が起こっているだろう? 何でも犯人は同一犯で、殺すことが目的であるかのように老若男女別け隔てなく殺しているらしい。怖いよねえ。そこで私は考えたのさ。何の考えもなしに、習慣で人を殺す人間というのはどういう気持ちで生活しているのだろう、とね」
ゾッとした。不本意にも人を殺すことを生業としている私である。彼女のその言葉は私を追いつめるのに充分なものだった。
私は、きっと罪悪感に苛まれているに違いないよと彼女に返した。
「そうかな? まあ確かに人を殺すことは悪いことだからね。普通ならそういう気持ちも生まれるだろう。けどね、この犯人は普通ではないよ。だって一撃で、確実に殺しているんだからね。怨恨も愉悦もない。これが異常でなくて何だろう。私は、この犯人は何も考えずに殺していると思うよ。欠伸をするように、くしゃみをするように人を殺しているに違いない。欠伸をするのも、くしゃみをするのも生理現象なのだから良心が呵嘖することなんかない」
言葉が出ない。どう反論したところで、彼女は私の意見に理解など示さないのだということが判るからだ。失恋にも似た感情が私の中に渦巻いている。蜷局を巻いている。
私は、君は犯人のことをどう思うと訊いた。訊かずにはいられなかった。
「どうって言われてもね。恐ろしいとか悍ましいとか、そんな感じかな。少なくとも前向きな感情は湧かないよ。例えば、納得の出来る理由のある殺人であっても、人を殺したという事実があるだけで、その人間に近付こうとは思わない」
この瞬間私は失恋した。気まずくなって椿から目線を外す。
「そんな深刻な顔をしないでくれよ。君を咎めている訳でもあるまいに。ただの世間話だよ」
椿は優しく笑いかける。しかし私の気の晴れることはなかった。
二時間程して私達は喫茶店を出ると、帰路につく。椿が送ってくれと言うので、私は彼女の住むマンションまで着いて行った。マンションはオートロックの整った外観をしていた。この世界は狂っている。何故私は今の今まで普通に生活していたのだろうか。答えは簡単だ。これは夢だから。答えとは何時の時代も何時の世代も簡潔であるべきだ。しかしこんな辟易するような現実があっては堪らない。私は早く夢が覚めないかと倦ねた。
「今日はありがとう。君も気をつけて帰ると良い。殺人鬼が彷徨いているかもしれないからね」
椿は笑顔で言う。冗談口のつもりなのだろう。しかし冗談にされては堪らない。
私は思わず、君は私のことをどう思うと訊いた。訊かずにはいられなかった。
「うん? どう、か。そうだね、私は君のことを————」
良く聞き取れなかったが、私はその言葉を理解した瞬間、全ての絶望を希望に変えて、彼女ののど元をナイフで刺したのだった。
page 3
こんな夢をみた。
椿は、なるほどと顎に手をやりながら興味深そうに私の夢の話を聴いていた。
「君は夢の中でも私のことを殺したのだね。いやあ、本当に真面目な男だよ」
何だか茶化されている気がする。確かに私は真面目な方だが、椿の言う真面目という言葉の裏には恐らく道理の判らぬ頑固者という意味が隠されているに違いない。
「それにしても興味深い話だよ。夢を見る人間なんて、人類史上君が始めてなんじゃないかな? 今絡繰りで過去のデータを調べたのだけれど、前例は見つからなかった。けどまあそれはそうだよね。夢を見るのは人体模型か狛犬くらいなものなんだから」
確かにそうだ。夢を見る人間など寡聞にして聞いたことがない。一介の殺人鬼である私は何の嫌味もなく不勉強な人間であるから、聞いたことがなくて当然だが。しかし、研究者である椿でさえ知らないというのならそれは都市伝説と同列に並べられる程には真実であるのだろう。
「ううん。ヒビ一つない学び舎か。面白い。本当に時代遅れだね。そして君と私はそこの生徒だった訳か。しかしおかしいことがある。私は青春など知らないし、学校に通ったことだってない。若気を知らぬ私がどうしてそんな夢に出演出来るんだい? それは君にしたってそうだろう? 君は青春を知っている風には見えないよ」
私は椿の質問に否定で返した。私は一応殺人の専門学校を出ているのだ。その中では、恋もあれば友情もあった。正に青春というやつだ。しかし青いものばかりではなかったような覚えもある。同級の学友を殺したり、想いを寄せる女子に殺されたりと、間違いなく赤もあったのだ。とするならば、私の春は紫であるのだろう。紫春とでも言おうか。
「へえ、殺人の専門学校というのがあるのか。私は世情には疎いから勉強になるよ。なるほど、君にも春があった訳だ。ならばその夢の中で君が青春を謳歌するのは間違いではないね。しかし私がその中に加わっているというのはやはり妙だよ。夢ってのは不思議なもんだね」
確かに不思議だが、よくよく考えてみれば、私の夢は私が勝手に見るものなのだから、そこに誰がどのような形で出てこようと矛盾も撞着もないのである。洗練された街並が良い例だ。今私達がいる街の建物は皆廃墟の様な状態で存在している。にも拘らず私の夢の中にそんな建物は一軒も存在しなかった。
全ては私の妄想なのである。憧れと言っても良いかもしれない。全てがきちんと整った世界。殺人が絶対的な悪とされ、私自身を正統に糾弾してくれる世界。確かにそれは私の憧れる世界だ。
「そうだ。君は夢の中で私を殺したらしいが、ちゃんと生き返らせてくれたのだろうね? 殺した後始末をしないのは君の悪い癖だよ。この前だって大変だったんだから」
椿は口を尖らせて言う。私は、判らないと応えた。
「判らない? どういうことだい?」
その先は覚えていないのだ。きっとそこで夢が終わったに違いない。私は椿にそう伝えた。
「ふうむ。夢というのは手強いな。中途半端で終わってしまうこともあり得るのか。なんだか私もみたくなってきたよ」
私は金輪際みたいとは思わない。あんな夢を見続けていたら神経が悪くなってしまう。
サテ、話はそろそろ終わりにしよう。私は彼女を殺しに来たのだ。椿は私の為に何度でも死んでくれる。そして何度でも許してくれる。偽物の恨みもなく、本物の辛みもなく、ただ笑って許してくれる。だから私は彼女しか殺さないし殺せない。今日も職務を果たす為に彼女に協力を仰いだのだ。
「お、始めるのかい? 良いよ。こちらの準備は済んでいる。殺し終えたらそこに置いてあるココアで生き返らせてくれ。頼んだよ」
私は頷く。前回は怖くなって逃げ出してしまったが、同じ失敗を繰り返すことはスマートとは言えない。こちらも覚悟を決めなければ。
私がナイフを握る手に力を込めると、椿は何かを言い残したのか、そうだ最後に——と腰を折った。
「君は私のことが好きなのかい? それともそれは夢の中だけ?」
私は首を横に振る。そうして椿ののど元をナイフで刺した。
彼女の死に様は普通の死に様だった。
-
-
夢の話
0











