柚子さんの味噌汁
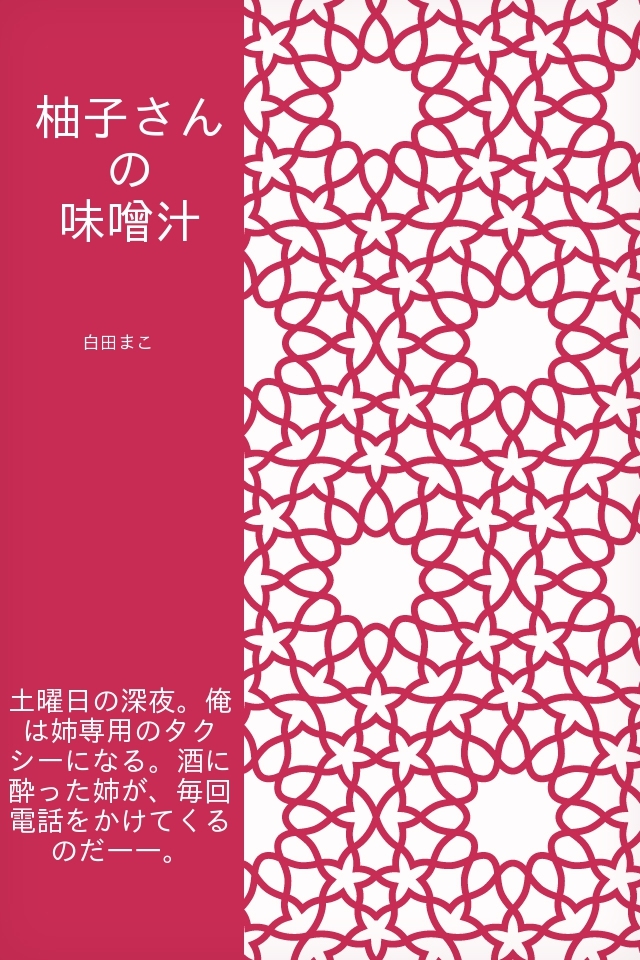
こんな夢みた。
テーブルを囲むように、家族四人が談笑している。
俺。そしてその横には父さん。俺と向かいあう様にして姉がいて、姉の横には母さんが。それが我が家の定位置だった。
「いただきます」
母さんがそう言うと、俺もそれにならい手を合わせた。
ご飯に、具だくさんのみそ汁。ご馳走なんて何もない。ずっと昔の我が家の日常風景だ。
ただ少しだけ現実と違うのは、そこにいる俺が五歳の頃の俺ではなく、成長した現在の十六歳の俺だということ。目の前に座る姉も、九歳の姉でなく、見慣れた二十歳の姉だった。母さんは俺が五歳の時に死んだ。だからこの姿で母さんと一緒にいるのは違和感しかない。
母さんの表情はさっきから少しも変わらない。遺影写真をそのまま貼り付けただけの綺麗な笑顔。俺たちはみんな冬服なのに、母さん一人だけ夏服を着ていた。だけど姉は、そんな母さん相手に凄く嬉しそうに笑っていた。
「けーすけ、コレが母さんの味だよ。美味しいでしょ」
みそ汁を片手に姉が断言した。真正面から向けられた姉の笑顔はなんだか眩しかった。俺は適当に相槌を打つと、みそ汁を口に含んだ。
みそ汁は確かに美味しかった。
これが母さんの味らしいけど、俺には姉の味にしか感じなかった。
――電話の音で目が覚めた。
「タクシー、迎え来てぇ」
土曜日の午前一時、月に二、三回の割合でこんな調子の電話がかかってくる。無駄にテンション高い声。また飲みやがって。自然とため息が漏れた。
リビングに行くとまだ明かりがついていた。テーブルの椅子にもたれかかる様に柚子さんが座っていた。柚子さんは自分の椅子ではなく、母さんの椅子に座っていた。そこに座るなんて珍しい事もあるものだ。
少しだけ昔の話。初めて新しく家族となった俺たちは、そろってこのテーブルで晩御飯を食べる事となった。その時、姉は柚子さんが母さんの椅子に座るのを嫌がった。母さんの場所に、部外者が座って欲しくないと。今思い出しても結構酷い言葉を浴びせて、姉は家から飛び出していった。
なので今は、姉さんが母さんの椅子に。その横に俺。俺の手前に柚子さん、その隣が父さんが座っている。それが新しい家族の、新しい我が家の定位置となった。ただ定位置こそ決めたものの、家族が四人揃って食事をした事はまだ一度もない。
柚子さんは椅子に座りながら、じっと携帯を眺めていた。
「柚子さん、俺ちょっと出てくるね」
電話越しの姉にも聞こえるよう、わざと大きな声でそう伝えた。
柚子さんには俺に気づくと、わずかに苦笑していた。柚子さんは何も言わずに、冷蔵庫にかかっていた鍵とマフラーと、それから手袋を俺に手渡した。
電話越しに居場所を確認すると、俺は自転車を走らせた。電話の相手は、俺の四つ上の姉だ。十九歳まで真面目に家事に勉強に勤しんでいた姉は、二十歳になった途端、ゼミ仲間と毎晩のように飲み歩くようになった。帰巣本能はあるのか、どんなに酔っても、毎夜姉は必ず自宅に帰ってくる。無理な時は俺に電話をかけ、こうして俺に回収を頼んでくるのだ。
一丁目の公園の前を通りかかると、声がかかった。
「けーすけ、お迎え御苦労さま」
ふらふらと体を揺らした姉が、両手を大きく振っていた。
「正体なくすまで飲むなよ」
「やだ、けーすけ。人類に透明人間はまだ無理よぉ」
「この酔っ払いが……。ほら、早く後ろ乗って」
俺は姉に自転車の後ろに乗るよう促した。自転車の二人乗りは禁止されているが、俺はまだ免許を取れる歳じゃない。辺りを確認し、ゆっくりと自転車を走らせた。人も自動車もいない。辺りには電灯と、虫の声だけしかいなかった。
「腰ちゃんと掴めよ」忠告してから坂道を下った。
「風、気持ちー」
姉が体を揺らした。テンションが高い。ほっとくと、そのまま歌でも歌いだしそうだ。
さっきまで上がってきた坂を、そのまま下っていく。スピードがどんどん上がっていく。ブレーキをかけ、スピードが出るのを軽く抑えた。遅い、と後ろから文句をつけられた。俺はもっとスピードを緩めた。事故るなんてごめんだ。そんな事をしたら、家の人に迷惑がかかる。
「そーだ、姉ちゃん。柚子さん心配してたよ」
「……へぇ」
姉の声が急に固くなった。姉は素直な人間なのでこういう時とてもわかり安い反応をする。
「別に大丈夫なのに、心配性だねあの人も……」
「そんな意地悪言うなよ。もう家族なんだからさ」
「もう、ね。……ふふふ、あんたら仲いいねぇ」
「俺、大人だから」
下り道が終わり、平坦な道になった。
しばらくその勢いのまま道をすべり、ペダルをこいだ。行きよりもかなり重い。ペダルを踏む力も自然と力が入った。ただひたすらに前を向いてペダルをこいだら、風が頬をチリチリと刺激してきた。
寒い。けど、マフラーと手袋がある分、普段よりはまだマシだった。普段は防寒具なんて忘れて直ぐ家を出ちゃうから、体を震わせながら自転車をこぐなんて事は日常茶飯事だ。
「――くしゅん」
後ろで姉のくしゃみの音が聞こえた。
「風邪? そんな軽装備でフラフラしてるからだよ。寒いんなら俺のマフラー勝手にとっていいよ」
「ヤダ。そのマフラー用意したのあの人でしょ。あの人は、あんたに用意してやったんだから、あんたがちゃんと使いなさいよ」
「よくわかったね」
「忘れ物の激しいあんたが、マフラーと手袋してりゃ、直ぐにわかるわよ」
酔っている割には、よく見ている。それだけちょっとした変化に敏感な性格だという事なのだろうか。
「あとで、ちゃんと礼いっときなさい」
「姉ちゃんってそういうとこ律儀だよね」
「そういう風に躾けられたからよ」
そういうものなのか。俺はどうだろう。そういう風に躾けられていたのだろうか。わからない。なにぶん忘れっぽいから。
まぁとりあえず、柚子さんには忘れない内にお礼を言っておこう。
てな訳で、「早く家帰ろうか」っと、俺は自転車のスピードを上げた。
「けーすけ、あんた何時からそんな家が好きになったの?」姉が茶化すように聞いてきた。
「別に昔も今も嫌いじゃないよ」
「そう……」
「でも姉ちゃんだってさ、家事とか、今は楽っしょ。柚子さん、料理も上手いし」
「ねーちゃんは、赤みそより、白みそが好きー。だからねーちゃんは、これからもずっと母さんの味しか我が家の味って認めない」
「まぁ、柚子さん地方の人だし。向こうは赤みそが主流らしいね」
「具もちがーう。わたしは具だくさんがいいの」
「そう? 俺は大根が入ってれば十分」
姉が俺の背中をポカリと殴った。
「ワカメと豆腐も入ってなきゃ駄目なんだって! あと、ニンジン、玉ねぎ、ゴボウでしょ……。母さんのみそ汁ってかなり具だんさんだったからね。わたしもそっくりに作れるわけじゃないんだけど――」
「別に、姉ちゃんが母さんの味をそっくりなぞる事ないでしょ」
上り道に差しかかると同時に、俺は姉の言葉を遮った。
「どうせなぞったところで、俺は母さんの事を思い出す事はないし、俺にとっては我が家のみそ汁は姉ちゃんの味でしかないよ」
ペダルを強くこいだ。重い。
一旦、足をつこうとしたら、後ろが急に軽くなった。
「酔いが覚めた」
自転車から降りた姉が、後ろを押してきた。一気に押すのが楽になった。そのままグイグイ自転車は進んでいく。
ふいに、後ろの力が弱まった。
「ねぇ、けーすけ。……わたしって子ども?」
「俺って姉ちゃんと違って、母さんの事なんてほとんど忘れちゃったし、その分抵抗ないんだよ。だから再婚とか、したきゃすればって感じ」
「けーすけ君は大人だねぇ。まだ子どもなのに」
「姉ちゃんは大人なのにな」
「うん。そだね……。姉ちゃんもう大人なのにね」
背中越しに姉の笑い声が聞こえた。だけどどんな顔をしているかまでは、わからなかった。
-
-
柚子さんの味噌汁
0











