受容ホルモン
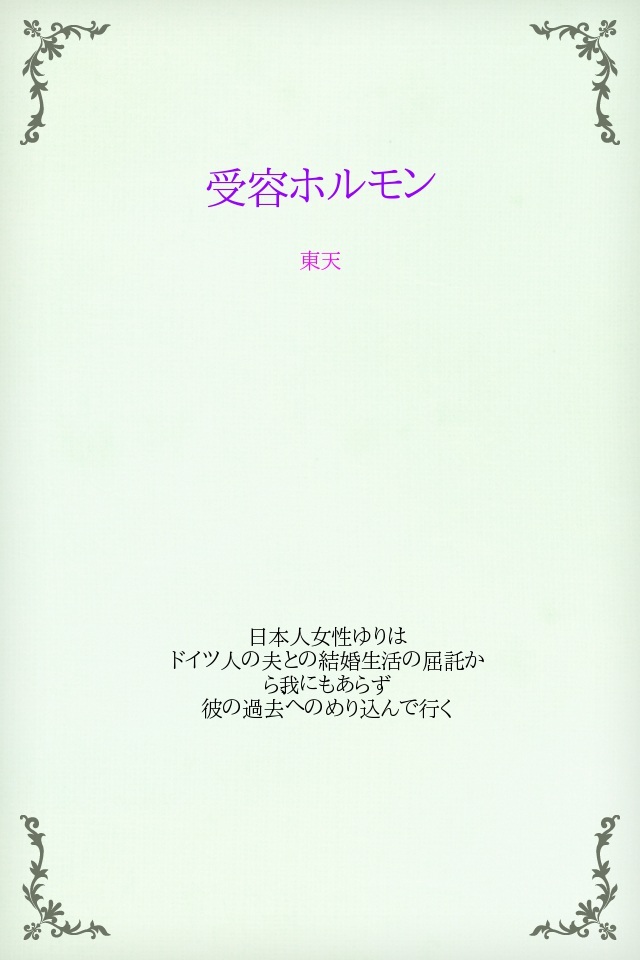
第1章( 1 / 5 )
二つの出会い
一 二つの出会い
ミュンヘン、カルルス広場の噴水際の石の上に、いつものように気楽な昼休みを過ごそう
と、ローザは使い込まれてよくしなう薄茶の革バッグを置いた。
オレンジをひとつ、並べてそっと置く。ダスターコートをするりと脱いだ。
そのとき香ったものが、体臭なのかジャニーンDの香りなのか、自分でももう区別できな
いくらいだ。
どこのドロガリーでも買える安物の香水を変える理由もなくて、五、六年来使っている。
大きな石はうっとりするような暖かさでローザの下半身を迎えた。
ダスターコートを二つ折りにしてふわりと膝の上に重ね、何となく撫で回していた。
「アノ、スミマセンガ」
やや不安定なアクセントで女の声がした。
ローザは、少し遅れて隣の石に腰を下ろした気配の女の、チラリと目の隅に入った黒髪が、
思い浮かんだままの瞳で、顔を向けた。
るりは、大きく開かれた鳶色の窓に対峙した具合になって、思わぬ近さにたじろいだ。
「今、何時頃カ、教エテクダサイ。時計ハ持ッテイルノデスガ、電池ガ切レタラシイノ
デス。」
ゆっくりした言い方の中に、どこか女が上の空なのをローザは感じた。が、ただ一瞬のこ
とだった。
自動的にトルコ系の険しい顔立ちを予想していたのが、反対の極のようなおうとつの少な
い女の顔に出会った途端、記憶の遠い連鎖の先にあるその影響のようなものが呼び起こさ
れたのだ。
ローザの視線はせわしなくその顔のあちこちを飛び移った。
るりには余裕はない。呑み込むように、ローザの全身を感得しようと瞳を全開させていた。
この瞬間しか無いかも知れないのだ。
するとロ−ラは頷きもせずに、薄オレンジ色のコットンらしいセーターの袖口を少しずら
して腕時計に目を落とした。
その膝の上のコートの、彼女のわら色の髪に似た色と、同じ色の眉と睫の張りを、るりは
逃さず検分する。
スナップ写真ではもっとぼんやりした印象だった、とわかる。
「十二時十五分です」
そういう声と、唇の動かし方と、頬の線とは、今時珍しい飾り気の無さだ。
アリガトウ、とただこだまのように言って、るりは機械的に時計をいじった。そうしなが
らも間近に息づく大柄な体の量感を、確かなものとして感じようと息を詰めていた。
ローザには女の年齢の見当はつかなかったが、上品で知的だと思った。眉は整えられ、唇に
は冴え冴えと深い紅が引いてある。
訊いてみずにはいられなかった。
「日本の方でしょうか」
るりは、思い惑っていた褐色の瞳を上げて力を込めた。
「ソウデスガ」
「やはり。こちらはもうどれくらいですか」るりはできるだけ屈託なさそうに少し考える
ふりをしてから、口元を笑ませて言った。
「一年半クライデス」
これが例の日本人の微笑なのかしら、とローザは思った。
「じゃ、ドイツ語はよくお分かりですわね」
この人も、時には女らしいしなをつけた物言いをするんだな、とるりは胸をつかれた。
「ユックリ話シテモラッタラ、ワカリマス」
ちょうど秋の薄雲が動いたらしく、陽光が一段と強さを増した。
聞き慣れた路面電車のうなるような騒音がひとつ去って、軽快な車輪のリズムだけが遠ざ
かって行く。
ローザはふと心地良さの中に引き込まれた。
ああ、と胸一杯のため息がでた。
「気持ちのいい日射しだこと!」
るりの耳が、びくっと突っ立った。心臓が特別な切なさで躍りあがった。
(ああ!だって。ああ!だって!あの声さえ聞こえなかったら、こんなきちが
い沙汰もせずにすんだのに。
聞きたくない、聞こえないでくれと願っている、でも本当はいつも聞き耳を立てて待って
いる。
叩きつぶしたいほどのこの自分。
何故こうでなきゃならないのだろう。
毎日ではない、そのかわり昼でも夜でもお構いなしのあの声、あのときの声。
ステレオのロックのリズムが天井から響き始めたら、必ず間違いなしの、あのああ、ああ、
が)
第1章( 2 / 5 )
「そうじゃありません?」
ローザは女の目を横からのぞいた。
(何て考え深そうな目つき。日本人の女はこんな目で彼の心を捕まえたって訳かしら。
ウーテは勿論電話をかけまくったとか。もう一人の年上の女さえも。わたしもかけずには
いられなかった。日本まで。
あら、でももう、彼の顔ぼんやりとしか覚えていない。そしてその他のことも。
そう、三年半、もう三年半経ったんだわ。あのころの私は、一体どうなっていたんだろう。さかり
がついたみたいだった。あんなことはあれっきりで、二度と起こらない。彼の方から断ち
切ってくれたおかげで。
私のトーマスは、今も私の大事な人。)
「本当ニ」
るりは、噴水のしぶき越しに空を見上げ、のろのろとやっと声を発した。
ローザは咄嗟にはつながりが見つからず、女を見つめた。
女は目を細めて、空を仰ぎ続けている。
「彼女は僕とセックスするためにだけ来たんだぜ」
るりの目の前の青い空気の中に、アクセルの薄笑いが浮かび、たばこの吸いすぎでかすれ
て粗いその声が聞こえた。
「昼休みに飛んできた。割れ目の入ったパンティをはいてだぜ。仕事が終わると、また
やって来て、何も言わずに抱きついてきた。買い物しなきゃ、とか言ってまた飛んで帰
るってわけさ。毎日だぜ。生理の時も何もあるもんか、タンポン入れたままでやるんだ。そして、自分でも呆れている。ゆっくり話し合うことなんかないのさ、飛び込みセックスなんだから」
るりははっきり覚えている。忘れることのできる言葉ではなかった。
体中を欲望とそれが満たされない苦しみが満たした。
天井からはこんな風にストレートな平手打ちを喰らっており、夫からはたえず顎にチョッ
プを喰らっていた。さらに自ら望んでこんな風に脚元をすくわれに来たのだ。
「昼休ミデスカ」
「そう、息抜きには外でぼんやりするのが一番ですもの」
「ホントニ」
「日本語は字を覚えるのがとても大変なんですってね」
女は、目を大きく見開いて見せ、先を促すか
のようにローザをじっと見守っている。
「だから、私がいつ行っても、彼、カンジとやらと格闘していましたわ。あっ」
と、ローザは右手をひらひらさせて付け加えた。
「以前の恋人が日本学の学生だったので」
第1章( 3 / 5 )
(もちろん、彼は勉強だけをしていたんじゃなくて、ちょくちょく飲みにも出かけていた。
ウーテはいわば第一夫人だったし、それに、私にだってトーマスという存在があったわけ
だから、彼がウーテと出かける分には文句は言えなかった。
でも、彼が一人で夜の町をほっつき歩いて別の女の子を引っ掛けようなんてしたときには、
嫉妬を本当に押さえきれなかったものだわ)
(この人はもう二十七,八なのだろうが、彼が表したように、今でも毒のない顔をしてい
ること。自意識の壁がない。自然な自分を自然に表してしまう。
今この人が着ているぴったりしたタイトスカートも、女という性が自然に現れただけの
ことだ。だから嫌味が無く上品ですらある。
お役所勤め、同棲中の男性も幼なじみの律儀で静かなタイプで、安定した長い結びつき。
そんなこの人が、何度も繰り返すオーガズム毎に、抑えを失っていき、彼の手で口を塞が
なくてはならない程になるんだって。ふん、何て嫌なんだろう。
最後にその果てが自分でも怖くなって、助けて、と叫びつつ、高い峰を越えて空のかなた
まで身をそらせて、長い長い放物線を描きながら飛び立っていく。
彼の何かが、彼女のどこかに、深く深く触れてしまったのだ。彼の存在そのものが、彼女
を発光させ、駆り立てていったのだろう。
理由など無くて。
何て嫌なんだろう。
最初、私も彼も、上の住人は赤ん坊もちだなんで思っていた。時々、泣き声らしいのが聞
こえていたからだ。
ロック音楽で赤ん坊をあやすのかしら、と不審には思った。
たしかにそれは、リズミカルに同じ叫びを短い間隔で果てしなく繰り返す、ごく小さな赤
ん坊の泣き声だった。確かにそう聞こえた。
しばらく耳を澄ませてみるが、変わり映えしないのでそのうち何かに紛れて、すっかり忘
れてしまう。
二,三週間たったある夜、しかし、私達はベッドに並んで横たわったまま、その泣き声
の変化を追っていく羽目になったものだ。
あれは、迫真のポルノだった。
女は延々と声を放ち続けた。
女の感じているものが、その波のような多様な変化のまま、手に取るように伝わった。
切迫したり、長い長いため息となったりした。
野太い声となったり、笛のような声になったりした。
私達は身じろぎもせず、その中に浸っていた。
聞き惚れていた。
にもかかわらず、その声の質は言いようもなく不愉快なものだった。
子供っぽいと同時に図々しい、生の声だった。
実に嫌な声音だった。
にもかかわらず、困ったことに、私の心臓は跳び出すほどに鼓動して、羨ましがっていた。
同じものを感じたがっていた。
意識して息を静かに吸わなければならなかった。
アクセルに気づかれたくなかった。
彼の平静な声が響いた。
「赤ん坊なんかじゃない。やってる声だ。クスリを使っていないとすれば、どこかのきち
がい女が、恥も外見もなく目一杯に演技しているんだろうな。呆れたもんだ。」
それは濡れタオルのように私を惨めに打った。
「天井ガコンナニ薄イトハ思ワナカッタ」
私は無理に、観察者らしく言った。
「天井は十分分厚いさ。そんな女がいるもんさ。人に聞かれて喜ぶ手合いだろう。大げさ
に叫んでいるだけだ」
それにしては余りに微妙に変化する、と思ったが黙っていた。
驚いたことにアクセルはやがて眠ってしまった。
男の呻き声も交ざり始めると、程なく静かになった。足音が天井でかすかにしたと思った。
ステレオが聞こえなくなった。
私は眠れそうもなかった。
耳が、いつまでも鮮やかに聞いていた。私は欲情に占領されていた。逃れられなかった。
そして自分が恥ずかしかった。
しかし恥や誇りがどうなっていようといまいと、見ず知らず声の主を、話に聞いたローザ
の姿に重ねて想像の限りを尽くさないわけにはいかなかった。
為すすべもなくさらされていた。ホルモンが脳神経のシステムを支配し、とっくに刺激と
反応のコントロールが決定されていた。しかし今は私という個人にとっては屈辱と怒りと
絶望と欲情の、それは監獄だった。
アクセルはいびきさえかいていた。私は浴室に立って行くしかなかった。小さな喜びを自
分に与えに。
無理もない、とその後で自分を容認し始めた)
第1章( 4 / 5 )
「ここでの生活は気に入っていますか」
ふと思いついて、ローザは尋ねた。
お馴染みの質問ではあったが、闇から日なたへ突き飛ばされたるりは、一瞬、理解し損
なったと思った。間が空いた。
「あら、ごめんなさい、うんざりでしょう、この質問には」
素直に自分に笑いかける相手に、るりも苦笑を返してかぶりを振った。
「オオムネ。タダ、我慢シテルト損ヲスルバカリ、トイウ事アリマスネ。日本人ノ美徳ガ
通ジナイ、トイウカ」
(確かに彼に律されてしまっている。お金になる急ぎの翻訳の仕事がある。真夜中
まで二人で取り組む。ある程度かたがつくと、私は寝に行くことを許される。
彼はなお三、四時間も推敲やタイプやらで起きている。明け方、ベッドに倒れ込んでくる。
もう三ヶ月もそんな日が続いている。五回以上なかったろう、その間に。そして、
二、三日おきにあの声を聞くという寸法だ。彼は仕事にいれ込んだときの常で、気づかな
いのがほとんど。気づいても、またやってるな、と呆れるだけだ。
聖人よ! 私だけがやられてしまう。耳をふさぐことは出来ない。
それどころか、彼が話し掛けたりしてよく聞こえないと怒鳴りつけたくすらなる。静かな
夜にもその幻の声を聞くほどに私の中に棲みついてしまった。
そのあげくが、こんな脈絡のない行動だ。
探索と発見と成功。この人を見ること。
自分に欠けているものをかって持った彼女と同化すること、それを望んだのか?
馬鹿げてる! どうかしてる!)
(すぐに彼のことを思いだしてしまう。何てことでしょう、今日は。
昼休みに、雨降りの日だけ行っていた小さなカフェテリアでアクセルを初めて見た。
トーマスは三日間の予定で出張だった。彼がいないからといって、私の生活に変化は起こ
らない。
彼の留守を利用して求めるような自由を必要としていなかったから。
昼食をアプフェルクーヘンとコーヒーで済ませ、私は椅子に凭れていた。)
店内はかすかな人声で充たされていた。
外の雨の気配が、中の空気をいつもより濃くしているようにローザには思われた。
そのせいで身体の輪郭が少し凝縮されたかのように、妙に明瞭に自分の存在が感じられた。
空気と皮膚の無数の接点の描き出す身体の線と、その内側を充たしているある重さとを感
じ続けた。何も考えていなかった。
その重さは、単に彼女の存在の重さであって、何らかの感情とか、意識や想念や願望とかの
人間的な認識の産物は外側に押し出されていた。
ローザはこの無心の状態が好きだった。その後では自分のことも、他人のことの、より愛
しく想われた。
自分がそんなとき、かすかに柔らかにほほえんでいることをローザは感じるともなく知っ
ていて、理由のない無償の幸せを味わった。
ローザの輪郭を充たしている灰色の無の画面に、突然、黒い雨傘が浮き出た。傘が閉じら
れた。
若い男の横顔が、雨傘の滴を追ってうつむいていた。こちらに顔を向けた。
黒い髪、黒い目と眉、黒いダスター。
顔と手の白さだけが操り人形めいて動いた。
長い指をした、大きな手だ。
白と黒の男は、ぐんぐん近づいてきた。ローザの前の一つ空いた席で止まった。
会釈も忘れたらしく、あっという間に腰を下ろした。黒いバッグから書類を出してすぐに
書き込み始めた。
中肉中背に比して小さめの顔は前髪に隠され、睫の先と鋭い鼻先だけが見えた。指の爪は細
く長い。
ウェイターが来て注文を尋ねた。男の顔がまた現れた。寄せられていた眉が額につり上げ
られた。
薄青いひげ剃りあとの中の唇が少し笑って、コーヒーと言った。薄赤い、一本割れ目のつ
いた、やや厚めの唇。
白と黒と一点赤の男は、さらに忙しく書き込み続ける。ローザは男を映し続けた。
次第に、彼女の身体の濃い線がゆるみだした。
少しずつ、認識と感情が動き始める。神経質のイライラだわ、とローザは思った。
一方で別の感じが、ローザの中で言葉になりかけた。その時意外な素早さで、金髪青眼肉
色の大きな男の姿が立ち現れた。トーマスだった。ローザは画面の中のその姿を見つめ
た。
幾秒だったのか、気がつくと男の視線がそこにある。わずかなためらいの後、二つの微笑
が交わされた。
-
-
受容ホルモン
0










