バカな風
-
バカな風は200円の有料書籍です。
書籍を購入することで全てのページを読めるようになります。
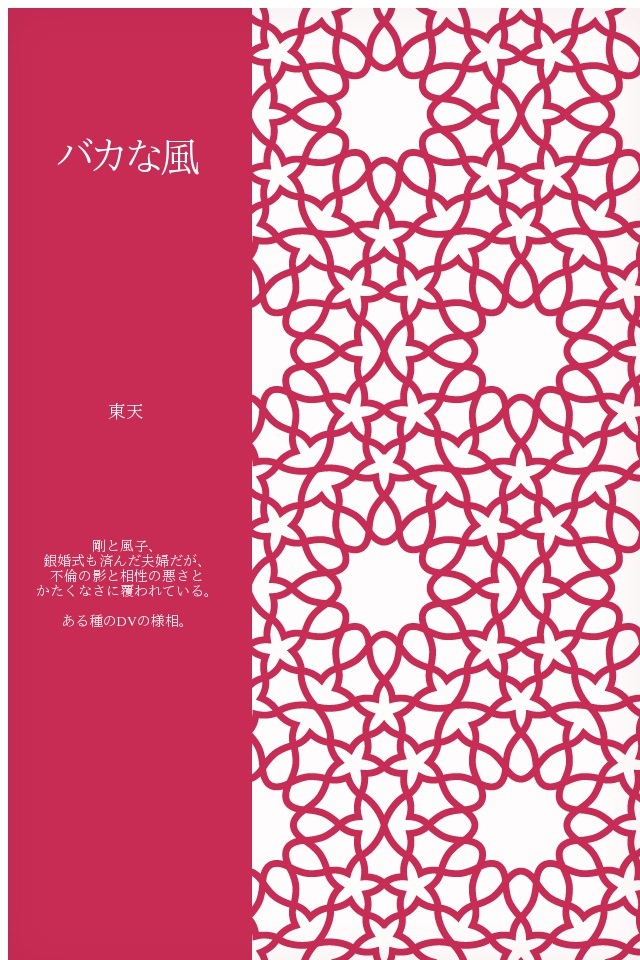
バカな風 全
バカな風
一 起きる人
さて、今日が幸運な日となってくれるといいけれど、と風子は、いたいけない雛鳥の鼓動にも似た碧色の振動が生れ出たこの日を、その現の世界を、もの悲しく覗き込む。双の掌に抱くかのように。
思い描けよ、朝まだき。
三月の星たちの煌々と燃えて輝く遥か遥かな宇宙のひろがりの、その下の、遥か下の、風子の眠っていた部屋の上では、雨雲と雨とがたゆたっていたことだろう。春まだ遠い頃の雨もよい,いつの間にかおぼろに光が満ちてきて、雨から靄へ、雨滴から朝露へ楓の枝が白々と真珠を並べる頃、囁くように、しっ、静かに、とでも言い合うようにかすかな、囀りが。
風子は窓の外へ耳を澄ました。眠りの世界は実に興味深かったのだが。
風子は逮捕されてしまった。ズチャリと両の手首で金具が響いた。女の警察官が道路に転がった真っ白い錠剤を三つ拾い上げたのだ。風子が落としてしまったのを。それらはトランキライザーにすぎなかったのに、
「ほら、麻薬を持ってたじゃないの」
と、恫喝された。生まれて五十年このかた、そんなにも風子をかっとさせた言葉はなかった、ということらしく(夢の中では)、自分でも呆れる程心身の芯から怒声が噴出した。
「ふざけんな、このバカ、麻薬なんかじゃねえよ。ただのただの安定剤だぁ。不正不正不公平、やめろぉっ」
全人生の怒りが怒濤となって噴き出た。夢の中では普通身動きが不自由きわまりないものだが,今回は面白い
程大声がグァラングァランと響き渡る。これは凄いぞ、と思う間もなく、自分の怒鳴り声から徐々に遠ざけられていった、寝室の気配の中へと。真っ白な三個の安定剤が、警官の白いシャツの背中が光を発していた。
辛うじて、これはこれは,とのみ風子は言葉を丸めた。聴覚が、たしか雀ではない鳥の鳴き交わす声の愛らしさに気を取られた時とりあえずは逮捕を忘れてしまった。
二 食べる人
白色に閉じていたブラインドを、斜めに開けると、遠い山並みの灰緑色がサクサク裂かれた景色として透けてみえる。楓の枝にびっしりと並んだ白い雨粒がちょうど二、三個落ちた。光があればダイアモンドのように輝いてみせるのだが。黒い炭素が凄まじい圧力によってのみ整列して放つ数学的直線的反射角さながら。
コーヒーは大丈夫だ。おいしくはないが水の代わりになり多分カフェインとポリフェノールの摂取は推奨さるべきもの、などと風子の頭は肯定している。
へいへい、と頭が合図する。トーストパン、また焦げ過ぎるよ、はいはい、そうでした、また失念、還暦近くなると朝はやはり寝ぼけております、最近、安定剤が多すぎるらし。
少しマーガリンをつけさせてもらう、不安がもくもくと季節外れの積乱雲。食べるとも、今のうち力をつけておかねばならぬ。ガリ、ゴク、ガリゴク、ジゴク、痛いのか悲しいのか怖いのかわからない栄養素の塊を呑み下す。誰もいないが孤独とは縁遠い、絶望と一緒だから。嵐の夜の黒い海が泳げない人に唯一の開けた場所としてある、絶望は後悔と恐怖に彩られている。しかし風子のそんな程度の絶望に何の意味があろうか、たんにバカらしいだけなのに。だから取り込まれるな、やり過ごすのだ。
うんうんと頷き、最後の一口と一切れを嚥下する。つかの間無為となる。自分の存在がはかなくなる。
「ピンポンピンポンピンポン」
三 食事を作る人
「お帰りなさい、おはよう、遅かったのね」
と、風子はチェインをはずし、ロックを外しドアを開ける。夫の眉根に皺が深い。肩までの長髪が風に乱れている。
あやすように笑いかけて、黙ったまま剛を先に通す。目の隅で観察しながら。今日は誰に怒っているのかしら。あざみ? 私?
あれ、とんでもない間違いに気づく。
(あ、いつの間にか時間がバックしてる、まだ頭の中は夢の世界らしい。あっちゃんが小学生だった頃)
夫の剛が三十代後半で、何度目かの失職中の時期だった。神戸での学生生活、就職と、「巌のように我の強い」剛でも破綻無くやって来た。風子は剛の性格をそう解釈していた。際立って美しい外見も有利に作用したはずだ、とも。
知り合ったのは通勤途中のお互いの一目惚れによる。剛の我の強さと猜疑心が、風子の真面目そうな柔らかさに絡めとられた瞬間があった。剛は己の感覚に従い、風子は喜んで引きずられていった。
結婚後間もなく、経済絶頂期のさなかに、最初の保険会社で周囲との衝突が繰り返された後、剛は文字通り辞表を叩き付けた。バブルがはじけていく中で、高卒の風子はよくあるごとく中小企業でパートの工員、本屋でアルバイトの従業員,うどん屋でパートの皿洗いなどをした。働くことは当然と思っていた。
派遣とか非正規とか、社会の仕組みに翻弄されながらも、剛は教育も知性も高いので重宝な存在ではあった。そのためにはしかし、相手や周囲が例外的に幸運にも、柔軟で優しい人々でなければならなかった。そんな場合、けっこう忠義心を抱くところが取り柄なのだろう、風子にはそんな態度の剛は少し可笑しい。
好々爺ばかりが世間にいるはずもなく、会社経営には不運もつきものだったりして、何度か失業状態になっていた。
(夜警のような仕事のあと完全に夜型生活になって、しかも失業中の頃——)
「敦は」
と、尋ねられた。敦には一度だけしか手を上げたことはなかった。
「今日は元気に学校に行ったわ」
ほっとして風子は元気に答えた。隙を見せないように風子は甲斐甲斐しく,という形を装う。卵とハムでいい?と呟き声になってしまった,少し空気がきーんと鳴ったのだ。
誰に怒ってる? それが肝心だ。
「あざみとまた喧嘩した、夜通し、大変だった、あの気違い女め」
風子は一生懸命パンを焼く、フライパンを操作する、ガタガタ戸棚を開け閉めし,要領の良い料理人となる。夫の訴えを口を挟まず聞きながら。
「おれに出で行けだと、着替えや本やいつまでたっても家から持ち出さない、奥さんと別れるつもりが無いんならもう来ないで、だとさ、おれが嫌だと言うと包丁を投げつけやがった、危うく二本目が突き刺さるところだった、ドアにぶつかって先が曲がっていたから余程本気だったんだ」
「二人とも怪我は無かったのね」
「あった」
「え、あざみが?」 「手首を切った」
風子はこれには流石に驚いて調理の手を止め、意識的に剛の目を見た。夫の身を案じ、その影響を案じ、ついでに若い愛人の身を案じた、かのように。
そ、そ、とのみ言った。
「そして夜中に病院におれの車で連れて行った,救急だ」 「手首ってまさか」「そのまさかさ、見て,と言いながら斬りつけたんだ」
(私としても手首でも斬りつけたかったわ、あざみの立場なら同じ反応をしたかも。ひどすぎるわ)
あざみが幼児を含む家族を捨てるはめになったのは、剛に迎合すればこそだったのに、剛自身は妻を捨てなかった。曰く、何故なら風子を愛しているからだ。
「大変だったのね、あのそれでお医者さんの反応は大丈夫だった?」
剛はそっぽを向いた。不運への怒りが溢れようとしていた。まずい,風子は、さあ、とテープルに夫を導いて、ハイ、コーヒー,ハイパンスプン、召し上がれ、と動き回ったものだ。食べるとそのまま浴室に剛が行くので、タオルや肌着をそそくさ風子は準備する、それは一時間ほっとすることができるからだ。多分この調子では一緒に入るように呼ばれないだろう。そう考えたものだ。
何とか剛の不機嫌をそらしてしまうと、今度は、寝取られた悔しさが、風子の心を悲しく締め付けたものだ。そんなに悔しく思ったことが今思えば不思議なくらいだ。理由を考えるよりも先にその悔しさで、裏切られた衝撃で体中がいっぱいになった。決してあざみに剛をとられまいとした。そのための寛大な妻の「ふり」だったものだ。あざみですらそんな「寛大さ」に驚嘆した。
細くて、乳房だけが大きい、眼の光る女だった。剛の外見に強く反応した。色白の頬の線が美しく、眉と鼻梁が逆らい難い男の横顔の魅力を造形していた。あざみ自身が自らの恋情によって女体を開花させて行ったのだ。あざみの激情によって剛もまた、男であることを確認出来たのだろう。そしてそんな関係に風子はジェラシーを感じたのだろう。
ある時期には、嫉妬と羨望と悔しさに身悶えしながら二人の住まいの周りを、風子は徘徊した。そして見た。雨の日に、風子が意地になって近くのバス停で立ったままでいる時、ふたりが喫茶店から出てきた。一本の傘の下、あざみは剛の腕にしっかりすがりつき、剛は肩を寄せて何か話しかけていた。風子が失ったものだ。失ったけれどもまだ欲しくてたまらなかったものだった。敦が横にいなかったら飛び掛かっていったことだろう。
あざみは風子との最後の電話で、風子を説得するように言った。
「外見はいい男、性格はとっても悪い」
二回も三回も繰り返した。その後で付け加えた。
「でも可愛いところはちょっとあるけど」
剛はその一本気と妥協の無さと自己過信からいつでも一つの剛だった。(剛の言葉をまとめると)風子への愛は彼の決意であるので変わらない、あざみとはあくまでもゆきずりのただの性関係だった。少し深い関係になってしまったのは、ひとえに風子の態度に原因がある。風子にはもう恋愛感情は無いのだろう。嫌な男だと思っているだろう、その点を風子は全然改善しようとしない、その充たされなさがすべての原因なのだ。一方、あざみの中にある彼の意に反する部分、たとえば飲酒は断固拒否する。風子に対しても同じ基本的態度を貫くことに変わりはない。あざみは生活の色々なところで剛に縛られ規制されるのに反抗しはじめた。それが別れの序曲だったのだ。
風子の場合、結婚の最初の数年ののち、風子は風子ではなくなった。本来の風子として愛した剛を、偽物の風子として愛することが難しくなったのだ。剛は、自分が愛するからこそ相手を拘束して当然だと思う。しかし、そうする程、相手が変化し、愛という感情が変質したり不可能になって行く仕組みが理解出来ないらしい。
剛の定義によれば、コインの裏表のように、愛と占有欲は当然の組み合わせである。彼の「愛」が、ただの独占欲であって、彼女をを丸ごと愛してはいないのに彼自身矛盾を感じないのか? 風子のそんな質問が、剛にはそもそもナンセンスなのであった。風子には、剛が本来聡明なだけにその点が理解不可能なことだった。二匹の愚かなハリネズミのようだった。
しかしもうそれも遠い出来事だ。
四 健康おたく
朝食の後、無駄な記憶の中に迷い込んでしまった自分にむっとしながら、風子は三月の気候に合ったズボンと長袖シャツに着替える。剛は夜勤で疲れたらしく簡単に寝入った。
「今でもわからないわ、きっと自己弁護かな、それくらいのズルは彼だってするかも,あるいは無意識にでも」
骨の折れかけた老人を介護するかのように、音を立てないよう鍵を回す。
リンパマッサージを習いに行く時間だ。荷物はリュックサック以外に、空っぽにして潰したペットボトルもかなりたくさん。これらはスーパーの収集かごにいれなければならない。
風子は義務を知る良識的な市民の誇りをオーラのように放つ。すぐ横で同じ動作をしている女性と、軽く会釈し合いながら,譲り合いながら。
仲間の一人、こみちさんと出会う。歯を剥き出して親しみを表す。嬉しそうに両方から目を細めて笑いかける。人生の親友ではないが、日常の親しい知人である。時計を見ながら、
「ちょうどいいね」
と、こみちさんが言う。風子も頷いて、
「今日は今井さんくるかしら」
「来ると思うわ、安定剤を変えたら調子よくなったそうだから」
「そう、そんなことあるんだ」
今井さんは、アルツハイマーの症状が最近進行してきていた。
「風子さん、ご主人はおうち?」
「そうなのよ、例の通りね。今日は何とか出てきたけど、また携帯かかってくるわね」 「善し悪しよね」
とこみちさんが当たり障りの無い風に応じる。花粉症の話、血圧、病院、孫、話題は尽きない。風子には余り人に言える話題がないのだが、情報は受け取る。
集会所につくと、もうお当番の金子さんが準備を済ませて先生の到着を今や遅しと控えていた。続々と中高年女性が集結して来るので、なかなか騒がしい。みんな浮き浮きしてきている。
今井さんは、人一倍喋っている。しかしいつも同じ内容なのだが、実にうまく人の輪の中で主導権を握ることが出来る。相手をする人々は少し困った顔をしながらも今井さんを、その小さい話題の外へと彼女を導きだそうと努力する。すぐにまた彼女の中に引き戻されるのだが。
祝先生が到着すると、今井さんは賑やかな挨拶を始める。五分を見計らって風子が困っている祝先生を今井さんの陽気な語りかけから解放した。
その間にゆったりした音楽が流れ出し、全員が美しく距離を保ってウォーミングアップを始めている。
祝先生は地球から直角に人々を立たせるのがうまい。あごを突き出させ,次に静かにあごを引かせる。
「頭のてっぺんから宇宙の、足の裏からは地球のエネルギーがしみ込んできまぁす」
祝先生の力強い声がみんなをピンと立たせた。それだけで呼吸の通り道が確保されたように幻想する。生の正しい場所に立っているかのように。神経を落ち着けてから、その場に腰を下ろして足の裏の数カ所を指で押す。足首から、ふくらはぎへ圧力を移動させる。
少々急所をはずれていても当たらずとも遠からず、と祝先生がいつもの冗談を言う。両手の掌で下肢を撫で上げる。すでに心地よい。膝を潤し,大腿まで一息に撫で上げると、鳥にでもなれそうな脳への刺激が生じる。性的な意味合いは全くない。こんな快感というものも心身には備わっている。風子は鳥になり、樹になり、星になる。
リリリンリリリンリリリン。
風子は輪を抜けて、荷物のところへ走り出す。チッと心中で舌打ちする。携帯電話をごそごそと取り出す。途中で目覚めた剛は風子の予定をまた忘れたのか。
「あ、そうか、忘れたよ」
剛は意外にあっさり答えた。がすぐに「朝ご飯は何だ?」
と、強い声音になった。うんざりした気分に充たされたが、
「わかってる、何か買って帰るよ。まだ寝なきゃ」 と、風子は平静を装って静かに反応した。
仲間の輪から、愛されてるねえ、奥さんがいないと心配なのよねえ、と冷やかしの声が聞こえる。悪意のない礼儀だ。「まったくもういやんなっちゃう」
風子は笑い半分の顔で動揺を隠したつもりだ。同じような境遇にあれば、わかる人にはわかる不自然さだった。幸いにもこの仲間には、風子を透視する女性は多分一人もいない。つまり総じて夫婦の力関係に特別の偏りはないらしかった。
全身に栄養と酸素を運ぶ血管に沿うように、リンパの小川がそれとも見えぬほどの細やかさで、張り巡らされている。リンパ液の湿地帯は、細胞の排出する液体と、その中の排出物や免疫物質をチェックする。そこが滞ればいわゆるむくみだ。糸のような小川から次第に水脈が作られていき、次第に本流へと流れていく。下肢から上へとリンパ液を流すのは筋肉の力である。
祝先生は筋肉を強くする運動に時間の半分を費やす。いわゆるスクワットが中心だ。それがすむと、手で皮膚表面を柔らかに撫でて流れを促す。
汗ばむけれどもすっきりとなって、いかにも健やか、という気分の一行が帰る準備に入る。
「風子さん,今日はうちに来る?」
と、鈴川さんが尋ねた。木彫りは唯一美的趣味といっていいものである。鈴川さんの小さなサークルに二回参加した。風子はおおざっぱな性格なので一彫りずつ進めていく作業に上達は望んでいなかったが、自分なりに丁寧さを心がけて、少しずつ形を彫りだしていく無心な時間は好きだった。ひたきを一羽、十センチ四方の木切れから彫りだす仕事はほとんど小さな体が現れるところまできていた。
「ご免なさい,駄目みたいだわ。主人が」
「そうよね、あのね、いつでも続きを彫りにきていいのよ。ちょっと電話して、駄目な時は私そう言うから」
「本当に。また寄せてもらうね」
「けんかしてもね、誰かがいないと淋しいわよ。一人は嫌よ」
と、鈴川さんが諭してくれる。彼女の夫はこのグループで知り合う前に亡くなっていた。
暖かい丼ものを、総菜屋で風子は買った。みんなはまたね、と挨拶を交わして三々五々分かれていく。
風子は一人になると、生姜焼き豚丼を胸に抱きながら、昔の友人を思い出しつつ歩いた。こんな私でもいいと言ってくれる人がいて、と森本夕子が手紙をくれたのは何十年も前のことだった。
夕子は可憐な美しい女性だったのに、何があって「こんな私」などと結婚相手に対し、卑下しなければならなかったのだろう。そして女の子が生まれたと聞いた。しかし二年も経たぬうちに夫は若死にした。毎晩枕の濡れない夜は無い、と夕子は書いてきた。夫は彼女にとって天使のような存在だったのだと。
またひとり、天使のようだった友人を思い浮かべた。いつも風子を助けてくれた。困り果てていると必ず声をかけてくれて、具体的に手助けしてくれた。あんなにも愛される資格はまるでない自分だったのに、と風子は呟いた。
そんな二人とも音信不通になり、思っても探してももう見つかる人ではなかった。
通りの先で手を振る人がいた。隣の奥さんだ。風子は喜んだ風に体を揺すって走りよった。双方から,どぅお?と明るく言った。
五 主婦である人
静かにドアの鍵を回す。風子の風来坊、と剛は折あるごとに言う。まるで外で自由を満喫しているかのように。運悪く今日のように、途中で目が覚める時には。
剛はすでに居間に居た。
「丼もの買ってきたけど、どうする?」
と、おもねるように風子は尋ねる。ふん、と音がするのが、よろしいという意味だ。
「もう一度暖めろ」「まだ温かいけど」
「暖めてくれ」
風子はレンジに丼を入れ、それから、しまった、と慌てる。コーヒーがまだだった。出来立てのコーヒーは剛にはいつも熱すぎるのだ。自分でもちょうど昼食を食べていい頃なので、かたわらインスタントラーメンを準備する。
「なんだ、君のは買わなかったのか」
風子はこっくりする。
「ラーメン、食べたかったから」
「バカヤロ」
風子はこの罵倒が大嫌いだが、口を閉ざしている。挑発に乗ったらだめだ。おれと同じもの食べたくないんだろ、とか、愛してるよ、とか嫌がらせにもっていくつもりなのだ。とは言え、うっかり口調を合わせて「私も愛してるわ」と言うとする、「バカヤロ、ウソツキメ」とくる。
「ちょっと醤油」「はい」「うむ」
「はい、唐辛子」
うまく進んでくれて風子には有り難い。これから仕事に出なければならないのに難癖を付けられては困る。その隙は見せられない。前回は遅刻してしまったのだ。午後毎日雇ってくれるところはどこでも働きに行く。客商売には向いていないので、どこであれ裏方の仕事に雇ってくれれば良い。それが現実だ。
剛は夜勤の職から朝方帰り、それから昼過ぎまで睡眠をとった。いつもはもう少し遅くまで眠っているのだが、と風子は剛の睡眠時間を計算する。
「おい」
「どうしたの」「お茶だ、お茶」
「あ,お茶ね」
「お茶ね,じゃないだろ、のろまめ」
「機嫌悪い、おおこわ」
風子も無駄には剛と長く暮らしていない。少しは茶化すことも出来る。失敗する危険もある。風子の強みは、剛が天涯孤独であり,友人もいない、あざみすら逃げていったことだ。風子しかいない。
「あたしが先に死んだらどうする?」
「知るかそんなこと!終わりだ」
その言葉は本気だと風子は思っている。心底ぞっとするが、とりあえず無視する。
六 仕事をする人
風子の目下の仕事場は、自転車で二十分離れた産直スーパーの店である。別に楽しい仕事ではない。家に置いてきたものは忘れることにする。労働時間は今では彼と変わらない位だ。文句を言いたい心は無視する。無視しなければ生きていけない。
比較的新しいその店の店主は、脱サラのような感じのもそっとした中年、店員はみなパートで三十代女性三人と風子五十六才である。年齢的には先輩格だが、仕事のできは格下なので、
「りんごを箱から出して下さぁい」
などと、指示される。手書きの値札やお奨め品の宣伝文句もこの種の店にありがちな素人臭さはあるものの、制作係の美佐子さんは腕を上げてきて,楽しそうだ。風子はどこの職場でも、リンパを整えた体力気力で一生懸命切り抜けてきたつもりだ。いつの間にか、和気あいあいという雰囲気の中心になっている。話術もないし、リーダーと言うのでは全くないのだが、悪意の無さが安心させるのか、ここひと月程で親密度が増してきた。間違ったりすることをお互い受け入れ,間違いが起こらないようお互い注意する。注意が悪意でない、という癖が職場についてくるのはおもしろいものだ。
週に一度しか会わない趣味関係の仲間とは、表面的な対話となる。しかし時にはぐっと深く突き刺して気持を見せ合ったりはする。心がそのせいで残る、慕わしい気持ちにもなる。
職場のようにほぼ毎日、緒に居る環境は、仕事だけの事務的な接触に終わるのが多い。それは仕事の量や厳しさに左右されるだろう。競争心ばかりに駆り立てられる雰囲気では、本当に神経がすり減り,それでも頑張るとやがて燃え尽き症候群になる。そんな責任を負わされないようにするのも一つの手だ。
来客が途切れたり,スタッフルームで一休みする時、寺本さんがいると少し妙な会話が始まる。実は不倫しているんだけど、彼とのセックスがもうひとつなの、と言い始める。美佐子さんは,急に素知らぬ風をする。お宅はどうなの、と寺本さんに突っ込まれると、
「うちは、べ、別に正常よ」
と、頬を染めてボキボキ言う。
「ピンと上までいくの」
「え、あ、も、ちろんよ」
「実はね、すごく嫌なことあったの、うちで」
と、風子が切り込んだ。居合わせた視線がぐっと向けられた。
「うちのだんなの彼女がさあ、もう以前のだけど、全然止まらないんだって、だんなが得意になって」
「な、ーー」
と、みんなの目が宙に浮いた。
「何がーーー、え、ピンと?」
「そうよ、ピン、なんてものじゃなくてピンピンピンピンよ、逃げて回ったって」「何で?」
「もう恐ろしくなってよ、彼女自身でも」
みんな静まって、動悸を押さえている。喉がごくんと鳴った人もいた。
しまった、これは強すぎた、と風子は白けた場をとりなそうと、
「きっとくすりでも使ったんでしょ、クワバラよね、ふざけてるわよね」
と、笑い声を放った。
何となく気もそぞろに、ぼつぼつと、それぞれが店の配置に付いた。
風子の心臓がドキッと弾んだ。喜び、ではない。いまさら恐怖ではないが、困った、見張られている、というドキッである。
我々は共依存なのだ,心理学の記事を読んで知ったその言葉を、いつものように自分に言う、諦めの呪文だ。剛も知らん顔をして、乾物の辺を見ている。誰かが、いらっしゃませ、と挨拶した。風子は見られないような隅に隠れて、座り込んで何かを整理するふりをした。後ろ向きになって、剛に気づかないようにみえるようにした。
どうしてそうするのか、自分でもわからなかった。家に帰れば、剛がこのことを非難するのは目に見えていた。
「おれがいても気づかなかったてか?ありえねえよ。恥ずかしい?おれが?せっかく顔を見に行ってやったのに、冷たい女だ。愛情なんかやっぱりな、なんもないんだろう」
七 哲学する人
四時間の労働を終えたのは間もなくのことだ。群青色の空のもと、風子はまた三々五々同僚と別れて帰路についた。剛の登場が与えた習慣的な不安と、それを諦観する作用とが胸を押しつぶした。
(剛によれば、愛は人を弱くする。傷つきやすくするんだそうな。それはわかる。でも、なんて言いながら、私を非難し暴言を吐き抑圧するのだ。愛なんて、大体いい大人がいつまでも拘るなんて、あり得ないよ。愛なんて生物の作戦にすぎない。狡猾な作戦だ。巧妙で効果的な生物戦略であるのに。)
風子は次第に自分一人の世界に沈み込み始めた。誰もいない。
冷たい風が毛糸の帽子の編み目からひしひしと沁み込んだ。愛情の由縁とその働き方の根本を知らなければならない。そこに全宇宙の真実と嘘の概要がある。
(私を次第に微細に分化していく。ますます少なくしていく。
ついには、最初の形、二つの大小の細胞の混雑したものとして、涙の雫のような水滴の中で、球体となり、なまこのようなものと化す。
たちまちのうちに、神経の中心とそこから延びていく形とを形成する。
六週間もたてばまなこの形が現れ、心臓が拍動し、小さな四肢すらも萌芽する。
ますます巨大化する。進展する。見事な神秘の連係プレイ、無限数の試みの最適な結果だ。
命令一下の、系統を意識しての発育ではない。近辺の要請にお互いに従っているのみらしい。隣の隣の隣の隣。
その隣りではもうアポトーシスの実行中で、その結果小さな指のかたちが生成してきた。自己組織化。この環境ではこの遺伝子がほどけるべきだ、とでもなっているのだろうか。
この秘密へとまだまだ人類は捜査中だ。道は遠い。しかしいつか果たすだろう。発生の秘密の全容の解明。もし地球がまだ棲息可能であれば。
などなどなど、の行程を経て、途中でミスプリントなどのせいで正しい発生が妨げられた場合、システム的に早目に除去される。脳内の神経網は構造的に基礎的配備が整う。
脂肪を蓄える期間が最後のひとつきだ。胎児は明るさ、音、親の声、言葉、母親の感情状態、などとっくに感じているらしい。そしてあのふっくら柔らかいぷちぷちのピンクの生物が日の下に出現する。肺胞をプチプチ開き、酸素を取り入れることが出来るまで激しく呼吸する、つまり泣き叫ぶ。
などなど、頑張って赤子を対象物として観察描写記録してみるが、考えてみると、だれひとりとして新生児でなかったもの、このすべてを体験し通さなかったものは、この世に生まれたものの中にはいない。他人事でなく自分もそうであったことが、覚えていないので、そうか自分もみんなもそうだったんだと考えつくとき、何かとても妙な、一体感、罪を免れたような気分になる。
そんなこんなで、無事に第一日目、第二日目、第三日目、と日を数えていくわけだが、まるで創造主の世界の創造にも匹敵するほどに、産めよ増やせよ世に充ちよ、とばかり増えていくもの、それは体重のみではない、脳神経細胞の網の目だ。
読んだところによると、まるで薮のように、絡みあうほどにびっちり増えてしまう。それからがまた大変な行程が始まる。
あらゆる刺激はその回数が増えるごとに、より強いより太い神経の回路の束を形作る。こうして環境に適した脳の回路が出来上がる。
こんなあんなするうちに、子どもは整備された環境にあれば、恐ろしく早く知識を吸収する。ママがすべてである。他には空腹と眠気と好奇心を感じる。快不快と不安も安心も感じる。
ああ、そう言えば喃語という時期があったなあ、懐かしい。ともかくいろいろな音を発声する。ありとあらゆる音で、言葉ではない音で話し続ける。周りの人のように発声しているつもりだろうか。楽しい自由なお話タイム。魔法の時代だ。
たとえばひとつの突破口は、こんな具合に見つかるだろう。
積もうとした積み木を落としたり、食べようとしたお菓子がうまく口に入らない時、あぁあ、と最も接触の多い、安心出来る人が言う。その音には慰められるし、がっかりや怒りをそらしてくれる効果がある。なので、同じ音を出そうと始めて試みる。これは結構簡単だった。
一つの失敗を巡って、母と子どものやりとりが始まる。対話だ。
「あぁあ」 「あぁあ」
「あぁあ」 「あぁあ」
と、際限なく喜びとともに繰り返す。もうばっちり接続した。
そのうちに、マ、という音に大好きな人はよく反応する。うっかり「ンマ」「マンマンマン」とか口が動いてしまおうものなら、ニコニコ笑って大喜びの声を出して大好きな人は励ましてくれる。「マ」真似をする。「マ」もう一度、「マ」真似をする。「マ」簡単だ。
もう一つよく聞く発音、余りにしばしば聞くので小さくても神経細胞で満杯の脳はすぐ慣れる。犬だってすぐ覚えるのだ、自分が呼ばれていると。自分というものが感じられるとして。まあ、犬も感じるだろう、自分の地位を、生存を、快不快を。
その音が聞こえたら、大好きな人を見る。笑っているので笑う。笑うとその人も笑う。楽しい。その音と一体になった感じなだ。その音がともかく切り離せなくなる。たとえば「あっちゃん」と、目の前で言われる。真似をする。「アッタッ」発音というより息がでているだけだが、また笑ってくれる。嬉しくてお腹のそこから空気が吐き出される。高い音だ。キャッキャッと聞こえる。楽しい。
ついに決定的な時が訪れる。
「ママ」が誰であるか、「あっちゃん」が誰であるか、おおよそわかってきた。
「あっちゃん、ママって言ってご覧、マ、マって」
「マ マ」と簡単に真似出来る。
「はあい」
と、ママが言った。なんだ?と、眼を丸くする。「もう一度、ママって言って」 「ママ」 「はあい」
お、これは真似っこ遊びだ。
「あっちゃん!」
と、ママが妙に強く言った。
「アーイ」
これでどうだ。ママは眼をきらきらさせている。「あっちゃん」 もう一度だ。
「アーイ」
嬉しさと喜びと誇らしさが爆発したみたいにママはくるくる回った。一緒に回ったら少し頭の中が変な気がした。
何度も遊ぶ。夕方に現れるパパの前でも、何度かやる。失敗はしない。
生後一年前後になると、ママのしていることを真似して付いて回る体勢になる。そばにくっついて、「アッタンも」と言う。すると「あっちゃんもしたいの、はいどうぞ」とか「危ないからダ、メ」とか反応してくる。諦めたり、怒ったり、アッタンの反応もそれぞれだ。
またしばらくすると、もうひとつ決定的な瞬間が来る。
あっちゃんは気づく。ママはあたし、という言い方もする。パパはおれ、という言い方をする。あっちゃんはどう言えばいいのかな。
「あっちゃんも」「それ、あっちゃんの」とかいう代わりに、じゃ、男の子だからオレかな。テレビの強い男はオレってよく言ってるし。
そこで、さまざまな要因を配慮して「オレもする、あるいはオレもほしい」と言うことにした。ここに、すでに他と異なる自分と言うひとつの存在が意識されている。他人ではなく、自分の快不快、欲動、嫌悪、不安、喜び、誇らしさを感じる。そのひとかたまりのものが自分である。この存在そのものである。)
風子は思い出して小さく笑った。「これだあれ」と、写真の中の敦を指差したことがあった。敦は見つめたがたちまち難しい顔をして考え込んだ。まだおむつをしていた頃だ。そんな子供が考え込む、不思議な光景でもある。あたたん、と敦は熟考の後答えた。
何と賢い子供であることか。一般的な赤ちゃん、だと認識してそれを記号で伝えた。母親は残忍な喜びに溢れて笑った、嘲笑した。これ、あっちゃんよ,あっちゃんよ、と言いながら笑い転げた。
敦は何も言わずになおも写真を凝視していた。母親の嘲笑に驚き耐えていたのだろうか。母親は子供を驚かせたことで、有頂天になるほど愉快だったのだ。
あっちゃん、敦は無事に自己同一性を育むことが出来た。その中身は幸いにも中くらいの満足と安心と誇らしさとで成り立っていた。現在にいて喜びがあり、あしたへの希望とがあった。時には嫌な気持ちも抱いた。耳鼻科へ連れて行かれるとき、欲しいものを買ってもらえないとき、遊び友達と仲良く出来ないとき。
しかし幸いにも幼児の頃まで辛うじて、敦は感情のバランスの適正な環境で育てられた。全身全霊で四歳の男の子であり、その周囲のまだ小さな世界の中にいて、それなりの感情をもつ、ただ一塊の存在である。
ああ、そうか、と風子は突然立ち止まった。剛はあの頃の敦のような一本気なのだ。世の中とその時々に折り合って、自分を合わせられない。そんなことを拒否している。一本の剛い曲がらない樹なのだ。だから風子への愛を貫くというのだ。それがどんな影響や反応を避け難く生み出すとしても、それが剛自身に不利益となるとしても。何故なら剛には余りにも明らかなのだ、自分が正しいことが。間違いや嘘や自己欺瞞、悪意、虐待、そんなものは頭にない。愛することは唯一ひとの誇るべき正義なのだ。
八 家族を束ねる人
敦は風子のただひとりの無償の愛情の対象である。風子の人生からなにか悟りのような認識が得られたとき、携帯から何気なく,押し付けがましくなくそんな感慨について彼方に住む敦に一言書き送る。敦はそれらを無視していっさい返事を寄越さない。風子はそれもあり,だと思って無視を受け入れる。
敦が一人で、家族内の不穏な空気に耐え,学校でのいじめや忘れ物の多さに耐え,思春期の驚きと恥ずかしさに耐え、初恋が無惨に破れたことに耐え、次第に男臭くなり,ごつごつと毛深くなっていったことに耐えて、大人になる。それを黙って感じながら,風子は、我が子が自分と違う人間になることに耐えていた。
いつも敦の意見や意志を風子は受け入れたが、片方では自分の考えや希望の影響がひそかに忍び込んでいるかもしれないことに注意した。敦が風子に似てまじめでありながら、風子に似ずウィットに富んでいるのは本当に楽しかった。敦と話すと、わくわくする思い出が増えた。
陽子は敦の妻になることを望んできてくれた。天恵そのものだった。敦が幸せで充たされていることを風子はどんなに喜んだことだろう。そう思い描いては風子は笑みを抑えられなかった。
そんな風にもう敦は巣立ってしまった。剛と古い賃貸マンションに残された。もっとも風子の母親が近くに弧老として独居している。風子などという風変わりな名前をつけただけあって、母親の名前も周子である。
幼い時は母親は絶対の、生存をかけた拠り所、つまり愛の対象であった。子供時代を過ぎると、風子は父親の人間性を高く評価するようになった。これは稀なことであったはずだが事実父の思いやりは海のようだった。
相対的に母の周子の価値が下がったのは面白いことと言わざるを得ない。つまり周子はかなり自己愛の強い、吝嗇で完璧主義な人物であることが、次第にわかってきたのである。自然児という面はあった。嘘をついたりおべっかをつかうことを風子に許したし時には推奨し、人種差別もわきまえていた。それをもって自然児の特徴ということが出来る。勿論自然児の良い面も持ち合わせていた。
一方父の義男は大脳皮質的な理念的な、不自然的な余りに温和な公正な、余りに無私な男であったがために,子供の風子には、操作されているような不快さが少し感じられたものだ。自分のことは自分でできるようになると、母を愛することが不必要になると、父への敬愛が増した。
義男との会話や触れ合いの親しく、信頼のおける感じを思い出しながら、風子は自宅方向に近づいて行った。星のまたたきを見つけた。生きていてほしかったなあ、と心の中で呟いた。ね、と星に向かって頷きかけた。
風は冬そのままの冷たさだった。何か嫌な不吉な逃げ出したいような感覚がふと甦る。すでに十年も経っていた。この絶望的な感覚は久しぶりに風子を捕まえた。敦のことを考えたせいで,敦自身が学校から帰りながら、逃げ出したい程に怯えて、不安で顔色も変わる程に怯えつつ、それでも帰る家であったことを思い出した。敦自身が数年前、告白した。風子はそんなことは言われるまでもなく知っていたのだ。気づかぬ振りをしていたのでもない。そうであるはずなのにそのことを考える余裕がなかった。
今,剛はよくある警備会社に短期の仕事を得ていた。余り人と喋らなくても良いと言う点と、剛自身が夜警のシフトをやりたがるのでこのまま続きそうだった。風子のパート先の産直店にふらりと現れてから、剛はそのまま仕事に出かけた。風子にとってその時間は母親の周子に夕飯をとらせる時である。
「かあさん」
と、風子は遠慮のない大声を上げて部屋に入って行く。板の間をどたどたと歩くのを、周子が好まないのは知っていたはずだが、もう忘れていた。周子も注意や嫌みをいうことは全くなくなった。笑い顔で嬉しそうに、「ふうちゃん」と、目を合わせてほっぺたの皺を伸ばした。そうすると元来の肌理の細かな色白の肌合いがつかの間甦ってきらりと光る。
子供の頃、家族って何、と義男に尋ねたことがあった。義男は明確に定義した。
「家族って、喧嘩もするし,気に食わないことも言ったりするだろ、他人だったらそれで本気に嫌いになって別れたりする、でもなあ、家族はそのうち嫌なことを忘れ,普通に一緒に暮らせるのさ、欠点を許すっていうのかな、別れたくないんだ」
周子が風子の心を傷つけたこともあった。その逆もあったことを思い出す。そんなことは昔話だ。周子にとって一人娘の風子が唯一の頼りとなって以来,ふたりはよく笑い合う。物忘れや、転んだり歯を忘れたり、花を写したり、食べこぼしたり、ごみを代わりに捨てに行ったり、ささいなことに笑い合う。笑い飛ばしている。そんなお互いになろうとは双方とも考えなかったのだが。おいしい、と笑い、まずい、と笑った。
周子の世代は、戦後の食糧難こそ味わったが,その後の希望に満ちた高度成長時代を生きてきて、人生の収穫に恵まれている。
周子はもとより豊かではなかったが,貧しくもなく預金も持っていた。その後ほとんど利子がつかないために目減りしていくのは致し方無いとしても、国民年金、介護保険ともに長期的な視点から見ると、最も手厚い状況にあると言える。
周子には幸いにもペースメーカーを装着するほどの心臓障害があったために、要介護認定を受けている。デイサービス,ヘルパー制度を利用するので、風子の介護もまだ楽しみのうちといってもよかった。
家事全般、得意とは言えない風子にも、料理は独創的なものならうまくできた。少なくとも周子と二人で食べる分には。周子は、暖かくて風子と一緒の食事では、たいていの場合、
「おいしかった、全部」
と、言って喜びをみせる。風子もまんざらではないので、それが介護が楽しみとなる要点であった。
剛の仕事の都合次第では、その後に、あるいはその前に、剛の食べる食事の準備が必要となる。食事の好みに関しても、真っ正直だ。健康のためとか栄養を考えてものを食べるのは邪道であって,うまいものと好みのもの、食べ慣れたものしか受け付けない。葉野菜を出すと
「おれはうさぎじゃない」
と、剛は言う。根野菜ははなから嫌いである。ビタミン不足になって吹き出物ができても譲らなかった。キャベツの似たのと生の大根は好きである。果物は幾種類か食べる。
周子の世話が済んで、風子は自宅に戻ろうとする。彼は早朝まで守衛さん、風子は夜気の中、星へも届けと吐息をフッと吐きつけた。
夜九時過ぎたころである。道路のほぼ斜め向かいに建つ、自宅のある市営住宅まで星や月を眺めて帰るのももう五年になった。その前の五年は周子が毎晩道を渡って風子宅へ通って来た。そうか、実は母親も料理が嫌いだったのか、と風子はわかった。昔、台所で、
「どうしてこんなに毎日毎日料理しなきゃならないんだろう」
と、周子がため息とともに言ったことを妙にはっきり覚えていたが、今の周子の状態ならともかく、まだ体の動いていた五年前にもいっさい料理しなかったことが、今頃合点が行く。趣味の書画か、庭の手入れ、そのほうが食べることより大事だったのだ。介護も受け,娘の風子がやっと煮炊きをしてくれるようになったので、周子にはいまが趣味三昧の生活であった。ほんとに運のいい人だな、と風子は思う。優しい真面目な夫,親孝行な娘。そう言えば、剛も真面目だ。余りにも自分に真面目だった。
九 夫婦として登場する人
風子がまさに小さなパソコンを開いた時,風子の携帯から最大音量でメロディが流れ出た。風子の知らない強い旋律だ。剛が勝手に設定しておいたらしい。風子が最近耳が遠いと剛は言う。
「はあい」「風子、いつも出るのが遅いね、返事するまで間がありすぎるぜ」
「そうだった?ごめん。で、何」
「ちょっと課長代理が顔見せてな、おれ暇そうなのでラーメンでも行くか」
「もう夕食すんだけど」
「構わない、おれともう一度食べろ」
風子は抑圧されたという感じをぐっと飲み込んだ。「いいわ、準備する」
と、パソコンを閉じた。もう一度携帯が鳴ったら、外に出る。いつもの激辛ラーメンに行く。すでに銀婚式は済んでいる。それほど長く暮らしていると相手の出方はお互いわかっている。
ポストのそばで剛に拾われて、車で二十分走る。剛は制限時速をきっちり守る。信号では歩行者および自転車にきっちり注意する。彼らは黒い服を来ていたり,ライト無しで信号無視で猛スピードで渡ろうとするからだ。従って剛は横断歩道を曲がるのに、他のドライーバーよりのろのろ進む。
前が空いていても、時速40キロは守る。後ろから危険を冒して追い抜く車も多いので、風子は気が気ではないのだが、もう何も言わない。剛と走っているとかえってこのまま事故死することもあるかと思う。でも剛は正しいのだ、制限速度で走っていたのだから。
「見ろよ、あいつ赤信号を突っ走ったぜ。まったく!おい、今追い越したのは禁止地帯だったよな、百キロは出してるな、まったく。何故みんな法律を守らないんだ、おい、また無灯火自転車だ、あれで事故が起こると自動車がいつも悪いんだよな」
剛は絶えず罵っている。
「運転に集中!」
と、さすがに風子が怒鳴る。いつもは静かな風子がときに怒鳴ると、剛が妙に神妙になることを最近数年体得した。妻の強みだ、風子はやった、という感じをつかの間楽しむ。
ラーメンをすする音を、なるべくたてないように剛が食べる。風子はほどほどにすする。剛がちらと見た。すするのを辞めて前歯で切り落とす。剛のあれこれの流儀は風子をいつも不安定にさせる。風子自身ではいられない。風子は雲散夢死してしまう、せいぜい不自由感が積み重なる。それが日常である。
しかし少なくとも、こうして外食すれば家事をしないで済む。命令一下、家政婦のように走り回らないでいいし、その分不満感は減る。剛は、風子の負担を軽くするために意図的に外食に誘うのだと言っている。少し気を使ってくれる様子を強調するところがおかしい。時にはまずい風子の料理以外のものを食べたいくせに、と思うが、やはり全体が滑稽なので少し笑った。剛は苦心して、熱いめんを口に押し込んでいる。
剛は、年をとってもいわゆるロン毛のスタイルを変えない、おまけに人目を引く程好い男であった面影が今も残っている。女に限らず男もちらと目を留める。若い頃は二人で歩いていると、町中で声をかけられることがあった。
「あの、すみません、自分はホモなのですが、あなたがとても気に入りました。いや、それだけを言おうと思いまして」と、丁寧に言われたことがあった。
この話はまるで人生の華ともいうべき、夫婦にとって数少ないほこらかに笑い合う話題である。そんないくつかのエピソードが、日常の不満や鬱屈を吹き飛ばす瞬間として働くとき、お互いを失うことがあれば、それは少なくとも友情を失うような、人生の味方を失うような喪失であるのだろう。風子自身そう感じたり、想像してみたりすることがあった。剛はいつも絶対に風子を失いたくない、とはっきり言った。まさにあざみとの重婚状態の真っ最中であっても。
美し気な夫と連れ立ち、夫に魅力的だと思われている妻として、夫婦として少し世間に身をさらすとき、風子は少し心が華やぐ。剛は一瞬にしてそんな少しロマンチックな風子の気分を壊すのが得意だった。あるいは一瞬にして恥ずべきパートナーに変身するのである。
十 ネットの世界の人
恥ずかしい、と風子が感じるのは、その時の食事でも剛がたえず誰かを批判してやまず、あらゆることに文句を付けることであった。そんなうるさい夫に我慢出来る人間がいるとは誰にも思えないだろうと思ってしまう。せいぜい自分も、似たような口うるさい文句好きの人種であると思われるだろう。あるいは、自分が世にはやっている家庭内暴力の犠牲者であって、それにもかかわらず出来るだけ平気な顔をしているのが、わかる人はわかってしまっているであろうことが嫌だった。風子自身を恥じた。
しかし剛は性格的に高慢であるとはいえなかった。むしろ人生の目的を、単に「生き残ること」と定義しているくらいだ。世の風潮に踊らされてキャリアなどを積もうとは思わない、潔い男でもあった。とは言え、剛にもやはり、思い出しては得意になる、いい気分を得られる核になる部分が人生の中にあった。高校時代まで剛は数学と絵画の天才であると周囲から思われていた。
その時の熱中の感覚、その成果と満足感、それらはやはり剛の中で輝いていた。人生の岐路に立った時、実学を選び就職に有利な工学を自ら決定したのだが、今ではその捨ててしまった夢の道が、唯一剛が好んで語るポジティブな、追いかけるには遅すぎるがいつまでも忘れたくない話題であった。
そんなものは風子にもある。それどころが夢の道はたくさん存在した。たくさん過ぎた。あれもこれも好きだ、というのは結局どれも選ばないのと同じである。案の定彼女の人生は、結婚して主婦であり母でありパートであるというありきたりのパターンそのものだ。にもかかわらず幻の、魔法の世界は賑やかに広がっていた。
四角い箱、ボタンを押すと光が射して来る。有機物である人類が、ここにたどり着いた無機質の電子の単純世界は一かゼロかで成り立つ。そこには算数とは違う法則があり、とてつもない計算の高速化と、この果ては原子にまで手をかける程の最小化への道筋が、すでに見えている。その流れにどうして風子も乗らずにいられよう。
剛は当然ながら、この金属と理論と電子の世界を理解した。敦はもっとよく理解して理屈を超えた直感と情感とでその世界へと、遥か彼方へと歩み去った。
剛は、その世界の危険を察知した。悪意とプライド、どちらかの入り口からその危険はこっそりと忍び込んで来る。たくさんの反悪意ソフトが作られるのは当然だが、それにまさる悪知恵も程度をあげてくる。その追いかけっこを剛は否、とした。
ほとんどパソコンに触らない剛に比べ、風子はインターネット接続の世界に魅せられている。悪意に襲われる可能性を軽視しているというより、自分を投入出来ることに魅入られている。
たとえば、風子は新聞やテレビに対する批評家の立場を取る。それに自ら描いた絵をつけることもできる。どんなに稚拙なものであろうと、誰に何も言われない。誰も見ないはずだが、見られる可能性は存在している。赤の他人が、風子のさえないページを仮に、読んだとしてその人の自由で何かコメントを書いて来るか、黙って無視するか、という結果になる。無数の人がそんなページを持っている。偶然がお互いを知り合わせたり、意図的にグループを作って、その仲間内でのみ連絡をし合っても良いのだ。
ネットサーフィンでコメントをつけて回り、やがて話の水準の合うブログやサイトをみつけたり、やがて大きな政治経済の塾のようなものが形成されたりする。その中心には本物の学者が居たり、あるいは遺族のグリーフケアなどの集まりへ発展したりする。
現実の風子には縁遠い出来事であるとはいえ、社会への関わりのまねごとは出来る。まねごとではあれ、そんなものも風子には普通の人間として必要である。
剛はメールもしない。携帯は風子と繋がっているためだけに持っているのだ。剛はきょろきょろしない。興味は自分と生活費と家族、風子、それだけだ。社会や周囲の存在は批判の対象として、剛の日常を飾っていた。
健康や食事や、身体機能とくにリンパに関して自分の記録としてのブログを風子は作った。そこでは字体の色を変えて書くことにした。それはそれで内容が把握出来る面白さがあった。最初、ブログの壁紙、というかデザインを各々の提供媒体によって選ぶ楽しみもあった。そのブログでは、風子はちょっと太った中年のおばさんで、実像に近い。そしていつも体重を気にして、重力六十キロと書いた。時々いやらしいコメントがはいっている。あわてて削除する。また入って来る。何を思ってんだかと、ぶつくさ言う。
洋風の今風の室内を墨絵風にデザインしたアンパランスな軽さ、それが今風子が使っている意匠である。ちょうど作り始めたのが冬至のころだったのでそれをハンドルネームした。冬空、というタイトルにした。それらのアイデアの出現や色柄との出会いの楽しさは、それだけで十分喜びを与えてくれる。
使い勝手を試し、またさまざまな別人になることが出来るために別のサーバーへ行く。
そこでは、澄んだ青い色のシンプルな真面目な雰囲気を使った。そして純文学風な短い詩のようなものを書き並べた。長編を並べると結局は順番が逆になるので、余り読み勝手は良くない、電子図書が盛んになる気配だそうだが、読みやすいかどうか風子はまだ知らない。未知の領域だ。
大手のヤフーにも風子はブログを開いてみた。主に日常の憂鬱を嘆くという趣向である。風子はここでは自然や植物の項目にチェックを入れた。あらゆる人々があらゆることについて、あらゆる趣向で書きまくっている。一つの語句、たとえばガーデニングと検索させる。何万というブログが収集されるのだ。どうしたの、みんな、と、呟いてしまう。風子もその一員である。一秒間に百近い新着日記がやってくる。その秒以下の単位で記される一覧表はオリンピックの、たとえば百メートル競技の計測と違わない。
風子はそんな電子の世界を、あるいはガーデナーとして、あるいは新聞好きの男性として、あるいはなり損なった老年の自称小説家として、そこらの小太りの健康好きおばさんとして、あるいは大人気の科学者ブログのおっかけとして、ユーチューブで猫好きとして、カリブ音楽好きとして、走り回っているのだ。現実の世界では、百メートル四方、ないしは二キロメートル遠方くらいしか走り回っていない。
現実の道路を自分の足で歩くと、膝が少し壊れて来る。外反母趾が悪化する。非現実の世界をあまりに闊歩すると、脚は大丈夫だったが、眼がかすんでくる。そこが風子のいる社会の一面である。
しかしもうひとつの社会もある。そこもまた電子の世界である。
アメリカから、他の文明国から、テレビは人間の夢をドラマにして制作放映して来る。そんな放映の中からおのずと観賞する番組が決まって来るのだが、風子はできるだけ録画と言う手を使って貯めておく。そうすると剛がいるときに、ふたりそろって見ることが出来るものもやはりいくつかある。
風子の方が興味の範囲が広い。剛はしっかりしたサイエンスフィクションか、戦士ものが好きなのだが、風子があれこれ見るので、つい一緒に毎週見たりする。もっともそんな場合は、集中出来ずに風子に向かってあれこれの自分の意見を述べ立てる。剛の意見をいう声がおおいに邪魔なので、風子は時にはつい、いらいらして言う。
「意見はいつも聞いているからさあ。そんなに色々言いたいんなら、ブログとか新聞とかに投書したらどうでしょうかねえ。よっぽど世の中の役に立つんじゃない、私に言われてもねえ」
「そんなばかなことしねえよ」
と、剛は一蹴する。しかし、その後少し考えているようでもある。
外国の、架空の世界の中で、大勢の人々が協力し合って、これでもか、という力の入れ様で、面白く極端に空想とリアルを混ぜ合わせて、美しいのみならず魅力的な存在感のある俳優を、つぎつぎと見つけてきてはエンターテインメントを提供する。それを享受するのは風子のような受け身の大衆である。しかし制作に関わっている彼らも時代の大衆の一人なのだ。ただ、制作者たちの名前はそこに書かれて残っている。風子の名前は、墓にしか残らないだろう。風子はどんな毎日を送ったか、何を感じてどんな外見だったか、僅か五十年も時が立てば風のように消えてしまう。何か、たとえば紙の日記があったとしても意味を持たない。燃やされてしまう。有名な作家の日記なら別だが。
ネット上の趣味のグループには自由に参加出来る。同年代の見知らぬ人々が集うそんな集まりは、まるで夢の中のようでありながら、画面に現れる文字や写真を実際に書き送る人間が存在して、各自のリアルな生活を暮らしている。
日々の些細な感慨が日記として公開される。それに対するコメント、コメントに対するコメント、そこでは知力の限りを尽くした丁々発止のやりとりが、礼を尽くした言葉で執り行われる。謎の人物として自分のある部分だけを提示することを前提とする、抜きつ抜かれつの、
ほめ殺しで、相手と自分の能力が高まる。新しい自己認知の世界がある。
十一 ボランティアを希求する人
十年来のノートパソコンを使って、風子にして別な風子の存在を、そうしてあちこちで味わうことが出来るのは、せいぜい一時間半程であるが、毎日少しずつ、いくつかの自分へと自分を切り分けて、それぞれ異なる書き手と交信する。
パソコンをパタンと軽く閉じた。疲れた眼を揉みながら、風子はもう次のドアへと向かっていた。歯を磨く。歯間ブラシを使うのが長い習慣になっていた。五十才を過ぎた頃、敦が母親に率直に言った。
「母さん、口臭があるよ、年寄りの。何とかしてよ」
そうは言われてもどうしたらいいのかわからなかったのだが、ともかく買ってみたのが歯間ブラシだった。そのあと普通のブラシで眠る前に十分磨くようにした。舌も少しこすった。
それは正しい方法だったらしい。口臭のない中年として高笑いも出来るし、顔を寄せて話をすることも出来るようになった。しかし、そうして世の中で少し気をつけていると、口臭にも種類があるとわかった。中年からの口臭は口内の汚れによる。しかし風子が注目したのは若人の、男女を問わない口臭であった。
それは特別な単一の、同じ臭気である。苦みのある化学物質の匂いだ。それは心身へのストレスの証拠であった。新聞の雑多な記事の中に、その情報を読んだとき、風子はすぐにわかった。スーパーや生協や集金や、急ぎ足の学生や、高校生や敦自身にも、風子は感じ取った。その兆候は、最初男性に多かったのだが、次第に若い女性にも広がった。結婚前の、これから妊娠すべき若いメスがすでに疲れておどおどしていた。恋を願望する力も減じたことだろう。自分のことだけでぎりぎりなのだ。不安と絶望を抑制することだけで手一杯なのだ。
そんな若者を、あるいはもっと悲惨であるはずの虐待されている児童を助けることはできないのだろうか、風子は歯を磨きながら鏡の中へ問いかける。絶対何かをしなきゃいけないのだ。社会全体で。必要なら無償のこの手で。しかし、仕組みと資格の中で、風子は役立たずであるだろう。わかっていたらとっくに何かを始めている、と頷く。
実際には、何をしている訳でもなかった。最も簡単なのは、町内の公園や空き地に花を植える「ちょっとボランティア」的な活動だった。しかし、そこで満足してはいけないと風子は思う。それで何も始めることが出来なかった。
まずいのは勿論剛の意見であった。健康のために週に一時間半、仕事に毎日約四時間、周子の世話に毎日二時間、それが剛の許すことの出来る風子の自由時間である。そうしながらも剛の妻以外であってはならない。この縛りが風子から社会奉仕の精神を無いも同然にしていた。被害者への少しの寄付金ですら、本当に必要としているところへは届かず、内部の上層部がかすめとるのみだ、と剛は強く主張して止まない。それを突破出来るのかどうか、風子は試したことも無いのでわからない。出来ないと思うので試さないだ。
夜に町内を見回るために、たとえば犬の散歩とかも或は有効であるかもしれない。日常的に怒声や泣き声の聞こえる家があれば要注意なのだ。
以前は、風子の家の方も要注意であった。風子が我が身の心配から、警察に見回りを頼みに行ったこともあった。警察から帰ってみると剛が烈火の如く怒っていた。黙って自転車で姿を消したからだ。そのころはまだ携帯がなかった。
もっとも剛は、あざみと連絡が取れなくなっても我を忘れる程猛り狂った。妻の前で愛人と連絡がとれなくなったと激高した。風子は心底失望したし、信じられない人だと思った。自分が一つの形でしか存在しない、それをうまく周囲の思惑に適用させることを、むしろ恥だと思っていたのだろうか。恥という感覚も無かった、そう言えば。恥じる必要が無かった。自分が自分であることを天地にかけて恥じる必要はなかった。剛がそう言った訳ではない、それは風子の推測であり、確信であった。それを阻止すること、それに反駁すること、それはありえない。剛の人権蹂躙であるからだ。
風子はベッドを整える、剛が起きっぱなしにしていたのだ。
まっすぐ上を向いて、脚枕をする。両腕は丹田の上にくむ。安定剤が効いて来るのでやがて眠る。時には詩の本をすこし読んだり、小難しい本を眠るために読んだりする。
剛は朝方帰ってきて、ひょっとして風子のパソコンを覗くのではないかとふと思う。いくつもブログその他に書き込んでいるのを知ったら、何というだろう。風子が剛の結界から大々的に手を広げているのを知ったら。
その不安に打ち勝つのは難しい。ポジティブに考えることにする。それが明るみに出た時、剛は別れを決意するだろう。黙っていることも嘘の一種で、剛は嘘をつかれたり騙されたりするのが死ぬより嫌いだった。従って、もし剛が剛であれば、恐ろしい修羅場になるだろう。しかし、怒る怒られるという従属関係がそこに余りにも露呈することになると、それこそ終わりかもしれない。風子が切れるのだ。
ボランティアという希求から、風子が出入りしているサイトがあり、メディアを論じるブログや新聞社の提供する読者サイトもある。そこらへんで何らかの発言をしているというだけの行動から、より一歩踏み出す必要と覚悟を風子自身、持っているのかどうか、不明瞭だった。それを考える環境に無かったのだ。
十二 虚実不明の寄り添う愛を見いだす人
沼の底から悪魔の手によってひきあげられるような、理由の無い恐怖が、眠りに落ちようとする風子を再び鋭い白日の意識下に引き戻す。すべてもう手遅れだ、もう殺されるしか無い、と一瞬にして悟る。現実に目覚める。
ある時期、あざみとの関係が終わった頃、彼女がきっと自分に復讐しに来ると信じた。夜中に目覚め、ドアがきしる音がきこえないか、耳を澄ませた。復讐者に対抗する方法を考えた。縄で縛ることができたら一番だが、それに失敗して、包丁で切り掛かってこられたら、身を低くし脚払いをかける、それだけでは足りない、何か拳法を習わなくてはと焦った。その時はやはり剛をすでに自分の味方だとみなしていた。
しかし今ではあざみ関連の恐怖は忘れ去られている。
今風子が曝されているのは剛への恐怖であるが、しかし実は恐怖を抱く程のたいした理由は無い。自分の生活は剛への強大な反権力を含んでいないんじゃないか、とも思う。浮気は勿論、心に想う男も無く、あるのは少しの不誠実と不満。そして、恐怖である。
もっとも、一日の大半を風子はその感情とは無縁に生活している。恐怖は薄まっているのみなのか。恐怖の対象を人間として愛することが出来るのか。愛はどこへいけばいいのか。恨みはどうするのだ。自分の罪悪感はどうなっているのだ。ぼんやりと、なるがままに風子の生活は進んでいく。
ついに風子は眠ったらしい、何故なら夢を見たからだ。
剛が倒れた、と会社から電話が入った。きっとそんなことになると思ってたわ、と一瞬思った。それは剛のわがままな生き方を、日頃から風子が心中では非難していたことを表していた。自業自得、とも思った。剛の生活全体が不健康そのものなのに、依怙地にそれを守り通したんだから。
夢の次の場面では、道ばたに剛がうつぶせに倒れていた。誰もそばにいず、救急車もいなかった。茫々たる都市のコンクリートに囲まれて死んだ鳥の黒い影のように横たわっている。白い顔の片側が見えた。
それは昔愛着していたお気に入りの男の横顔である。剛のすべてを愛していた、いつもいつも、そして永遠に離れたくなかった、ずっと抱いたり抱かれたりしていることが真の望みだった。まだ良く知らないうちに、一瞬のうちに恋の虜になったのだ。そんな風子がいた。風子は衝撃のために大きくあえいでいた。どうしよう、どうしよう、とやたらにくり返した。
しかし、風子の姿は現れず、心だけの存在だった。剛は茫々たる世界の中で一人黒い点として横たわっている。
親も無く、妻も無く、友も無く、仲間も無く、唯一の血縁である敦はいつも父親を敬遠していた。剛の中で、彼の母親は剛を可愛がらない人物として固定されていた。父親とは縁が薄かった。唯一可愛がってくれた祖母に対しては、何らかの罪の意識を抱いていた。その最期の時を十分に見守ることが出来なかったという。そして、剛のただ一人この世で繋がるはずの風子は、剛にはじきとばされていた。もう冷たいのか、まだ息があるのがわからない剛の影に風子は近づいてもいなかった。
野生のヒョウか何かのような、孤独に生きるほか無く、孤独に死ぬ、それが風子の夫だ。
剛の恐ろしい程の孤独な姿が、虚ろな風子の中の心のようなものに届いて襲った。今さら、愛している、同情している、最期まで見捨てない、とか言っても何も変わらないその孤独を、理解した。哀れさに落涙した。
「なぜそこまで自分をひとりぼっちにする。なぜ私のそばに来なかったの。同情も哀れみもあなたは拒否するのね、きっと。もっと愛させてほしかったのに、いつも私と言うあり方を拒否したじゃない、どうして。あなたは私を愛してなんかいなかったし、そうだ、私もあなたと言う人間を受け入れられなかった。愛って幻、幻にすがりついてこの一生すごすのはもうたくさんでしょ。あなたもそれに目覚めてほしい。愛なんか幻、ありうるのは家族としてのグループ感情」
と、語りつつ、風子は目覚めていった。
ドアのカギが回って、剛が帰宅した。今日は早い。風子はふとんに一層もぐった。もし剛が今ここに入ってきたら、優しく抱きしめることができるだろうか。そんな気分ではある、と思った。仲間として、孤独を癒すものとして。
それを剛が受け入れるかどうか、風子にはわからない。剛はあくまでも風子を愛していて、風子からは愛されていない、というスタンスのままであろう。自分の次の反応が吉と出るか、ただの嘲笑と自己憐憫であるか、風子にはわからない。
「あなた、おかえりなさい」
と、風子は寝とぼけたような声をかけた。
了
-
バカな風は200円の有料書籍です。
書籍を購入することで全てのページを読めるようになります。
-
-
バカな風
0











