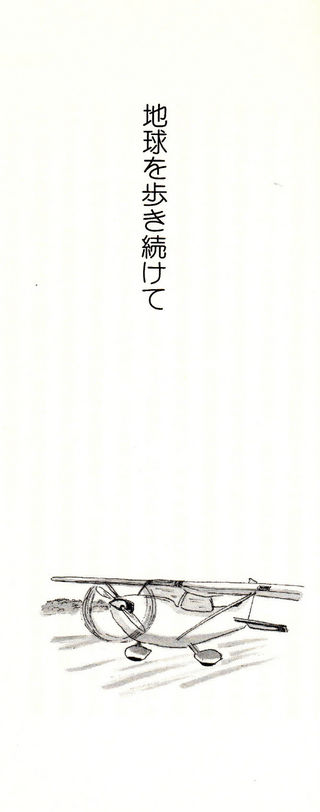父さんは、足の短いミラネーゼ
アメリカでの遭遇( 8 / 8 )
タホ湖
タホ湖
ミュリエル・ジェイムス博士のワークショップが開かれたのは、カルフォルニア州とネバダ州にまたがるタホ湖の夏だった。ミュリエルはその頃、毎年夏の間、このタホ湖でいくつかのワークショップを開いていた。一つのワークショップは基本的に週末を含んで一週間で構成されている。僕はそこで3週間過ごした。ミュリエルはTA(交流分析)の生みの親である、エリック・バーン博士の数少ない直弟子の一人で、世界的に知られた心理分析学者であり、TAの推進者だ。日本にも度々来て、講演やワークショップなどを開いている、明るい、人懐っこいおばあちゃん先生だ。
その夏のワークショップには、世界中から20人程が集まった。ミュリエルの指導を受けてTA(交流分析)をより深く体験するとか、今持っている問題から、精神的な健康を回復する目的とかで集まっていた。それは夕日に染まったタホ湖畔のバーベキュー・パーティ-で始まった。ミュリエルの最愛のご主人であるアーニィが準備してくれたバーベキューのためのいろんな食材と、火を作る道具達とビールが、私たちを浜で待っていた。そこに集まった人たちは人種はおろか、性、国籍、言葉、宗教、年齢、金持ちとか貧乏とか、職業、肌の色、などなどの属性のまったく違ういろんな人たちだった。僕の参加したワークショップには、アメリカ人、メキシコ人、スペイン人、ニュージーランド人、オーストラリア人、日本人、フランス人などが参加していて、本当に国際的なグループだった。夕日が落ちかかるタホの水辺が暗くなって、炎が明るさを増してその夜はふけていった。
ワークショップは、タホ湖の水辺にある林の中のコンドミニアムで行われた。すべの活動は、そんなコンドウでの疑似家族の縁組で始まる。ミュリエルがいろんなことを配慮して作る。全部で5家族が出来上がった。僕のところは5名の家族。日本からの肝っ玉母さん(有名な病院の女性の精神科医)、やんちゃな末っ子は若い日本人、分からず屋の長男はスペイン人、悩みの多いネブラスカのジュディ、そして僕。このグループで、最低1週間、24時間、4LDKのコンドウで、一緒に寝泊まりする、食事を作る、買い物に出掛ける、遊ぶ、話す。こんな環境だから必然的に仲良くなってしまうし、隠し切れずに裸の自分が出る。そしていつのまにか家庭に似た家族の役割ができてしまう。例えば僕はさしずめ親父役とか…
午前と午後の合わせて6時間は、ミュリエル指導のワークショップが一つのコンドウに全員が集まって開かれる。TAはグループ・ワークが基本。TAは自分自身を良く知る為に、自分のやった行動、発言を、他の人がどのように受けとったのかを、率直に、しかし、肯定的な表現でフィードバックしてもらう。人は自分の行動については、なかなか自分自身で正確に知ることはできないからだ。
集まった人達の中には、他人との関わりの中でうまく行動できなくて、悩んだり、自分を否定したり、逆に他人を否定して問題を起こしている人などがいる。一方、長い間セラピストとして他人を助けることに専念していて、逆に自分自身が疲れてしまったお医者さんもいた。もちろんTAを勉強するために集まった人もいる。ミュリエル研究者でTA研究者である早稲田のF教授も一緒だった。いろんなモーチベーションを持って集まった人たちだった。
基本的にTAは、人のパーソナリティイは3つの要素でできていると考える。1つは「親」からの要素。2つ目は「理性的な、理論的」要素。そして3つ目は、「子供」の要素だ。これらの三つの要素が時と条件によって変化して現れてくる。ストレスを受けたり、自己否定などを受けたりすると、歪んだ行動を現わす。そして対人関係を悪くする。
ミュリエルのスーパー・バイズのもとで、TAの理論の理解と、そのサンプルとして、参加者の具体的な行動を分析することで、自分自身を深く知ることができてくる。そうして、最終的に自分自身で自分の問題や行動を自律的に解決していく。僕の場合は、とにかく自立心が強くて、ほかの人に「頼らない、甘えない」が強く出てしまって、人との間に垣根を作ってしまう傾向があった。ミュリエルのグループ・ワークに参加して、他人にたいして率直になって、自分の弱みも含めて、自分をそのまま開示することができるようになった。また時には他人に甘えてもいいんだよ、との許しを得た。これで本当に、他人との間でリラックスした関係ができる。大変な発見だった。
フィールドでのワークもすばらしい体験だった。シェラネバダ山脈の山奥に入り込んで、自分の深いところに存在する、自分の気づかない感情や問題の存在を発見するワークだった。深い森の中に、皆が一人一人ばらばらになって散っていく。自分一人になって、他の人は妨げない。頭の中は何も考えないで、空白な心の状況を作り出す。他の人にはできるだけ会わないようにして、森の中で一人ぼっちになって、体と心を一時間以上空っぽにする。無意識の感覚にしておくのだ。風が林の中を通り過ぎていく。2000メーターを越す高い峰が、空を区切っている。小川を渡る。
自分の感覚が真っ白いキャンバスになるのを気長に待つ。そして十分に空っぽになったら、今度は急に自分の感覚を積極的に、意識的に外の世界に向ける。そして何が自分に飛び込んでくるのかを見定めるために、目を見開いて鋭敏になる。そんな感覚で歩いていると、あるものが僕の感覚に飛び込んでくる。「僕はここにいるよ!」って無言で叫んでいる。それこそが自分の心を大きく占めているものなのだ。それは大きな木の切り株で、森のちょっとした空き地の真中に存在していた。そして、それは僕が長い間、面倒をみていなかった飼い犬のアンナの姿だった。それは優しさだった。優しい気持ちを僕に起こさせてくれるのに十分だった。自分も十分に甘えられる優しい生き物だった。自分を開放して、弱さも、甘えもそのままにだせる自由な、そして自分をゆだねられる関係の象徴だった。純粋無垢なパートナーだった。「なんだ、僕は本当に優しいものを求めているのだ、飢えているのだ」と気がついた。
このフィールド・ワークの感想を僕とシェアし合った看護婦さんの場合、見つけたのは、日本のそれとは違って、とても巨大なアメリカの松ぼっくりだった。そして松ぼっくりを形作っている一つ一つの片の先をよく見てみると、そこには鋭い針が1本ずつ、生えていたのだ。彼女は看護婦としての自分の仕事をうまくやっていけなくなっていて、自信を失って、このワークショップに参加していた。なんとか自分の持っている問題の本質を見つけようとしていたのだ。彼女が発見したのは、自分の心の中に存在している他に対する「厳しさ、思いやり不足」の状態の自分を発見したのだ。ナースになった時、最初に持っていた優しさが何時の間にか荒んでいってしまって、患者さんに対して優しさを失ってしまっていた自分に気がついたのだ。女としてはイカツイ感じの彼女の厳しい感じの目に、その時涙が浮かんでいるのを見た。その日以後、ちょっと優しい顔を見せるようになっていた。
フィールド・ワークのなかで一番印象的だったのはプーリングだった。「人を信頼することができない人は、他人を当てしないから、他人の助けを決して受け入れられない」という、体験学習だった。プーリングはネバダ砂漠の中、カールトンシティの温泉プールで行われた。このワークは、基本的は人々が昔々母の子宮の羊水の中で、すべてから守られて、たゆたっていた幸せな感覚を追体験して、自分を完全に開放することができることを確認するのが目的だった。2人1組で、自分は上向きでプールにとにかく何もしないで浮く。もう一人が支えたり安心させたりして、浮いてもらう努力をする。2人の間に信頼感があって、力を抜いて任せきりになれれば、自然と浮く。しかし心理的に信頼感の持てない相手だと、体のどこかに力が入って、バランスを崩して沈んでしまう。僕の相手のスペイン人は何回やっても沈んでしまった。僕はイグナチオに「僕を信頼してくれないのは淋しいな」と言った。彼は無心になった、その瞬間、彼は静かにプールに一人で浮かんでいた。感激だった。それから2人はもっと仲良くなった。そして自由に振る舞えた。
自分に対しての自然体、本来的な自分を開示することができれば、自分も自由だし対人関係も円滑。そしてお互いに、率直でポジティブなフィードバックができれば、より良い友人になれる。このワークショップでそんな体験をすることができた。この体験は、その後の僕の生活にとって非常に根本的な影響を与える本物だった。その後の、僕の生活の仕方ががらりと変わったのだ。
地球を歩き続けて( 2 / 4 )
ブラッセル近郊、ラ・フルプ
ブラッセル近郊、ラ・フルプ
べルギーの首都ブラッセルの南、ラ・フルプという小さな村に、I社のヨーロッパ教育センターがある。古戦場のワーテルローの近く、森に囲まれた広いサイトだ。
周りにはないも無い。田園と森がどこまでも続くベルギーの田舎だ。
ここにお客様を対象としたマネジメント教育や、コンピューター技術者教育が行われる施設がある。何日も滞在していただくわけだから、ホテル顔負けの宿泊施設、レストラン、バー、体を動かすジムやプール、広い森の中の夜も使える散歩道やジョギングの小道、バレーやバスケットコートなどもそろっている。
もう一つすばらしい施設がある。それは二24時間オープンの図書館だ。もちろんコンピューターも使い放題。このサイトはお客様用の教育施設ではあるが、同時にI社の技術専門教育にも使われる。一番長いのは3ヵ月にわたるSEグループの合宿教育課程だろう。だから24時間勉強できて、しかもグループで検討会が開ける場所が必要なのだ。
幸せにも、僕は3回ほどここで専門教育を受けた事がある。僕の一番長い滞在はは3週間のコースだった。ここはブラッセル市内まで、車で30分弱の場所で、シャトルバスがブラッセルとの間にサービスされている。だからクラスが終わってから、夕方ブラッセル市内まで出かけることができる。最終バスはブラッセル中央駅の側から11時半発だから、けっこう夜のブラッセルも楽しむのは簡単だ。
グラン・プラスを中心とする旧市街は、とても居心地のいい場所だ。正面に向かって右側の建物、端っこの店はお気に入りの気持良いところ。軽く食事もできるが、ビールやアペリティ-フを飲みながら街を眺めていると、いつのまにかどんどん時間がたっていく。4月に行ったときなんかは、暖炉に火が燃えていてとても気持がいい。もちろん天気のいい日には、テラスに出て広場を眺めながらの時間となる。
ブラッセルと言えば、レースやチョコレートなんかが有名だ。しかし、ベルギーはあまり知られていないようだけれど、実は新鮮な海産物の豊かな国でもある。ちょっとグラン・プラスを離れて歩くと、そこには新鮮な魚介類のレストランがいっぱい並んでいる。牡蠣だとか、ちょっと下茹でした蟹、海老なんかも氷を敷いた大皿に乗って出てくる。しかも決して高くはない。店お勧めのバターベースのソースとか、マヨネーズソースもいいのだけれど、やはり僕にとってはレモンと塩が最高だ。冷たい白ワインと相性がよく、けっこうな量を食べている。夕方には各店が思い思いのデコレーションで客を招く。きれいで目移りする。
その道を有名な小便小僧の立つ路地の方へ歩いて行くと、すぐにムール貝で有名な店が現れる。ここでは大げさではなく、本当に洗面器ぐらいの大きさの鍋にいっぱい、ムール貝がワイン蒸になって香り高い大蒜ベースのソースに浸かって出てくる。そうなると、キリキリに冷えた白ワインの出番となる。一人で食べ切れるかなと心配する暇もなく、どんどん入っていって、いつのまにか鍋は空っぽになっている。付け合せの焼いた硬いパンも素晴らしい脇役だ。
ブラッセルにはたくさん、昔からのショッピングモールがある。全て屋根に囲まれた3、4階建ての空間が現れる。喧騒はなく、人々がゆっくりウインドウを眺めて、品定めしたり、買い物をしたり、ゆっくりとした時間がある。
2週間以上の滞在になると、なんとか宿題を早く片をつけて、週末によく出かけたものだ。ラ・フルプで知り合った若い友達たちと、ゲントやブルージュの町を訪ねたりした。でも彼らと濃い時間を過ごしたのは研修センターの中だった。一緒に飯を食ったり、課題で議論したり、はたまた一緒にビールを飲んだりだ。
ラ・フルプのレストランに隣接したバーでは、ウイスキーとかスピリッツのような強いお酒は置いていないが、ビールとかワインとかはサービスしていた。ここで僕の最大の発見はベルギー・ビールとの出会いだった。フランスにしても、イタリア、スペインにしても、これらラテンの国のビールは、ドイツやイギリスのビールと飲み比べてみると、どこか薄く、甘く、軽く感じて、僕はけっして手を出そうとはしなかった。
ところが、イギリスからきた友達に奨められて発見したのが「シーメイ」と言うベルギー・ビールだった。濃い色で、しかも香りが高い濃厚なビールだった。しかもそれを注ぐグラスは独特の形をしていて「シーメイ」の名前が入ったものだった。ビールは酸化や香りが飛ぶのを嫌って、縦長のずん胴のグラスで出されるのが普通だ。しかしこのグラスは、大きなシャンパングラスのような、口が大きく広がった美しい形をしたビアグラスだった。赤みを帯びた濃いビール色の液体を注ぐと、白い泡が広い口に厚く作られて、ビールを守ってくれる。ベルベットのような滑らかな濃い液体をするりするりと流し込む。素晴らしかった。
驚いたことにこのビールを造っているのは、修道院の尼さんたちだということだ。僕のビールについての概念を変えるものだった。こうして夜の更けるまで「シーメイ」の魅力に惹かれていた、僕と友達たちが記憶に立ち返ってくる。
地球を歩き続けて( 3 / 4 )
仕事のオーストラリア
仕事のオーストラリア
メルボルンの飛行場
メルボルン空港は大手航空会社の大型ジェット機の発着もあるが、もっと身近な空港でもある。僕たちはこの空港を何回も利用したが、それは小さな飛行機をタクシーとして使ったのだ。
オーストラリアでは小型飛行機がいろんな形で使われている。200キロも離れているところには車で行っていられない。そこで貸しきりの小型プロペラ飛行機とかヘリコプターが皆の足としてチャーターされる。僕たちは、あるカスタマーのいろんなサイトを訪れるため、この小型飛行機のお世話になった。そんな中で愉快なことがいろいろあった。
ある時は300キロも離れた地方都市のお客のところに行くのに、ちょっと大きめの飛行機を使った。僕たち客は7、8人一緒だったかと思う。双発の、ちょっと大きめの、定員10名ぐらいの飛行機だからクルーは2人いた。メルボルンの曇り空を飛び立って内陸に向かう。3000メーターぐらいに昇ると風が強い。めんどうみの良い、コーディネーターをしているMが、皆を良い座席に座らせて、自分は一番後に乗り込んで、飛行機の扉のすぐ後ろの狭い席に着いていた。彼の座っている前にある扉のまわりから風が入ってくる。みるとコックピットの上のランプが赤かく点滅していた。
クルーの一人が後ろの方にやって来て、扉をバタンと強く引っ張っている。何回か繰り返しているが、しかし赤ランプは消えない。飛行機の扉は完全には閉っていないようだ。それで風がひゅうひゅう入ってきていたわけだ。メカニックは肩をすくめて、しょうがないなといった感じでロープを取り出して、扉のハンドルを近くの柱に縛り付けてコックピットに帰っていった。それからがMの大変な時間となった。フライトは2時間弱だったと思うけれど、Mはその間ずっとそのハンドルを、両手でしっかり引っ張り続けていた。そんな彼を見て、みんなは噴出したい気持ちと、もう一方では気の毒にとの気持ちが襲ってきて、口数が少なくなった。
Mは次のフライトからは、めんどうみのいい顔をかなぐり捨てて、お偉方たちをも先置いて早めに乗りこんで、扉から離れた良い席を占めていた。それが皆の笑いを誘っていたのを鮮明に思い出す。
キャンベラからの定期便
時刻表に乗っているけど、本当は飛ばないこともある定期便がある。オーストラリアの首都キャンベラは、メルボルンとシドニーの中間をわざわざ選んで造った、全くの人工の都市だ。このキャンベラから、さらに内陸に100キロほど入った田舎町まで行くには、単発の小型プロペラ機に頼るしかない。
これがその定期便なのだが、予定どおりには飛ばない。お客がいる場合のみのフライトになる。行きは良いとしても、目的地からのフライトは機材がなくなるんだけど、どうするんだろうなんて思ったけど、聞くのを忘れてしまった。
僕たち2人はとにかく予約を入れた。その飛行機は定員4人で僕たち2人が乗り込んでちょっと待っていると、子牛ほどもあるお尻のでかい、若い女の子が飛行機の狭い入り口をすり抜けて乗りこんできた。僕たち2人は後ろの一列にならんで座って、固唾を呑んで見ていた。どうやって座るのかなと心配しながら。その若い子は、前の2つの並んだ席を一つのでかいお尻で占拠して座り込んだ。僕たちは心配そうに顔を見合わせた。「この飛行機はちゃんと飛ぶのかな」と訝りながら。
パイロットは、これも結構太めのつるっぱげのおじさんで、飛行機の透明なキャノピーは、そのおやじのつるっぱげのすぐ上にあるから、紫外線がしょっちゅう、おやじの頭を刺激しているのを立証しているような感じだった。
僕たちの手荷物を客室のすぐ後ろの荷物入れに放り込んで、飛行機はエンジンを全開にして、一つしかないプロペラをきりきりと回して滑走路の方へタクシーを始めた。滑走路に近づいてエンジンはさらに高回転だ。その時、ジープが何やら叫びながら飛行機と平行して突進してきた。パイロットはスピードを落として、ジープの男の言っている事を聞いていたが、飛行機がとまった。パイロットは扉を開けて降りていった。実は荷物室の扉がちゃんと閉っていなかったのだ。ポンと掘り込んだ僕たちの荷物は、飛行機が走るたびにボンボンと飛び跳ねていたのだ。幸いグランドの担当者が見つけてくれたから良かったものの、あのまま飛び立っていたらとしたら、僕たちの荷物はどうなっていたのだろうと冷や汗だった。
再度、単発機は思い切りエンジンを吹かして、やっと三人分ぐらいある若い女の子を持ち上げて飛び立った。フライト中はちゃんと飛行機が飛んでくれることを祈りながら手を握り締めていた。山脈を越えるとき、やはり飛行機はかなり揺れた。荷物室の扉が閉っていてよかったと実感した。とにかく僕たちは目的地に無事到着した。のんびりしたオーストラリアの田舎の思い出だ。
国旗たちの複雑なはためき
僕たちが訪れたクライアント企業は、もともとはオーストラリア軍の直系企業だった。だがその頃、親方日の丸ではないが、企業体質は古く、民間企業からの軍への納入や新しいオッファーでその内部調達率は急激に低下していっていた。企業の存在意義が急速になくなっていたのだ。しかし、古き良き時代の雰囲気はそのまま、人達の間に温存されていた。
そのサイトにビジターがあると、入り口正面の国旗の掲揚柱にビジターの国旗を掲げるのが礼儀になっている。僕たちのグループは、アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、そして日本人で構成されていた。したがって歓迎の国旗はこんな国の旗がはためくことになる。僕は国旗を立てて迎えられるなんてことは期待もしていなかったし、経験もなかった。だから日の丸が掲げられているのを見たときは、ちょっとびっくりした。チョットは誇らしいい気持ちもあったけれど、同時に第二次世界大戦の尾をひいて、対日感情が必ずしも本当のところでは良くない、保守的な雰囲気の強い軍関係のサイト。日の丸を掲げた当直将校の気持ちが複雑なものとして透けてみえた気がした。
イギリスの影響が強く残っているこんなサイトでは、午後は立派なティータイムがある。ポットに入った紅茶、クリーム、そしてビスケットか軽いケーキがでてくる。なかなか、打ち解けた雰囲気にはならないで、アメリカ人が中心になって、クライアントとの関係を作って会議を行っていた。そんな中、日本のコンサルタントが黙って、ボーと突っ立っていて良い訳がない。僕は自分の下手な英語を最初に謝って、自分たちが体験した、自分の会社の改革について話し始めた。「技術革新が進んで、従来の工程、プロセスが不要になって来て急速に仕事が減ってきたこと」、「1400人の会社に700人分の仕事しかなかったこと」、「自分たちで、自分たちの仕事を新たに作り出すしか他になく、旧来の延長線上では何も未来が生まれない状態だったこと」、「新しいことを始めるには、そこにいる全員の危機感と、変革についての強い意志が必要だったこと」、「幸い技術は立派に持っていたこと」、「全く新しいことをやっていく、リスクをどんどん試していったこと」などを少しずつ話していった。
実体験に裏打ちされた話だったのが良かったのか、いつかそこにいる人たちの注意が暖かいものに変わっていた。彼ら、誇り高いオーストラリア人の心のどこかにあったかもしれない「肌の黄色い日本人に教えを乞うことなんか何もないよ」というような雰囲気ががらりと変わっていった。そのサイトの訪問は、とても印象に残るものになった。クライアントとの複雑さは、次第に解消していった。
-
-
父さんは、足の短いミラネーゼ
5