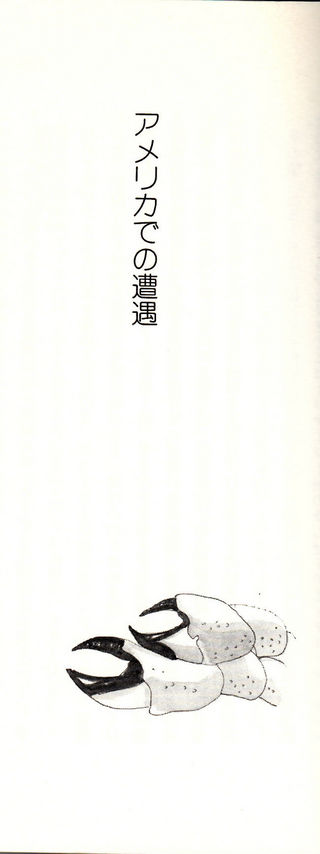父さんは、足の短いミラネーゼ
フランスの風と香りを吸って( 2 / 4 )
南フランス・モンペリエの思い出
南フランス・モンペリエの思い出
モンペリエ
南フランスのモンペリエという街をご存知だろうか。地中海に面したマルセイユよりもっと西、スペイン寄りの古い街。フランスでも最も古い大学の一つがある小さな街。地中海からちょっと入った平野にある街。海まで車で10分も走ればパラバスという海岸に出る。モンペリエにはロ-マ時代の水道橋もある。まるで昔のままの城壁に囲まれたヨ-ロッパによくあるまちだ。
こんな町で、若い日に3か月を過ごした。もちろん仕事で。仲間は男ばかり僕を入れて同じ位の年頃5人。時は2月から5月初めの春の来る頃。ちょうど僕はイタリアからかえってきて、1年にもならず「ヨ-ロッパに帰りたい!帰りたい!」との気持ちで一杯の頃だった。
街はちっちゃいけれどなんでも揃っていて、オペラ劇場、1つ星レストラン、パリのブティックにも負けない店と町並み。街の中心はラ・コメディで真ん中にオペラ座、そしてカフェが回りを取り巻いている。天気のいい早春にそこに座ってぼんやりしていると、そのまんま時間が過ぎていくのが気持ちいい。街の中心の通りを登っていくとその先にはローマ時代の大きな水道橋がそびえている城跡に至る。そんな通りの中程に石畳の広場があって朝市が立つ。街の中は細い通りばかりで、車が通れるような道はわずかしかない。薄暗い細い道を歩いていると、いつのまにかこの広場に出てくる。朝市には花や野菜や肉なんかがテント小屋に賑やかに並ぶ。街中に生活のすべてがある。
僕の頭で苦労した床屋さんもこの広場にあった。なぜかと言うと、僕の髪は日本人にしても硬くて大変なのに、フランスの床屋さんは柔らかい細い髪になれていて、それにラゾー・カットをやるのだ。僕の髪はとても硬くて、ラゾーカットにはまったく適していない。とうとうその床屋さんは刃を駄目にした。僕は上客ではなかったに違いない。困った顔を今も思い出す。
モンペリエから車で10分も走ると、地中海に面したパラバスという海岸にでる。観光客用のレストランや、土産物屋が並んでいて、早い春には閑散とした雰囲気だ。このパラバスには、僕たちがモンペリエの下町に見つけた数少ない、いわゆる「バ-」で働いている女の子が住んでいた。このバーに飲みにいっての深夜、僕の猛スピ-ドの酔っ払い運転でよくこの女の子をパラバスの家まで皆で送って行った。もちろんむちゃな話だ。この店を見つけたのは、こんな方面ではとても鼻の利くMだった。そのバーは狭い石畳の路地に、壁に小さな赤いランプがついていて、ちょっと薄気味悪い、ひっそりとしたモンペリエの下町の一角にあった。日本のバーのような雰囲気があってくつろげて、金がない割に僕たちはよくたむろしたものだ。その女の子にちょっと気があったのは僕だった、もちろんそれだけだったが。
モンペリエではSとMと僕の3人が、ほとんどいつも組んで行動していて、ほかの2人は一人一人で動くのが常だった。この3人のうち車の運転ができるのはMと僕だったので、3人で一台の車に乗ってよく出かけたものだ。
僕たちがいたのは小さなホテルで、カフェも食堂もない、単なるシャワ-付きの部屋があるだけのこれまた古い物だった。僕たちは長く滞在したので、いつの間にか朝のフレンチ・ト-ストとコ-ヒ-だけは、特別にロビ-で出してくれるようになった。
仕事には毎朝2台の車に分乗して、町の東にある会社まで出かけた。毎日、朝日が真正面から差し込んできて、運転しにくかったのを覚えている。そういえば、帰りも今度は西日がまたまた運転する僕の目に差し込んで、行きも帰りも太陽がかなり高くなるまで悩まされたのを覚えている。ホテルでも英語が話せる人はいなくて、僕たちはほんの片言のフランス語で会話していた。Sが大学時代にフランス語を選択していて助かった。
モンペリエの町では、金があればほんとに立派なレストランを楽しむこともできた。よく行ったのはトロア・ロアという町の真ん中あるレストランだった。ここには大きな石の炉があって、目の前で肉でも魚でもお好みに合わせてグリルしてくれる。イタリアでもそうだったが、夕食はやっぱり2時間ぐらいかかっていた。4人で行ったときは、3本ぐらいのワインを開けていた。そのころのMは酒がほとんど飲めなく,Nもちょっと飲むと真っ赤になる人だったので、Sと僕が、完全に割り勘勝ちだった。Mはいつもエビアンかジュ-スで飯を食べていた。この店では頼めばピツッアも、その炉で焼いてくれた。でも圧巻はペッパ-・ステ-キだった。熱い肉の中はほんとうにやわらかく、ちょっと見には、まるで黒胡椒の塊のようなステ-キはほんとうに旨かった。
毎日こんな所で飯は食えないから、ラ・コメディの近くのイタリアンレストランにも足を運んだ。ここでは僕のイタリア語が役に立って、店の家族とも仲良しになってしまった。その後何年も経って、モンペリエにいったとき大歓迎をうけたのを覚えている。ここではイタリア料理が安く食べられた。我々のお気に入りの店の一つになった。もっと金のないときなんかは、アルジェリア料理を安く食わせる店にも、勇気を奮って出かけたりしたものだ。米の料理とか、トウモロコシの粉で作った米に似た小さなパスタなんかを、クスクスというソ-スでからめた、スペインのパエリアのような皿を好んで食べたのを思い出す。そんな時はフランスの甘っぽいビ-ルが付きものだ。グランドの近くのセルフ・セルビ-スは最後の砦だ。学生なんかもよく来る、安いが取り柄の店で、結構お世話になったものだ。ヴェトナム料理にチャレンジしたこともあった。
そんな食事の後では、下町のバ-でコニャックかパスティスをやったものだ。パスティスというのはその昔、フランス人が好んで飲んだ、青臭いきちがい酒、アブサンを現代化した代物で水で割って飲む。水を入れると白濁する。僕はやっぱりコニャックのほうがよかった。
そんなバ-の近くには屋台がでて牡蛎を食わせてくれた。これが嘘のように安くて、レモンと塩だけで食べる。パリの牡蛎屋でのバロンも旨いけれど、目の前の地中海で取れたユイトッルもほんとうに美味かった。しかもいくらでも食べられた。幸せだった。とにかく外国に住んでいると、食べ物が非常に大切な生活の張り合いになってくる。
ラングドッグ
Sが車の運転を練習したいというので、僕とM、Sとでよく近くの町まででかけた。セーテ。ここはパリ-ダーカル・ラリーがフランス本土でも行われていたときには、ラリー車がここからみんな地中海を渡り、アフリカに舞台が移ったのだった。そのほか、グラン・モット、ル・グロ・デ・ロア、エグモルト、セントマリ-・デゥラメ-ルなどロワ-ル河口辺りをよく走ったものだ。この辺、カマルグには野生の馬が群れを作って暮らしている。どちらかというと湿地帯で、広い草原に灌木が生えている。なかでもエグモルトはほんとうに昔の城が、そのまんま町として残っていて、時間を過去にスリップしたような変な感じになったものだ。もともとは海に面した城塞都市だったのだが、ローヌ川が土砂で海を遠くに運んでしまって、今は陸の真ん中になってしまった。街の中はちゃんとした町並みが無人で続いていて、ちょっと変な感じだ。
もちろん近くのアルルとかニ-ムなんかには皆と観光で行ったものだ。フランスに闘牛があるのをご存じだろうか。南フランスにはスペインの影響が強くあって、本場の闘牛をやっているには驚いた。ちゃんと牛を最後に殺してしまう。僕たちは何回かニ-ムに闘牛を見にいったのを覚えている。小さいけれどちゃんとした闘牛場があって、試合の前には牛をちゃんと見ることもできる。白い乾いた砂地の闘牛場は楕円形をしていた。
僕たちが行ったとき面白いことが起こった。闘牛士が出てくるまで、牛を怒らせるためにいろんなことをやる。その中のひとつに、馬に乗った人が、槍で牛の背中を傷つけるのがあった。馬はしっかりよろいを着て、腹のあたりも防御している。馬の上の男たちが牛に槍をつきたてて血を流す。牛は痛がって荒れ狂う。ついには牛が怒って、馬の腹を角でついて馬を横倒しにしてしまった。馬も上に乗っていた人も大慌てだ。しかし牛は怒って攻撃の手を緩めない。慌てた闘牛士の助手たちが、牛の気を自分たちのほうに向けて、やっと馬と乗っていた人を救った。観衆から大拍手だ。それは牛に対して、そして馬に対してだ。その後、闘牛が現れた。しかし、その後も思わぬことがいくつか起こった。闘牛士は何人も出てくるのだが、うまい奴とそうでないのがいる。へたくそなのが一人いて、ちゃんと牛を扱えない。ついには牛に引っ掛けられて宙高く舞った。観客から悲鳴が上った。もちろん大変なことにはならずにすんだ。
闘牛士は本当に格好いい。パトロン、パトローネがついていて、試合が終わると牛の耳を切り取ってそのパトロンに投げて贈る。それが礼儀なのだ。ワインとバケットを手に、人々は一日を興奮して過ごすことができる。一日に何頭もの牛が死んで行って一日のトロが終わる。明るいニームの楽しい一日だった。残念ながら、スペインの闘牛は見たことがないけれど、フランス人の友人に聞くと、フランスのほうが小規模ですぐ近くで見ることができて、興奮するといっていた。本当かどうかは僕には分からない。
ミヨウ
モンペリエでは結構小さなドライブに出かけた。マルセイユにブーヤベースを食べに行ったり、グラースまで香水工場の見学に行ったり、それを日帰りでやっちゃうので結構疲れる。一人ですごく楽しんだのはゴルジュ・デゥ・タルン「タルンの喉」という谷をドライブした時だ。フランス中央高地の中の谷で、アメリカのグランドキャニオンを小さくしたような谷だ。48号線を北西に上って行って山に入る。谷への入り口がミヨウという町だ。ここからフロッラクまでの80キロ位の谷が続く。古い小さな館がレストランになっていたり、手彫りのサボや、いろんな木工品を売っている小さな店と出合ったりして、風景と村がそのまま中世フランスのようだ。ちょっとした高地が、羊たちの群れを見せていて、田舎だけれどちゃんと人が住んでいる。谷川の水量は豊かで、しかも急流だ。岩にぶつかって白い波をかんでいる。流れの辺には、必ず柳が生えていて岸を守っている。こういう時、その感動を分かち合う人がいないのは、ちょっとさびしいなとも思う。
ワイン付きの昼飯をとりながら、自分の心の記録にこの風景と雰囲気を閉じ込める。急流と高い頂にさえぎられた狭い空を仰ぎ見ながら谷をさかのぼる。やがてフラロックに至る。後で知ったのだが、このあたりはロックフォール・チーズの産地だった。ここからは川と分かれて厳しい山道だ。舗装はされているのだが、細い曲がりくねった道が急な登り坂になる。モンテ・エグアルへの登りだ。エンジンがうなる。タイヤもきしむ。沢の水が道をぬらしている。九十九折の細道を上り詰めると、フランス中央高地の高台が見通せる。
疲れを取るために休憩。道の際に落ちてきている沢の水で顔を洗う。冷たくて気持ち良い。顔をぬぐってふと気が付くと、僕の眼鏡がない。顔を洗う時に、ちょっと近くの草の上においたのに。ぞっとした。こんな険しい山道を、近眼の僕が眼鏡もなくて降りて行くなんて。あせった。よく周りが見えないのだが、とにかくそのあたりの叢を探る。でも見つからない。あせりの汗が噴き出してきた。小さな沢を探って、流れにそって小さな滝壷に届く。慎重に慎重に底をさぐる。そこから下は、さらにはるか下まで沢が落ち込んでいる。とうとうと水は流れつづけている。軽い眼鏡はさらに流れて行ってしまうかもしれないのだ。どのくらい時間が経ったのか分からないが、水のよどみに硬いものを探り当てた。あった。本当にほっとした。こんな危険がすぐそばに存在するなんて、という心境だった。眼鏡をかけて周りを見た。ほんとにもうちょっとのところで、下の下まで落ちる急な流れになっていた。心を落ち着けるために深呼吸をした。沢の水を手ですくって飲んだ。うまかった。3桁の道路標識を離れてやっとふもとの2桁の道に出た。モンペリエまでは一気の下りだった。楽しさと怖さを味わったドライブだった。
バルセロナ
もう時効だから話してもいいと思う。復活祭の休みに、みんなでスペインのバルセロナまで出かけたことを書こう。
じつは日本から来た女の子がモンペリエの大学に通っていた。その女の子は、Mを好きになってしまって、Mも独身だったから、テニスを教えたりして、結構楽しんでいた。ちょっと太目のその子は、美人とはいえないが、かわいらしい女の子だった。M、S、Hと僕に、その女の子が一緒に2台の車で出かけた。南フランスの海岸を地中海にそってどんどん西に走っていった。ナルボンヌ、ペルピニアンを抜けていよいよスペイン。町並みも少しずつ、あくの強いスペイン風に、なってきて重くなってきた。
バルセロナは港町、コロンブスの記念の塔が港にある。港から一直線のカタルーニア広場までの大きな通りが、ランブラス大通りで、通りの中央に幅広い歩道がある。そこを人たちが夕暮れになるとゆっくり歩く。車はその歩道の両側を流れている。おおきな街路樹があってとってもくつろげる通りだ。バルセロナではイタリアと同じで、夕方、人々が家族とか仲間とか恋人とかでゆっくり町を散歩するのだ。知り合いに合うとお互いに声をかけて挨拶を交わしている。けっこうみんな着飾った感じだ。
バルセロナで感激したのは日本の屋台みたいな店、バルだ。ちょっと簡単に、酒の肴になるものを目の前で作ってくれる。えびや小魚を炭火で焼いてくれたり、小さな烏賊をオリーブオイルでちょっとソテーしてくれたり、それをレモンと塩で食べるとほっとする。いかの墨煮に似た真っ黒いのが出た時は本当にびっくりした。うまかった。もちろん本当の夜の食事はレストランでするのだが、開くのは夜の9時過ぎだから、それまでのちょっと小腹がすいた時に、こんな店でアペリティーフを飲みながら人々は過ごすのだ。そんなことでもバルセロナが好きになってしまった。
バルセロナの夜をどう過ごすかが問題だった。その女の子はもちろんMと一緒にその夜を過ごすつもりだった。しかしその頃はどちらかというと、Mはもうその女の子のことをちょっともてあましていたみたいで、割を食ったのは僕だった。食事に出かけるのは9時過ぎということで、その夜はナイトクラブでも行ってみようということになった。待ち合わせはホテルのロビーと決まって、おのおの自分の部屋に引き上げた。時間になって、ロビーで僕とHとその女の子とがいくら待っても、MもSも降りてこない。部屋に電話したけど誰も出ない。3人は待ちぼうけというわけだ。Hは、ちょっと僕は出かけてくる、といって一人で出かけてしまった。残った二人はどうしようもない。その子は、僕にとっては、Mの彼女以外の何者でもなくて、まったく個人的な興味はなかった。待っても、待ってもMは現れず、その子は泣き出しそうになって、僕が何とかしてあげるしかなくなってしまった。
結局仕方なく、その夜は彼女を僕が面倒を見ることになって、ナイトクラブに2人で出かけた。彼女のご機嫌はまあまあとゆうところで、深夜4時ごろの帰宅となった。僕にとっても、バルセロナのこの夜はとてもつまらない思い出になってしまった。あとでMに詰問すると、その夜、SとMは前からの希望で、自分たちだけでバルセロナの女性と仲良くなりに行ったということだった。何だって僕が彼女のめんどうを見なくちゃあならないんだと、怒りがこみ上げてきた。あとでMは僕に謝った。これでMにおおきな貸しができたのは言うまでもない。
バルセロナの思いではいっぱいだ。サクラダ・ファミリアのガウディもピカソも皮細工も、復活祭の仮面行列もピンチオの丘のチュウリップも、みんなみんないい思い出となった。4日間もいたのだろうか。郊外にも出かけた。罪滅ぼしだったのかもしれないが、Mと僕とで一日モンセラットという郊外の聖地に出かけた。カソリックの修道院のある古い山の聖地だ。高い岩山をうがった教会があって、ヨーロッパ中から信徒が巡礼してくる。高い岩山にロープウエイがかかっていて、はるかバルセロナまで見渡せる高さだ。
フラメンコを見るにはかなりの覚悟がいる。始まるのは夜の10時過ぎだし、終わるのは朝4時ぐらいだ。ちゃんと腹ごしらえをして、徹夜のつもりで観にいかなければならない。すさまじいエネルギー、リズム、音、汗と集団の乱舞。観客もすごいエネルギーがいる。タバコと汗のにおいの中にいる時間から開放されて出てくると、夜明けの近い冷たい空気が心地よい。まったく異質の時間の中にいた自分を実感する。ちょっと経験できない余韻が、体のなかに続く。もう帰って一杯飲んで、朝寝をするしかないって感覚だ。でも驚いたことに、スペイン人達はその朝10時ぐらいからは働き出すっていうのだ。すごいとおもった。僕にはエネルギーが足りない。
バルセロナから帰って、仕事は期限に近くなってきつくなった。もう皆遊んではいられなくなった。しゃかりきで働いた。バルセロナに一緒に行った女の子と、Mがもめてるってことを聞いたけど、僕はどうしようもなかった。
日本に帰ってきて、しばらくしてMは別の女性と結婚した。小太りのモンペリエの女の子とは違って、筋肉質のスポーツ好きの背の高い女性だった。
フランスの風と香りを吸って( 3 / 4 )
パリ、初めての
コンシェルジェ
あこがれのパリの日々はフォーブル・サントノレから始まった。初めての僕のパリ滞在にあったって、フランスのI社はホテルを、こともあろうにフォーブル・サントノレのど真ん中、エリゼー宮のはす向かいのクラシックなホテルにとってくれた。
もともとフランス本社はこの近くのパレス・ヴァンンドームにあったのだから、彼らからすればフォーブル・サントノレにホテルをとっても不思議ではない。しかし、初めての旅人からすれば、アメリカ風な近代的なホテルしか想像していなかったから、とてもフランス、フランスした世界に偶然入り込んでしまったことになる。
四つ星のこのホテルのエレベーターは古く、ガラスと鉄柵に囲まれた優雅な乗り物だ。クラシックなロビーの真ん中から静静と上っていく。建物全体が、どこか、かすかに古き時代の匂いを送ってくる。部屋は通りに面した古い色調で、バスタブはなくてシャワーだけだった。古い、古い匂いが染み付いているようだ。もちろん臭いわけではなくて、空気そのものがオーデコロンのような、遠い時の匂いがする。
ホテルを一歩外に出ると、そこはもう有名な店の並ぶフォーブル・サントノレそのものだ。ついたときはもう夕暮れだったから、店のショウウインドは灯が入って、きらきらと、とても優雅だ。ステンドグラスのような、光の屈折がとても店を美しく見せている。コンシェルジェと言う存在を知ったのもこのホテルだった。なんでも相談役で、コンシェルジェが紹介してくれたガイドと会うことになる。こちらの希望を聞いて、それに見合った良い店を一緒に付き合ってくれる。僕のフランス語は大学の第三外国語で1年やっただけだから、まったく駄目。そういう中での、このサービスは本当に助かった。
何が食べたいかといって、まずはうまいワインと牡蠣と言うことになる。重い夕食は、いつでもどこでも取れるから、旅人にはちょっとというところ行ってみることになる。白ワインがとてもよくて、牡蠣はいろんな種類が出てきて、どんどん食べられる。生臭さはまったくない。トッピングもいろいろ試してみる。何の脈絡も無く、パリにきたらエスカルゴを、ということになって、その店に連れて行ってもらう。ガーリックトーストとの相性が抜群。やっぱり、ちりちりに冷えた白ワインと言うことになる。あこがれのパリの夜は、ハッピィな夜になった。コンシェルジェのおかげだ。
モンマルトル
パリはメトロでどこにでも気軽に行ける。モンマルトルは親父の心のふるさと。ピガールで降りて、ゆっくりゆっくり丘を登っていくと、いっぱい、いっぱい懐かしい風景が現れてくる。もちろん物理的には初めてでも、どこかで見たユトリロだったり、ロートレックだったり、佐伯や荻須の世界であったりする。デ・ジャヴというのが本当にいっぱい現れてくるのだ。
パリの建物は古くて、味がいっぱい染み込んでいる、という感じがする。坂道に広がる狭い小道を行くと、日本の焼鳥屋みたいな、串焼きを食べさせてくれる屋台みたいな店に出っくわす。串に刺した肉をワインで食べて、さらに歩く。パン屋さんから、長いフランスパンを小脇に抱えた、中年の男性が出てきたり、おじいさんが人力で木の荷車を引っ張っていたり、いたるところに生活が匂う。店の前の清掃もダイナミックだ。水道の蛇口を盛大にあけて、歩道側の側溝に水をザーッと流すと、どんどんごみが坂を水といっしょに下っていって、最後にマンホールの口のなかに吸い込まれておしまいだ。
モンマルトルの丘の上から見ると、建物の屋根の煙突たちがとてもいい。いろんな形の、いろんな色の煙突たちが、一軒一軒のアパルトマンを代表しているかのようだ。モルタルの四角い煙突のてっぺんは、たいていオレンジ色の土管のようなパイプ状になっている。煤けて時間を感じさせてくれるものや、ちょっと割れて中の煤が真っ黒に見えたりする。そればかりをカメラで狙って見る。望遠で見ると、ずっと、ずっと、そんな煙突たちが果てしなくパリの町全体に広がっている。街に高低差がこれほどないと、ちょっと気がつかない風景だ。そんな発見が、うんと得をした気分にしてくれる。
オランジュリーからマルモッタン
パリには、その後何回か滞在することになったが、たくさんあるパリの思い出の中で、やはり一番呆然と立ち尽くしたのは、オランジュリーで始めてモネの大作にとり囲まれたれた時だった。普通の展示室から階段を下りて、一階のちょっと薄暗い部屋に入ったときだった。僕は言葉も感覚も失って立ちすくんでいた。動けなかった。すごかった。少々薄暗い、オーバルな部屋に、モネの睡蓮の連作が置かれていた。
僕がやっと気がついて、中央においてあるイスに座り込んでしまったのはどのくらい経ってからだったろうか。とにかく長い長い時間がそこで流れた。MOMAで初めてモネを見たときも、やはりそうだったけれど、瞬間、どこか異次元の世界に自分が取り込まれた感じになる。この2部屋が、もう僕にとってパリでの一番の場所になっていた。
ブーロニュの森に近くにマルモッタンを訪ねる。メトロをミュエットで降りて、ラヌラグの庭を横切って歩いていると、僕の大好きな犬、黒いシュナウツァーが颯爽と散歩している。ぼくはフランス語を話せないけれど、身振り手振りで飼主の女性の許可をえてカメラを取り出し、シャッターを切った。僕の家にいるのはミニチュアだけれど、やはり感じは同じだ。子供たちにいい土産ができた。その後、日本に帰って下のちびがスタンダード・シュナウツァーを飼いたいと言って困ったことになったのを思いだす。印象派がスタートする由縁の「日の出」をみてモネ三昧は終わった。
パリでは色んな美術館を見たが、僕にとってはモネと、ポンピドウ・センターのシャガールに尽きる。
ラ・デファンス
僕の仕事でのパリはラ・デファンスだ。最初に行ったときにはI社のヨーロッパ本部は確か、タワー・ノベルにあったと記憶しているが、その後はデファンスに自分の社屋、タワー・パスカルを建てて移ったので、ほとんどがタワー・パスカルの思い出だ。
パリに高層ビルができ始めたのはモンパルナスが最初だと思うが、本格的に高層ビル群が作られ始めたのは、パリの旧市街を離れ、セーヌを渡ったすぐのラ・デファンスだ。初めてセーヌを越えてタワー・ノベルの高みからパリを見たとき、「わー」と歓声を上げたのを覚えている。旧市内には基本的に高層ビルはなく、大体4,5階までの建物に統一されて作られているから、タワーから見るとモンマルトルの丘までずっと見通せた。足元がセーヌ川まで鋭角に抉り取られているような錯覚に陥って、立ちすくんだ。
オペラから高速電車ですぐだが、ラ・デファンスはパリとは思えない。でも新宿の高層ビル群と違って、職住混在。人の住む沢山のアパートメントが、ビシネスタワーとうまく調和して建てられていて、単なる無機質な町になるのを防いでくれている。またタワーを含めた建物たちが、まるでデザイン・コンクールでもやっているかのように各々が個性的だ。それでいて全体の雰囲気を壊している物はないのがうらやましい。
I社の連中もやはりフランス仕込みで、食べものには目がない。自分のビルには勿論立派なカフェテリアがあるのだが、「タワー・パスカルより、フランスI社の入っているタワー・フランクリンのカフェテリアの方が味がいい」と言って、昼休みにタワーの間の連絡通路をぞろぞろ、ぞろぞろかなりの社員が賑やかに移動する。もちろん僕も皆についていった。IDカードを見せれば自由にフランスI社に入ることができた。しかし、突然うまい昼飯をもとめての社員の大移動はできなくなった。僕のいた間に、会社は「フランスI社とヨーロッパI社は別会社。各々のカフェテリアへの補助金の支出も別々。だから、ヨーロッパI社の社員はタワー・フランクリンのカフェテリアを使用しないように」との通達が出た。その後、社員の間で当分ブツブツと不満の言葉が続いたのを覚えている。僕達は残念ながら、タワー・パスカルで食事するしかなくなった。
ラ・デファンスでの思い出のなかには、ちょっと苦い思い出がある。ラ・デファンスのヨーロッパI社ではしょっちゅう、各国の人が集まって会議が行われる。その際もちろん公用語は英語だ。
会議で本当に悔しい思いを何回もした。例えば、20人位のいろいろな国の人たちが集まっての会議だとする。アメリカ人、イギリス人の英語はまあ何とか分かる。イタリア人、スペイン人、ドイツ人の英語は一度、頭のなかでちょっと考えと分ったりする。だが、僕がいくら頑張ってもフランス語圏の人の英語はもういけない。特にフランス語のイントネーション、アクセントで英語を話されるともういけない。
僕の耳はアイウエオを聞くようにできていて、アルファベットをそのまま聞き取れるようには残念ながらできていない。習い覚えた通りの発音とイントネーションで、英語が話されると何とかなるのだが、フランス訛りの発音、イントネーション、アクセントで話されると、それは僕の英語プロセッサーの能力を超えているのだ。会議で何回も聞き返して、理解しようとするのだが、僕一人のために、会議は待っていてはくれない。会議はドンドン先にいってしまうことがある。特にフランス人が議長だったりするともうお手上げ、最悪だ。残念、困った、悔しいと何度思ったことか。
アルファベットを聞いて育った人たち、アルファベットを聞く耳をもった人たち、すなわち僕以外の全ての出席者は皆、フランス人の英語を完全に理解しているのだ。後になって少し慣れてくると、フランス訛の英語も耳に入ってくるようになったけれど、短期決戦の会議ではとても太刀打ちできない。「・・・アグレマンってなんだっけ? アグリ-メントなんだ」なんて考えているうちに会議は進む。その後、友達と話して分ったことだけれど、アルファベットをベースとする言語を話す人たちは100パーセント、その子音の発音を聞き取っているのだ。それは例えば、いくら強いインド訛で話されても、子音の多い北欧の国々の人たちの特有の発音も例外ではない。
後になって本で読んで分ったのだが、日本人以外の人は、子音のプロセスと母音のプロセスを、脳のなかで分離して行っているようだ。すなわち、子音は右脳、母音は左脳だそうだ。一方、日本人は、言語が身に着く3歳から4、5歳頃までに、子音を右脳でプロセスするように訓練されないと、子音も本来母音プロセッサーである左脳によって、母音と一緒くたに処理されてしまうとのことだ。この幼児期の時機を逃がすと、その後いくら努力、訓練しても左脳の呪縛からは解き放たれない。結果として大部分の日本人は子音のプロセスが基本的に苦手なのだ。
原因は日本語。日本語では、子音が単独で存在することはほとんどなく、必ずと言っていいくらい、後ろに母音がくっついてくる。それで子音は右脳でプロセスされることなく、全て左脳にまとめて処理させていることになっているようだ。この現象は、日本語を話す日本人だけに、確認されている事象のようだ。バイリンガルと言われる人たちは3、4歳まで外国で暮らして、子音のプロセスが母音と無関係に聞き取れるらしい。僕のようにカタカナで英語を始めた人間にとってはまったくまったく、うらやましい限りだ。
でも、ラ・デファンスで、誰にも分らない英語をしゃべる人達いたのを述べておこう。それはれっきとした英国国民、スコットランド人の一部だった。彼らの発音は、同じイングランドの人たちにも分らないそうだ。とても妙な話ではある。
フランスの風と香りを吸って( 4 / 4 )
モスクワ・シェレメチボ空港
モスクワ・シェレメチボ空港
ヨーロッパへ飛ぶのに、昔はとてつもない遠回りをしていた。一番昔はアラスカ経由だった。しかもアンカレッジはまだ良いほうで、ひどい時はフェアバンクスなんて、アメリカ軍の北極基地があるような、氷の真ん中に飛んでから、パリとかロンドンに飛んだものだ。売店以外なんにも無いターミナルで1、2時間も待たされて、とにかく無駄だった。その後、やっとモスクワ経由で飛べるようになった。そのおかげでモスクワのシェレメチボなんて飛行場に何回か降りるはめになった。
ある時、大発見をした。滑走路の全体が、着陸する前にどういう加減か非常に良く見えた。びっくりした。一本の滑走路が、平らではないのだ。波打っていて、水平が出てはいないのだ。ちょうど雪が積もっていて、それで白い地面が起伏が起伏でグラデーションになっていて、はっきりその起伏が見えた。一本の滑走路が途中で二回も三回も、緩やかだけれど、丘になったり、下りになったりしているのだ。本当に驚いた。そこに、僕達の飛行機は、降りて行くのだ。着陸して、逆噴射をして、確かに停止するまで、機体がふわふわするのを感じてしまった。ロシア、その頃はまだソヴィエト連邦だったけど、やっぱり大まかなのかなと思った。
シェレメチボでは色んな物を買った。マトリョーシュカ、バラライカ、アルメニアのコニャックだとか、キャビアだったりした。そんな売店とか食堂で見たのは、ロシヤ・スタイルの算盤だった。二段になっているのは日本の算盤と同じだが、五の位が五つ玉になっているのだ。どうやって繰り上がるのよく分からなかったけれど、とにかく太ったお婆さんがぱちぱちとそれで外国為替の計算して、それで金を払ったものだ。交換レートは、お婆さんにお任せで、信じるしかほかない。
よほどの事が無ければソヴィエトの飛行機には乗るな、という会社の指示があったが、やむをえず、何回か使ったことがある。ヨーロッパに向かう時に何時間も、シェレメチボ空港で待たされた事がある。きちっとした理由説明があるわけでもなく、狭く暗いターミナルで代替の飛行機が来るまで待たされた。まったくサービス精神は見られなかった。スチュワーデスは太ったおばさん。にこりともしない。飛行中は乗客と同じ座席に座って眠り込む。ワゴンがしまってあるギャレットの留め金がちゃんとかかっていなくて、ちょっとした振動で扉が開いて中のプレートやなんかが飛びだしてきても、我、関せずだ。これもびっくりだ。通路に食器なんかが転がっていてもそのまま次のサービスを始めるまで置いておかれる。日本の飛行機に乗ったら、その違いに大感激だった。もちろんチョットやり過ぎのところもあると思うけど。
いつだったか、オランダの大学生たちと、東京行に乗り合わせたことがある。彼らは団体旅行で、半ばそのセクションは貸し切りになっていて、賑やかだった。酒が入っていて、たまたま近くに座っていた僕にもグラスを差し出してくれた。もちろん彼らの持ち込みのボトルで、強い酒だった。それはぼくが始めって知った「ジュニーブラ」と彼らの発音していたオランダ・ジンだった。ちょっと独特の匂いがするが、いい酒だった。またジュニーブラの入っていた、素焼きの、ちょっと茶っぽい、背の高いストレートなボトルがとても良くて、まだ半分以上も残っているボトルを、彼らから譲ってもらって、持って帰ったものだ。その後、僕の好きなジンの定番になった。
窓の下にはうねうねとシベリアの原野が川のうねりを見せているだけだから、他にすることもない。6時間以上も彼らと飲み続けた。全く修学旅行のノリだった。びっくりしたことが起こったのは、飛行機が日本海に出るとあっと言う間に本州の山々を飛び越えて、太平洋に出た時だった。飛行機が銚子沖の九十九里浜の上空を旋回し着陸のために高度を下げて、片方の翼を上げて機体を傾け、回転し始めた時だ。突然ざーっと、水が天井から窓をつたって、頭の上に降ってきた。右へ傾けば右側に、左へ傾けば今度は左側の窓を水が滴った。
あれは真夏だったのだ。軍用飛行機を改造したような代物だから、機体の気密性が弱くて、空気中の水分が、冷たい機体にふれて水滴に化けて天井一面に付いてしまっていたのだ。それが機体のバランスが崩れるたびに水の滝となって落ち込んで来たのだ。何しろ湿度の高い東京だから。悲鳴があがった。皆びっくりした。なかなか体験できない、希有な思い出だ。
それ以後は、再びソヴィエトの飛行機に乗る気はなくなった。
-
-
父さんは、足の短いミラネーゼ
5