Wuthering Heights
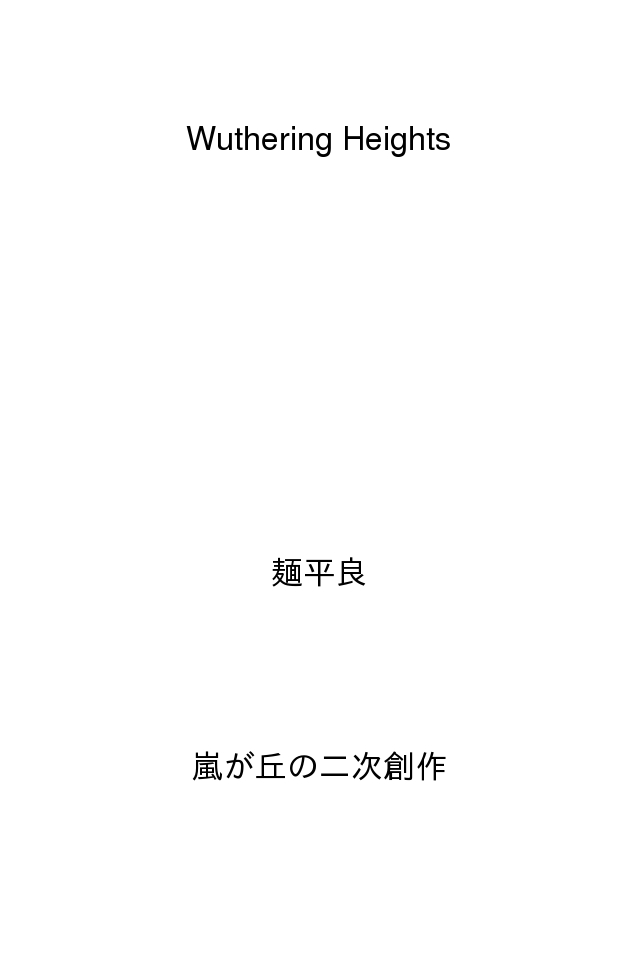
丘の上にぽつんと建つ、一軒の屋敷がありました。そこでは一組の夫婦、その間に産まれた兄妹二人がわずかな使用人達と共に暮らしています。
ある時、父親が仕事で一週間程屋敷を空ける事があったのですが、その日の夜、吹雪の中ようやく帰宅したのです。
帰宅した時、父親は一人ではなく一人の男の子を連れていました。歳は娘のキャサリンと同じ6歳くらい、浅黒い肌に黒い縮れ毛、決して醜いわけではないのに、何とも嫌な感じを、使用人や息子達は受けました。
おまけに父親が買ってきた、息子や娘達へのお土産が、帰宅途中に壊れてしまっていたものですから、息子のヒンドリーはますます気を悪くし、自分への土産物が壊れたのだって、急に現れたこの男の子のせいに違いないと考え、ますます彼への憎悪を強めました。
何か都合の悪い事が起こった時、人は証拠や根拠そっちのけで、自分の嫌いな人間のせいにしてしまうものです。
父親が言うには、帰宅途中に拾った、ジプシーらしき集団の捨て子らしいとの事で、うちで養子として育てるつもりのようです。
その男の子は、ヒースクリフと名付けられ、父親はヒンドリー以上に彼を可愛がりました。ヒンドリーは、ますます面白くありません。母親も同様で、ヒンドリーがヒースクリフに負ける所の無いよう、発破をかけるようになりました。
しかしヒンドリーは、座学の成績についても運動にしても、大変優秀で、ヒースクリフより勝っているのですが、それでも父親のヒースクリフへの偏愛は変わりません。
母親の苛立ちは募るばかりです。ひょっとして、あのヒースクリフは主人の隠し子なのではないかしら?などという疑念も浮かぶようになり、ヒンドリーに因縁をつける事で、その怒りや苛立ちをぶつけるようになりました。
父親からは愛されず、母親からは理不尽にも鬱憤をぶつけられ、ヒンドリーは徐々に鬱屈し、ヒースクリフこそが元凶であるとして、彼をますます憎悪するようになりました。
父親の他に、もう一人、娘のキャサリンがヒースクリフに好意を抱きました。ヒースクリフとキャサリンは大変仲が良く、兄弟のようにというよりも、まるで二人で一人と言っても良い程で、二人はいつも屋敷の外にある荒野で座っていたり、走り回っていたりするのです。
ある時、転機が訪れました。ヒンドリーがすっかり成長し、一人前に仕事もするようになった頃、父親が急に倒れて床についたのです。
その頃、同様にヒースクリフもまた、父親から仕事を教えられ、父親はヒースクリフに跡を継がせようと考えていた様子でしたが、ヒンドリーはヒースクリフを下男の地位に変えてしまいます。その上、何かと理由を付けては虐待したりと罰を与えるようになりました。
日々、理不尽な仕打ちに遭い、肉体的にも精神的にも踏みにじられ続けるヒースクリフでしたが、それでも屋敷に居続けたのは、キャサリンへの執着のためでした。
キャサリンは今でも変わらず、ヒースクリフと共に荒野で過ごす事が多く、荒野が、そして互いが互いにとって唯一の居場所でした。
自分の半身のようでもある、キャサリンが無事である事が、今のヒースクリフにとっては唯一の救いなのです。
しかしそれでも、ヒンドリーへの憎悪が無いわけではありません。ある夜、遅い夕食を台所でとったヒースクリフは、たまたまそこに居た使用人のネリに尋ねられます。
「あんた、よく我慢するね。私だったら屋敷から逃げ出してるよ。」
「そりゃ、お父様を置いて出て行くわけにはいかないさ。それに、キャサリンも居るし…」
「へえ、優しいじゃないの。見直したわよ。なるほど、ヒンドリー様だって旦那様の息子であり、キャサリン様のお兄さんですものね。」
ヒースクリフは黙って座ったまま、手を組み、じっと炉端を暗い目で見つめながらこう言いました。
「ヒンドリーへの復讐は必ず果たす。奴より先に、俺が死ぬことの無いよう願うばかりだ。」
「まあ!何て事を言うの!復讐は神様のなさる事よ?」
ヒースクリフは何も答えず、変わらず炉端を見つめています。その目には感情が無く、憎悪さえも見えませんでした。
一方のキャサリンは、ヒースクリフの現状に胸を痛めていました。そして、父親が遠くの療養所へ送られた頃、ある決意をします。
ある夜、ネリが土間で縫物をしている所に、キャサリンは報告があると言って、現れました。
「エドガーとの結婚を決めたの。」
エドガーとは、少し離れた場所に住む資産家で、ヒンドリーの薦める縁談相手です。縁談は随分前から在り、あとはキャサリンの判断一つで決まる所でした。
「それは、おめでとうございます。」
ネリは微かに微笑みながら、受け流すようにそう答えた。
「何か言いたそうね。」
「そんな事はありません…ヒースクリフもきっと、これを機にこの屋敷への未練を絶つ事ができるでしょう。この屋敷にはもう、旦那様もおられませんし…ヒースクリフはようやく自由になれます。皮肉ではありませんよ、こうあるべきなのです。ヒースクリフもここを出て、より良い人生を生きるべきなのですよ。」
「ヒースクリフがここを出る?一体どこへ行くと言うの?あなたの言い方だと、まるでどこか知らない遠くへでも行くかのようだわ!とんでもない、私達は二人で一人なのよ?離れては生きられない!」
ネリは訳が分からず、困惑した表情になりました。
「ヒースクリフはお兄様から、今酷い目に遭わされている。だから私がエドガーと、お兄様の薦める相手と…周囲の誰もが賛同する相手と結婚して、そして世界と調和するの。
そうすれば、私達二人は生きられるわ。
ヒースクリフは世界と不調和なのよ。このままでは、私達二人とも野垂れ死にしてしまう…」
そう言い、キャサリンが俯いて顔を両手で覆っていると、台所の扉が開閉する音が聞こえました。
嫌な予感のしたキャサリンは、急いでその方向へ向かうと、ドアの外、遙か遠くにヒースクリフの走り去る姿が見えたのです。
キャサリンは急いで後を追いましたが、彼の姿はあっという間に見えなくなり、彼女は絶望してその場に座り込んで泣き叫びます。
ネリはキャサリンに寄り添い、諭しました。
「これで良かったのです。エドガー様と一緒になるためには、彼らと仲良く過ごすためには、ヒースクリフは邪魔な存在、在ってはならない存在なのですから…いえ、ヒースクリフは最初から存在すべきではなかったのです。」
奇しくも、その時同時に、父親の訃報が届きました。ヒースクリフはもちろん、誰も見舞いに行く事を許されず、またヒンドリーも一度も見舞った事がありませんでした。
送られた療養所は、資産家の主人が滞在するとは思えぬような環境で、父親はそこで孤独に息をひきとったそうです。彼は最後まで、ヒースクリフを心配していたのですが、とうとう再会する事は叶いませんでした。
ヒンドリーは母親に対しても冷淡でした。まるで彼女が見えないか、存在しないかのように振る舞っており、ある日彼女は転んで骨折したので、夫と同じ療養所へ送られ、間もなく訃報が届きました。
そんなヒンドリーの鬱屈した心に、フランシスという女性との結婚で日が差し始めました。
ヒンドリーは、フランシスと親戚による縁談で結婚したのですが、このフランシスによる癒しと慰めにより、心の平安を得る事ができたのです。
フランシスは優しく、そして浅はかでした。そしてヒンドリーを含めた周囲の人々は、そんな彼女の性質を敬していました。
浅はかであるという性質は、決して悪い事ではない。むしろ好ましい性質であると、ヒンドリーは皮肉ではなく本気でそう信じていたのです。なぜなら、世の中深く考えた所でどうにもならない事ばかりであり、深く考えれば考える程に悪い思考へ向かう事がしばしばだからです。
そんな訳ですから、ヒンドリーにとってフランシスは聖母と言っても良いような存在であり、そのフランシスが突然、原因不明の死を迎えた時の落ち込み様は酷いものでした。仕事にも手を付けず、食事もほとんどとらず、魂が抜けたようにただ、ぐったりと座っているばかり。
近くに住む、妹夫婦達は打つ手も無く、ただただ心配しておりました。
その妹、キャサリンは、エドガーの元に嫁ぎ、すっかり上手く馴染んでいるように見えます。エドガーはもちろん、夫の妹であるイザベルとも、揉め事を起こさず仲良く過ごしていました。
しかし、キャサリンに付いて来ているネリには、キャサリンが非常に苦しそうに見えます。それも、日に日にその苦しみは限界に近付いているようにも見えるのでした。
ある日、ネリとキャサリン二人きりの時、キャサリンが放心したように窓の外をぼんやりと眺めているのを見たネリは、思い切って声をかけてみました。
「キャサリン様、大丈夫ですか?非常にお疲れのように見えますよ?あまり無理をしないでくださいね。」
「…無理をしなければ、とても保てないわ。ねえ、ネリ、私はここに来てからずっと、演技をし続けているの。でも演技をするのは疲れるし、それに私は名女優じゃないから、その演技が正しいのかどうか、演技を間違えてしまったらどうしようとか、いつも不安で怯えて、悩んで…まるで、体に合わない型でも着て、型を着なくても構わない人達と一緒にランニングでもしている気分よ。皆は何も着ず、自然体だから楽々走っていけるけど、私はそうじゃない。それでも平気なフリして、実は無理をして皆と同じ速さで走っている。
でも、もうそろそろ限界…私は倒れそう…」
そう言って、頭を抱えるキャサリンに、ネリはどう声をかければ良いのか分かりませんでした。
その時、玄関のベルが鳴り、誰かが尋ねて来た事が分かったネリが玄関へ向かうと、尋ねて来たのはなんと、ヒースクリフだったのです。
キャサリンの喜び様は、まるで長い間失くしたままであった宝物を見つけたかのようで、彼女はヒースクリフを自宅に上げて、夫のエドガー達にも引き合わせたのですが、エドガー達はヒースクリフにあまり良い感じを受ける事ができませんでした。
ヒースクリフは小奇麗な身なりをしており、礼儀正しい、決して横柄ではない態度をとっていたのですが、身分や素性、今まで何をして財を成したか等が曖昧であり、エドガー達は彼を胡散臭いと感じたのです。
しかもヒースクリフは、しばらくヒンドリーの屋敷に滞在する事になったと言うのですが、ヒンドリーは現在、普通の状態ではありません。そしてヒースクリフはヒンドリーを憎んでいるはず。それらの事を考えると、ヒースクリフが何か良からぬ事を考えているように思えて仕方ないのです。
しかしエドガーは、バランスのとれた男でしたから、表向きヒースクリフに当たり障りなく接して送り出し、とくに何も手を出すような事はしませんでした。
ヒースクリフは、精神がすっかり弱ったヒンドリーを賭博やアルコール、薬漬けにし、屋敷や資産を担保にして、ヒンドリーの全てを奪ってしまいました。
やがてヒンドリーは衰弱し、ヒースクリフへの呪詛を呟きながらこの世を去ったのです。
ヒンドリーにはフランシスとの間に、ヘアトンという男の子を授かっていたのですが、ヒースクリフはヘアトンを、まともに教育も受けさせずに下男として働かせるようになりました。
このような状況を、心配して見に来たネリが目にして、エドガーやキャサリン達に知らせたので、エドガー達のヒースクリフへの印象はますます悪化しました。
しかしキャサリンだけは、ヒースクリフを擁護します。
「確かにヒースクリフのした事は間違っていると思います。けれど、あの人はその昔、長い間お兄様から理不尽に虐待されていたのです。だからと言って、彼のしている事が許されるわけではないとも思うけれど、彼の身に立ってみれば気持ちが分からないでもないでしょう?彼自身の何もかもを否定するのはやめてください。」
しかしエドガーもイザベラも、キャサリンのその訴えには答えず、相変わらず苦虫を噛み潰したような顔をしてヒースクリフの方を見やりました。
「ヒースクリフさん、あなたをキャサリンが、そしてキャサリンをあなたが必要としている事は知っている。しかし今のあなたのままでは、キャサリンの傍に居る事を許すわけにはいかない。
なぜなら、キャサリンは我々の世界の人間なのです。キャサリンと再び共に在りたいと願うのなら、あなたも我々の世界の人間にならねばならない。
まず、このイザベラを妻としなさい。そう、キャサリンの代わりに。」
イザベラもエドガーと同じ考えであったようで、兄と同じく厳しい表情を変えずに、ヒースクリフを見つめています。
キャサリンは驚愕したような顔になりましたが、すぐに全てを悟ったような、もしくは諦めたような脱力した悲しそうな顔で、目を伏せました。
ヒースクリフも、一瞬驚愕しましたが、すぐに余裕のある表情を浮かべ、その申し出を受けたのです。こうしてヒースクリフは、イザベラと結婚し、あの元はヒンドリーの物であったが今はヒースクリフの物である屋敷へ連れて行ったのでした。
しかしその結婚生活は、とても幸せとは言えないものでした。イザベラはヒースクリフを、兄エドガーのような人物に変えようと手を尽くし、ヒースクリフはそ
れを知っていたけれども、激しく抵抗したのです。
先に根をあげたのは、ヒースクリフでした。彼は自分の放つ言葉が、イザベラに全く理解されず、それ故に彼にとってトンチンカンな受け答えをイザベラから受ける事が延々と繰り返される日常に疲れてしまったのです。
一方のイザベラは、全く平気でした。彼女は本来、あまり物事を深く考えない性格であり、嫌な事もすぐに忘れ得る人間だったので、夫のヒースクリフと理解し合えない事についても悩む事が無く、そもそも理解し合う事自体について考えもしなかったのです。
やがてイザベラは、男の子を出産。リントンと名付けられました。
しかしヒースクリフはついにイザベラを愛する事は無く、彼女との関係に疲れ切り、段々彼女を憎み、疎んじるようにさえなったのですが、イザベラは気にもしていなかったので、ヒースクリフにこっそり毒を盛られた等と気づく事もありませんでした。
こうしてイザベラは、原因不明の突然死を迎えたのです。
一方のキャサリンは、イザベラがリントンを出産する2年程前から身籠り、そして寝込んでいました。
ほとんど何も食べず、一日中ベッドの上で虚ろな目をして横たわっており、何か話しかけても、まともな返事がありません。
周囲は妊娠のために具合が悪くなっているのだろうと、楽観的に考えていましたが、原因は他にあるような気が、ネリにはしていたのです。
ある日、ネリがいつものように食事を持って、キャサリンの部屋に入ると、やはりキャサリンは虚ろな目をして横たわっていました。
ネリが窓を開けて空気の入れ換えをしてから立ち去ろうとすると、急に珍しくキャサリンが声をかけてきたのです。
「夢を見たの。」
ネリはびっくりして、キャサリンを見やり、傍にあった椅子に座ると、彼女の話を聞く姿勢をとりました。
「夢の中で、私は死んでいて、天国に居たのだけれど・・・」
「まあ、キャサリン様!そんな縁起でもない・・・」
「でも私、天国に居る事が全然嬉しくなくって・・・こんな所に居たくないって、駄々をこねていたら、神様がお怒りになられてね、天から荒野に、そう、あの荒野に落とされて・・・それで、私は荒野に来たの。
それで嬉しくて、本当に来たかった場所へ来る事ができたと思って喜んでいた・・・そんな夢だった。」
ネリは訳が分からず困惑していました。と、後ろの方で物音がしたので振り返ると、いつの間にかそこにはヒースクリフが忍び込んで来ていたで、ネリは思わず大声を上げそうになりました。
しかし、その時キャサリンの虚ろな目に光が差し、ヒースクリフと話をしたがっている事を悟ったような気がしたネリは、この侵入をとりあえず黙認する事にして、部屋の外に出て、扉の前に立っていることにしました。
キャサリンは、すっかり力を失った目に涙を浮かべて言いました。
「なぜあなたがヒースクリフなのかしら…あなたがエドガーか、もしくはそのような人物だったなら、こんな苦しむような事にはならなかったのに。
イザベルと、結局上手くいかなかったのでしょう?なぜ上手く適応してくれなかったのよ?!それだから、私はますます弱る一方なのよ。」
「そんな…なぜ、俺がイザベルと共に在る事ができなかったか、キャサリンになら分かるはずだ。」
ヒースクリフが困惑したように答えます。
「ええ、そうだったわ。私とエドガーだって、同じだったもの…エドガーはそう思っていないかもしれないけれど。
私はもう駄目。こうなった今、ヒースクリフ、あなたがあなたでい続けてくれる事しか、私は願わないわ。そしていづれ、来てちょうだい、待っているから…」
「キャサリン?!」
「先に、荒野で待ってる。」
キャサリンはその後、無事女の子を出産。数日後、衰弱死しました。
キャサリンを失った事を、彼女の家族は悲しみ、ヒースクリフもまた悲しむと同時に悩み苦しむ事となりました。
キャサリンを殺したのは一体誰なのか?キャサリンがあの時言ったように、自分の存在がキャサリンを追い詰めたのかと考え、しかしそれを認め、受け入れるには、彼はあまりにも弱すぎたため、そこから目を逸らすために、エドガー達へ矛先を向ける事にしたのです。
エドガー達が、キャサリンを殺したのだという事にしたヒースクリフは、エドガーへの復讐を決意しました。
母親と同じ名を与えられた、その娘キャサリンは、姿は母親に似ていましたが、性格や気質は父親譲りで明るく健やかに成長しました。
活発な彼女は、よく馬に乗って原っぱを走り回るので、父親のエドガーは、ヒースクリフの住むあの屋敷には絶対に近寄らぬようにと注意し、彼女の守り役であるネリにも気を付けてやってほしいと度々言っていたので、ネリも気を付けて彼女を見ていました。
しかし人間、してはいけないと戒められれば、余計に興味を掻き立てられるものです。それも、誰が何をしているのか、何の情報も与えられていないお屋敷ですから、気にならないわけがありません。
キャサリンは何度も、こっそりその屋敷へ伺おうとしましたが、その度ネリによって阻止されていました。
ところがある日、いつものように帰りの遅いキャサリンを心配したネリが、嫌な予感がして、ヒースクリフの居る屋敷の近辺まで行ってみると、キャサリンはヒースクリフと何やら立ち話をしていたのです。
「キャサリン様!何をしているのです、その人に近づいてはいけません!さあ帰りましょう。」
ネリは慌てて、彼女に対して不服そうなキャサリンの手を引き、帰ろうとしました。
「待ってよ、ネリ!私、これからヒースクリフさんのお屋敷へお伺いしたいの。ヒースクリフさんからお聞きしたわ、この方はお父様の妹の夫で、お屋敷にはお二人の間に産まれた私の従弟が居るそうよ。私、ぜひ彼にお会いしたいわ。」
ネリはもちろん、頑として反対しました。しかしキャサリンからあまりに熱心に乞われ、また彼女の決意が非常に固く、変える事が不可能であるように感じ、とうとう根負けして、二人でヒースクリフの屋敷へ迎え入れられたのでした。
ヒースクリフの屋敷の庭へ入ると、間もなく一人の下男が野良仕事をしている最中に出くわしました。
ネリはそれがヒンドリーの息子、ヘアトンであると気付きます。ヘアトンはネリ達を認めると、人懐っこい笑顔と張りのある大声で挨拶してきました。
「ヒースクリフ様、おかえりなさいまし!」
「・・・ああ。」
ヒースクリフは困惑したような、戸惑っているような複雑な感情を感じさせる様子で、ヘアトンに応じています。
ネリはそれを見て、不思議な、妙な感じを受けました。
ヘアトンは、ネリとキャサリンを認めると
「お客様ですか?初めまして、俺はヘアトン。この屋敷の使用人です。」
と、溌剌とした様子で軽く自己紹介をしました。
「初めまして、私は近くの屋敷の使用人でネリと申します。」
「私はキャサリン。その屋敷で暮らしているわ。」
ネリとキャサリンは、薄暗い部屋へ案内されました。暖炉の火が燃える前のソファーに、誰かが座っています。
近づくと、その人物がはっきりと分かりました。小柄なためか、少女と思われたその子は、天使のように可愛らしく、美しい美少年でした。
ただ、顔色が悪い事が薄暗い中でもよく分かり、表情は無表情で覇気が無く、目はまるで死んだ魚のように何も見ていないかのようです。
「息子のリントンだ。」
リントンはそう父親から紹介されましたが、ネリとキャサリンを見ても何の反応も示さず、振り返っただけで、すぐに暖炉の方へ顔の向きを直しました。
「挨拶ぐらいしたらどうなんだ?!」
ヒースクリフが忌々し気に怒鳴ったので、リントンだけでなく、ネリ達もびっくりしました。ヒースクリフは、まるで蛆虫でも見るような目でリントンを見ています。
弾けるように驚いたリントンは、慌てて立ち上がり、二人に向かって挨拶をしました。ただしそれは、非常に面倒くさそうで、声には感情が無く、気持ちの良い対応とは言えぬものでしたが。
(この子の外見は、あのイザベラ様にそっくりだわ。でもイザベラ様のような明朗さが全く感じられない…一体ヒースクリフはこの子をどんな方法で育てたのかしら?それとも性質については、全くイザベラ様に似なかったのかしら?キャサリン様が母親のキャサリン様に似なかったように。)
そうネリは思い、彼に対してあまり良い印象を持ちませんでしたが、キャサリンだけはリントンを一目ですっかり気に入ってしまいました。
うっとりした笑顔で彼に近寄り、話しかけます。
「初めまして、リントン。私はあなたの従姉のキャサリン。あなたのお母さまのお兄さんの娘で、すぐそこの屋敷に住んでいるの。」
「知ってるよ。お父様から聞かされていたから。」
リントンがつっけんどんに答えたのですが、ヒースクリフが再び忌々し気に息子を睨みつけたので、リントンは縮み上がって、しかしそれでもどうすれば良いのか分からない困惑した様子で目を泳がせるのでした。
ヒースクリフはその部屋を退出したのですが、その足取りから彼が非常に不機嫌である事が窺えたので、リントンは非常に不安そうで泣きそうな表情になったのです。
「君たちが帰った後、僕はお父様からまた大変な目に遭わされる…」
「まあ、リントン…大丈夫よ、そんな事無いわ。」
「大丈夫だって?何を根拠に。何も知らないくせに、他人事だと思って…そもそも君たちがここに来なければ、こんな事にはならなかったんだ。」
「ごめんなさいね、リントン。私が上手くやれなかったからだわ。」
キャサリンはまるで、幼児をあやすようにリントンに語りかけます。
「リントンさんの仰る通りですよ!私達はここへ来るべきではなかったのです!さあ、そういう訳ですから帰りましょう、そしてリントンさんのためにも、もう二度とここへは来ない事です!」
ネリはキャサリンを引っ張って帰ろうとしました。しかしキャサリンはそれを振り切り、そっぽを向くリントンに再び駆け寄り、優しく語りかけました。
「ねえ、リントン。私は本当にもうここへ来ない方が、あなたの幸せのためなのかしら?もしあなたが許してくれるのなら、私はあなたにいつでも会いたいのだけれど。」
「好きにしたら良いだろ。でも来たからって、君が気分良くなれるよう接待してもらえるとは限らないからね。」
「そんな事!あなたに会えるだけで嬉しいわ。ありがとう、リントン。」
最後まで不愛想なリントンに、キャサリンは心から嬉しそうにそう言うのでした。
ネリはため息をついて首を振り、二人は帰途につきます。
ヒースクリフに挨拶をしてくるからと、ネリはキャサリンを先に行かせて、ヒースクリフの居る部屋へ行きました。
ヒースクリフは書斎のような部屋で一人、窓に顔を向けています。窓の外ではヘアトンが仕事をしていますが、ヒースクリフは彼を見ているわけではありませんでした。
その時のヒースクリフの目は虚ろで、何も見ていないようであり、ネリはリントンがヒースクリフに似てしまった事に気付いたのです。
「驚きましたよ。てっきり私、あなたはヘアトンを虐待する事でヒンドリー様に復讐しようとしていると思っていました。
なのに、そんな様子が全く無い。ヘアトンは素直にあなたを慕っているし、あなたも満更でもなさそうじゃありませんか。…それにしてもあの子、ヘアトンはきっとフランシス様に似たのでしょうね。ヒンドリー様に見られた暗いものが全く感じられない。」
「そのつもりだった…お前の予想は外れていない。しかし俺はどうしても、ヘアトンを嫌えなかったんだ…それはヒンドリーの面影が、ヘアトンに見えないからなのか?!しかしそれでも、ヘアトンがヒンドリーの息子である事は確かなんだ!
ヘアトンにより、ヒンドリーに復讐しなければという思いと、ヘアトンへの好感との葛藤で、俺はあいつにどう接したいのか分からなくなっている!
ああ、あいつがヒンドリーの息子でなかったら…もしくはヒンドリーによくよく似ていたら、こんな葛藤に苦しむ事は無かったのに!」
「私には、あなたがむしろ実の息子であるリントンを憎んでいるように見えますよ?」
「ヒンドリーの息子、ヘアトンに対して、俺の息子のリントンを一級品に仕立て上げる事で復讐するつもりだった。
最初リントンを見た時、俺に全く似ておらず、イザベラにそっくりだったから、俺は安堵したし、嬉しかった。俺はこの子を愛する事ができるかもしれないとも思った。俺はイザベラを愛していなかったが、彼女を敬するところがあったので、彼女の性質を帯びた俺の子なら、と。
ところが日が経つにつれて、中身については全くイザベラから何も受け継いでいない事が分かったんだ。
あいつは…生まれながらにして、人間の屑だ!あいつの言動を見ていると、腹が立たない事が無い。
ひょっとしてこれは、俺の計画を頓挫させるための、ヒンドリーの呪いなのか?」
「たとえイザベラ様に似ていて、あなたの面影が微塵も見られなかったとしても、あなたはリントン坊ちゃんを憎んだでしょうよ。…だってあなたは、そうは言ってもやはりイザベラ様を憎んでいたのだから。」
ネリは部屋を出て、キャサリンと共に屋敷を後にしました。
キャサリンとネリが、ヒースクリフの屋敷へ入った事は、間もなく父、エドガーの知るところとなり、しかしエドガーは冷静で温厚な性格なので、いきなりきつく叱りつける事は無く、むしろキャサリンの方が、リントンら我々の親戚の居るあの屋敷を、なぜ訪ねてはならないのかと詰め寄りました。
エドガーは冷静に説明しました。ヒースクリフについて、彼が悪意を持ってエドガーらを見ていて、良からぬ事を企んでいるであろう事、彼女の母親の兄であるヒンドリーに彼がした事等を。
それでも、リントンに会いたいがために不服に思うキャサリンのため、エドガーは譲歩する条件を提案します。
キャサリンがリントンと会う時、エドガーの屋敷の敷地内のみである事、ネリを付いて行かせる事です。ヒースクリフはその条件を受け入れました。
そして数日後、リントンと会うためにその場所を訪れたキャサリンとネリでしたが、先に到着していたリントンの様子に驚愕します。
元々体が弱いのか、顔色の優れない少年でしたが、ますますそれが悪化しています。目はもう何を見ても、死んだ魚のようで、頬も体もやせ細り、今にも倒れ込みそうなところを懸命に堪えて座っている様子で、というのもどうやら、少し先で見張っている父親、ヒースクリフへの恐怖からなのでした。
「リントン!一体どうしたっていうの?!酷い顔色…それだけじゃない、こんなに痩せて。ヒースクリフさん!これはどういう事です?リントンは病気だわ、今すぐ医者に診せてあげて!」
「キャサリンさん、もちろんですよ。しかしそのためには、あなたにも一緒にうちの屋敷へ来てほしい。」
ネリはもちろん、頑として反対しました。しかしリントンも共に哀願し、キャサリンはネリに負けない程の頑固さで、ヒースクリフ宅へ行くと言って聞かず、結局すったもんだの末に、二人は再びヒースクリフの屋敷を訪れる事となったのです。
2人が屋敷に入ると、ヒースクリフは扉を閉め切り、
「さあ、キャサリンさんにはこれから、うちの息子のリントンと結婚してもらう。そしてもう2度と実家へは帰さないからね。」
そう言って、キャサリンを屋敷に軟禁する事を宣言しました。
「リントンと結婚する事は願ったり叶ったりですから構いません。けれどお願いです、最後に父に会わせてください。」
「駄目だ。あんたはもう、死ぬまでこの屋敷から出る事は叶わない。」
「そんな、必ず戻って来ます!私がリントンを愛している事はご存知でしょう?」
縋りつき、嘆願するキャサリンを突き飛ばしたので、彼女は床に叩きつけられました。一体どうすれば良いのか分からず、泣いてしまった彼女にネリが寄り添います。
そしてそんな2人を、暴力を受けたのが自分でなくて良かったという風な様子で、リントンが安堵の表情を浮かべながら眺めていました。
「何をニヤニヤしている?」
ヒースクリフが凍りついた表情と、冷酷な目でリントンに近寄り、途端にリントンは酷く怯え、体を強張らせました。大きく開いた目は怯えを映し出しており、父親から逸らしたいのに、逸らせばもっと恐ろしい事が起こる気がして逸らせないという風に固まっています。
ヒースクリフは、椅子に座ったリントンを拳で殴り、椅子から床へ落下した彼の腹を何度も蹴り始めたので、キャサリンが慌てて駆け寄り、リントンに覆い被さってヒースクリフから引き離しました。
「止めてください!それよりも…私がここへ来たら、リントンを医者に診せてくださるとおっしゃっていたではありませんか!早くお医者様を…」
「こいつを医者にだと?こいつにそんな金をかけてやる価値は無い。こいつはね、キャサリンさん、あんたと結婚させて、エドガーの屋敷を手に入れるためだけに必要だったんだ。それが済めば、もう役目は終わりだ。こいつにはもう、1文の価値も無い。」
「そんな…あなたの実の息子じゃないですか!」
そう訴えるキャサリンの腕の中で、リントンが愕然とした表情で父親を見上げます。
ヒースクリフはネリだけを、屋敷から出して返しました。
ネリからの報告を聞き、エドガーは非常に心を痛め、心配しましたが、かと言って打つ手も無く、とうとう心労のためか病に伏せてしまいました。
さて、キャサリンとリントンの挙式がささやかに行われましたが、キャサリンは父エドガーの胸中を思うと、心配で胸がいっぱいでした。
さらに、訪ねて来たネリから、父が病の床につき、今にも死にそうだと聞いてから居てもたっても居られず、リントンにどうか逃げる手助けをしてほしいと嘆願しました。
リントンはキャサリンが父親を思う気持ちなど分かろうともしないような子でしたし、キャサリンが泣いていても、ちっとも憐れみの情など湧く事もありませんでしたが、父親のヒースクリフも、屋敷の使用人らもヘアトン以外は彼を毛嫌いする中、キャサリンだけが、自分に優しく接してくれて、愛してくれて、その事についてリントンは全く感謝の気持ちは持っていなかったけれど、嬉しくはありましたし、失いたくありませんでした。
ヘアトンは彼に親切ではあったし、父親の虐待を見かければ庇ってくれたりする事もありましたが、彼はリントンと同じ空間に居る事自体が稀でありましたし、それにリントンは父が自分を嫌悪するのと対照的に、ヘアトンに好感を持っている事を知っていたので、リントンはヘアトンに対して消えれば良いと思う程の嫉妬心を抱いていました。
それはともかく、キャサリンがあまりにも懸命に嘆願し続けるので、この願いを聞かなければ、彼女の愛を失うのではと密かに恐怖したリントンは、彼女が逃げ出す手助けをしたので、彼女は帰宅し、父親の死に目にどうにか会う事ができたのです。
父親と再会したキャサリンは、これ以上心労させないために、ヒースクリフもリントンも自分にとても良くしてくれていて、仲良く暮らしていると父に話したので、エドガーは安心してこの世を去りました。
葬儀を終えたキャサリンを、ヒースクリフが迎えに来ました。
「もちろんあなたのおっしゃる通りにするつもりです。最初、申し上げたように私はリントンを愛していますもの。」
それを聞いて、ヒースクリフは一瞬苦々しい表情を浮かべ、答えました。
「そりゃ結構な事だ。しかしせいぜい覚悟しておいた方が良い。今回あんたが逃げる手助けをした事で、私から酷い目に遭わされたものだから、リントンはあんたを随分逆恨みしているんだよ。
俺と同じくらい力があれば、あんたをあんな目に、こんな目に遭わせたいと呪詛のようにぼやいていてね。
なにしろ体が弱いし、力も無いから、悪知恵を働かせる事だろうよ。」
キャサリンは青ざめた顔で、ヒースクリフに詰め寄りました。
「あの人に何をしたの?!私は一人で逃げ出したのよ?!リントンがその手助けをしたなんて、一体何を根拠に…」
「あいつがやったに決まっているさ。…いや、真実などどうでも良い、人はね、何か都合の悪い事が起これば、根拠や証拠そっちのけで、自分の嫌いな人間のせいにしたがるものなんだよ。」
「嫌いな人間!実の息子に対して、どうしてそんな事を!」
「あいつのあまりに不愉快な性質を、あんたはまだ思い知っていないようだな。あれだけ見て来たというのに…まあ、良い。これから屋敷に戻り、もっと一緒に過ごすようになれば、さすがに嫌になるはずだ。」
「あなたは、私とリントンを憎み合うようにさせたい様ね。確かにリントンは私を愛する事が無いかもしれない。けれど、私はあの人が私を愛する分まであの人を愛して、それでもおつりが来る程なのよ。」
こうしてキャサリンは再び、ヒースクリフの屋敷へ戻りました。屋敷に着くなりリントンを探すと、リントンは満身創痍でベッドに横たわっています。
父親から散々痛めつけられた彼は、ベッドまで移動する力も無く、見かねたヘアトンが服を着替えさせて、ベッドに運んだのです。
そしてヘアトンがそのように手当てをしてくれている間、リントンは彼がヒースクリフの虐待を止めなかったと言い、呪詛のように恨み言を呟いているので、ヘアトンは彼を憐れに思いました。
かれは、できればリントンを看護してやりたかったのですが、主人のヒースクリフがそれを許さず、彼がリントンの周囲に近づく事を頑として阻止し続けたので、元々体の弱いリントンは、キャサリンが来る頃には虫の息でしたが、キャサリンを認めると、表情の無かった顔が悪鬼のように歪み、キャサリンへの呪詛をぼやきはじめます。
「どうしてもっと早く帰れなかったんだ?君が向うで幸せに過ごしている間、僕は君が受けるべき罰を、とばっちりを受けていたんだ!
僕を愛しているなんて本当は嘘だろう、僕を良いように利用するためにそう言っていたんだ。そうでなければ、こんな事するはずが無い。」
キャサリンはリントンに駆け寄り、泣きながら許しを乞いました。
「ごめんなさいリントン、こんな事になっていたなんて…」
「こんな事になっていたなんてって、君はパパが僕にどんな風であったか、よく目にして知っていたはずだ。こうなる事を予知して上での事だろう!」
「いいえ、いいえ、まさかたった一人の息子であるあなたに、こうまでするとは…それにヒースクリフさんは、お父様の屋敷を手に入れるためには、私と結婚するあなたが必要だと…だから、私が戻るまではあなたに何もしないはずだと安心していたの。」
「そうだ…君のお父さんが死んだ…だから、君の住んでいた屋敷も、馬も、君の物は全て僕の物になったんだ…!」
リントンは悪意を持ってそう言いましたが、キャサリンはちっとも気を悪くせずに答えました。
「ええ、そうよリントン。だからちゃんと元気にならないと…ヒースクリフさん、今すぐお医者様を呼ばせてください。私には今、お金がありません。ですからどうか、彼に医者を…」
「言ったはずだ、あんたの住んでいた屋敷を手に入れた今、こいつにはもう生かしておく価値は無い。」
「ヒースクリフさん!あなたは憎い私を苦しめたくて、リントンを苦しめるのですか?どうか目を覚ましてください、彼はあなたの一人しか居ない息子です。私を苦しめる方法は、他にもあるはず。」
「私が憎んでいるのは、キャサリンさん、あんたそのものではない!あんたの、この忌々しいリントンへ向ける愛、その方向性を憎んでいるんだ!こんな奴はまっとうな愛を向けられるべきではない。憎まれ、疎まれ、消えるべきであり、そうあってほしいと願っているんだよ。私は本当に、こいつに消えてほしい!存在そのものが不愉快だ!どういうわけか、こいつさえ居なければ、心安らかになれる、救われるような、そんな気がするのだ。」
驚愕するキャサリンの横で、悪鬼の顔から呆然自失した顔に変わったリントンは、固まった表情のまま、自然と見開いたままの目から涙を流し始めました。
「何を理由に泣いているのか、はっきりとした理由はわからんが、少なくとも他人の為で無い事だけは確かと思えるな。おそらく自分を憐れんで泣いてやっているんだろう。こいつは精一杯の憐みや気遣いを、自分のためにしか発揮する能力を持っていない屑だからな。」
ヒースクリフが冷たく言い放ち、たまらずキャサリンが出て行ってほしいと叫び、彼は部屋を後にしました。
そして翌朝、リントンは自室のすぐ真下の庭で、血を流して死んでいるところを発見されたのです。彼はキャサリンの目を盗み、力を振り絞って窓から飛び降りたのでした。
リントンの死を、キャサリンだけが悲しみました。ヘアトンは、そんなリントンとキャサリンを憐れに思い、今まで以上にキャサリンを気遣うようになりました。
数年後のある天気の良い日、ヒースクリフはエドガーの妻である亡きキャサリンの墓の前に立っていました。数メートル先では、キャサリンがヘアトンに読み書きを教えています。
「あの二人は、いづれ結婚するでしょうね。」
ヒースクリフが振り返ると、そこにはネリが居ました。
「リントンの父親としては、複雑な気持ちかしら?」
「いや・・・それこそ、おそらく俺の願う結末であった。二人ともリントンの事など早々に忘れ、健全な精神の者同士で幸せになってほしい。
俺が本当に憎んでいたものは、ヒンドリーでもエドガーでもない。俺自身の病んだ心であった。リントンはその象徴、俺の病んだ心そのものであった。だからリントンが死んだ時、ほっとした。胸の閊えが取れたような心地だったのだ。」
「・・・なんて酷い事を・・・あの子は・・・リントンはリントンですよ!あなたの実の息子ではあるけれど、あなたとは全く別の一人の人間です。
随分と自分に都合の良い解釈ができるものですね!あなたは要するに、リントンに自分の重荷を押し付けたのです!
・・・でもね、重荷は押し付けられるものではありません。あなたはリントンに重荷を押し付けて、平安を得られると思ったかもしれないけれど、むしろ重荷はますます重くなる事でしょう。」
ネリはリントンの事が大嫌いでしたが、それでも非常に憐れになり、涙目でヒースクリフを叱責しました。
ヒースクリフは墓石をぼんやりと見つめて、ネリに応える気配はありません。
俺には見えるのだ。あの世でのリントンが。地獄へ落ちる事となったリントンが、自分は父親のヒースクリフを裁くため、ただそれだけのためにこの世にひり出された事を知らされ、神への憎悪と悲しみにまみれて地獄の悪魔どもにしょっ引かれる姿が。
人間に産まれたからといって、必ずしも神に愛されるとは限らない。神に愛される存在かどうかは産まれる前から決まっている。愛されない人間は、神に愛される人間を引き立てるために使われ、そして地獄へ捨てられる。
ああ、リントン・・・俺もいづれそこへ行く。すまなかった、お前を一人にはしない。お前が受ける地獄での責苦をできる限り俺が引き受けよう。
ヒースクリフは初めてリントンのために嘆き、涙を流しました。
「すまない、キャサリン・・・俺は荒野へは行けない。地獄へ落ちるから。」
-
-
Wuthering Heights
0











